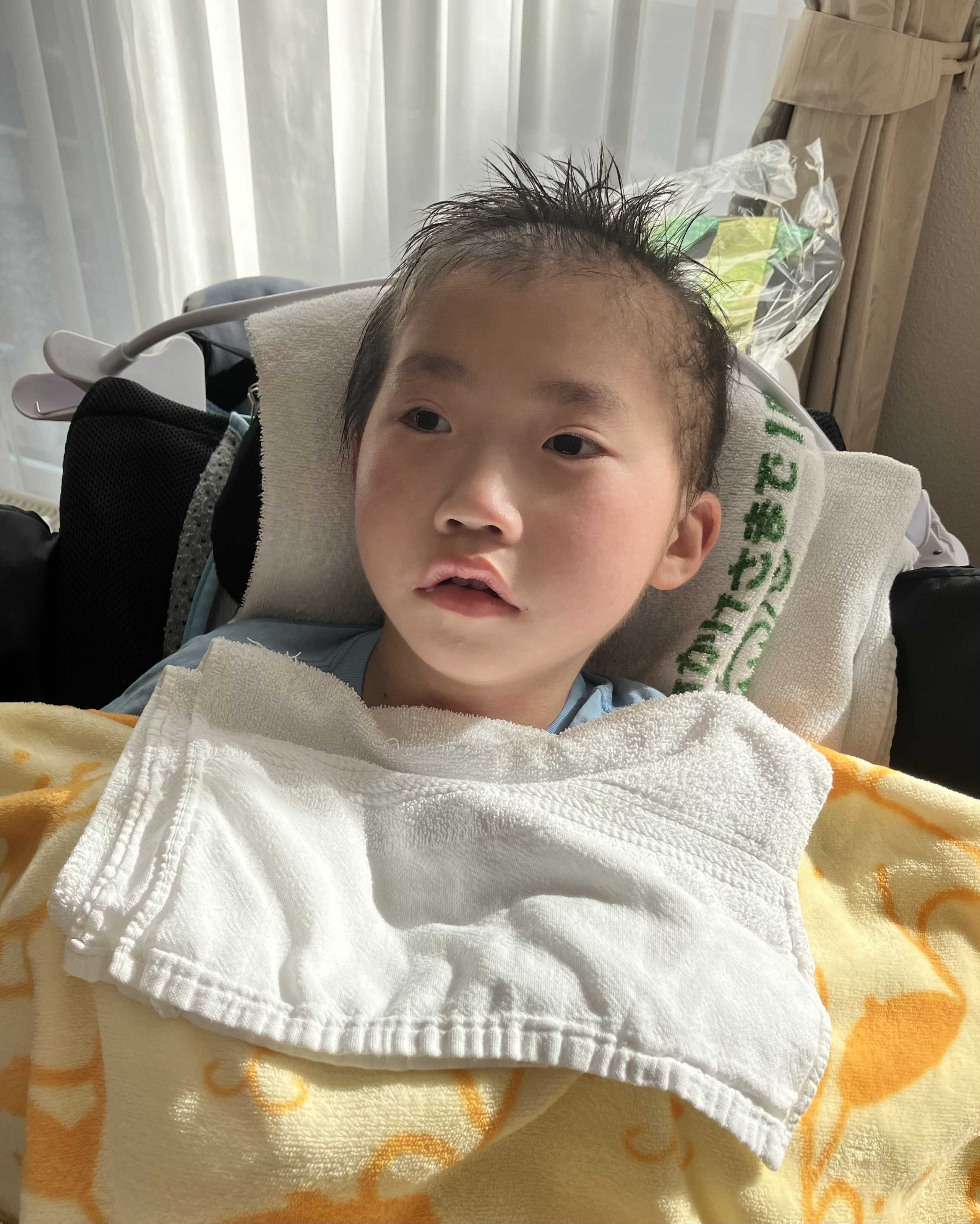2013年06月の記事
全42件 (42件中 1-42件目)
1
-
不快な感情
プロ野球やサッカーで自分の応援するチームが劣勢になって負けそうなとき、勝っている試合を途中で逆転されてサヨナラ負けを喫したとき、あるいは何連敗もしている時、不快な気持ちになることはありませんか。私は広島カープのファンですが、ここ何年もBクラスでいつも不快な気分に覆われています。思い出すだけでも腹が立ちます。テレビ観戦していても、劣勢になるとチャンネルを変えます。その日のプロ野球ニュースは見ません。たまたまプロ野球ニュースになるとまたチャンネルを変えます。カープが負けた時は新聞も見る気がしなくなります。友人と話していても、どうしてカープが弱いのかという話になります。みんなそれぞれに見解を持っています。監督が悪い、フロントが悪い。なぜもっと金をかけてよい選手をとらないのか。などなど。よいところは全然見ません。たとえば観客動員数が少ないにもかかわらず、ずっと黒字経営を維持している数少ない球団であるという。この努力はすごいことだと思う。でも赤字になってもいいからもっとよい選手を獲れ。これが本音ですが。なにはともあれまず勝ったという結果が欲しい。選手個人は努力するのは当たり前だ。その努力のプロセスよりもまず勝つことだと思っている。つまり不快な気分をなんとか取り去ろうとファンはみんな躍起になっているのである。気にしないようにしようとすればするほど、気になってますますカープの動向に注意が向いて、かわいさあまって、憎さ百倍となるのである。そうかといって、無視するという人も完全に無視しているのではない。試合があると途中経過を常に気にしているのである。悪循環である。このからくりは神経症の発症パターンと同じです。精神交互作用の打破、つまり不快な気分を抱えたまま、なすべきことに手を出してゆくことしか手がないようです。早く不快な感情を流してしまうのは、それが一番なのです。現在カープが弱いというのはまぎれもない事実です。その事実をみて、不快な気分に陥ってしまったというのも事実です。事実はどうすることもできません。事実を受け入れ、事実に服従することしか、とるべき手段はないようです。
2013.06.30
コメント(0)
-
自分のミスへの対応
先日会社の人事担当の部長から36協定の届け出用紙に私の同僚18名の署名押印を集めてくれと依頼がありました。その部長はミスなどがあると徹底的にその当事者をいじめるというタイプで、社内でも煙たがられている人でした。その人のために退職を余儀なくされた人が数名おられるのです。事前の電話で、印鑑はシャチハタではダメ。また新入社員2名は署名不要という指示を受けました。全員を集めての会議の冒頭でその用紙を回覧して署名してもらうことにしました。その日は重要案件の説明と質疑応答が予定されていましたので、その用紙には何枚か付箋に注意事項が貼りつけてありましたが、私は気にも留めず署名押印して次に回しました。最後に全員が署名押印されたものを見て「しまった」と思いました。署名不要の人の1名が署名しているのです。また付箋に署名日付を5月25日と指定してあったのです。私は心配性ですから、会議の内容よりも、そのミスが気になり当日の夜はほとんど眠ることができませんでした。間違ったところを修正テープで書き直そうかなどといろいろ考えました。なんとかミスがなかったことにしようと気をもんだわけです。夜そうゆうことを考えると悪い方悪い方に考えてしまうのです。朝になりました。会社に出て腹は決まりました。もうどんなに厳しく非難されてもそれは甘んじて受けてみよう。清水の舞台から飛び降りる覚悟で電話しようというものでした。森田理論のまたとない応用です。多少声が震えているのが自分でも分かりました。すると案の定部長がネチネチと嫌味を言われるのです。仕方がありません。自分が間違えたのですから。「申し訳ありません」と謝るばかりです。しばらく聞いていますと、急にトーンが変わり、相手がこんなことをいうのです。あなたはまだましな方だった。他の部署は鉛筆で書いているものがいた。また不信任のところに署名押印しているものがいたというのです。また私はすぐに謝ってきたから自分でなんとかするというのです。どうにもならなかったらまた協力してくれと言われたのです。案ずるよりも産むが易しとはこのことでしょうか。以前はこんな時、能力のない奴だと非難されることを恐れて、ごまかしてばかりいたのです。そして報告をずるずると先延ばししていたのです。そして何日も苦しんできたのです。そんなことを繰り返しているうちに以前胃潰瘍にもなりました。こんなところでも森田の威力をつくづくと感じる毎日です。
2013.06.29
コメント(0)
-
事実よく見る
イチローは自分で体験して確認できたことを信頼しているという。ことバッティングに関しては周りの人のアドバイスは無視するという。自分が体験していないことを、無条件に信じてしまうと迷いが生じるという。バッティングが迷いによって崩れてくるのを警戒しているのである。イチローの頭の中には過去に対戦したピッチャーの投げた球がすべてインプットされている。その経験をもとにして対戦方法を即座に決断している。多くの可能性の中からいまの状況の中でできうる一つの対戦の決断をしているのである。感性を研ぎ澄ましてバットを振ることだけを考えている。自分で決断したことで失敗しても恐れることはない。失敗しても次の対戦に役立つ何かの感覚を得ることが大切だという。これは観察に力を注いだ森田先生の考えと完全に一致している。先入観、机上の論理を排除して、自ら実験したり、現地に赴いて確かめたその事実を大切にされていた。そこで感じた感性を大事にされていました。熱湯に手をつける実験でも幽霊の探索でも、普通の人がばかばかしいと思う事でもすべて体験によって確かめられている。事実本位というのは、まずはよく観察して本当の事実を掴むという事から出発しないといけない。
2013.06.28
コメント(0)
-
子供のわがままに森田理論で対応する
幼児がデパートやスーパーなどでほしいものを見つけると、そこに座り込み「あれを買って」と泣き叫んだり、床に身を投げ出して大暴れする事がよくあります。普通の親は、「もう連れてこないわよ」「そこは服が汚れてきたないから立って」などといっています。または大声で強く叱ったり、叩いたりして恐怖心を与えておとなしくさせようとします。あるいは抱き上げたり無理やり手を引いて別の場所に移動してほしいものをあきらめさせようとします。反対に「そんなに欲しいの。仕方ないわね。今度だけよ」といって買い与える親もいます。こんな時は森田を応用したらどうかと思います。叱りしけるでもない、子供におもねるでもないその中間というとどんな対応があるでしょうか。ある親が、汚い床に腹ばいになりやりたい放題の子どもに、「いいんだよ。このまま自由に泣きわめいても」といって、ほおっておいて買い物を続けていました。子供はしばらく泣きながらのたうちまわっていましたが、効果なしと判断したのかそのうち泣きやみ、「お母さん、待って」とお母さんを追っていったのです。私はこれをみて思わず森田先生と一緒だと思いました。この対応でいいのだと思いました。安田さんという方が、子供の夜泣きがひどく眠れない、どうしたらよいでしょうかと森田先生に質問しました。うるさいと思うのも純な心である。子供のことだから仕方がない。「我慢しなければと型にはまっては少しも進歩はない。一方叱りしけたり、懲らしめたり、菓子を与えて機嫌をとるなどの軽率な行動はもっといけない。神経質者はどちらかに態度を決めなければということが多い。白か黒かどちらかに決めたがる。どうしてよいか分からないときは、うるさいなという純な心はそのままにして、態度を保留にする事である。ああうるさい、どうしてやろうかとああも思いこうも工夫して、子供を観察したり、他のことをしていると、いつとはなしに、子供は泣きやんでくる。なるほど子供はなくだけ泣けば泣きやんでくるものだという法則を発見する。
2013.06.27
コメント(0)
-
感情を抑えつけない
幼児はかけっこをしていてよく転びます。擦り傷をつくりすぐに泣きます。そんな時親が子供に向かって、「あんたが走ってたからよ。そんなことで泣くんじゃないの。我慢するのよ。」あるいは「痛くない。痛くない。こんなことでワンワン泣かないの。男の子は泣かないの」ということがあります。子供はその言葉を聞くと、どう思うでしょうか。「痛くても、それをストレートに表現するとお母さんに叱られるんだ。どんなに痛くても泣いたりするのはいけない事なんだ。我慢しなければいけないんだ」と感じるようになるもしれません。何かにつけて、こうした対応を受け続けていると、感情を自由に人前で出してはいけないんだという事が自然に頭にインプットされないでしょうか。もし子供がそう感じたとすれば、大変悲しいことです。というのは、そんなふうに育てられた子供は、「感じたことをストレートに表現するのはよくない。自分の感情は押し殺して、意志の力でコントロールしなければいけない。」という「かくあるべし」人間になってしまいます。そして感じを押しころそうとやりくりを始める子は、イヤな感情を避けるようにもなります。そんな子供が大人になると、泣きたいときに泣けず、うれしいときに喜べず、笑いたいときに笑えず、怒りたいときに怒れない人間になってしまいます。いわゆる無気力、無関心、無感動の人間になってしまいます。森田理論ではどんな嫌な感情でも意思の力で押さえつけないこと、そのイヤな感情を持ちこたえること、味わってみるという態度を養成するように勧めています。これは我慢することとはちょっと違います。場合によっては行動は我慢することも必要ですが、嫌な感情は我慢する必要はありません。我慢してはいけない。腹が立つときは人を殺したいぐらいにいくら恨んでもよいのです。
2013.06.26
コメント(0)
-
正岡子規と森田
道後温泉に子規記念博物館があります。子規の足跡を訪ねることができます。子規は新聞「日本」で俳句や短歌の革新を訴えました。その内容は事実をよく観察して、その対象を写生するように写し取るというものでした。それは万葉集の考え方に近いものだったようです。森田の事実本位の考えに通じるところがあります。弟子が多く高浜虚子、伊藤左千夫、森鴎外など俳句、短歌のみならず、小説、書や絵画にも及びます。また夏目漱石とは松山で50日ほど一緒に住んでおり、多くの影響をお互いに与えたようです。森田理論との関連で書いてみます。子規は「メモ魔」であったそうです。こまかい日常茶飯事を丁寧にこなしてゆくためには、メモしてやるべきことを忘れないようにすることが大切ですが子規も同じ生活スタイルを持っていたのです。次に子規は大変好奇心が旺盛だったといえます。まず野球に興味を持ち「野球殿堂」入りされています。それから旅行好きで東北秋田まで旅行されています。松尾芭蕉のようだったようです。森田理論でも好奇心にそっていろいろと手を出すということはとても大切です。亡くなったのは東京の根岸だったそうです。根岸といえば「根岸病院」のあるところで森田先生のなじみの場所です。そこで正岡子規は、7年にわたる肺結核と脊椎カリエスによる仰臥に、耐え忍ぶことのやりくりや心構えを求めることをしなかった。病苦に泣くのみであった。極貧の中にあって看護人もなく、寝返りを打つには柱につないだ紐を引っ張ってこれをやるという仕儀であった。子規は痛みと喀血の耐えがたきことを、はからうことなくただ慟哭していた。痛みに常に襲われながらも俳句と随想の創作活動は続けていった。死の二日前まで書いていたのが「病床六尺」である。これこそが森田先生がよく言われる「日々是好日」ではなかろうか。享年35歳であった。作った俳句は約22000首。最後に子規の句を2首。松山や秋より高き天守閣柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺
2013.06.25
コメント(0)
-
まずは事実の把握に努める
親は子供に対して、よく事実を把握しないで価値判断をして指示、批判、命令、強制、叱責をします。まずは具体的な事実をよく確認するという態度を身につけたいと思います。具体例を「わが子を活かす一言、潰す一言」 鈴木博 祥伝社をもとにして紹介します。たとえば、子供が友達とあまり遊ばないとします。その時に、親はすぐに「うちの子は友達に興味を示さない。協調性がない」と価値判断します。事実は「うちの子は1日に3時間ぐらい本を読んでいて、外で遊ばない。」ということであって、他人に興味があるかないかは、これだけでは判断できない問題です。また病気で入院したおばあちゃんの見舞いに行かない子供に、「思いやりのない子だ。自分勝手なことばかりする」などと判断します。見舞いに行かないというのはまぎれもない事実ですが、その理由は子供に聞いてみないと分かりません。安易に親が判断する問題ではありません。理由を聞いてみる。そしてさらに子供がいったことに対して、お母さんは「あなたの話をこうゆうふうに聞いたけどこれで間違いない」と確認する態度で接することが大事です。「うちの子どもは無駄遣いばかりする」というお母さんがいます。これではあまりにも抽象的です。具体的に事実を話すことが大切です。うちの子は月に3000円も使っています。これが事実です。その先そんなにこずかいを使ってはいけないと判断し、子供を叱責したりすることは余計なことです。事実の観察、事実の承認にとどめて、その後の行動は子供に任せるしかありません。「うちの子は不良と付き合っている」の具体的事実は、「うちの子は最近髪を染めた子供と付き合っている」です。事実をよく観察して、その事実をまず認めるという事は、相手を「かくあるべし」で翻弄しないで、相手の存在や行為をまずは認めるという事です。
2013.06.24
コメント(2)
-
明日の投稿はお休みです
明日は集談会の派遣講師として、他の集談会に参加します。講話の内容は、「森田理論の全体像」に絞って説明してこようと思っています。生活の発見会はなぜ、このテーマを大々的に取り上げないのか不思議でしようがありません。森田理論の基礎編を一通り学習した後は、応用編に進むわけですが、応用編の最重要テーマは「森田理論のスキーム」の学習です。ここを押さえないから、森田のキーワードをいくら何回も繰り返して学習しても絵にかいた餅になってしまうのです。生活に応用することができないのです。自分の生き方に反映できないのです。発見会会員は6000名を超えてから、減少してきました。しかし社会不安障害の人は300万人いるといわれています。また精神科の病院には人があふれかえっているといわれています。本来私の試算では発見会会員は3万人程度が妥当な最低限の会員数だと思っています。これは飛ぶ鳥を落とす勢いのダイエーが短期間に没落していった過程とダブってしまします。学習の方向性を見誤ったとしか言いようがありません。精一杯みんな努力をしているのですが、今も立ち直りを見せているとはどうしても思えません。明るい未来が見えてきません。でも、心の問題を抱えた魚が海でうようよ泳いでいるような状態ですから、あきらめるわけには早すぎます。できる限りのことはしてみようと思います。明日は森田先生がよく話しておられる、正岡子規記念館を訪ねてみようと思います。
2013.06.22
コメント(0)
-
対人問題を起こす人
対人葛藤を生む原因の調査によると、次の4つがダントツであったそうです。1、相手が平気でルール違反をする。2、相手が全くの期待はずれである3、自分のプライドを損傷傷つけた4、相手のために欲求不満に陥ったまず2は子供が自分の思っていたようにしないと期待はずれとなる。また会社では部下がノルマを達成してくれないと、その部下は期待はずれとなる。「かくあるべし」が強い人は、他人が、自分の理想とかけ離れたことをすると期待を裏切ったとみなして、不満がたまっていく。そして指示、命令、叱責で相手をとことん否定してしまう。対人葛藤を減らそうとすれば、森田理論の学習をする必要があると思う。1のルール違反であるが、これも日常生活でいくらでも経験することである。無理な割り込みをする。約束を守らない。黄色信号、赤信号を無視する。借金を踏み倒す。貸してあげたものを返さない。挨拶を返さない。夜中に騒音を出す。ゴミ出しの決まりごとを守らない。町内会の役をすっぽかす。授業中に私語が絶えない。等々身近に癪に障ることはたくさんあると思います。身近な例をあげて考えてみましょう。約束の時間になっても友達が集合場所に現われないというのは、典型的なルール違反である。この約束違反は、場合によっては自分にとって期待していた楽しみや利益が失われるという事だから、損害を受けたという事になります。だが事はそんなに単純なものではない。それに加えて、3のプライドを傷つけられたという事がプラスされてとてもイヤな気持ちになるのである。むしろこちらの持つ意味が大きい。約束を反故にされたという事は、相手が自分のことを軽視している。大切な友人だとは思っていないという事の証明ではなかろうか。反対に相手を大切にして、重要視していれば30分前から集合場所に行って待つことは別に苦とは思わないはずだ。1は単独ではなく3と合体してなんともいえない不快感となるのである。つまりここでいいたいのは、いつも約束を破っている人は、他人の立場に立って物事を考えることができない人ということになる。という事は、「かくあるべし」を前面に出して、他人を非難、叱責、指示、命令で動かそうとしている傾向が強く、森田理論の核心部分の事実本位に相手を見ることはとてもできそうにもないということになります。他人にそのように接するという事は、自分に対しても自己否定の枠から完全には抜け出ないで停滞を余儀なくされるということになります。
2013.06.22
コメント(0)
-
対人関係のポイント その5
この日本人の特徴をよく理解してほしいのである。そうすると対人関係で苦しまないで生きてゆける道が開けてくる。森田理論を活用して生きていく道があるのである。森田理論で私が考えていることは、欧米のよいところと日本のよいところの両方を取り入れて、バランス感覚を意識することである。小泉首相のとき、竹中さんが全面的に市場原理、競争原理、自己責任を持ちだし、すべてを欧米流にしようとした。これではうまくいかないと思う。今までの歴史を無視するからである。日本人は他人の気持ちを思いやりながら生きていくという基本的な生き方が根強くある。まずはこれを基本としないといけない。優先すべきはこれである。でもそれにあまりにも偏ると、とても息苦しい。今対人関係で悩んでいる人はこれ一辺倒である。煙の充満した中で息をしているような状態になる。そこで、欧米に学び、自己を確立することを取り入れることだ。自分の意見が持てるようになること、自分のやりたいことを見つけていくことだ。そして自分の意思で行動していくこと。この欧米の自立を基本とした考え方を少しとり入れて、バランスをとるつもりで生活していると破綻することはないと思う。それはサーカスの綱渡りをみているとよく分かる。長い棒のようなものを左右に揺らしながらバランスをとって前進している。するとハラハラしながらなんとか渡りきってしまうのである。欧米の自分で自分の人生を切り開いていくという考えを、1割でも2割でも取り入れた人は強くなれる。決して対人関係を苦にして自殺するようなことはないと思う。人間関係の極意はここにあると思います。さらに森田理論学習で深めてゆきましょう。
2013.06.21
コメント(0)
-
対人関係のポイント その4
世間がまず先にありきということになると、極めてきついルールに従うことを求められる。和を乱したり、反抗的態度をとったり、約束を破るものは最終的には排除される。排除されることは群れの外に出されるということであり、そこで待っているのは、死以外のものはない。つまり他の人の気持ちを思いやり、自分を抑えていかないと日本ではうまく生きてゆけなくなる。自分と世間との利害が衝突する時は、必ず世間のしきたりや決めごとに従わなくてはならない。これは自分を押し殺して生きていくことになり、葛藤を生み苦悩と結びつきやすい。よい面としては、相手の気持ちを思いやることで、犯罪が世界一少ないことにもつながっている。日本では世の中の流れが一定の方向に向かい出すと、この空気は誰も止めることはできない。台風の進路を変えることができないのと同じである。これは多くの人が世間を離れては生きていけないと思っているからである。日本人は世間から見放される、外されるということをいつも気にして恐れているのである。つまり、自分の気持ちを殺して世間に迎合するということに陥りやすい。
2013.06.21
コメント(0)
-
対人関係のポイント その3
欧米の人間関係の特徴は何か。欧米という国は生まれ落ちると、自立して一人で自分の人生を切り開いていくことを求められる。それはちょうど親に産み落とされた動物が、その瞬間から自立して生きていくことを求められるようなものだ。すると敵は多い。卵から孵化した魚はほとんど他の魚の餌になる。自分以外の周りのものは、対立するものであって敵なのである。そういう過酷な運命にあるから、ハリケーンなどがあると必ず略奪が起きる。戦利品を取り上げたかのように、堂々と手をふって略奪ができるのである。欧米から見ると、東日本大震災で日本人のマナーの良さが大々的に外国のマスコミに紹介されていたが、日本人はバカか臆病ものぐらいにしか思っていないのです。その点日本は違う。言葉が適切でないかもしれないが、自分が所属する世間がある。その世間の中にいることで自分が生きていけるという関係である。世間から離れて自分ひとりだけでは生きていくことはできない。欧米と違い個人が先にくるのではなく、世間があっての個人なのである。これは米作りをみるとよく分かる。米作りには水が必要だ。水は基本的には村の総意によって管理されている。決して自分勝手なことは許されない。もしそんなことをすると村八分にされる。つまり生存する事が不可能なのだ。この日本人の世間に気を使いながら生活するという遺伝子は、骨の髄まで貫徹されているのである。
2013.06.21
コメント(0)
-
対人関係のポイント その2
一方欧米などでは、世間に謝るなどといった対応は特に社会問題とはならない。むしろ間違った対応となる。1995年沖縄で米兵による「少女暴行事件」起きた。その時アメリカから母親がやってきて堂々とテレビに出て、「うちの子供は悪くない、日本の警察にはめられた」といった。証拠もあがっているのになぜ反論できる余地があるのか。もし日本人が同じことをすると、その親は袋叩きにあうだろう。アメリカの社会を知る必要がある。アメリカでは「わたしが悪かった。すまない。」ということは、どんなに自分が悪くても禁句とされている。交通事故発生時自分の非を棚にあげて、もっともらしく相手を攻撃してくる。また車の保険に入る時は、「事故を起こした時、自分の不利になることは絶対に話さない」という約束をして加入できるのである。非を認めて謝ってしまうと、責任をとらされるからである。つまり私が何をいいたいかというと、日本と欧米は他人や社会との関わり方が全く違うということである。この違いを森田理論に絡めてよく理解していくと、対人関係がスムーズに展開する可能性があるということである。
2013.06.21
コメント(0)
-
対人関係のポイント その1
プロ野球の加藤良三コミッショナーが、統一球の変更を勝手にやったことに対して、「私は、これは不祥事だとは思っていない」といってバッシングを受けている。私はこれを見て、これはコミッショナーの引責問題になる可能性が高いと思う。というのは、この問題は欧米ならともかく、日本の社会には決して受け入れることのできない言動だからである。普通日本で不祥事があった場合、どんなに相手に非があることであっても、とりあえず、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんと謝るのである。日本の企業の危機管理としては常識である。まずは真摯に反省して、真剣に謝るという姿勢を見せるべきだったのである。自分が心底そのように思っていなくてもかまわない。世間の人から見て、反省して心から謝っているように見えるということが大切なのである。以前雪印の食中毒問題が発生したとき、確か社長がマスコミの取材に答えてこう言った。「私はこの問題に対して、毎日寝ずに対応しているんです。」この言葉で大ブーイングが起きた。食中毒になった人たちへの謝罪ではなく、自分の体のことを心配していたのである。それで多くの日本人の反感をかったのである。この場合もまず不祥事を起こしたことに対して、頭を下げて謝ることが大切だったのである。大企業の社長なのに、簡単な社会常識がなかったのである。あるいは自己主張が過ぎたのである。
2013.06.21
コメント(0)
-
元部長さんのいらだち
部長で定年退職した人が、用事があって会社に顔を出したところ、以前の部下がそっけない態度をして腹が立ったという話を聞いた。受付で不当な対応を受けたというのである。昔の地位や権力の名残で、待遇に対して丁重に大事に扱われてしかるべきだという意識があったのだと思う。対人恐怖で苦しんでいる人は、いつもそんな状態を期待して現実とのギャップに苦しんでいる。我々は部長さんのように昔の栄光を持っているわけでもない。画家、音楽家、俳優、スポーツ選手のように能力を持っていて、注目されるのが当然というような存在でもない。それなのに自分はすべての人からどこまでも大切に扱われ、重要人物として一目置かれるように期待している。ここが普通の人と大きく異なるところである。普通の人は、その時対応する相手が、自分をどのように扱かうかという事を、事前に自然な行為として予測している。予測以上に対応してもらうと喜び、予測以下だと自尊心が傷つけられ、腹が立つのである。たとえば、社長室を訪ねた時、「ちょっと、その件はあとにしてくれ」といわれて腹が立つ人はいない。そのように対応されるかもしれないことを予測しているからである。反対に、部下が、「いま忙しいので、その件はあとにしてください」といわれれば途端に機嫌が悪くなります。部下は上司である自分を、何はさておき丁重にもてなしてくるべきだという予測を立てているからである。こんな例はいくらでもあります。普通の人は時と場合に応じて、自然に臨機応変に切り替えながら生活しているのです。それが当たり前になっています。これに対して神経質者はすべての人から丁重に扱われることを期待しています。こんな違いがなぜ発生するのか。これは神経質者が強固な「かくあるべし」を持っているからである。人から常に高評価をされなければならない。バカにされてはいけない。等と現実離れした高い自己評価をかってに設定して、そのように相手が自分を取り扱ってくれることを期待している。思想の矛盾に苦しんでいるのである。「かくあるべし」を減らして「事実本位」に少し切り替えてゆくことが大切です。
2013.06.20
コメント(0)
-
森田先生と丸井教授の論争
森田先生は精神学会で東北大学丸井清泰教授とお互いに論戦してぶつかり合っておられた。感情むき出しの攻撃であったという記録が残っている。詳しくは「森田正馬癒しの人生」を参照してください。現代でも学会など学術的な討論の場で、相手の研究成果、論点、主張などに対して痛烈な批判や反対意見が出されることがあるという。ここで面白いのは、批判やこき下ろされた人の対応が2つに分かれるという。一つは自尊心が傷つけられて不快になり不機嫌になる人。もう一つは厳しい意見や質問を歓迎して、やり取りを楽しんでいる人。普通学者というのは自分の研究分野に対して絶対的な自信と確信を持っているものである。自分の一番の存在意義、よりどころとなるものである。それをこき下ろされればたちまち意気消沈するのは普通のような気がする。それを意に介さない人はどうゆう人なのであろう。多分その人は、いままでの研究の蓄積により、文献や論文、講演や研究成果の発表によって、ゆるぎない強固な自信と自己評価を自分なりに確立しているのではなかろうか。そしてさらに研究を深めていこうという意思を持っている。だから前進につながる批判はうれしいのである。高良先生がその道のエキスパートにあることが、人間関係の改善に役に立つというのはこの事を言われているのだと思う。確固たる自信と自己評価を持っていない人は、他人からの批判、叱責、無視に対しては弱い。そういう自信がない人にどう対応すればよいのでしょう。私はそういう人に「かくあるべし」を押し付けてはますます、自信をなくし、自尊心やプライドを傷つけることになると思う。認めてあげる、受容して共感してあげる。よいところはほめてあげる。評価してあげる。森田理論の原点に立った対応が、その人の自信となり、前進していける力になると思う。これが子育て、対人折衝の基本だと思う。ぜひ身につけたいところである。
2013.06.19
コメント(0)
-
「生の欲望」を深耕する
躁の夫を持つ人の相談です。夫は私よりも2歳年上の会社員です。結婚して15年になりますが、急に気が大きくなり、はしゃぎまわるのです。過去も3回同じような状況になったことがあります。そのため会社も2度替わりました。ほとほと困り果てています。今回は約1か月前からはしゃぎ出しました。誇大妄想というのでしょうか、急に気が大きくなり、次からつぎへと高価なものを買いこんできます。ゴルフなどしたこともないのに、高級な用具をひと揃え買い込んできます。夜も寝ないで方々に電話をかけまくったり、友人や後輩を誰かれかまわずに誘って飲み歩きます。先日は会社の上司からも、「仕事が手につかないようだ。ミスも多いからしばらく休養するように」というお叱りを受けました。本人にいたっては極楽トンボで、他人の注意を全く意に介さず、今日も会社に出かけてゆきました。このように躁病になると、ハイテンションになり、不安の制御が全く効かなくなり、周囲の人に迷惑をかけることになります。欲望と不安のバランスが崩れるということは大変な問題を引き起こすことが分かります。早くお医者さんの治療を受けることが大事です。私はこのプログを始めて、「生の欲望」は一つの学習単元として独立させてもいいのではないかと考えるようになりました。というのは、欲望は常にバランスの上に正常に機能するということ以外に、もう一つ大きな意味があると思っています。我々日本人は、生の欲望を発揮することよりも、人の顔色をうかがい、周囲に迎合するという面が前面に出てくる傾向があります。対人恐怖症の神経質者の場合は特に顕著となります。自分の意思をしっかりと持つ、自分のやりたいことに積極的に手を出す。という態度に変えるためにはこの「生の欲望」の単元はしっかりと掘り下げて学習した方がよいと思います。
2013.06.18
コメント(0)
-
孫を甘やかせない
孫が我が家にやってきました。台風がやって来たようなものです。興味のあるものはなんでも引っ張り出します。網戸などはバリバリにされてしまいました。四六時中接している親は大変だと思います。親はつい子供を叱ってしまいますが、その時は少し聞いていますが、すぐに元に戻ります。そのうち兄弟げんかは始まるし、マンションの両隣、上下からクレームが来ないかと心配しました。私はできるだけ孫のそばにいてやり、ほとんどのことは自由にさせて、危ないものを振り回したり、高いところから落ちそうになったり、道路を走ったりすることだけは注意していました。これは孫だからできることであって、自分の子どもには「かくあるべし」丸出しで接してきました。法事に行って聞いたのですが、両親が働いていて、おじいちゃん、おばあちゃん子の家がありました。手とり足とりつきっきりで子守りをしているそうです。あまり甘やかせずに、好奇心が旺盛で、自立心や積極的な子どもに成長するように願うばかりです。ともすると風邪をひかないようにと子供に厚着をさせてしまう事があります。登校、下校途中の事故が心配で車で送り迎えする人がいます。外で遊ぶと風邪をひいたり、ケガが心配で家の中にいっぱいおもちゃを与えて家の中で遊ばせる人がいます。自転車を買うと交通事故に遭うのが恐ろしいと、買い与えない人がいます。子供が病気になり、お医者さんが子供に症状の事を聞いているのに、子供の受け答えを制して、親が説明してしまう事があります。これらは子供のためではなく、親が不安と向き合う事が出来ないのです。そうした不安が心の中にあると、その不安を打ち消すために、子供たちの心を無視してしまうのです。子供たちにとっては、いろんな経験をする機会を奪われ、自主的に活動するチャンスを取り上げられることになります。子供の成長にとってはマイナスに作用してしまいます。親が不安を取り去ってスッキリと安心しようとすると、子供に大きなマイナスの影響を与えてしまいます。親が森田理論を応用して不安を持ちこたえるということが、実践できるようになるとよいと思います。
2013.06.17
コメント(0)
-
竹村健一氏
昔よくテレビに出ていた竹村健一氏がこんなことをいっていた。「人間が人と同じような行動をするのは、多くの場合、そのことを本当にやりたいからではなく、人と同じようにしていないと、人から責められたり、いろんなことを言われたりするからだ。普通はそんな状態に耐えることができない。そのため、自分の気持ちを殺して、無理にみんなと合わせて同じことをやっている」そして発想を変えてプラス思考で生きていくことを提案されている。「たとえば、今、恋人がいないとか、恋人ができないと悩んでいる人がいたとする。それならば、他の人たちが恋人とデートで使っている時間を、仕事でも趣味でもスポーツでも自分がやりたいことに使えると考えてみればいいのだ。また、デートに使う資金を、自分のために投資できる。現在、人とうまく付き合えないことで悩んでいるのならば、うまく付き合おうと考えようとはせずに、思い切って付き合わなければよいのだ。そして人と付き合うことでとられる時間やお金を、自分のやりたいことに投資してみることである。」自分の意思に反して、義務や指示で面白くもないことをイヤイヤやるのではなく、自分のやりたいことに目を向けて、自分を大切にして、自分本位に生きていくことを勧めておられる。これは森田理論では、生の欲望は人に左右されないで、自分の中から湧き出してきたものが本当の生の欲望だということです。そうでないことろからでてきた生の欲望は、本当の意味の生の欲望ではありません。自分を追い込んだり、苦しめるものにすぐに変化してきます。大変参考になります。
2013.06.16
コメント(0)
-
強迫行為について
確認行為で悩んでおられる方は明念倫子さんの本をお勧めします。「強迫神経症の世界を生きて」です。ガスや電気、鍵の確認行為を何度もしないと気がすまないという人は、普通の人と比べると次のような特徴があります。普通の人でもたとえば鍵が閉まったかどうか気にしています。でも「ガチャ」という音を聞くと、心配はしていても大丈夫だと納得しています。そして不安があっても出かけていくことができるのです。ところが確認を繰り返す人は、大丈夫だとは納得ができないのです。音で確かめても、不安の気持ちが優っているのです。その不安の気持ちにとらわれてしまうのです。不安の気持ちにとらわれていけばいくほど、神経症の深みにはまっていくのです。不潔恐怖で何回も手を洗わないと気がすまない人もそうです。外出してバイ菌や細菌がついたのではないかということにとらわれる人もそうです。明念さんは、生泉会という強迫行為の自助グループを作られて学習されています。その中で普通の人のように不安だけども、人間に自然に備わった大丈夫だと反転するその気持ちの癖をつけていくことがポイントだといわれています。また五感(見る、聞く、味わう、触れる、臭う)を信頼する態度をつくことが大切だといわれています。まず、確認行為の際のドアの閉まる音、鍵の閉まる音、ドアの閉まった感触などに意識を集中してしっかり味わうようにします。次に何度か確認したら、「閉まっている」という事実は湧かなくても「確認した」という事実は認識しているのですから、その事実にすがってそれ以上は確認行為はしないようにすることが大切だといわれています。強迫行為をともなう強迫神経症は、生活の発見会の中に強力な味方がいますので、ぜひ参考にしてください。
2013.06.15
コメント(2)
-
事実は両面観で見ること その2
私は先日中古車を買いました。一週間後、バッテリーがあがってエンジンがかかりません。どうしてこんなことがあるのだ。欠陥車だったのだろうか。いらだちがどんどん膨らみました。販売店に連絡するとそんなはずはないというのです。またすぐに対応はできないなどというのです。怒り心頭です。大事な約束があったのですが、電話で断りキャンセルました。二時間ぐらいしてやっと充電器を持って来てくれました。私はもうバッテリーを替えるつもりでいました。でも原因が分かりバッテリーは替えなくて済みました。それは慣れないものでスマートキーでドアを閉めたのですが、後ろサイドのドアが完全に閉まっていませんでした。それでバッテリーが上がってしまったのです。いつもでしたらそんなドジな自分が嫌で、自己嫌悪してしまいます。自信がなくなってしまいます。運が悪い自分、ついていない自分に嫌気がさしてしまうのです。そこにはもはや事実には目が向いていなくて、自分のふがいなさばかりに目が向いているのです。この時はこの両面観を応用してみました。この失敗は、今後のことを考えるとよかったのではないか。よかった理由を考えてみたのです。一回失敗したので二度と同じ失敗はしなくなる。この学習によって次からは慎重になる。つまりこの件でロードサービスのお世話になることはないはずだ。自宅の駐車場だったので助かった。外出先でバッテリーあがりにならなくてよかった。今度からはスマートキーに頼らずきちんとドアを点検しよう。スマートキーの使い方を教えてもらってよかった。車の仕様書を読んでみよう。すると今までのように自分を責めて落ち込んで、長くイライラすることはありませんでした。これをさらに応用して、今度何か問題が起きた時、問題が起きて「よかった」ということを考えてみようと思いました。悲観的、否定的なことは考えずに、困った問題が起きて、まず「よかった」といってみる。そしておもむろに「よかった」理由を無理にでも考えてみるのです。そうするためには事実をよく観察しないと「よかった」という理由は見つかりません。このようにしてよかった理由、助かった理由を考えてみることによって事実はより正確につかめるようになるのです。みなさんも実践で確かめてみてください。
2013.06.14
コメント(0)
-
事実は両面観で見ること その1
事実は自分の一方的な主観だけで見てはいけません。私たちが事実をみるときは悲観的に、否定的に見る傾向があります。この見方が我々を苦しめているのです。世の中のあらゆる出来事はそうなるべき必然性があって、事実となって我々の目の前に現われています。けっしてあなたを困らせてやろうとか、いじめてやろうとして事実が発生するあるわけではありません。あなたがその事実に対して価値判断をおこない、腹が立つとか、不安だとか、運が悪いとか、ついてないとか思っているだけなのです。つまり事実を悲観的に、否定的にみているのは、あなたがそのように一方的に勝手にみているだけであり、その思いはあまりにも偏り過ぎています。つまり誤った見方をしていることになります。ほとんどの人はそのことに気がつきません。自分の感じたこと、考えたことが正しいと思っています。それ以外の考え方はないと思っています。この考えを修正していけるととても楽な生き方に変わってきます。これは森田理論では両面観の学習となります。森田理論学習のポイントです。事実をより正しく見ようとすれば、楽観的、肯定的にも見なければいけません。否定的な面と肯定的な面の両面を過不足なく見ることができた時が、事実をよく見たということになります。神経質者の場合は、物事を悲観的に、否定的に見る癖が身体の中に染みついていますから、そうした視点からすると、否定的な面はこの際見なくてもよいと思います。それよりも力を入れることは、事実を楽観的に、肯定的に見ようと努力する態度の養成です。そうすればやっとヤジロベイがバランスをとってつりあうような状態になります。調和が生まれてきて、事実を正しく見るということにつながります。これを実際の生活の中で自然にできるようになるまで意識して取り組んでみましょう。次に分かりやすい例を出してみましょう。
2013.06.14
コメント(1)
-
欧米と日本のかくあるべしの違い
欧米と日本の「かくあるべし」教育は違いがあります。欧米の「かくあるべし」は、○○してはいけない。つまり「禁止」です。タブーを犯してはいけないという「かくあるべし」です。だから「禁止」された事以外は、基本的に何をしてもよいという考えなのです。目をつぶりますから、どんどん興味のあることには挑戦してみなさいという事です。自由の幅が大きいということになります。日本の「かくあるべし」は、○○しなければいけない。指示や命令に従わせるという「かくあるべし」です。指示された事以外はしてはいけないということになります。自由自在に手を出してみるという事は、基本的には許されません。そしてきちんと指示、命令に従って行動しているかどうか監視されています。日本の「かくあるべし」は身動きがとれなくなり、窮屈になります。ストレスがたまってゆきます。そのストレスをためたままにしておくと自己崩壊してしまいます。そのストレスを解放する過程で多くの問題が噴出してきます。欧米は対人恐怖の人は日本人に比べて少ないといわれています。また、日本に多いいじめの問題はないそうです。これは「かくあるべし」のちがいからくるのかもしれません。
2013.06.13
コメント(0)
-
ひきこもりについて
引きこもりについては和歌山大学の保健管理センター宮西教授の活動を紹介したい。「引きこもり回復支援プログラム」が大きな成果をあげている。引きこもっていた和歌山大学の学生は100%近くが卒業し社会に復帰した。また5年以上引きこもった一般の人も、その84%が半年以内に外出できるようになったそうです。ポイントは、引きこもりは親子間が、密着しすぎている。密着しすぎている親子関係の中に、第3者が入り込んでいって、空気を変えることが大切だというこのプログラムは4つの段階がある。ステージ1では、医師などの専門家が直接出向いて、当事者を診察する。統合失調症、発達障害、うつ、対人恐怖症、視線恐怖症の診たてをおこなう。そして医療介入が必要なケース以外のひきこもりの人に対して、メンタルサポーターの「アミーゴ」(スペイン語で気心の許せる友人、仲間)を派遣する。アミーゴの派遣は1回2時間で週2回おこなう。利用料は1時間1500円。半年をめどに契約をおこなう。ステージ2では、医師などの専門家が引きこもり当事者と面会。当事者とアミーゴが一緒に外に出られるように仕向ける。その際不安や緊張感が高まるので薬物療法を一時的に行う。第3ステージは、外出した当事者が、安心して集う「居場所」を設定してあげる。アミーゴと一緒に数カ月は参加してもらう。「うるさくない専門家がちょこちょこ顔を見せて、みんなで一緒に遊べるような場所」が理想的であるという。仲間作りのきっかけを作るのだ。第4ステージでは、ソーシャルスキルとコミュニケーションの問題をはかり、社会に復帰させる。当事者は仲間と遊んだことがない、恋人ができたことがない、異性と話したことがないという人が多い。そこでこの「居場所」で集団療法によって、人間関係やコミュニケーションの能力を回復させていく。時間をかけて粘り強く行っていく。こうした活動が成果をあげているのです。この活動は九州大学、神奈川工科大学などでもおこなっているそうだ。詳しくはホームページをご覧ください。
2013.06.12
コメント(0)
-
神経症になってよかった
私は小さいときから人見知りや人の思惑が気になるたちであった。社会人になってからは最悪であった。訪問営業の仕事なのに、人に会うことができない。人より実績をあげたいのに、足が仕事先に向かないのだからとても苦しい。自分に大きな問題があると思っていた。最近、かっての同僚たちが、次々に定年を迎えている。私は、驚きでいっぱいである。どうしてあのくるしい、訪問営業の仕事を約40年も続けてこられたのだろうか。自尊心を傷つけられるような日日をどうして乗り越えたのだろうか。不思議である。断られて苦しいながらも、なぜ次の訪問先に足を向けることができたのか。私は9年で退職しました。でも、私は神経症で苦しんだおかげで森田理論に出会った。これはとても幸運であった。神経症に苦しまなかったとしたら、森田は知らずに死んでいったことだろう。森田で出会ったおかげで、人生の半分以上は、死んだも同然の人生であったが、人生の後半はこの上ない至福の時間を過ごさせていただいている。また、このプログで自分のように長く苦しまなくて、早く充実した生き方を身につけてもらいたくて、森田の考えを多くの人に伝えたいという強い意欲も出てきた。考えてみると、大きな壁にぶっかって、それを乗り越えようとするプロセスが、後で振り返ると人生の醍醐味なのかもしれません。葛藤や苦しみを抱えることは決して悪いことではありません。そこから縁が生まれるのです。森田を学習している人は素晴らしい人がたくさんいますので、ぜひお近づきになって、おこぼれをいただく姿勢がよいと思います。
2013.06.11
コメント(1)
-
物忘れと考える力
先日の集談会で聞いた話だが、40代ぐらいから多くの人は物忘れが少しづつでてくるという。50代、60代、70代とどんどん増えていく。歳をとるとメガネをはめているのに、メガネを探すこともあるそうだ。これはどうも受け入れていかざるをえないようだ。記憶をつかさどる脳細胞が少しずつ破壊されているのかもしれない。メモを活用したり、目につくところに置いたりして対処するしかない。でも、考える力は人によって差がでてきます。脳が成長する人、退化する人がでてくるのです。先日も100歳近い染物師のドキュメンタリー番組があったが、後進に指導したりして我々と全く違わない。脳が元気そのものであった。ところが、これには毎日そうゆう脳を鍛える生活をしていないとすぐに退化してくる。東北大学の川島教授などがその方面の第一人者だ。宇宙飛行士が宇宙から戻ってくると、筋肉や骨がすごく痩せてくるという。つまり廃用性萎縮というものだ。それも短期間で急速に進行するという。毎日退屈だなあ、なんか楽しいことはないかなあ、テレビ三昧、ギャンブル三昧の生活は脳の廃用性萎縮が起こり、認知症などに陥りやすいのではないか。集談会はこうゆう話がたくさん聞ける。それが刺激となり、自分なりにブログなどで発信できる。うれしいことだと思う。集談会はそれぞれ独自に運営されている。運営の仕方によってずいぶん違うのかもしれない。
2013.06.11
コメント(0)
-
イチローに学ぶ
イチローの生活から森田理論に関係することを整理してみよう。イチローはルーティーンを大事にする。毎日決まった時間になすべきことを淡々とこなしてゆく。それを継続している。イチローが本格的に野球を始めたのは小学校3年生の時からである。相手は父親だった。学校から帰ると、軽いキャッチボールから始める。次は50球前後のピッチング。その後はティバッティングに移る。210球をこなした。そして内野ノックと外野ノックをそれぞれ50球をこなした。最後はフリーバッティングである。我々でいえば日常茶飯事のなすべきことを丁寧に継続していったということである。次にイチローはバットやグラブを驚くほど丁寧に磨く。道具を丁寧に扱う習慣のないメジャーの選手にはこの光景が奇異に映るらしい。生活用品にしても衣類にしても少々高くても長持ちのするものを買うという。そしてそれを丁寧に扱い、いつまでも使い続ける。森田でも「物の性を尽くす」という考え方をする。その物の持っている価値をどこまでも活かし尽くすという考え方である。自分についても、無い物ねだりをしないで、いま備わっている能力や力をどこまでも活かしてゆくという事である。さらにイチローは小さな変化を見逃さないで、それを分析して次のバッティングに活かすことを常に考えている。だから大活躍したあと浮かれたりすることはない。その余韻に浸っていると、慢心により感覚が鈍ってくるという。森田では一つのことにこだわらないで、なすべきことややりたいことを実践して、感情を変化流転させて、自然の流れの中で無意識化していくことを目指しています。またカメレオンのように外部の変化に対しては、自分を変化させて外部に合わせてゆこうという考え方です。外部の変化を自分の思い通りに、コントロールしていくという考え方ではありません。
2013.06.11
コメント(0)
-
自覚を持つということ
森田では「事実本位」ということを口がすっぱくなるほど言います。だが森田理論を学習して「かくあるべし」体質を、「事実本位、物事本位」の体質に変えなければならないというような大それた考えはやめた方がよい。そんなことはできない。難しい。そもそも多くの人は「かくあるべし」体質は生まれてこの方20年以上もかけて身につけたものである。身体の芯から染みついているのです。過去を変えることができないのと同じように、自分の体質は変えることはできません。その体質を抱えたまま生きていくしか方法はないとのです。森田理論を学習する人はなんとしても症状を克服したいという強い意志を持っている。しかしその願いはかなえられることはないでしょう。ではどうしたらよいのでしょう。できることは、自分は変えることはできないという事実を認めることです。そうした状況を自覚することです。すると結果として自分を救うことが出来るのです。逆説的なことをいいますが、救われることはないという事実を正しく認識することが、結果として自分が救われるという事なのです。変な理屈かもしれませんが、これが真実なのです。事実本位でどんな事実も認める、受け入れるということができれば、「かくあるべし」はどんどん小さくなってきます。その方法論は事実を4つに分けて、それぞれの心構えやノウハウは今まで投稿してきました。しかし、それが先行しては、逆に「かくあるべし」がさらに強化されることになります。つまり「かくあるべし」を小さくしてゆくためには、強い「かくあるべし」を持っている自分がいるという自覚を深めるということが出発点です。基本的にはこの出発点に立たないと先には進めないということです。「かくあるべし」の実態、どうして「かくあるべし」が生まれてきたのか、そうした人間の特徴、葛藤や苦悩の現実等などの学習は欠かせません。
2013.06.10
コメント(0)
-
芝生の庭を考える
今日集談会に参加して二次会の居酒屋で貴重な話を聞きました。私はこの居酒屋での懇親会で役立つ話を聞くことが多く、欠かせないものとなっています。私は田舎に親が亡くなり、誰も住んでいない家を管理しています。その庭に芝生の庭が6坪ぐらいあります。さざんか、きんもくせい、かいずかいぶき、柊もくせい、ユズリハ、まき、つつじ、シャクナゲなどを植えています。どの木も大きくなりました。生垣としてレッドロビンを植えています。レッドロビンはすぐに成長しますが、剪定バリカンで何とか対処できます。でも芝生の雑草には手をやいています。管理できないのです。雑草を引っこ抜いたり、草刈り機で刈り取ったりしています。それでも次から次へと雑草が生えてきます。憎らしいぐらい生えてきます。私は当初芝生を植えてゴルフ場のような芝生、野球場のような芝生、ヨーロッパの庭園のような芝生をイメージして庭作りを考えていました。でも結局うまくいきませんでした。雑草に手をやいて、ついに芝生を止めてコンクリートで固めて、上に砂利を敷こうかと考えていました。今日聞いた話では、ゴルフ場の芝生は大変手入れもされてきれいにみえます。しかし実態は何種類もの除草剤を散布して、雑草を退治しているとのことでした。そのおかげで、周辺の住民はとても大きな被害を受けているらしいのです。それであんな芝生が保たれていたのか。初めて気がつきました。これはゴルフをする人も影響を受けないはずはないと思います。考えてみればヨーロッパのように植物があまり育たないところで、生命力の強い芝生を育てるにはよいかもしれません。日本のような高温多湿なところで、どこからでも雑草の種が飛んで来るところでは無理なことです。日本は初夏から秋にかけて雑草が次から次へと生えてくる土地柄です。そんなところでそもそも無理をしてヨーロッパのまねをして芝生を植える必要があったのかということです。人間の勝手な思いつきで、芝生を植えることは後でさまざまな問題を発生させて、植えた本人が苦しむことになるのです。日本で芝生を栽培することは少々無理があるということです。それならむしろ雑草を思う存分生やして、その中に我々の食料となる植物を植えて共生させればよいのではないのか。と考えさせられた次第です。まだ考えがはっきりとしたわけではありませんが、考えるきっかけをいただいたことに感謝したいと思います。
2013.06.09
コメント(0)
-
長所を見つける
山崎房一さんが子供たちにテストをしました。長所を3つ、短所を3つ書きなさいというものです。子供たちの半数は長所を1つも書けません。みなさんはいかがですか。できたら自分の長所を10個ぐらい書いてみましょう。そして身近な人の長所も10個ぐらい書いてみましょう。長所を一つも書けない子供は、ドアが開閉されるたびにそっちの方向へ目をやり、プリントを配布する様子にも何か落ち着きがありません。特によく目立つのは、先生に対する態度です。彼らは、明らかに先生の存在を気にかけています。先生の発言内容ではなく、先生の存在に注意を向けているのです。そういう子は聴き洩らす、意味を取り違える、早とちりをするなど学習能力が落ちてしまうのです。彼らは先生の存在を気にするあまり、「さされないかな」「ノートの中をのぞかれないかな」、ひどい例になると「先生は僕のことが嫌いかな」と余計なことばかり考えています。どうして長所より短所ばかり気にかけているかというと、家で両親から、叱られてばかりいるからです。指示、命令、禁止で動かされているからです。森田理論でいう「かくあるべし」の押し付けです。(いじめない、いじめられない育て方 PHP文庫より)
2013.06.09
コメント(0)
-
奇跡のリンゴ
本日この映画を見てきました。このモデルになった木村秋則さんのことはこのプログで既に紹介しました。今日見た感想です。山崎勉が木村家のおじいちゃん役。戦争中ラバウルに出征した経験を持っていた。ラバウルは玉砕したのだが、運よく日本に帰れたのだろう。渋い演技が光る。役者としては、高倉健、役所広司などと遜色ないと思う。圧倒的な存在感がある。木村さんの無農薬、無肥料の挑戦は、農薬散布で奥さんが具合が悪くなることから思いつかれたようです。無肥料、無農薬のリンゴ栽培の挑戦で、10年間無収入で家族に苦労をかけていたが、女の子3人はそれぞれ立派に成長していることに感動した。木村さんは山になるクルミの木に全然虫がつかない、病気にならないということにヒントを得て無肥料、無農薬栽培を成功させていた。その内容を知りたい人は映画を見ていただくとして、今の農業は、米作りにしても野菜作りにしても一般的には肥料、農薬、除草剤をふんだんに使用している。心ある生産者は心に痛みを感じているのである。中国の野菜や食べ物は敬遠している人が多いようですが、日本も決して安全とは言えない。その結果として一つには2人から3人に1人はガンになるのではないのでしょうか。これは食べ物が、命をつなぐものではなく、儲けるための手段として生産されているからかもしれません。
2013.06.08
コメント(0)
-
元中日落合監督に学ぶ
元中日の落合博満監督。どんな人間でもよく見ていると何かしら取り柄があるという。たとえば岩崎達郎選手。打率はほとんど1割台。それでもずっとプロで飯を食っている。それは守りに関してはレギュラーに匹敵する力を持っているからだ。落合監督は彼を2009年に1軍に引き上げてから、2011年終盤まで一度もファームに落とさなかった。2010年は出場78試合、85打席しか打席に立っていない。ほとんど守備固めで、打率は1割8分である。打率から見ると、他球団なら首になるような選手である。しかし彼は守りがいいので、チームに必要不可欠な選手だった。他球団からトレードを申し込まれても絶対に出せない選手だった。落合監督は岩崎選手の守備を高く評価して、評価査定を上げた。岩崎選手は契約更改で驚いていたという。見る人は見ているのである。つまり一軍のレギュラー選手ではないが、スーパーサブの選手なのだ。そうゆう選手は「守り勝つ」野球を目指していた中日にとっては欠かせない選手だったのである。落合監督は、「打つこと、守ること、走ることなんでもいい。肩の強さや体力でもいい。これだけは絶対に負けないという一芸を磨けばプロで飯を食っていける可能性がある」という。これは我々に自信を与えてくれる言葉だ。これを我々に置き換えると、我々は元々神経質という素晴らしい性格特徴を生まれながら持っている。それを認識して、自分のできることや長所を育ててゆけばよいということになる。しかし残念なことにダイヤの原石を見て、これを磨けば価値があるということに気づいている人が少ない。むしろ捨てようとしたり、鉄などと換えようとしたり、簡単に人にやってしまっているような人が多いと思う。神経質の性格特徴の学習では、性格の両面性をよく理解してほしい。森田理論で神経質の性格特徴をよく学習して、活かしていくのが我々の目指す道だと思う。
2013.06.08
コメント(0)
-
自分本位の生き方 その3
そのためには、森田理論は次のような提案をしています。まず興味のあること、好奇心の湧いてきたものは、尻軽になんでも手を出していくことです。一つのことに手を出すと、自分に向いているか、向いていないかは判断できます。向いていることは、弾みがついてさらに行動が広がっていく可能性があります。そういうチャンスは何度もやってきません。そのチャンスがやって来た時は素早く手を出すことが大切です。森田先生は自分の専門分野でない講義を依頼された時、まずイエスと引き受けて後からどうするか考えたといわれています。次にそして手をつけたことはそのものになりきることです。どんな些細なことでも、真剣に取り組むことです。一心不乱に創意工夫をしてゆくことです。このような態度で生活してゆけば、自分のやりたいこと興味のあることは必ず見つかります。それを大きく育ててゆけば、他人の思惑や「かくあるべし」に振り回されることなく、自分を主体にした自立性のある生き方ができると思います。そうなれば、「たかが人生、されど人生」という気持ちが湧いてくるでしょう。生きることが楽しくなり、自主性、積極性がでてきて、プラスの好循環が始まると思います。
2013.06.07
コメント(0)
-
自分本位の生き方 その2
結局そういう人は、自分で自分のやってみたい欲望に、勝手に歯止めをかけておられるのです。いくら歳をとっても、多少危険を冒してでも、三浦雄一郎のように好きなことを存分にして死ぬ方がいいのではないでしょうか。面白くもない人生を送っている人は、自分に素直でない人です。自分のやりたいこと、興味のあることに対して、時間がない、金がない、格好が悪い、体力がない、頭がついてゆかない、仲間外れにされてはいけない、みんなに嫌われてはいけない、などと自分でさまざまな言い訳を作っている人です。そして楽しく、生きがいを持って行動する人生を回避しているのです。これでは人生は苦痛でしょう。自分の主体性がなく、他者に依存しているのです。進学を決めたり、就職先を決めたり、結婚相手を決める時でさえ、親兄弟、先生、友人などの意見に左右されているのです。好きでもない分野に進み、好きでもない仕事や職場にしがみつき、結婚相手も高学歴、高収入、高身長で判断しているのです。そしていつも愚痴をこぼしているのです。そこには世間体、見栄だけがクローズアップされ、自分の気持ちが全く感じられません。気が進まないことを無理やりしているのですから、気持ちが晴れることはありません。夫婦ともそのような状態で、子供の教育費、家のローン、車のローンなどに追われてアップアップの生活です。それは生きるために必要悪だと多くの人がいいます。それは一面真実ですが、私の言いたいのは、そのために自分の意思を殺してはいませんかということです。そのために自分を偽り、自分のやりたいことを犠牲にして生きていくことが、はたして幸せな生き方でしょうか。森田では自分の意思や意向を第一番に大切にして、自分に素直な生き方を目指すことを教えてくれています。森田理論学習によってそんな生き方を身につけませんか。
2013.06.07
コメント(0)
-
自分本位の生き方 その1
私は日本に生れてよかったと思っています。戦争もなく食べるものも恵まれています。そして自分のやりたいことがその気になれば、ある程度は何でもできるような状況にあります。もし自分の人生に絶望しておられる人がいるとすると、それは考え方を少し変えるだけで素晴らしい人生に転換することができます。そして一生を終える時、とても幸せな人生だったと感謝して死ぬことができると思います。そのためには人の思惑によって生きることを止めて、自分のやりたいこと、興味のあることにフォーカスして生きていくことだと思います。よい意味での自己本位に生きていくことです。人に迷惑をかけない、将来がこれ以上悪くならないのだったら、できうる限りそうした方がよい。集談会に参加されなくなった人に電話をかけてみました。すると私はもう年だから、参加することがはずかしいといわれるのです。でも集談会の意義は認めているといわれるのです。とても残念だと思いました。集談会はよいと思われるのに、どうして世間体を気にする必要があるのでしょうか。生涯森田で好きな学習を続けられたらいいのではないでしょうか。後輩のために一肌脱ぐわけにはいかないのでしょうか。意義を見出している人なら、這ってでも出てくるべきだと思うのです。それがあなたの為でもあり、人のためにもなるのです。集談会で、あなたは歳をとり過ぎているから参加しないでくれ、というような人がはたしているでしょうか。むしろ反対に、含蓄のある味わい深い話に、聞き惚れる人がいると思うのです。
2013.06.07
コメント(0)
-
西郷隆盛に学ぶ
よく会社などで「その場の空気を読んで発言するように」「出る杭は打たれる」「郷に入れば郷に従え」などといわれる。これは自分勝手な行動は慎め。基本は集団の意思に合わせて言動をおこなうという戒めだろうか。私は自分の意思を封印して、人の思惑に合わせるということをいっているとしたら賛同できない。神経症で苦しんできた体験からすると、人の思惑を優先して生きてきた結果、今までずっと苦しんできたのです。この先もっと人の気持ちを優先させなければならないのか。お前はまだ苦しみようがたらないから、もっともっと苦しめといっているような気がするのです。自分がみじめになるだけです。この問題を解決する手掛かりを森田理論学習で見つけました。森田先生曰く。「西郷隆盛は西南の役で死んだが、彼はもともと戦争には反対だった。そうした自分の意見はしっかりと持っていた。しかし行動としてはみんなの意見に従ったのだ」西郷隆盛はただ単に、取り巻きの人たちの意見を取り入れたのではない。自分の意志を大事にしていたのである。その間とても葛藤があったと思う。これは連合艦隊司令長官山本五十六がアメリカとの戦争に反対していたというのとダブります。この話しは我々神経質者にとって学ぶべき点が多い。森田理論の根幹にかかわる問題だと思う。つまり自分の意見を持たないで、相手に付和雷同するのではなく、自分の意見をしっかりと持っているということが大切なのです。そのうえでの行動なのである。ここがポイントである。自分のこうしたいという気持ちをまずしっかりと持つということ。しっかりと確認するということ。他人がこうしようと言ったから、私は意に沿わないけれどもそれに従うというのではない。いつも出発点は自分の気持ちなのである。これは常に自分の感じから出発して、次に理知で調整するという考え方につながる。そういう自分の立場を固めて、自分の意思を通したい。そうかといって相手の意思を全く無視するということもできない。どうしょうかと悩むのである。突破口を求めて創意工夫するのである。こうした行動スタイルの流れを確立することがとても大切です。森田の精神拮抗作用そのものの考え方です。そうしたスタイルを推し進めてゆけば、いつも人の思惑に左右されて、重苦しい生活から抜け出すことができます。森田理論学習を深めてゆけば、必ず身につけることができます。
2013.06.06
コメント(0)
-
手塚治虫氏の境遇に柔順なれ
宝塚歌劇場の近くに手塚治虫記念館がある。手塚さんは子供のころからの山をかけずり回り、自然の中で育ってこられた。スケッチを見ると素人離れしている。でもすんなりと漫画家になれたわけではなかった。育った時代はちょうど戦争の真最中だった。親は何度も漫画を書くことを禁じた。また学校の先生も、「漫画を描くのは非国民だ」叱責した。漫画どころか教科書を読むことさえ、「国策協力をせずに自分の勉強を優先させることはけしからん」というような風潮が日本全国を覆っていた。やりたいことがやれない。職業選択の自由はなく、多くの人が戦場に送られた。相当なストレスを受けていたのである。やむなく体の弱かった手塚さんは、親に進められて軍医を目指した。医学博士にまでなっている。そういう意味では自分の意に添わなくても、与えられた境遇の中で精一杯努力をされたのである。そして戦後すぐに漫画家としてデビューされた。昭和21年のことである。その後の活躍は言うまでもない。後年手塚さんは次のように言われている。「何年かの医学生だった経験、曲がりなりにもインターン、病院勤めをした経験は無駄にはなりませんでした。そういうものがぼくにもっと人の命という事を真剣に考えさせてくれたのです。」その後の「ブラック・ジャック」という作品に活きている。自分の置かれた状況に不満を抱かず、境遇に柔順になって、その時々で精一杯努力をする。その努力の過程に幸せがある。努力即幸福はこのことをいうのである。
2013.06.05
コメント(0)
-
いじめられっ子とお母さん
山崎房一さんの本からエピソードをひとつ紹介します。A子さんがいじめられ始めたのは、中学1年の3学期からでした。7,8人のグループから目の敵にされ、「臭い」「ブス」毎日のように悪態をつかれ、ときにはビショビショに濡れた雑巾を投げつけられたこともあったという。お母さんはA子さんがいじめられて帰ってきても、A子さんがその理由をうまく説明できないと、「あなた、頭がどうかしちゃったんじゃないの」とうすら笑いを浮かべていたというのです。同情することは全くありませんでした。そのいじめっ子たちは家に電話をかけてきて、お母さんに、「A子を出せ」とA子さんを呼び捨てにする無謀ぶりだったそうです。そのたびごとにお母さんは、「A子、電話」と、その受話器をA子さんに投げ捨てるように渡していたそうです。A子さんは、いじめっ子に「違うわ、それは誤解です。ごめんなさい。そんなこと言われても」としどろもどろ、時には涙を流していたそうです。お母さんの態度は、A子さんがいじめっ子と対峙しなければいけないのに、後ろから石を投げつけているようなものです。後ろ盾を失った子供はとてももろいものです。戦闘意欲は失われ、自己否定の強い人はほぼ立ち直ることはないでしょう。このお母さんは、このことを山崎さんに相談して態度を変えました。演技をしたのです。学校でA子さんがいじめられ、先生が注意を与えたというのですが、この先生が、「いじめる方も悪いが、いじめられる方にも問題がある」と発言したというのです。お母さんは学校に乗り込み先生に抗議しました。先生はいささかあわてたそうです。家に帰って娘に一部始終を話して言いました。「お母さんはどんなことが起こってもあなたの味方ですからね。」A子さんは目を丸くしてお母さんの顔を見つめ涙をこぼしていたそうです。それ以降A子さんはいじめっ子に対してびくびくすることはなくなってきたというのです。お母さんとの連携が、子供を強くしました。子供たちは、両親の愛の言葉に触れるとたちまち勇気を取り戻すのです。森田理論を学ぶものは、このエピソードに学ぶことは多いと思います。私たちもかくあるべしが強いだけにそのような対応をとりがちです。でもどんなに問題を抱えている人であっても、その人の味方になってあげること、その人の立場に立って応援してあげること。それが森田理論の事実に従うという事ではないでしょうか。
2013.06.04
コメント(0)
-
ユーモア小話
生きがい療法の伊丹仁朗先生のすごいところは、森田理論を学習だけに終わらせないところだと思います。森田先生の実践されていることは、難病治療の患者さんたちに具体的な実践として提示されていることである。その方たちは、生活の発見会の会員のように森田理論を深く勉強されているわけではありません。しかしながら実践という面では、一歩先をいっています。イメージトレーニング、体験学習として看護学校などでの闘病者の「一日教授体験」、富士登山、モンブラン登山、オーロラ体験ツアーなどがあります。これらは伊丹先生が森田先生の著書を読まれて発想された事です。その中にユーモアスピーチというのがあります。伊丹先生曰く、「ユーモアスピーチを作ることは、心理面で大変良い効果があるように思われます。なぜなら、日々ユーモアの題材はないかと、周囲の広い世界の方に注意が向かい、また、材料が見つかり話をまとめる過程は、川柳を作るのに似た創作体験ともなります。話をする際には心配、不安はそのままに、今現在の目標を実践する体験にもなり、自分の話で他人を笑わせ、愉快にすることで、人の役に立つという手ごたえを感じることにもなります。」ここで私が以前作ったユーモア小話をひとつ紹介します。題は「気丈夫な犬」です。犬の15歳といえば人間で言えば、100歳にちかい。昔、三浦友和だったような犬も今やその面影はない。散歩に連れて行けば、あっちによろよろ、こっちによろよろ。耳はたれ、シッポはだらしなく垂れて、息もすぐに上がり、昔勢いよく電信柱におしっこをひりかけていたのに、尿結石を患って出が悪い。とにかく、朝から晩まで寝そべっているのがよく似合う今日この頃。でも運動しないと、病気になるのでなんとかだまして散歩に連れ出す。しばらくすると、前から5歳ぐらいのメス犬がやってきた。人間で言えば30歳の熟女といったところか。すると今までだらしなくイヤイヤついて来ていたのに、急に飼い主の前に出て、耳をピンと立て、シッポをくるりと巻いて青年のように歩き始めたではないか。そして、チラチラとメス犬をみては、潤んだ目をして何回もまばたきをしている。ひょっとするとウインクをおくっているつもりだろうか。そして、不覚にもヨダレまでたらしている。げんきんな犬だね。しかし、メス犬が通りすぎた後は、すぐに元に戻ったのは言うまでもありません。チャン チャン
2013.06.03
コメント(0)
-
精神拮抗作用について
仕事するふりをするのに一仕事これは以前私の作った川柳である。人の思惑、特に自分を非難されたりするのが耐えられなくて、雑談の輪に加われず、いかにもいま仕事が忙しくて雑談などできないというふりを装っていたのである。心は仕事にはなく、みんなの雑談の内容に耳をそばだてて聞いていたのである。ああ、なんと情けない奴だろうか。と自分を卑下していたのです。さて先日こんな話を聞いた。電車に乗っていた時のこと。向かいの席に知り合いを見つけたというのです。相手も自分に気がついているのではないかと思うとどうしたらよいだろうとおもった。席を立って知り合いのところに行って言葉を交わした方がいいだろうか。そしらぬ顔をするのは気まずいし、そうかといって相手の顔を見つめて、目があった時うすら笑いをするのもなんかおかしい。無視して車内広告でも見ていようか。それとも寝たふりをしておこうか。いろんな考えが堂々巡り、居ても立っても居られないほどイライラしてきた。どうしてこんなことで悩むのかといっても、悩んでしまうのだから仕方ない。早速森田理論で考えてみよう。問題は自分のどうしようもない感情を、なんとかスッキリとしようとしていることである。不快な感情に向き合おうとしていない。味わうという気持ちがない。感情を受け入れようとしていないことである。つまり自分を押し殺してしまって、無理して相手に合わせていこうという態度が決定的に間違っているのです。この場合相手はどうでもよいのです。自分のイヤだなあという感情が大事なのです。そうした感情を持った自分を責めてはいけない。許してあげる。認めてあげる。いつもそのスタンスを維持すること。これにつきます。自分の感情を粗末に扱い、自分の感情に敵対する人は、自分のこうしたいという気持ちや意思までも粗末にしてしまいます。そして次第にそうした気付きがどんどん失われて、無気力、無関心、無感動な人間に変化してきます。人の思惑によって自分の行動が左右されてしまう人間になってしまいます。生きづらさを常に抱えて生きていくようになるのです。自分の人生ではなく他人の人生を生きていくようになるのです。森田理論では精神拮抗作用というキーワードがあります。それによると、この場合まず大切なことは、自分の感情、自分の気持ち、意思をしっかり信頼していくこと。まずはそれに沿って動くことを基本とすること。これが抜け落ちることが多いのです。次に外部の状況をよく観察して、その内容を把握していくこと。そして最後にその二つの調和点、妥協点を探すことを考えてみる。難関はいくつかありますが、この生活態度が身につけばぐっと楽な生き方ができると思います。
2013.06.02
コメント(0)
-
一人一芸のすすめ
私は趣味として昔懐かしいチンドンミュージックを携えて、主として老人ホーム、ディケア、地域のイベントなど頼まれればどこへでも出かけている。そこでいろんなアマチュア芸人と出会う。若いのはモダンダンスのグループくらいで、どちらかというと年輩の人が多い。楽器ではウクレレ、ケーナ、サックス、アコーディオン、三味線、その他の芸としてどじょうすくい、南京玉すだれ、傘踊り、銭太鼓、田舎芝居、日舞、フラダンス、手品、落語、民謡、ひょっとこ踊り、紙芝居などである。私はこの人たちの影響で、どじょうすくい、獅子舞、浪曲手品をほぼマスターしてしまった。サックス演奏と合わせて4つの持ち芸を名刺に刷り込んで配っている。この面では森田先生と肩を並べるまでになった。今はチンドン屋のイベントが多いのですが、ゆくゆくは出前イベントとして2人ぐらいで組んで、ちっと出かけて30分ぐらい楽しんでもらうような活動を月に2回から4回ぐらいのペースでできたらと考えているところです。毎日短時間ながら芸の練習もおこなっており、毎日とても充実しています。私はみんなに一人一芸を勧めていましたが、自分は一人四芸になりました。この手の同好会は探せばいくらでもありますので、みなさんもおひとついかがでしょうか。もうはじめておられる方には、失礼しました。
2013.06.01
コメント(0)
-
まず自分の意志を優先する
私の以前の体験です。上司から仕事を頼まれて、今日はコンサートの予約をしているので断りたいのだけれども、安請け合いして、「いいですよ」と引き受けたことがあった。その結果、深夜のサービス残業である。当然コンサートはお流れとなった。この心理は、もし「今日は用事あるので申し訳ないのですが、お引き受けできません」などといえば、上司から嫌われるのではないか。能力のないダメ人間と思われるのではないか。あるいはあからさまに文句を言われるのではないかと心配したのである。自分をないがしろにして、上司の思惑ばかり気にしているのである。これは森田理論に照らして考えてみると、間違った対応であることは一目瞭然である。そもそも一番大きな誤りは、そこには自分の意思が全くないことである。自分の気持ちを無視しているのである。自分は上司の仕事を引き受けたくない。自分の仕事で手一杯だ。早く仕事から解放されて、楽しみにしていたコンサートに行きたい。これが本音である。表面的には平静を装っていても、自分の気持ちに嘘をつくから、面白くない。自分が嫌になる。仕事が嫌になる。生きていくのが嫌になるのである。森田先生は感じから出発して、理知で調整して行動しなさいといわれています。この場合も一緒です。自分の気持ちを大事にして、その気持ちをよりどころとして行動することがとても大事です。そこがまさに出発点です。自分の気持ちを第一番に打ち出しておいて、それから上司から依頼された仕事に目を向けるのである。そしてこの場合どうすればよいのか考えるのである。間違っても上司のごきげん伺いを優先にしてはいけない。ここが肝心なとこだ。二番目として理知で調整するのである。調整するために考えるのである。これは歌舞伎や落語でいう「間」にあたるものである。神経質者はその「間」というものを作ることができない。これは自分の意志がないから作りようがないのです。歌舞伎や落語では「間」がないと、それこそ「間」の抜けた芸となるのはおわかりだろう。「間」をとって考えると、多分意固地になって自分の考えを一方的に通すことはなくなるだろう。また上司の要求を自分の意に反してまで引き受けることもなくなるだろうと思う。つまりその場、その時に応じた適切な双方の妥協点を探るようになるだろう。双方のバランスをとる方法を探るということである。双方が勝利者となるウィン・ウィンの考え方である。自分のこうしたいという気持ちを無視して、相手の思惑に合わせ、よく思われようと企てることは最初から調和が崩れてしまい、神経症の蟻地獄に陥ってしまうことをよく考えてみてほしい。
2013.06.01
コメント(0)
全42件 (42件中 1-42件目)
1