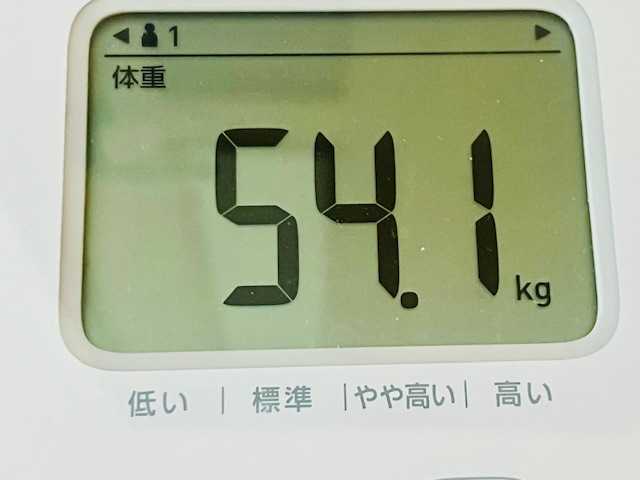2013年09月の記事
全50件 (50件中 1-50件目)
1
-
援助希求行動について
森田ではグチを言うのは、注意をそこに向け続けて症状を悪化させて、他人を悩ませるので言わない方がよいといいます。グチを言う人をダメな人と決めつけている面が強いように思います。でも、イライラや悩み、怒りや憎しみ、苦しみを自分ひとりで抱え続けるのは精神的によくありません。どんどん窮地に追い込まれて、終いにはもう手遅れとなってしまうことがあります。自分で自分の問題を解決できないときは、家族、友達、先生、専門家、自助組織などに相談したり、助けを求めることが必要です。弱音を吐き、他に助けを求めることを「援助希求行動」と言います。人間として自然な行為です。集談会にもそうした役割があります。だから今後はグチや弱音を吐くことを、人間に自然に備わった「援助希求行動」と呼んではどうでしようか。学校の教師は子供や親に振り回されて、大変苦しい思いをしておられる方がおられます。そんな時、「自分の受け持ったクラスは自分でなんとかするのがあたりまえ」と、問題をすべて自分ひとりで抱え込んだりすると、どんどん悪循環になります。最後には校長先生や同僚から、「あなた何をやっているの」「あなたがしっかりしないからこんなになったんですよ」といわれると、精神的におかしくなり、休職や退職に追い込まれる先生もおられます。一番いいのは先生同士で愚痴を言い合ったり、援助したり、励まし合ったりすることだと思います。それが不可能なら他の自助グループで助けを求めることが必要でしょう。とにかく一人で抱え込まない。悩みを相談する人を見つけること。必ずそんな自分に共感し受容してくれる人たちは存在します。そのうえで正しい解決方法のヒントをたくさん提示してくださることでしょう。神経症の症状に陥った人は、自分一人で解決策を求めて四苦八苦するよりも、早く森田理論で立ち直った人に助けを求めることです。生活の発見会にはそういう人が何人もおられます。そして集談会に集う人たちは惜しみない援助の手を差し伸べてくれることと思います。
2013.09.30
コメント(2)
-
知・情・意について考える
夏目漱石の「草枕」の出だしは次の言葉である。「山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」よくいわれる知、情、意のことである。理屈を言いだすと人間関係が悪くなる。気分本位になれば、物事は前に進まない。「かくあるべし」を持ち出せば、現実とはギャップが広がるばかりである。知、情、意のバランスをとらないと事は進展しないということを言っているのだろうか。森田理論で知、情、意を考えるときは、情、知、意の順番で理解するとスムーズに理解できる。森田理論では、いつでも感情から出発する。次に理性で調整して、感情と理知のバランスをとって意思決定する。そして行動実践という流れとなる。知が先にきては、症状が悪化するばかりで、治癒することはない。もう少し詳しく説明しよう。行動したり、何かに注意を向けていると感じがでてくる。喜怒哀楽、愛、憎しみ、欲望などである。それが脳に入ると、脳は活発に動いて対応策を探し出そうとする。その際動員されるのは、過去の楽しかった記憶や嫌な思いをした記憶、過去の失敗や成功した経験、さまざまな知識の集積などである。総合的に判断するのである。判断にあたっては、多くの記憶、多くの失敗などの経験が役立つ。つまりデーターが多いほど正確な判断に役立つ。またデーターは悲観的なものだけではなく、楽観的なデーターがバランスよく蓄積されていることが望ましい。より選択肢が広がるからである。こうして解析されたデーターをもとに我々は意思決定をおこなう。ポジティブな意思決定をする場合もあるし、ネガティブな意思決定をする場合もある。その時その場の状況による。臨機応変な決定ができることが望ましい。一般的にはポジティブな選択がよいといわれるが、簡単には決められない。そして意思決定に基づいて行動するのである。行動するということは、感じの発生、脳での判断、脳での意思決定という段階を経て実施されているのです。よく他人にこうしなさい、ああしなさいと行動を強制することがありますが、本人にとってはこのステップを踏まないで、いきなり行動を求められるということになります。これは自然の流れからはずれているということです。指示、命令による行動は軋轢を生みますし、無理やり押し付ければ自主的行動が押さえつけられて、周りの目ばかりを気にするようになります。感じから出発する。純な心の体得は、森田では大切な学習項目となります。
2013.09.28
コメント(0)
-
対人恐怖症の人へ言いたいこと
学校で友達とうまく付き合うことができずに悩む人が多い。また会社での人間関係で傷つく人も多い。森田でいう対人恐怖の人である。私もそうであった。学校ではいじめに遭ったり、無視されないようにいつも神経を使っていた。会社では仕事で会社に貢献するという気持ちよりも、会社での良好な人間関係作り上げることに最大の価値を置いていた。いずれの場合も頭の中の大部分は人から嫌われないこと、人からよく思われることで占められていた。おそらく90%は寝ても覚めてもそのことにエネルギーを使っていたと思う。森田を学習していて思った。もし頭の中でそのことに費やす時間や比率が70%、50%、30%、10%というふうに比率が低下してきたとしたらどうなるのだろう。そう考えただけで生きる力が湧いてきた。なるほどポイントはそこにあったのか。それでも人からバカにされる、非難される、無視されることはとてもつらいことだ。でも比率が下がっているので、いつまでもそのことに関わりあっているわけにはいかない。つまり視野狭窄になり自分で自分を追い込むことは避けられる。つらい、イヤだ、逃げ出したいという気持ちを抱えたまま目の前のことに手をつけていかなくてはならない。そのうち自分のやりたいことや好きなこと、得意なことを見つけ出せれば十分に生きていける。私は以前曽野綾子さんの次のような話を紹介した。寿司屋の大将でカラオケもへたくそ。ゴルフの腕前も最低。経済観念は全くない。教養というものもない。でもそれを笑いの種にされても悠然としている事が出来るのは、自分は寿司を握らせたらだれにも負けないという自信があるからだ。その自信に支えられて生きていけるのだ。高良武久先生も10年一つのことに取り組んでいれば、その道ではエキスパートになれる。そうなれば、人間関係に振り回されることはなくなるといわれています。人間関係で悩んでいる人は正面から解決しようとしてはいけない。外堀から埋めていくことである。日常生活は規則正しくなっているのか。食事の支度、洗濯、そうじ、後片付け、車の洗車、靴磨き、整理整頓、風呂やトイレの掃除、歯磨きはきちんとしているのか。子どもや夫婦、親子の対話はしているのか。友達や仕事仲間にたまには気を使って何かをしてあげているのか。対人関係で悩むのはいい。でもその前に今書いてきたことがほったらかしなら、そこにこそエネルギーを傾けるべきだろう。森田では生活のバランスという。日常生活、仕事、家事、趣味、社会生活、健康などのバランスをとった生活のことだ。対人で悩む人はバランスが大きく崩れて一つのことに偏っているのではなかろうか。バランスを意識していくことが、対人のとらわれから抜け出す大きなポイントとなる。これに「かくあるべし」を減らすということを身につければ、対人恐怖症から脱却できることをお約束します。
2013.09.27
コメント(0)
-
かたよらないということ
加島祥造さんは伊那谷の老子と呼ばれている。加島さんの著書に、「求めない」というのがある。誤解しないでほしい。「求めない」と言ったって、どうしても人間は「求める存在」なんだ。それをよく承知のうえでの「求めない」なんだ。食欲、性欲、自己保護欲、種族保存欲みんな人間の中にあって、そこから人は求めて動く・・・それを否定するんじゃないんだ、いや肯定するんだ。五欲を去れだの煩悩を捨てろだのと、あんなこと、嘘っぱちだ、誰にもできないことだ。「自分全体」の求めることは、とても大切だ。ところが「頭」だけで求めると、求めすぎる。「体」が求めることを「頭」は押しのけて、別のものを求めるんだ。しまいに余計なものまで求めるんだ。これは欲望の暴走の危険性のことを言っていると思う。食欲、性欲、自己保護欲、種族保存欲は人間の根源的な欲望だと思う。森田では欲望のない人は哀れであるという。どこまでも欲望は追及してもよい。ただ普通の人は精神拮抗作用で説明しているとおり、欲望の暴走には制御がかかるようになっている。制御がかかると欲望が暴走するということない。人を押しのけて自分の私利私欲を満たすような行為、人に迷惑をかけるような行為、自然を自分の意のままに操ろうとするような行為は、普通は歯止めがかかるように人間はできている。ところが現実には、一部の人間はその自然の摂理を無視して、あくなき欲望の追求に明け暮れている。そういう人はバランス感覚が崩れている。サーカスの綱渡りの芸でいえば、途中で墜落して地面にたたきつけられるようなものだ。森田を学習すると「調和」は自然界すべてに通じる普遍的真理であると学ぶ。神経症に陥るのは、欲望を忘れて、不安のみにとらわれて精神交互作用によって観念と行動の悪循環の果てに引き起こされたものであると学んだ。一方あくなき欲望の追求に走る人もいる。その人たちは不安を無視して自分たちの欲望を満たそうとしているのである。どちらに転んでも将来に大きな禍根を残すのは明らかである。「過ぎたるは及ばざるが如し」ということわざもある。バランス感覚、自然の調和、精神拮抗作用をおろそかにすると必ず破綻が待ち構えている。私たちは森田理論の通り常にバランスを心がけて生活してゆきたいものだ。
2013.09.27
コメント(0)
-
子供の喧嘩
子供はよくけんかをします。友達や兄弟でおもちゃの取り合いはしょっちゅうあります。それをみている親の反応はどうでしようか。集談会で聞いたのですが、その方は以前いつも仲裁に入っていたそうです。そしてあなたが悪いと白黒をはっきりさせて喧嘩を止めさせていたのです。大体お兄ちゃんだから我慢しなさい、弟に貸してあげなさいと言っていたそうです。するとお兄ちゃんの態度はいつも大泣きして暴れまわるのだそうです。最近は兄弟げんかが始まると、すっとその場を離れていくのだそうです。気になるのでしばらくして見に行くとほとんど自分たちで解決して、思い思いに遊んでいるのだそうです。子どもの喧嘩に親の仲裁は必要なかったのです。これはぜひ実践したいことです。森田でいえばどうにもならないことは、スッキリしようとしないで、そのイライラを持ちこたえて生きていく能力を獲得しましょうということです。昔から子供の喧嘩に親は出ていかない方がよいといいます。今は自分の子がよその子にいじめられて帰ってくると親が相手の家に電話をしたり、乗り込んでいって苦情をいう人もいるそうです。事態が収束できる筈もなく、さらに問題を悪化させます。そもそも喧嘩ができるというのは、悪いことではなくよいことだと思います。そこを勘違いして喧嘩は悪いもの、してはいけないものと決めつけています。自分の言いたいことややりたいことを言えることはよいことです。自発性が育っていると見るべきです。子供の成長にとって経験しなくてはならない大切なものです。反対にもし自己主張ができず自分の気持ちを抑えて、相手に自分の遊んでいるおもちゃをすんなり渡す子がいたとしたら、とても末恐ろしいことだと思います。また小さいときの喧嘩は人間関係の訓練になり、大人になって大切な対人交渉力を身につけているのだと思います。稲森さんなどしっかりした会社の経営者は、小さいときはガキ大将でみんなをまとめて遊び回っていたという人が多いのです。
2013.09.26
コメント(0)
-
ネット麻雀三段
私はネット麻雀をはじめて10年以上になる。今三段である。二十級から一級、そして初段、二段、三段である。この先六段の人は見たがそれ以上の人は見たことがない。一段上がるのに一年ぐらいかかる。野球の打率のように成績によって上がったり下がったりするので大変だ。また私は1日半荘1回しかやらない。運だめしのようなものだ。でも麻雀で得たことは大きかった。その一つは負けて勝つということだ。誰かがリーチをかける。すると私はすぐに戦闘モードから、撤退モードに切り替える。無条件にそうしている。まだテンパイしていないのに、強硬策を採ることは自滅することが多い。すると後悔する。一回でも満貫を振り込むと即負けにつながる。ようするに、勝つことは、まず振り込まないことなのである。形勢が悪いと思えば、終盤になれば、降りることしか考えていない。それが初心者のころは全部勝ちたかった。相手がリーチをかけている。自分はまだリーチの二歩手前でも、「行ってしまえ」で突っ走っていた。たまには勝つことがあってもトータルでは下位であった。これは森田の学習が大きかった。森田は素早く変化に対応せよと教えている。危ない、やられると思ったらすぐに撤退できる勇気を。ここは勝負と思ったら積極的に果敢に挑戦する勇気を。そんな気持ちで対処していると、仮に負けても納得できる負けなのである。最善の策であったので、仕方ないと納得できる。悔いのない負けなのである。次につながる、貴重な負けなのである。人生でいえば、やれることは全力を挙げて精一杯の努力をする。挑戦しても明るい将来のイメージが描けない、手をだすことで将来が益々悪くなる。人に迷惑をかけるばかりである。こんなことは絶対に手を出すべきではないと考える。
2013.09.25
コメント(2)
-
コミッショナーの辞任について
私は6月21日のブログにこう書いた。プロ野球の加藤良三コミッショナーが、統一球の変更を勝手にやったことに対して、「私は、これは不祥事だとは思っていない」といってバッシングを受けている。 私はこれを見て、これはコミッショナーの引責問題になる可能性が高いと思う。 というのは、この問題は欧米ならともかく、日本の社会には決して受け入れることのできない言動だからである。(一言断っておくが欧米では加藤さんのような対応をとらないと、必ず損害賠償問題に発展する。厄介なことになる。) 普通日本で不祥事があった場合、どんなに相手に非があることであっても、とりあえず、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんと謝るのである。日本の企業の危機管理としては常識である。 まずは真摯に反省して、真剣に謝るという姿勢を見せるべきだったのである。 自分が心底そのように思っていなくてもかまわない。世間の人から見て、反省して心から謝っているように見えるということが大切なのである。 先日加藤さんは、もっともらしい理由は付けていたが、事実上解任された。少し遅くなったが、火種は長らくすくぶっていたと思われる。我々森田を学習しているものは何を学ぶべきであるのか。感情と行動は全く別物として扱うということである。どうしてキャリア官僚経験者がそんな森田の常識、それも初歩的なミスに気がつかなかったのだろう。おごり、変なプライドに固執していたとしか思えない。このように感情と行動の分離はとても難しい。それができないから神経症に陥ったともいえる。でも、森田ではその方向に向いているということが大切である。あとは、自分一人では難しいのだから、集談会で切磋琢磨することである。
2013.09.25
コメント(0)
-
子育てを考える その2
先日外孫2歳が我が家にやってきました。すこし歩くとすぐに「抱っこ、抱っこ」というのです。私は安易に抱いてやりませんでした。「足があるのなら自分で歩け」と言ってやりました。じいちゃんにいっても抱いてはくれないと思ったのか、自分で歩いていました。4歳の孫は偏食です。うどんが好きなのですが、そればかり食べるのです。そして食事に飽きると席を離れてうろうろしはじめたのです。すると父親が、みんなが食べ終わるまで椅子に座っていなさいと言いました。険悪になりました。私はひそかに父親を応援しじっと見ていました。すると孫は「お父さんなんか大嫌い」と言って泣き顔になりました。このように子供のしつけをするときは、しょっちゅう子供と対立します。でも親はここで懐柔してはいけません。しつけは親の責任です。大きくなって困るのは子供自身でもあるのです。まだチラシ寿司がまだ皿の上に残っていました。父親は「残さずに全部たべなさい」と言いました。孫は渋々全部食べていました。でもしばらく経つと父親と仲よく竹馬で遊んでいました。私は一つ失敗をしました。その公園にはミニのお家がいっぱいありました。2歳の孫に「ウルトラマンのお家を見に行こう」と言いました。孫は興味を示し何回も「ウルトラマンのお家を見たい」というのです。すると母親が、実際にはそんなものはないのに嘘をつくのはいけないといいました。私もすぐに嘘を言って子どもを手なずけるのは駄目だと思いました。反省しました。子どもというのは無意識によく覚えているものです。おじいちゃんが平気でうそをついた、これは決して消えるものではありません。これからはもっと孫と真剣に向き合おうと思いました。
2013.09.25
コメント(0)
-
子育てを考える その1
子供を過保護で育てる。子供の気のおもむくままにまかせて甘えさせる。これは親が子供の生の欲望の目を摘み取ってゆくことになります。公園でわが子が他の子に泣かされたりすると、我慢できずに引き離したり、気を紛らわせたり、抱き上げたりするお母さんがいます。買い物に行ってこれが欲しいというと、ダメだと言いながらも最後は「今日だけよ」と言いながら子供のいいなりになるお母さんがいます。子供が、「くそばばあ」といっても苦笑するお母さんがいます。子供が殴りかかってきても叱らないお母さんがいます。子供の時間割までお母さんが見ている家もあります。忘れ物をすると自転車で学校まで届けるお母さんもいます。家事手伝いは一切させないで上げ膳据え膳で、王子様女王様扱いで大事に、壊れ物を扱うように至れり尽くせりの育て方です。これでは自立して生きていく力はでてこないのではないでしょうか。生の欲望の発揮以前の問題です。無気力、無関心、無感動、無作法な子どもは親の育て方が大きいのです。何かするときでも、「お母さん、これしてもいい」と、母親の顔色を気にする子供は要注意です。人の思惑を絶えず気にする対人恐怖症の子どもを作ってしまいます。
2013.09.25
コメント(0)
-
「約束は必ず守らせる」というしつけ
史上最年少ヨット単独無寄港世界一周を果たした、冒険家の白石康次郎さんがいる。小学校1年の時母親が交通事故で亡くなった。兄妹の3人の子どもを育てたのは父鉱造氏であった。兄と自分に厳しくしつけたのは、「自分の言葉に責任を持て」ということだったという。康次郎さんが小学校低学年の頃。父親と買い物に行った。大きなスイカを売っていた。どうしても食べたくなり親父にねだった。すると父は交換条件を出した。「お前が自分でスイカを家まで持っていくなら、買ってやろう。」康次郎さんはもちろん大きくうなずいた。ところが、スイカは重すぎた。気がつくとスイカを入れたビニールのネットの袋の細い持ち手が食い込み、指の色が変わっている。最初は我慢していたが、足どりもだんだん重くなっていく。僕はついに音をあげた。「重い。もう、持てない。」すると父親はこう言った。「お前が持つと言ったんだ。指がちぎれるまで持て」僕は仕方なく、歯を食いしばり、ありったけの力を振絞り、とうとう家まで持っていった。深い満足と誇りを持つことができたという。父は素晴らしいしつけをしていたのだと思う。子どもには、どんなことがあっても約束は守らないといけない。すると子供は、自分の言動には責任がある、ということを身につけるようになる。普通は「持てない」と言うと、「だから無理だと言っただろう」「しょうがないな。かしてみな」と言って子どもからスイカを取り上げてしまう。親は子どもに厳しくするよりも甘やかす方が楽なのだ。約束したことを意地でも守らせようとすると子どもと摩擦を起こす。それを恐れて子どもを甘やかせる親が多いのである。でもそんな子どもが大きくなると恐ろしい。言行不一致で他人に迷惑をかけるのは平気、自分の得になるのなら人を蹴落とすのは当たり前という大人になるのです。
2013.09.24
コメント(0)
-
テレビ漬けの弊害
人間をボケさせる方法があるそうです。一日中せまい部屋に閉じ込めて情報を遮断するのです。宇宙飛行士の訓練でそうした実験をすると、体よりも先に精神状態がおかしくなってしまうそうです。宇宙に飛び立つと、小窓から地球を眺めることで癒されるといわれています。次に一日中テレビを見て過ごすという生活はどうでしょうか。テレビから情報はたくさん得られるように思います。ところがこれは平面的な情報です。写真を見ているようなものです。これでは脳の機能を維持することは難しいという人がいます。五感をフルに使っていないために、廃用性萎縮が起きてしまうのです。私が最初にプロ野球観戦に行った時のことです。芝生の鮮やかな緑、鳴り物を使った派手な応援、球場の大きさ、周囲の人たちの表情、選手たちの躍動感など球場の雰囲気に圧倒されました。テレビを見ているだけとは大違いでした。クラッシックのコンサートに出かけた時も、CDから流れる音楽を、家の中で聴いているのとは全く違いました。実際に第九合唱団員になり、オーケストラの後ろで「歓喜の歌」を多くの人と合唱した思い出は、今も懐かしい記憶として活き活きとよみがえります。体感というのはすごいのだと思います。体感しないで、テレビ中心の生活をしているとどうなるか。周囲の変化に対して反応が徐々に衰えてくるのです。森田では周囲の変化に常にアンテナを張って、その変化に合わせて自分の行動を瞬時に適応させていくということを重視しています。ところがテレビ漬けの生活はその能力を奪ってしまいます。人に話しかけられても、即座に対応できなくなります。できても遅くなるのです。相手の表情などから状況を読み取り、適切な反応を示すことができなくなるのです。変化に対応できなくなると、神経症と同じで思考が堂々めぐりするようになります。行動と思考の悪循環が始まります。テレビ三昧で目を動かすことが少なくなるとそうした弊害が起きてくるのです。ここでも森田的生活がいかに大事であるかが分かります。
2013.09.24
コメント(0)
-
森田の研修会
今年になって、私共が春前から長らく準備を進めてまいりました、森田の研修会がやっと今週開催の運びになりました。思い出せば長い準備期間でした。参加者もまずまずの人数が集まりました。普段は顔を合わすことのない人たちが一堂に会しますので、とても楽しみです。実質世話人2人で何回メールでの打ち合わせをしたのか分からないぐらいです。考えられる問題点はほぼつぶしました。みんなに参加してよかった。役に立ったといわれる研修会のめどが立ちました。今回は今までになかった森田理論学習の新しい視点を大胆に提示いたします。合言葉は、「新しく集談会にきた人を、ざるで水をすくうようなことは止めよう」です。そのための森田理論学習の変更です。もしこのプログをご覧になっておられる方で、参加される方は大いに期待してください。ちなみに世話をする我々も有意義な森田実践ができました。ありがたい経験をさせていただいて大変感謝しております。
2013.09.23
コメント(0)
-
森田の達人
信頼できる人、尊敬できる人はどんな人だろう。生活の発見会には何人かはそういう人がいる。そういう人の共通点を探ってみたい。まず相手を大切に扱ってくれる。よく話しを聞いてくれる。最後までよく聞いてくれる。ただ聴くだけではない。その上で自分の意見をしっかりと話してくれる。自分の体験したことを基礎にして話してくれる。理想や「かくあるべし」の押し付けはない。つぎに自分の存在を丸ごと認めてくれる。人と比較するようなことはしない。ただ生きているだけでいい。あるがままに存在していることに価値がある。そこに視点をすえておられる。ミスや失敗、悪いことをしても、否定しない。将来につながるよい経験をしたと、許してくれるのである。またもがき苦しんでいる時、じっと付き添ってくれる。いつも気にかけていてくれる。そしてどうにもならなくて助けを求めた時、必ず助けに入ってくれる。アドバイスをしてくれる。そして他人がうまくいったり、成功すると自分のことのように喜んで祝福してくれる。あなたの成功や幸福を自分のことのように喜んでくれる。うらやましいのは、自分の生活スタイルに満足している。あんな人になってみたいなというオーラがある。決してお金がたくさんあるわけではない。質素な生活である。でも日々の生活がすごく意味があり、一つ一つの日常茶飯事がとてもいとおしいという気持ちが体全体からあふれているのである。最後に森田理論を自分のものにしておられる。極めておられる。生活が森田そのものになりきっておられる。すべての生活は森田理論をベースにして成り立っているのです。いわば森田の達人になっている人です。私もそうゆう人になりたい。
2013.09.23
コメント(0)
-
子供のしつけについて
子供を甘えさせない。過保護に育てないためにどんなことをしたらよいのだろう。子供ができたら先人からノウハウを学ばなければいけない。それも正しいしつけについての基本的知識を身につけないといけない。学習しないで、自己流に流されるような子育てはうまくいく可能性が少ない。その点森田理論学習も同じである。子育てやしつけは、0歳児から始めなければならない。寝る時間、起きる時間を決める。基本的生活習慣をつける。テレビをダラダラと見せない。添い寝はしない。している場合は止める。ひとりで寝させる癖をつける。抱っこをせがんでもいつも要求には応じない。冷蔵庫を開けて自由にジュースを飲んだり、食べ物をとって食べたりさせない。お菓子を好きなだけ食べさせない。間食はさせない。何をどう食べさせるかは親が主導権を持つ。きちんとした食事の習慣をつけさせる。子供のいいなりは駄目である。子供の食べるものは皿に盛って全部食べさせるようにする。ニンジンなど細かく刻んで隠して食べさせるようなことはやめる。食事のマナーはきちんとしつける。子供と約束したことは徹底して守らせる。途中で約束を変更してはならない。子供を叱るときは、徹底的に叱る。あとから、なし崩し的に子供の機嫌を取るようなことはしない。ダメなものはダメと言いきれる親になろう。決して妥協はしないこと。これだけのことを0歳から3歳ぐらいまでにきちんとしつけられれば、その後の育て方はきっと楽になる。孫がいる場合も、祖父母は甘やかせて過保護にしては、親の教育が台無しになる。そうした視点から親の子育てに協力しよう。参考文献 こうすれば子どもは「ちゃんと」聞き分ける。PHP研究所 田中喜美子著
2013.09.23
コメント(0)
-
子供の食事
若いお母さんは、子供の食事で気になることは、自分の作った料理の食い付きだそうです。子供にうけるかうけないかに注意を払っています。よく食べてくれたものは「あたり」、そうでないものは「はずれ」となります。「はずれ」た料理は食卓から消えていく運命にあります。なかには子供に「まずくて食べれない」といわれると、自分のことを非難され、自分が否定されたように感じるお母さんもいます。昔からお母さんは、子供の成長や家族の健康を願って、栄養のあるもの、バランスのとれた食事を朝昼晩と用意してきました。子供が少々嫌いなものであっても、「これを食べなさい。食べないのなら食べなくてもよい」というぐらいのイニシァティブを持って料理を作っていました。子どもは嫌いなものでも我慢して食べるということを学んでいきました。現代は子供のリクエストにこたえて、それぞれの子どもの好きなものをいろいろ取り揃えて、好きなものを食べてもらうというように変わってきています。朝は、菓子パン、カステラ、カップめんという家庭もでてきているそうです。食べるものは個人個人バラバラ。食べる時間もバラバラ。こんなことで家族して機能していくのでしょうか。家族はいまや烏合の衆の集まりです。またこういうふうにして子供の言うとおりにしていると、子供は「食べてやっているのだ」という横柄な態度になってしまいます。当然わがままな子供に育ちます。そのわがままはしだいにエスカレートしてきます。成長してわがままが聞き入れなれなくなるとどうなるでしょう。当然「我慢する」「耐える」ということはできなくなります。この世は自分を中心に回っており、なんでも自分のやりたいことや考えたことが通るはずだという誤った考えを持つようになります。小さい子供はすぐにきれて泣き散らし、大きくなった子は親に反抗して、家庭内暴力に向かうのではないでしょうか。さらに悪いことに社会人となった子は自分の思い通りにならない問題が起きると、すぐに困難を回避したり逃避したりするようになります。対人折衝能力が育たず、弱い者にはけんかをうり、強いものには巻かれて劣等感を募らせていくことになります。社会生活がスムーズに送れなくなってしまうのです。そういう家庭は、食事のしつけ、箸の持ち方、会食のマナーなどはほったらかしとなります。そうしたしつけができていないのです。すると他人に迷惑をかけても悪いと感じることができない大人になってしまいます。また本来家庭では、親の意見と子供の意見は常に対立しています。いつも子供のいいなりになるということは、対立を避けて、子供に干渉しない他人行儀な家族関係を作ってしまいます。子供にとっては自分の意見が通らないこともある、我慢しなければならないこともある、つらくても耐えなければいけないこともある。そういう経験が不足してきます。親と対立して自分の意見を主張してみる。そして親に言い負かされて悔しい思いをする。さらに親との和解の道を模索していく能力を身につける機会が持てなくなってしまう。あまりにも子供の意向を尊重して、子供の一挙手一頭足に親が合わせているととんでもないことが起こります。子供がわがままになり、気分のままに好き勝手なことばかりするようになります。本来親は子供をきちんとしつけて、大人になって苦労しないように毅然とした態度が求められます。食事で子供のいいなりになって、場当たり的なもので対応するということは次から次へと問題を拡大させるということです。食事を作るという日常茶飯事に自分の意思を込めて真剣に取り組んでいくことは森田の原点であると思います。
2013.09.22
コメント(0)
-
自分を信頼する
心豊かで自分の納得できる生き方をするためには、人生の「主役」が自分でなければならない。それが唯一生きる喜びを体全体で感じることができる。しかし、人からよく思われたい、人から一目置かれるような人間になろうと思えば、自分を抑えて人の立場や気持ちを尊重して生きてゆくようになる。自分の悲しみ、苦しみ、失望、不安を隠して、人に迷惑をかけないように、なるべく人の気持ちに沿って生きようとする。醜いありのままの自分は、人を不愉快にさせるので隠してばかりで、決して人前に出そうとしない。自分の気持ちのよいところばかり出したりして、苦しい部分を封印していると、ありのままの自分を出せなくなって息苦しくなる。苦しむようになる。そうならないためにはまず、そうゆう自分を自覚することが大切だと思う。自分は常に人の思惑に左右されて、主体的に動くことのできない人間である。否定するのではない。事実を事実として認識するだけだ。そこが自分が再生していく出発点だ。人の思惑が気になる自分はひとまず横に置いておいて、自分のために、自分ができることを精一杯してみることである。それを1つでも2つでも身につけていく。10年ぐらい真剣に取り組んでいけばその道に詳しくなる。エキスパートになれる可能性がでてくる。すると自信がでてくる。そうすれば、ミスや失敗をして、人から少々非難されたり、否定されても、自分自身の中に大きな後ろ盾を持っているので、自虐ネタとしてみんなに笑いを提供できるのである。
2013.09.21
コメント(2)
-
依存症からの脱却
インターネットなどで読者の反響が大きくて炎上したなどということがいわれる。また、匿名で相手を中傷誹謗する書き込みを繰り返す人がいるという。ウィルスの入ったメールなどを送りつけて喜んでいる人がいる。こんなことを繰り返す人は、何かに不満を持っていて、憂さ晴らしのために、やっているのだろうが、感情の法則からすると自分の行為に刺激を受けて次から次へとエスカレートするばかりである。中毒症状と同じで、止めようと思っても自然にキーポードを叩いてしまう状態だと思う。ギャンブル依存、アルコール依存、薬物依存、セックス依存と一緒だ。もしこれから逃れようとすると、手厳しいしっぺ返しを食らわないとその呪縛から逃れられないのである。私も以前パチンコに凝って、家に帰ろうとするのに自然に足がパチンコ屋に向いてしまうというパチンコ依存症にかかったことがあった。年間予算を10万円と組んでも1カ月ぐらいですぐに使ってしまう。自分ではこんなに湯水のようにお金を使ってはいけない。と押さえつければつけるほど反対に行動としてはエスカレートしてしまうのだ。なんとかしなければともがいていた。足を洗えたのは負け続けてお金がつづかなくなり、やむなく断念することになってからだった。森田でいう恐怖突入だった。最初は禁断症状がでたがしばらくすると楽になった。行かないことが習慣化すると、行かなくても平気になった。ここ10年ぐらいはパチンコ屋に入ったこともない。身近にもギャンブル依存、アルコール依存、薬物依存、セックス依存で生活が破たん寸前という人をたくさん見てきた。人ごとではない。森田と一緒でどん底まで落ちないと立ち直りはないのかもしれない。自分一人で解決できないときは、人の助けを借りることだ。今はそれぞれに自助グループがあるのでまずは参加してみることだと思う。生活の発見会と同じでたぶん温かく迎えてもらえると思う。
2013.09.20
コメント(0)
-
生命エネルギーとは
川田薫さんという学者がいる。生命の起源について科学的に研究をしている人である。この人の研究では、海と陸地の境で生命は誕生したという。ミネラル(岩石などの鉱物)と、水、大気、太陽の光の化学反応によってアミノ酸のようなものは作ることはできる。詳しくはユーチューブで1時間にわたって解説されているので参照してほしい。私が注目したのはこれから先のことである。こうして生体というものができるが、生体が動くということがどうも理解できなかった。生体はしばらくするとさかんに動き始めるというのだ。川田さんはこう考えた。どこからか生命エネルギーがその生体に入り込んでいるのではないか。そして生命エネルギー体として存在しているのではないのか。生命エネルギーというのは質量がある。ネズミを使って実験すると、ネズミが死ぬ時、早い遅いの違いはあるが、かならず質量の変化が観測される。これは生命エネルギーが生体から離脱していることでないか。これは人間も同じだという。母親のおなかの中で器官に分化してくるときに生命エネルギーが入り込んでいるのに間違いないといわれるのです。人間は親が勝手に産むのではなく、自分が親を選んで生まれてきているのだ。だからかってに、こんな自分に産んでからにと親を逆恨みすることは間違いだといわれるのです。自分がこの世に生まれるときはプロクラムを持ち、課題を持ち、役割を持って生まれてきているのだ。でも生命体として宿る前にはいったんすべてを消し去って生まれてくるのだ。自分の使命に早く気がつくことが大切だ。私が川田薫さんを知ったのは、元メンタル記念財団の岡本常男氏であった。「石ころにも命あり」というテープを送っていただいた。NHKの深夜便「心の時代」のテープであった。川田さんは前科学振興事業団の研究員であり、生体と生命エネルギーが合体して生命エネルギー体としてこの世に存在しているのだといわれている。このテープを聞けばあなたの生き方に影響を与えると思う。さらに森田を深めてほしいということでした。今考えると岡本さんは、人間の肉体は死んでも生命エネルギーは死なないのだと確信しておられたのだと思う。そう仮説を立てて生き方を考えることがとてつもなく大切なことに思える。
2013.09.19
コメント(0)
-
自分の意見を持つ
戦艦大和はアメリカ空軍によって東シナ海で沈められた。広島県呉市から打たれた主砲は、四国の愛媛まで届いたという戦艦大和がもろくも沈んだのである。護衛の航空部隊もつかない出撃は、自殺行為であり、作戦として形をなさないというのは多くの人が分かっていた。それなのになぜ出撃させて多くの若者の命を無駄死にさせたのか。戦艦大和の出撃に関して、小沢中将は、「全般の空気よりして、当時も今も大和の特攻出撃は当然と思う」(文藝春秋1975.8)といっている。この戦時下では、全体の空気が日本を重苦しく支配して、反対の意見を述べようものなら即時戦犯として処刑される運命にあったのである。特攻隊員にしても同じであった。この時代は自分の意志は全体の空気によって一方的に押し切られていったのである。いまの時代はその当時とは違って形式的には自由に自分の意見を述べることができる。しかし「空気読みの達人」を目指している人が依然として多い。いつも周囲の目を気にして、周囲に合わせるという立場をとり続けている人が多い。この生き方はとても苦しい。空気を読むということは、読めないよりはよいのは決まっている。しかし、もっと大切なことは、人に合わせる前に自分の意見をしっかりと持つということだ。自分の「生の欲望」に正直に従うということだと思う。曲がりなりにも「生の欲望」を持つことができれば、次に相手の意向との妥協点を探すという段階に入ることができる。森田理論学習は、「生の欲望」の発揮を横においては成り立たない理論である、ということをよく学習してほしい。
2013.09.19
コメント(2)
-
☆人を先入観で決めつけてはいけない
ユーチューブで見つけた話を紹介します。ある女の先生の経験。「可能性のない人はいない」ある小学校でいいクラスを作ろうと一生懸命な先生がいた。その先生が5年生の担任になったとき、一人服装が不潔で、だらしなく、遅刻をしたり、授業中居眠りをしたり、みんなが発表するとき一度も手をあげない少年がいた。先生はどうしてもその先生が好きになれずいつからかその少年を毛嫌いするようになった。中間記録に先生は少年の悪いところばかり記入するようになった。あるときその少年の1年生からの記録が目にとまった。そこにはこう書いてあった。「朗らかで、友達が好きで、人にも親切で、勉強もよくできて、将来が楽しみ。」とある。間違いだ。他の子供の記録に違いない。先生はそう思った。2年生になると、「母親が病気で世話をしなければならず、時々遅刻をする。」と書かれていた。3年生では、「母親の病気が悪くなり、疲れていて教室で居眠りをする。」3年生の後半の記録では、「母親が死亡。希望を失い悲しんでいる。」4年生では「父は生きる意欲を失い、アルコール依存症になり、子供に暴力をふるう。」先生に激しい痛みが走った。ダメだと決めつけていた子が突然深い悲しみを生き抜いている生身の人間として自分の前に立ち現われてきたのだ。先生にとって目を開かれた瞬間であった。放課後、先生は少年に声をかけた。「先生は夕方まで教室で仕事をするから、あなたも勉強してゆかない。分からないところがあったら教えてあげるから。」少年ははじめて笑顔をみせた。それから毎日教室の自分の机で予習、復習を熱心に続けた。授業で少年がはじめて手をあげたとき、先生に大きな喜びが起こった。少年は自信を持ち始めていた。6年生では先生は少年の担任ではなくなった。卒業の時、先生に少年から一枚のカードが届いた。「先生はぼくのお母さんのようです。そして今まで出会った中で一番素晴らしい先生でした。」それから6年またカードが届いた。「明日は高校の卒業式です。僕は5年生で先生に担任してもらってとても幸せでした。おかげで奨学金をもらって医学部に進学する事ができます。」10年たってまたカードが届いて、そこには先生に出会えたことの感謝と父親に叩かれた体験があるから、感謝と痛みのわかる医者になれると記され、こう締めくくられていた。僕はよく5年生の時の先生をよく思い出します。このままダメになってゆく自分を救ってくださった神様のように感じます。大人になり、医者になった自分にとって最高の先生は5年生の時に担任してくださった先生です。そして一年。届いたカードは結婚式の招待状だった。「母親の席に座ってください。」と一行添えられていた。先生はうれしくて涙が止まらなかった。
2013.09.18
コメント(0)
-
☆事実の分析について
マスコミによく出ておられた堀紘一さんの大学受験の話が面白い。彼は東大受験を決めたのは高校3年になる春だったそうです。猛勉強を始めたわけではない。東大の過去10年間の入試問題に目を通すことから始めたそうです。過去5年間の入試問題は簡単に手に入れることができたが、それ以前の5年間の問題集はなかった。神田の古本屋で3日間探してやっと手に入れた。次には大きな模造紙を買ってきて、10年間の全教科の問題がどのように出されているのかを分析したそうです。この作業にも3日ほどかかった。その中から見えてきたものは大きかったという。たとえば生物では、「遺伝の問題」と「分類体系の問題」が一年ごとに、過去10年一度の狂いもなく交互に出題されていた。そこで直接東大に出向いて訳を聞いた。ここが森田先生とよく似ている。すると詳しく教えたくれたそうです。それは二つの研究室が交互に持ち回りで20点の配点問題を作っていたことが分かった。当面この順番は変わらないだろうという。世界史では教科書に載っていない問題がでていた。聞いてみると別の教科書に載っているということが分かった。その教科書を自分の高校の先生に頼んで取り寄せてもらったという。また文系では数学3は出題範囲から外れているのにも関わらず出題されていた。これも訪ねていって聞くと、入試では差をつけないといけないので、教科書の最後に導入部分として紹介されているところから出題したといわれた。そこで私は高校の先生にお願いして微分積分の授業だけ受けさせてもらったという。堀さんの着眼点はたいしたものです。普通はやみくもに全項目をまんべんなく学習すると思う。なかなか努力のわりには成果が得られにくい。堀さんは対象の「観察と分析」から始められている。それを突き詰めれば自然と対処の仕方が分かってきたというのである。目標を達成しようと思うと、相手をよく観察して、相手をよく知るということが不可欠である。森田理論の事実本位の考え方そのものである。
2013.09.18
コメント(0)
-
自分の存在理由を見つける
Aさんは30歳の女性です。独身です。4年生大学を卒業して、東証一部上場会社に入社しました。最初は飲み会などにもよく誘われていました。ところが最近はケースに自分が呼ばれることがなりなりました。かっての同僚たちは結婚してどんどん退職し、自分よりも若い人たちが増えてきました。顔のシミやシワも気になって自分が嫌になるそうです。若手女子社員が雑談していると自分の悪口を言っているのではないかと不安になるというのです。エステやカルチャーセンターに通ってみてもむなしさを感じて長続きしないというのです。この例は自分が歳をとっていく不安もありますが、自分の生きる方向が定まっていないことの不安が大きいと思います。周囲の人は結婚、子育て、キャリアウーマンとして自分の生き方を持っているのに、自分はいまだにそういう核になるものを見つけ出していない。そういう不安です。自分に信頼が寄せられないのです。NHKにプロフェッショナルという番組があります。この人たちは自分のすすむべき道をしっかりと持っている人です。その道を突き進んでいる人です。そうした人は失敗が気になりません。失敗は次の成功のための餌のようなものです。自分のアイデンティティをしっかりと確立させています。自分を信頼し自信を持っています。他人の悪い評価は自虐ネタとして笑いの種にする事ができるようです。自分のやりたいこと、進むべき道を見つけることは、自分の生きていく土台作りのようなものです。それがないと、他人の顔色をうかがいながら生きていくことになります。ストレスがたまるばかりです。森田では自分の感情を大切に扱うことを重点的に学習します。私はそれに加えて自分のこうしたいという意思を大切に扱うこと。それを前面に押し出して生活する態度を身につけること。なければそうしたものを養成して確立していくこと。これも森田理論の学習に通じると思います。大切なポイントです。
2013.09.17
コメント(0)
-
己の性を尽くすということ
人間には23対の染色体がある。男と女はXとY染色体によって分かれている。染色体は二本の長い鎖がらせん状に巻いている。遺伝子はアデニンA、チミンT、シトシンC、グアニンGという4つの塩基配列によってできている。その数なんと30億もあるという。すべて解読されており、現在1日で解読可能である。解読すると病気の成り立ちが分かるという。肺がんなどの病気にかからない人と病気にかかりやすい人を比べると、塩基配列が違っているという。肺がんになる人はALK遺伝子が関与していることがある。この遺伝子は細胞分裂を促す遺伝子で、塩基配列が違っている事で肺がんの細胞分裂が暴走することがある。治療としてはALK遺伝子が働かなくする方法があるという。ある患者は咳が止まらなく、一方の肺の半分ぐらいががん細胞におかされていたが、この服薬治療で、1ヶ月で5分の1ぐらいに縮小していた。この塩基配列は、私たちの体が細胞分裂する時、コピーミスをおこすことによって後天的に病気の火種を抱えることにもなる。先天的な遺伝子の異常だけではないということだ。30億分の1のコピーミスによっても重大な疾患に結び付くこともあるそうです。次に、この遺伝子はスイッチがオンになっているか、オフになっているかが重要であるという。これを遺伝子のメチル化という。家の配電盤を思い出してほしい。ブレーカーがいくつもついている。家庭ではすべてをオンにして電気を使っているが、人間の体ではスイッチをオンにしている時とオフにしている時としょっちゅう入れ替えているということです。病気になるというのは、病気になりやすい塩基配列の人が、スイッチオンに切り替えられた時である。ですから逆にいえば、ガンになりやすいタイプの人が、スイッチオフで生活できれば病気にかかることは軽減できる。それを自覚して予防すればある程度は防げるのである。私は痛風持ちである。多分塩基配列に問題があるのだろうと思う。でも問題があるということを自覚しているので、毎月病院へ出向き経過観察している。1回症状がでただけでその後は出ていない。また、効果は少ないらしいが食事に気を使っている。プリン体の多い食品、飲物を加減しているのである。もし自覚がなかったとしたら、私の好きなビールは飲み放題、かつおのたたきや白子、辛子明太子は食べ放題という生活を続けているだろうと思う。遺伝子はスイッチがオンになっているか、オフになっているかは生活習慣と大きく関わっているようである。たとえばがん細胞は、誰でも数千単位で毎日作られているという。でも全員ががんを発症するわけではない。小指の先ほどのがん細胞の生成には10年程度の歳月が流れているという。その間ストレスを少なくして、白血球の中のリンパ球と顆粒球のバランスを整え行けばがんの退縮が起きることは十分に考えられることだ。ストレスの多い生活、不規則な生活が遺伝子スイッチをオンに切り替えているのではなかろうか。自分の体は自分のものであって自由自在に酷使するという考え方は慎みたい。自分の体は預かりものであり、できるだけメンテナンス、ケアを心がけ、体をいたわり大切にする心掛けが大切です。森田では「己の性を尽くす」と言います。私も予防できることは普段から気をつけてゆきたいと思う。
2013.09.16
コメント(0)
-
生の欲望の発揮と人の思惑への配慮
アメリカでは子供が悪いことをすると家に閉じ込めてしまう。自由で勝手気ままな行動を制限して罰を与えるのである。アメリカでは自由を奪われるということに苦痛を感じる。反対に日本人は子供が悪いことをすると家の中に入れずに外に出してしまう。つまりもう保護の対象ではないから、自由に一人で生きていけと見放してしまうのである。日本で見放される、外されるということは社会的な死を意味している。だからみんな恐れているのである。これは文化の違いだと言えばそれまでだか、それぞれに長所短所が入り交じっている。いずれも偏り過ぎると、さまざまな問題として表面化される。日本の問題に絞ってみてゆこう。こんな事件があった。「佐世保小六女児同級生殺害事件」である。小学校6年の女児が学校内で、同級生をカッターナイフで切りつけて殺すという事件である。この被害者と加害者は普段から仲の良い子供として周りから見られていたそうである。殺害のきっかけは、加害者が教室で被害女児におぶさった時、「重い」といわれた事や、ネットで悪口を書かれた事といわれている。どちらかというと殺人事件にまで発展しそうな問題だとは思われない。これは息苦しいまでに学校では、毎日友達に気を使って生活しなくてはならない中で起きた事件のような気がする。お互いに縛り縛られあって、やれ携帯メールだといって「つながってなくちゃなんない症候群」の状態にあったという。(小林道雄氏「感受性の未熟さが非行を招く」)閉塞的で窒息状態にあったのである。自分の行動が常に相手によって監視され、価値判断を下されるということは考えただけでも重苦しい。このように自分の勝手な自由な行動が制限されると、ちょっとした不快な出来事であってもすぐに耐えられなくなり、爆発するのである。我慢に我慢を重ねた最後に大爆発するのです。大人でも会社の中で、周りの人の動向ばかりを気にして、仕事がうわの外という人がいる。悪化すると出社することができなくなる。佐世保の事件と同じ構図である。本来人間は、他人の思惑を気にすることは二の次にして、自分気持ちを大切にし、やりたいことに自由にのびのびと取り組んでいる時に、この上ない快感を覚えると思う。それを封印して、人に合わせること最大の価値を置いて、他人に気を使うということは、その自然の流れに反することだ。水は上から下に流れるのに、無理やり下から上に流そうとするようなものだ。ここは森田の出番だ。自分の「生の欲望の発揮」を第一に考えること。これが重要である。これをないがしろにすることは、生きることがつらくなる。まずは一つでもそうしたものを持つことが大切だと思う。最終的には自分の「生の欲望」の発揮と他人への配慮がバランスが取れていかないと、まともな生き方には結びつかない。でも神経質者の場合はその前に、自分というものを前面に打ち出して生きるという姿勢が持てないということが問題である。「生の欲望の発揮」は森田理論の根幹である。十分に学習してほしい。
2013.09.15
コメント(0)
-
無意識の感覚に任せてみよう
ジョゼフ・マーフィー牧師によると、私たちの意識のうち自分で自覚できる顕在意識は全体の10%であり、それ以外の90%は潜在意識(森田でいう無意識)といって、自覚していない中で生活している。これは車の運転でとてもよく理解できます。車の運転は無意識に体が反応して適切かつ正確な行動がとれています。ほとんどの人、ほとんどの場合そうなっています。反対にもしチェンジレバー、アクセル、ブレーキなどの場所や動きなどにとらわれて、意識がそこに引きつけられるようなことがあると、とても危険極まりないことになります。初心者のうちは意識的な行動は仕方ありません。しかし、ある程度経つと無意識的行動に変化してこないと支障をきたすようになるのです。森田ではとらわれた時は、注意をそこに向けて感覚が高められた状態であるといいます。それが、いつの間にか無意識の状態に変化してきたときが、症状から解放された時だと説明されています。私はチンドン屋で曲がりなりにも、アルトサックスを吹いている。そのことがとても実感できるのです。初めてやる曲は、もどかしいほどゆっくりゆっくり指使いを覚えていきます。テンポやリズムは上手な人の模範演奏をPCM録画機に録音して、何回も聞いて感覚を掴みます。それを何回も何回も繰り返すのです。バカになって練習を繰り返すのです。カウンターを持って100回。200回と繰り返すのです。同じ曲ばかりやっていると飽きるので、他の曲などで気晴らしをしながら、またその曲に戻るのです。何日も何日も繰り返すのです。500回から1000回繰り返していると、譜面がなくても、暗譜で指が動いてくれるようになります。練習というのは恐ろしいものです。不思議なことが起きるのです。無意識に手が勝手に正確にキーを押さえている。あとで振り返ると意識していなかったのに、うまく吹けたという状態が増えてくるようになるのです。その時意識は邪魔になってきます。無意識で演奏できないと間に合わない。曲になっていかない。ところがたまに迷いがでてくることがあります。この次はどこのキーだったかなとか、うまく吹けるかなという一瞬の迷いです。また本番中に少し色気を出して、感情豊かに吹いてやろうなどと思うと途端に調子を崩すことがあります。また仲間のしぐさなどが気になると間違いやすいのです。つまり無意識の状態になって、淡々と指の動きに全幅の信頼をおいて、まかせきっている時がうまくいく時なのです。普通観念では、意識していないと間違いが多いように思いますが、それは認識の誤りです。無意識にならないと音楽は成り立たないのです。言葉ではうまく言えないところがあるのですが、たしかにそういう「はまる」「そうしたゾーンに入る」ということがあります。ここで私が何を言いたいかというと、無意識のうちに体が動いたり、自然に行動していたりする瞬間を作るということが大事なのではないかということです。最初のうちは意識して、なんでもかんでもとりあえず行動しますが、しだいに無意識の行動に変化してこないと物事はうまく展開してゆかないのではないかと思うのです。
2013.09.14
コメント(0)
-
ありのままの自分を受け入れる
以前の生活の発見誌に福井さんが若林繁太先生の講話を紹介しておられました。二歳の時に小児マヒになり、その後手が動かない、足が動かない、言葉がしゃべれなくなった女性の話です。当時31歳だったそうです。すべてご両親がつきっきりで世話をしておられました。頭はしっかりしていたそうです。その人は、「私はこの世の中で邪魔な人間だ。いらない人間なんだ。こんな人間は早く死んだ方がいい。そのほうが世の中のためになる」と思っていたそうです。ところが発達した時代になって、特別障害者用のワープロができて自分の意志を伝えることができるようになりました。その子はこのワープロを使って自分の思いを書くようになりました。その中にこんなことを書いていたそうです。「私はいま、生きがいを持っています。それはこの世の中でみんなが自分の仕事に失敗したり、自殺をしたくなったり失望することがあるでしょう。だけどその時は私を思い出してください。私は手も足も口も動かない。だけど生き続けているんですよ。私を考えたら、あなたなんかいいじゃないですか。もう一度やり直してください。頑張ってください。そして、それでやり直してくれたらそれが私の素晴らしい生きがいだ」この人のすごいところは、手足が動かない自分をいろんな葛藤の末に、受け入れることができるようになったことです。そして、受け入れた自分を踏まえて、自分が人のために役立つことをみつけて実践されていることです。すごく感動する話です。私たちもどんなにハンディキャップがあっても、決して自分で自分を見捨てないで、励まし、いたわりあって、自分を大切に生きてゆきたいものです。これができるようになれは、自分のありのままの事実に服従するということになります。
2013.09.14
コメント(0)
-
発達障害の治療にあたって
発達障害という病気があります。日本ではあまりなじみがありません。あっても知恵遅れで社会適応できない人ぐらいな認識でしょうか。確かに学習能力に問題のある人もいますが、気が散りやすく、一つのことに集中できない。いつも落ち着きがなくそわそわしている。キレやすい。衝動的。人と上手にコミュニケーションが取れない。など幅広い症状があります。これは性格の問題ではなく、脳の発達のアンバランスによるものとされています。この症状の人は他の人から見ると、変わり者、自分勝手な人とされ邪魔者扱いされます。そのことが本人を孤立させてうつや引きこもり等の二次障害を発生させているという。発達障害の専門医であり、本人も発達障害の星野仁彦氏は次のように言う。「発達障害を繰り返した人は深刻な二次障害を起こし、社会から見放されて、自己嫌悪に陥っています。そんな痛々しい姿で私の診療所にやってきます。そんな人にこれは脳の機能障害の問題であり、治療を受ければ治るというと安心します。今まで自分の性格の問題だとばかり思っていたのです。」自分の性格の問題ではなかった。自分はダメな人間だと卑下することはないんだ。自分の長所にも目がいくようになり、それを活かすにはどうしたらよいか。どうふるまえばよいか、社会生活をよりよくするための様々な工夫にも取り組めるようになります。また家族や周囲のサポートも受けやすくなります。療育手帳や精神障害者福祉手帳を取得することで障害者雇用制度の利用も可能となります。つまり発達障害ではその症状を正しく診断を下すということが一番なのです。そして自分も家族もその事実を認めるということが治療の出発点となります。これを神経症に置き換えてみると、「かくあるべし」という色眼鏡をかけて事物を見ないで、事実を正しく見て、事実を受け入れていくということではないでしょうか。
2013.09.13
コメント(2)
-
リーダーの役割
昔東京オリンピックがあった時、女子バレーに鬼の大松監督がいた。スパルタの練習で選手達をしごき、「俺についてこい」という言葉が有名です。そして優勝しました。「巨人の星」の星飛雄馬は、父親の星一徹のスパルタによって巨人の星になった。学習塾の先生でカリスマといわれる教師がいる。授業が分かりやすい。面白い。生徒の高い学習意欲にさらに火をつけて学力を向上させる。また日産のゴーン社長のように、瀕死の会社を短期間で立ち直らせた人がいる。この人たちはリーダーがはっきりとした高い目標を持っていた。リーダーが先頭に立って選手、生徒、社員を引っ張っていった。リーダーにはリーダーシップの他に、選手たちをひきつける人間的魅力があったのだろう。リーダーに全幅の信頼を寄せていたのだろう。そのうち、この人についてゆけば自分の夢がかなう、という信念のようなものがでてきたのだろう。だから選手たちは、苦しい練習に耐え抜くことができた。つまりいつの間にかリーダーと選手達の間に大きな目標が共有化されたのである。選手とリーダーが一枚岩となったということです。一頭のライオンと5頭の羊がいる組織と一頭の羊と5頭のライオンがいる組織が闘うとどちらが勝つかという話がある。たとえ一人でもリーダーがしっかりと信念を持っていて、組織をまとめ上げる力があると、勝つ可能性がでてくるというたとえである。でもこの時、もし選手たちがどうしても、その目標を共有化できなかったときはどうなるのか。それは選手にとっては強制労働のようなものだ。義務感で仕方なしにやるということだ。義務感でやる練習は苦痛そのものだ。当然モチベーションはあがらずに、成果に結びつくことは少ない。それは「かくあるべし」の押し付けになってしまうからである。だからリーダーの役目で大切なことは、選手、生徒、社員がいかに自分自身で目標を見つけ出してくるか、闘志を奮い立たせてくるのか。そのおぜん立てをしてゆくことだと思う。これが大事なところです。ここを間違ってはいけない。最初から無条件でリーダーについていくような選手はいない。やっているうちに、興味や関心がでてきて、初めてモチベーションが高まっていくのである。医者でも自分が患者を直してやる、という姿勢で患者に接すると医師も患者もしんどいという。すれ違いが多くうまくはいかない。集談会でも悩み多き人がやって来た時、先輩会員が、症状を自分の力で治してやろうと意気込むと、アドバイスする人はとてもしんどい。またしんどい割には、相手には響いていない。治すのは患者本人、症状克服するのは症状を抱えた本人だという認識をしっかりと持てば、対応は自ずから全く違うものになると思う。
2013.09.12
コメント(0)
-
ドタキャンと気分本位の関係
私は今月末に森田の研修会の世話をしている。ところが今月上旬に当日法事の案内がきた。今年6月の時点で9月に法事があることは分かっていたので、親戚に電話をして事情を話しておいた。ところがお寺さんの都合がつかず、当日にしたとのことだった。どうしても抜けられない研修なので、家内にお参りさせてもらうことにした。これは先方も分かっていたことなので快く快諾していただいた。皆さんも前から予定を組んで先方と約束していたにもかかわらず、自分が入院することになったり、家族に不幸があったりしてどうにもならない事情でドタキャンすることがあると思う。それは事情が分かれば相手が納得してくれると思うし問題はないと思う。ところが前々から相手と約束していたにもかかわらず、どうも気乗りしなくなった、億劫になった、めんどくさくなったという気分本位のキャンセル、ドタキャンを平気でとる人がいるがこれは厳に慎みたい。いったん約束をした以上は、どんなに気分が落ち込んでいても、億劫になっても、少々の用事が入っても、万難を排してでも約束を果たす行動を取らないといけない。それが相手に対する礼儀というものではなかろうか。気分本位で行動をころころ変えると、決して相手からの信頼は得られなくなる。またそういう人は、どこでも気分本位の行動を何回も繰り返す。またある団体でそうした行動をとる人はどこの団体に属しても、常に気分本位の行動をとりがちであり、敬遠されているのだが、本人は気付いていないケースが多い。また気分本位の人は、気分で行動するために時間にとてもルーズとなる。また会議の席上、気分本位の発言が多く、相手の気持ちなど思いやることはない。相手をどん底に追いやっていても、全く知らん顔になることがある。ドタキャンの時でも相手にわびるという気持ちは全く持たない。自分の言い訳を言葉巧みに説明するのだが、本人はうまくごまかせたと思っているが、その魂胆は見え見えなのである。相手は話すことすらイヤになる。森田先生は気分本位の人は、不快な気分によって困難を回避したり、困難から逃避するようになる。すると意識は常に内向化し、自分の心と体に向かうようになる。心の不安、身体の震え、異常に向かうのである。つまり抑うつ感が強くなってくるのである。そこで抑鬱を回避するために、森田でよくいうところの行動に救いを求める。趣味や観劇、ボランティアなど少しでも興味があることはなんでもかんでも手を出して、内向する心をしいて外向させようとする。そうしないと不安に押しつぶされそうで、イライラするのです。つまりネズミが糸車を回しているような状態になる。これは蟻地獄の底からは這い出すことができるが、真の解決法ではない。最終的には気分本位の行動が事実本位の行動へと変化してこないと、抑うつ感は決して簡単にとれるようなものではないのである。気分本位の軽はずみな行動は慎みたいと思う。
2013.09.11
コメント(2)
-
他人からもっと頑張れと言われても
日本人は「頑張れ」という言葉がよほど好きなのだろう。日本語の「頑張れ」は、「耐えろ」「現状に甘んじるな」「休むな」という意味で使われることが多い。自分が自分を鼓舞している言葉ではない。他人が自分を脅している言葉である。ちなみに英語には「頑張れ」にあたる言葉はないそうです。自分で見つけた目標に向かって努力してときは、はたからみて頑張っているように見えているだけで、本人の気持ちとしては楽しんでいるのである。頑張れという言葉は、他人が「かくあるべし」という目標をその人に設定して、そこに無理やり追いこんでいるのである。その人を追いこむ言葉です。本人にしてみれば、自分自らやる気になったことや、楽しいこと、気力が満ちている時は頑張れるのである。反対に人から指示・命令されたこと、苦しいときや、意気消沈している時は頑張れないのである。それも自分の事実なのである。病院で余命いくばくもない人に「頑張って」と励ます。手術の前にも「頑張って」、麻酔が切れて痛みがでてきたのに「もう少し頑張れ」と言って励ます。頑張りたくても頑張れないのに、まだ頑張らなくてはならないのだろうか。私は頑張るか頑張らないかは本人に任せたらよいと思う。私たちのできることは、興味が起きるようにいろんなことを体験させたり、見せたり、聴かせたり、匂わせたり、味わったり、触れさせたり、情報を教えてあげることにとどめるほうがよいと思う。
2013.09.11
コメント(0)
-
東京オリンピック招致の勝因
それにしても東京の最終プレゼンは、見ていて涙がでるほどの内容であった。これは日本人が考えたものだろうか。これはイギリスのオリンピック招致請負コンサルタントのニック・バレー氏によるものだそうです。バレー氏はロンドンオリンピック、リオデジャネイロオリンピックのコンサルタントもされていたそうです。オリンピックの招致に熟知した人の後ろ盾があったことが最大の勝因だと思います。森田理論の習得も同じです。パソコンの操作でも分からないことに出会ったとき、一人で解決しようとすると時間がかかります。そんな時詳しい人に聞けばすぐに解決することが多いと思います。森田理論学習も理論がきちんと整理されている、実績もある、修養も進んでいる人についていくことがまず一番大切だと思う。その上相手を思いやる人であればよいと思う。森田理論は確立されているようで、実は最近まで理論と呼ばれるようなものはなかったのです。理論というからには、理論全体の体系、スキーム、キーワードの関連性、鳥瞰図、理論の生活への取り入れ方などが理路整然と整理されていないといけません。そういうことがよく分かっている人の後ろ盾がとても重要になると考えています。整理されていないと混乱と戸惑いが生じます。
2013.09.10
コメント(0)
-
どんなに問題があっても、自分は自分を守りきってみせる覚悟2
最近私はこう考えるようになりました。自分というのは肉体、ものを考えることのできる脳をもっている実体としての自分の存在があります。ところがもう一方に、それらを客観的に眺めて是非善悪の価値判断している、もう一人の自分が必ずいます。歳をとると実体としての自分は、寿命がくると死んで行ってしまいます。その時自分を常に客観的に見ていた自分はどうなるのでしょうか。心身同一論で言うように、その自分も未来永劫無くなってしまってしまうということなのでしようか。もう一方の見方としては、肉体が死んだあとも、魂のようなものは体から抜け出して、生き続けて、いづれまた生き返るのだという人もいます。でもこれは死んでしまわないと誰にも分かりません。こんなことを軽々しくいってはいけないのだろうと思います。しかし私は仮にそういう立場に立って考えることは意味があるように思えます。その先に今生きている意味として、見えてくるものがあるからです。例えば自分の肉体が死を迎える直前に、もう一人の自分(魂とでもいいましょうか)に対して、「今まで自分の味方になってくれてありがとう。見捨てないでいつもかばってくれたね。このご恩は決して忘れません。感謝しています。あなたとペアを組んでほんとに幸せでした。またいつか生まれ変わるようなことがあったら、またぜひあなたとペアを組んで生きてゆきたい。今後ともよろしくお願いします。」こういうふうに言われたら、もう一人の自分はとてもうれしいと思うのです。私自身は二人の自分が折り合いをつけて、こうゆう自分でありたいと強く願っています。これが反対に、「あなたは何かにつけて私を否定し続けてきました。私は、それでどれほど苦しんできたか、あなたは考えたことがありますか。もう今後あなたとはペアを組みたくありません。もう永遠にお別れです。もう二度と会うことはないでしょう。さようなら」と自分の中にいる二人の自分が、永遠に和解できずに別れるとしたら寂しすぎると思うのです。むなしい限りです。分かりあえないままなのですから。さらにこのように仲たがいをして、自分を否定し続けた人は、他人をも平気で否定する人が多いのです。その人にとって、寂しさ、むなしさは二重になり、二人の関係の修復は永遠に不可能になると思うのです。
2013.09.09
コメント(0)
-
どんなに問題があっても、自分は自分を守りきってみせる覚悟1
私は身長は163センチしかありません。頭は禿げています。老眼、近眼、乱視、赤緑色弱です。尿酸値が高く痛風持ちです。痔の手術もしました。そして仕事に行けなくなるほどの対人恐怖で人生の大半は苦しんできました。勉強もあまり出来ずに、希望の大学は落ちて浪人しました。ミスや失敗の数々は目を覆いたくなるほどです。これが私の実態です。これがまぎれもない事実です。そんなあるがままの自分を肯定して生きていきたいのですが、悪いことに自分の中に、こんな自分を毛嫌いして、否定し、罵倒するもうひとりの自分がいるのです。他人に馬鹿にされるだけならまだいいと思うのです。ところが自分がそれに輪をかけて自分をバカにしているのです。他人からもバカにされ、それに輪をかけて自分が自分のことを罵っているのです。最悪です。そうなれば生きていてもなにも面白いことはありません。いっそのこと死んでスッキリしようか。そうならない方が不思議というものです。そのように思っている人は、多いのかもしれません。どんなに問題があっても、救いようのない間違いや失敗をしても、せめて自分は自分の最大の味方になれないものでしょうか。どんなピンチでも、どんなにか追いつめられても、自分は自分を最後まで守りきって見せるという態度にはなれないものなのでしょうか。
2013.09.09
コメント(0)
-
盗心について
全集5巻397ページよりいま金が欲しくて、盗心が起きる。この心は否定してはいけない。この心はそのまま自由に解放させて、泳がせておけばよいのである。するといろんな考えが起こる。100円ぐらいのはした金は盗んでもしようがない。しかし1万円となると、ちょっとおっくうで気味が悪い。どれくらいの程度に見切りをつけたらよかろうとか、結局は盗んで罪を恐れる苦労をするよりも、我慢した方が得だとか、さまざまに考えている間に「心は万境に随って転ず」でいつの間にか、その悪心も流れ去って、安楽な気持ちになっているというふうである。強いて自分の心を、無理やりに押さえつける必要は少しもない。人を殺したいほどの憎しみの感情でも、人を押しのけてでも欲しいものを手に入れたいという欲望でも、どこまでもその感情は自由自在に泳がせておくことだ。その感情は放任するしか手がない。その時身体に少し異変があるかもしれない。ブルブルと震えながら、泣きながら、血走った表情をしながらでもよい。そして次に相手をやり込めたり、蹴落とすことを考えてみることだ。それも一つだけではなく4つも5つも案を出して、どれが一番有効だろうかと考えてみることだ。すると3分も経てば、最初の感情はひと山登って、下り坂。少し変化が起きているはずだ。少なくとも感情に引きずられて即思いつきの行動にはならないはずである。森田理論は感情は感情。行動は感情とは別物という考えなのである。行動は「生の欲望」に沿ってどこまでも貪欲に追いかけていけばよい。その時不安、恐怖心、不快感がうまく「生の欲望」の暴走に歯止めをかけてくれるようになっているという考えなのだ。
2013.09.09
コメント(0)
-
原因を確かめる
私は一回救急車で運ばれた事があった。50代のころだ。明け方盲腸付近が痛み出したのだ。とにかく痛い。のたうちまわるとはこのことだ。ふつうは我慢して夜が明けて病院に行くのだが、その時はあまりのことにこのまま放置していたら死ぬかもしれないと思った。けたたましい救急車のサイレンが聞こえた。私はトレンチャに乗せられエレベーターで1階に降ろされた。すると騒ぎを聞きつけた居住者が10名ぐらい様子をうかがっているのである。それにも気が動転した。また救急車に横になっていると、頭が下がって足が上に持ち上げられているような気がした。また救急車があまりにも揺れて、そのたびに腹に痛みが走った。病院についてからも腹が痛い。震えが止まらない。吐き気がする。点滴を打つだけで、2時間ぐらい苦しんでいた。その後医師の診断結果がでた。盲腸ではないという。尿道結石だという。尿道に石のようなものが写っていた。原因が分かってしまうと、痛みはあっても、急に不安が消えていくようだった。私の不安は原因が分からずに、自分で勝手に死に直結する病気ではないのかと判断してパニックに陥ったのである。森田先生が夜道でススキが揺れた音を聞いて、幽霊がでたと思って慌てふためくという話があるが、私も全く同じであった。苦しくてもその原因をよく見ないといけない。観察しないといけない。事実関係が分かれば、不安は解消して冷静になり適切な処置をとることに集中できるのである。
2013.09.08
コメント(0)
-
意識することと、無意識でいること
サッカーの岡田武史監督がこうおっしゃっています。脳には新皮質と旧皮質があって、人間の脳だけが新皮質が発達している。新皮質というのは物事を考えたり、判断したりする理性的な活動をになっているのですが、旧皮質に比べると処理速度が非常に遅いのです。サッカーでも、ボールをもらった時に、パスするかドリブルするかを新皮質で考えているようでは遅すぎます。旧皮質を使って素早く自然に体が動くようにならないと、いいプレーはできません。これはどういうことかというと、基本的なことができるまでは、新皮質を使ってさまざまに工夫を凝らして、意識して理性をフル回転させて技術を体に覚えこませるということです。これは意識的な行動です。ゆっくりと時間をかけて反復練習を繰り返すことです。そして、練習によって、ある程度の高い確率でできるようになったとします。いったん試合に入ると、無意識に判断しポジションをとったり、足が動くということが必要なのです。試合でパスしようか、ドリブルで行こうか、シュートしようか理性で判断していては遅すぎるということです。理性が優っていては試合では全く通用しないということです。森田理論では症状で苦しいときは、一つの不安にとらわれて、なんとかその不安から逃れたいと意識を一点に集中させている時です。とらわれていない時というのは、症状に対しては無意識の状態です。とらわれないためには症状はあるがままに受け入れてなすべことをなすという生活態度を堅持するということです。そうすると症状に対して無意識の状態が必ず訪れます。サッカーでいえば一心不乱にボールを自由に扱えるように練習をする。失敗を繰り返しながら、さまざまなフォーメーションを試してみる。そういう努力を積みます。そして試合になれば意識はお休みいただいて、無意識に全面的にお任せする。あとで振り返ってみると、無意識に身体の方が勝手に反応して動いていた、という状態がベストなわけです。岡田監督は、森田理論の真髄を語っていると思います。
2013.09.07
コメント(0)
-
意欲の高め方
やる気というものはどうしたらでてくるのでしようか。森田では物事を観察し、見つめていたり、なりきることによって感じがでてくる。感じがでてくればやる気がでてきて、自発的に行動するようになる。創意工夫がでてくればさらに感じが高まる。どんどん好循環が始まるといいます。意欲がでてきたり、モチュベーションが高まることが活き活きと生きることにつながります。今日はそれ以外のやる気を高める方法を考えてみたい。私の取り入れていることです。1、 ライバルを持つ。私たちは負けず嫌いです。同じぐらいの力の人か少し上の人をライバルとして意識するようになると、途端にやる気に火がつきます。2、 目標を持つ。それも小さな目標を持つ。こまかい雑用をきちんとこなしていくようになれば、仕事の回転がよくなります。小さなトラブルも未然に防ぐことができるようになります。仕事を追っていくようになると仕事が楽しくなります。弾みがついてきます。3、 人に評価される。自分のやったことを上司や同僚から評価されると、さらにやる気が増してきます。4、 見返りがある。報酬がある。評価が給料やボーナスなどに跳ね返ってくればますますやる気になります。また何か達成すると自分に自分がプレゼントを考える。5、 やる気のある人やグループに参加する。自然にやる気がみなぎってきます。集談会でも治った人の側にいて薫陶を受ければそれだけ自分も早く治ることができます。6、 心身をいったん弛緩状態に意識して落とす。これは森田理論の緊張と弛緩状態のリズムを作るという応用です。人間の行動は波のようにあがったり下がったりを繰り返しているという現象を利用するのです。
2013.09.07
コメント(0)
-
両面観で事実を見る
顔色の黒い人はよく見られません。場合によっては肝臓でも悪いのではないか。酒の飲み過ぎではないのか。遊んでばかりいるのではないか。勉強してないのではないか等です。これは一面の見方です。森田先生はそんなことではその人を見たことにはならないはずだといっておられます。逆に色の黒い人は多くの利点があるといっておられます。汚れが目立たない。健康相に見える。女難、男難除けになる。力が強そうに見える。威厳があるように見える。夜逃げする時に人の目にかからない。などです。醜貌恐怖の人がおられます。それがなかったら人と対等に接して、女性にも持てるのではないかと思っておられると思うのです。でも私は仮に醜貌恐怖が無くなると、その人の人生を暗転させるような事件が発生すると思います。つまりその人は人からよく見られたい、人を自由にコントロールしたいという欲望が強いのです。それが野放しになり、やりたい放題のことを自信を持ってやりだすと、ハタ迷惑この上ないことになります。でもこの醜貌恐怖を持っているおかげで、それが結果的にセーブとして働き、やたら女性に手を出して多くの人に迷惑をかけるということが避けられているのです。男性には性欲が強くて自分が電車の中にのって痴漢でもするのではないかと気にする人がいます。そして満員電車には全く乗れない人もいます。女性専用車両があるのだから、男性専用車両を作ってほしいという人もいます。また両手を吊革にひっかけて痴漢はしませんよとアピールしている人もいるようです。男性は満員電車で女性と接近するとむらむらと欲望が湧いてどうしようもなくなります。私もそうです。これは自然現象です。反対に全く意識しないという人は、種族保存欲求がなく生命力が貧弱であるということです。だから性欲を減退させよう。感じないようにしようとすることは不可能であり、無意味であり、生命力あふれた人間から遠ざかることです。性欲には自然にかなったよい面と暴走すると社会的に迷惑をかけるという両面で見ないといけません。すべての物事にはプラスがあれば必ずマイナスがあるということです。それはコインの裏と表の関係です。そうゆう見方で事実を見れるようになること。そして2つの事実のバランスを微妙にとっていくこと。これを森田は目指しているのだということをしっかりと認識してゆきましょう。
2013.09.06
コメント(0)
-
死地に生を得る
王選手は荒川コーチとともに血のにじむ練習で一本足打法を完成させた。王さんの打ちこみの練習は打撃投手がねを上げて、別の打撃投手に変更してまでも行われていた。王さんは練習の意味を次のように話しています。「バッティングは感性だけど、根本は体に覚えこませる。徹底的に身体に染みこませる。その繰り返しなんだよ。なぜ長い時間打つかといえば、長く打てば当然疲れる。疲れた時って体は正直なんだ。自然体になるんだよ。つまり、体が勝手に無理のない自然の動きをしてくれる。自分の脳が描いている理想のスイングではなく、体が自然に回転する動き、それって実は理想のフォームなんだよね。だから、徹底的に体を痛めしけて、もう限界っていうところでスイングしたのが理想だということ。どこにも力みがなく、どこにも邪念がない。徹底的に体を疲れさせたからこそ、体が一番スムーズなスイングを出す。」これは神経症から解放される道とよく似ています。神経症はイヤなことをやりくりし、つらいことから逃げるという行動を繰り返すことから、精神交互作用で固着してきます。玉野井幹雄さんは、神経症が固着して、どんなに苦しくても治すことをやめた時に転機は訪れる。このことを地獄に家を建てて住むと表現されています。絶体絶命の立場に立って、神経症を治してやろうとか、やっつけてしまおうとかいう気力がなくなった時に、初めて神経症が治るのだといわれています。いったんそうした地獄を見た人が立ち治ると、鬼に金棒だと思います。再発することはないと思います。それは神経症の発症のからくりが身をもって体得できるからです。いつまでも神経症が治らないといっている人は、どこかに神経症は治す道があると思って、まだまだ対決するエネルギーが残っており、絶体絶命の心境にならないからだと思います。パニック障害の方が森田療法で短期に回復される例をよく見受けます。この方たちは生きるか死ぬかというとても厳しい状況に、このむと好まざるにかかわらず追い込まれるために、かえって死地に生を得るということになるのです。
2013.09.05
コメント(0)
-
自分の死後はどうなるのか
森田先生は死の恐怖ということを言われています。死はどうすることもできない。死は恐れざるを得ない。これは確かに真実です。これが究極の恐怖だと思う。最近「生きがいの本質」飯田史彦さんの本を読んで感じたことがあります。人間が死んだあとはどうなるかということです。2つの考え方があると思います。一つには死後世界などはない。死んだら骨と灰になってしまう。それでおしまいというものです。二つ目には、そうではない。死後体は無くなるが、魂は生き続けるというものです。輪廻転生の考え方です。しかしこれは、我々にはどちらが正しいのか全く分からない。死んでみないと全く確かめようがない。あてずっぽうでいっても仕方ない。臨死体験を持つ人もいるようだが、どうも説得力に欠ける。こういう前提に立って考えるとすると、私は、魂はいつまでも生き続けるという考えを前提にして、今を生きていく方がよいと思う。死んだらもうおしまいという考えに立つと、不安や恐怖がどんどん大きくなる。またこの世で相手を押しのけてでも、自己中心的に享楽的、独占的、支配的な生き方に偏ってしまうと思う。そうした破れかぶれの生き方というのは、どうも違和感がある。仮に魂が生き続けると考えると、生き方が変わってくると思う。よい意味で、今現在の生き方に影響を与えると思うのです。自己中心的な生き方ではなく、他人に尽くすような生き方、将来が少しでもよくなるような生き方、他人に感謝するような生き方に変わってくると思う。この世で精一杯生きていかないと次にはつながらないと思うからだ。次に生まれ変わる時に、さらによりよい生き方ができるように努力するようになると思う。もし仮に、死んだらそれですべては終わりという結果なっても、そういう生き方ができれば、それはそれでよいのではないかと私は考えます。歳をとればとるほど1年1年があっという間に過ぎてしまいます。一日一日を大切に生きていきたいと思う今日この頃です。
2013.09.04
コメント(0)
-
他人とのかかわり方
森田の相互学習をしてきて、他人に自分の「かくあるべし」を押し付けてはいけないことはよく分かった。そしたら他人とはどうかかわったらよいのか。これも森田理論の学習でよく分かったことがある。他人が活き活きと生活するためには、好奇心を発揮してさまざまなことを経験する中で、感じが高まり、意欲がでてきて積極的な行動が自然とできるようになることである。それが軌道に乗れば生きることが楽しくなってくる。それを少しでも自分が援助できればよい。このプロセスの中で自分がどうかかわれば、相手の役に立つだろうか。私は最初の部分でかかわればよいと思う。その後は相手に任せることがよいと思う。ここでは相手が関心や興味をひいたり、好奇心を引くような関わりが持てれば最高だと思う。それ以上の事は小さな親切大きなお世話となる可能性が大である。具体的にいえば、自分の多彩な趣味や好きなスポーツ、感動した本、映画、テレビ情報、自分の得意なもの、自分の体験したこと、挑戦したこと、今現在取り組んでいる事、自分の考え、お得な情報などを相手に提供してあげることだと思う。全部が全部相手に関心を持ってはもらえないと思うが、たまには刺激を受けて自分の生活の中に取り入れたり、新たに挑戦してみようという意欲につながったりするものがでてくると思う。そういう人間関係を築いていくことが大切だと思う。
2013.09.04
コメント(0)
-
「ゆとり」について考える
以前「ゆとり教育」ということがいわれていました。また「ゆとりある暮らし」、「ゆとりのある老後」ということもよく言われます。ゆとりという言葉を分析すると、経済的に余裕がある生活、時間的に余裕のある暮らしということを示していると思われます。お金の面では給料や年金で毎月の生活費を賄い、退職金や親の遺産が転がり込んでくれば貯金して余裕のある生活となります。また時間的には、掃除、洗濯、食事の準備などのこまごました雑事はできるだけ家電や他人に任せて、自分の自由な時間を作る。今の世の中、掃除は掃除ロボットもあります。洗濯はほとんどの家が全自動洗濯機です。食事も外食に行く機会が増え、自分で作るという人も、宅配サービスを利用する人もでてきました。こうしてゆとりある資金と時間を作り出した人はたくさんいます。その人たちは、満ち足りた生活をしているのでしようか。ゆとりのある生活を作り出してなにをしているのでしょうか。ゆとりある資金と時間で、もともと自分のやりたかったことに振り向けているのでしょうか。一般的には、夜更かしをして、家の中でごろごろして、テレビ三昧。ギャンブル三昧。旅行やグルメ、趣味に没頭し、観劇を楽しんだり、気のきいた人はボランティアなどが多いのではなかろうか。全員がそうだとは思いませんが、次のようにいう人がいます。「私は釣りが好きで、現役のころは退職したら毎日釣り三昧の生活を楽しむことを励みに頑張ってきました。でもそれが実現して毎日好きなことをしているのに、充実感といったものがないのです。そのうち釣りにも飽きてしまいました」若い時に苦労して、年齢を重ねてやっとゆとりある生活を手に入れて、さあこれから思い切り楽しむぞと思って始めた生活のどこに問題があったのだろうか。私は思う。山のあなたの空遠く幸いすむと人の言う。実はそんなところには幸せはないのではないか。日々過ぎ去っていく日常茶飯事の中、雑事、雑用、雑仕事の中にこそ幸せの種はあるのではなかろうか。手を抜いて自由な生活を手に入れるという目標設定自体間違っているのではなかろうか。森田先生はたくさんお金を貯められました。でも余分のお金は寄付されています。普段の生活はせんべい布団にくるまり、詰襟の服を着用されていたという。ところが日常生活は風呂焚きにしろ、便所の汲み取り、マキ割り、ご飯炊き、ウサギやニワトリを飼い、野菜のくず拾いにまで手を出され、大学での講義、入院生の指導、外来患者の診察、通信指導、形外会での指導などどれをとっても一心不乱に取り組んでおられました。これから分かることは、普段は面倒だ、億劫だと思えるような日常生活に真剣に向き合うことの中に、心満ち足りた生活は待ち構えているのではなかろうか。
2013.09.04
コメント(0)
-
ピンチのあとにチャンスが来る
1970年代80年代に現役でバリバリに働いていた人は、毎年昇給があるし、ボーナスもこんなにもらっていいのかという時代を経験されていたと思います。あらゆる職業が右肩上がりでした。ところがバブルがはじけた90年代以降はしだいに右肩下がりで、ボーナスはすすめの涙、私のところなどは給料カットもありました。そして今は混迷の時代になってきました。混乱の時代です。こんな時代では親の援助のある人はともかく、子育て、家のローンなどを抱えた人は大変だと思います。夫婦共稼ぎという家も増えてきました。将来年金がまともにもらえるかどうかもよく分かりません。でもせっかく森田理論を学習しているのですから、両面観で考えてみませんか。一つは好むと好まざるにかかわらず、頭をフル回転させなければやっていけない時代だということです。今までのように作れば売れるという時代ではありません。お客様のニーズを予測し、仮説を立てて、実行する。うまくいかなければさらに修正していく。その繰り返しでお客様の変化を追いかけていく。そうした創意工夫は、いまの時代だからこそ手をつけられるのではないでしょうか。真面目に向かっていけば、自分の能力が育って成長できる環境にあると言えるのではないでしょうか。また不況だから全部の業種がダメかというとそうではありません。リサイクルショップ、エコカー、カーシェアリング、ブックオフ等の古本屋、レンタルビデオなどははやっています。不況は大変です。でもこれは最大のチャンスだという人がいます。その人たちが次の時代を作っていくのではないでしょうか。ピンチの後にチャンスがくるといいます。このまたとないチャンスをとらえようではありませんか。
2013.09.04
コメント(0)
-
かくあるべしでは相手は動かせない
自分がこれから勉強しようとしていた時に、突然親から、「テレビばかり見てないで、宿題しなさいよ」といわれると、急に勉強する意欲がなくなることがある。これはなぜだろうか。森田でいう「生の欲望」にのって勉強を始めればよいと思うのだが。これは指示、命令、批判されることに対して、人間は拒絶反応があるのだと思う。それは自分が今現在勉強をしていないという事実を否定されるからだと思う。自分の行動の事実を他者から否定されることは、そこに他者との間に軋轢を引き起こすのである。どうすればよいのだろう。一つの例として、この場合、「お母さんは、あなたが早く宿題を済ませてくれるとうれしいんだけどな」と自分の気持ちを伝え、あとは子供に任せる気持ちが大事だと思います。森田学習でいう私メッセージでの対応です。押しつけとか、体罰とか、義務感で行動をさせることはできても、継続することは困難です。自分が自ら目標に向かって努力しようと思わない限り、困難に打ち勝って前進することはできない。この例では、「かくあるべし」を子供に押し付けることによって、勉強しようという意欲を摘み取ってしまったのである。「かくあるべし」で叱咤激励すればするほど、才能は伸びてこない。むしろ本人をダメにしてしまう。肝に銘じておきたいことである。
2013.09.03
コメント(0)
-
森田理論で見つけた生きる意義について
私は生きていく上で大切なことが2つあると思っている。一つは自分にとって自分が最大の理解者であること。味方になってあげること。どんなに劣等感があっても、どんなに弱みを持っていても、ミスや失敗をしても常にバックアップ体制をとってあげること。決して後ろから石を投げつけたりしない。最前線で戦っている自分に対して、できるだけしっかりと援護射撃ができること。そんなことは当たり前だという人もいるかもしれない。私の場合は、自分という一人の人間の中に二人の自分がいた。片方の自分が、現実でのたうちまわっている別の自分を、常に厳しく監視していて、是非善悪の判定をおこなっていたのである。こんな不幸なことはない。この世の地獄である。人からはどんなに批判的に見られてもいい。でも自分だけはどんなに厳しい状況になっても総力を挙げて自分の味方になってみよう。いたわり励まして、支えていこうと決めたのです。もう一つは、私は対人恐怖症になって仕事で躓いた。どうしても人間関係をうまく築くことができないで苦しんできた。でも今考えれば、これは神様が自分に対して与えた課題、宿題だったのではないかと思う。神様はそうした問題を自分に与えて、どのように対応するのだろうかじっと見ておられるのではなかろうか。これは人間に生まれてきたからには誰にでも与えられていると思う。例外はありえない。私の場合、人生の大半は苦しみの連続であったが、やっと森田理論に出会い解決の糸口を見つけ出した。まだまだ完全に解決したとは思えない。さらに修養を積んでいく必要がある。でも未来には明るい光が見えてきた感じがする。森田でやっと、神様が自分に課した課題や宿題を解決する道筋が見えてきたのです。これが私にとっての生きる意味だったのではなかったのかと思えるのです。このことに気がついたというのがうれしいのです。
2013.09.02
コメント(4)
-
小学校4年生の憂鬱
宮川俊彦さんの「心が壊れる子供たち」という本に子どもたちの本音がのっている。「毎日決まった時間になると学校に行きます。そしていっぱいのお友達にかこまれて楽しく一日を過ごします。授業もふつうです。そして、だいたい決まった時間になると帰ってきて、少し休んでから塾に行きます。そこには友達がいます。先生も楽しいです。7時ちょっとすぎに帰ってきます。お父さんもお母さんも明るいし、私のことを大切にしてくれます。文句のない毎日だと思います。でもふとこれが生きているってことかなと思って不安になってきます。死んじゃったら、と思うことも多くなりました。」(小4女子)欲しいものはなんでも買ってもらえ、親にこれをやりたいといえばいくらでも資金援助をしてもらえる。何も不足していないように見える。いや恵まれ過ぎている。それ以上のことを言えば罰が当たるのでは。そうだろうか。子供たちの言動から何を見てゆけばよいのか。それは一言でいえば「生きがい」の喪失である。いくら物質的に恵まれていても、「生きがい」のない人生は、人間である以上生きていくことはできないのである。ましてや子供たちは親から「かくあるべし」で、親の価値観に無理やり従わされ、日常生活は学校、塾やスポーツクラブで一日中息つく暇もない。また仲間外れにならないように、友達との人間関係に異常に気を使わなくてはならない。窒息状態で何とか毎日をこなしているのである。自分を抑圧した生活が楽しめるはずもない。最近は反発する意欲もなく借りてきた猫のように割り切っている子も多い。でも心のもやもやは晴れない。こうした子供たちに森田は応用できないだろうか。人間が生きるということは何か。生の欲望の発揮から解説できないだろうか。また「かくあるべし」は人間に葛藤や苦悩をもたらすものであること。自然に服従して生きる生き方が最も人間らしい生き方であることなど。森田はもっともっと社会に警告を発信してゆくべきだと思う。
2013.09.02
コメント(0)
-
今日も充実の一日だった
今日は9時から「半沢直樹」が楽しみだ。NHKで地震の番組もあるので録画することにして後で見たい。今日はBS朝日の「神秘の大宇宙」の連続録画を見たが、興味は尽きない。宇宙銀河の映像はとてもきれいだった。引力と遠心力でバランスをとりながら常に流動変化しているというのが、とてもおもしろい。あと、人体の仕組みの番組も見逃せない。脳の仕組みにしろ、免疫の仕組みにしろ、人間はよくこれほどまでに進化してきたものだ。いろいろと試行錯誤を繰り返して、今にたどりついたことに感動を覚えています。さて今日は「獅子舞い」の稽古に出かけてきた。生徒5人。先生一人。先生は有名な構造設計の一級建築士だ。生徒も多彩で、警察の元刑事。現役の学校の先生。元電気工事の社長とその奥さん。元刑事さんと話をしたところ、今県の南京玉すだれの先生をしているという。また安来のどじょうすくいで2カ月に一回ペースで老人ホームの慰問をしているという。娘さんはなぎなたで高校生を週3日指導しているという。師範の免許があるという。私の趣味の仲間は、とにかく元気いっぱいの人が多い。好奇心いっぱいなのだ。こうゆう人と付き合ってると、自然にエネルギーがたまってくるような気がする。
2013.09.01
コメント(0)
-
不安を抱えたままなすべをなす
森田先生の言葉です。我々は何かにつけて、疑問と不安は絶えず出没して、これを一つ一つ解決して、しかる後初めて安心することのできるものではない。ただ我々は疑問は疑問として、これが解決の時節を待つよりほかに仕方はなく、日常の生活は周囲の刺激から、次から次へとめまぐるしく引きまわされて、不安も不安のままに、いつまでも執着していられるものでもなし、「流れに浮かぶウタカタのかつ消えかつ結びて」変化極まりないものである。強迫観念も、この理を知って、無理にただ一つのことを解決しようと、もがかずに、素直に境遇に柔順でありさえすれば、苦しい不安でも、水のうえの泡のように、水の流れの早いほど早く消えて、跡をとどめぬようになるものである。不安を抱えたままなすべきことができるようになることは一つの能力です。この能力は森田理論学習と修養によって身につけることができます。この能力を身につけると症状に対する見方が180度変わってきます。
2013.09.01
コメント(0)
-
集談会は心の居場所
25年8月号の特別寄稿「現代における森田療法のあり方と集談会の役割」という記事にはびっくりした。この方は大学4年生で、文化人類学を専攻しているという。この人が何回も指摘しているが、集談会は同じ神経症の人が集まる「居場所」としての役割がある。同感である。職業も性別も年齢も異なる人が月一回集まり、森田理論学習をして、あとで懇親会をする。それを継続する。自然と人間関係ができてくる。月一回の薄い人間関係だが、中身はとても濃いい。また、支部活動などで幅広い地域の人たちと知り合い交流の輪を広げてきた。27年も続けてきたので今や私の財産である。もしこの居場所がなかったとしたら、とてもさみしい人生となっていたと思う。私はこのほか家族の人間関係、仕事の人間関係、趣味の人間関係などがあるが、集談会の人間関係が一番中身がよいと思う。さらに森田理論学習によって、自分のすすむべき道も見つけることで出来たのだから、集談会から離れられないのである。
2013.09.01
コメント(0)
-
一呼吸置く態度を身につける
自分の子どもや会社の部下、親や配偶者の話を最後までよく聞かずに、途中で話の腰を折ってしまうことがあります。聞いている本人は、最後まで聞かなくても相手の言いたいことは大体よく分かる。自分の方が経験も知識も豊富なのだから自分の方が正しい。聞くことよりも、是非善悪の判定をして、正論を教えてやる。指示、命令、禁止、強制でもって相手を導く。これらの気持ちが強いのでしょう。そうすると子供や部下はすぐに反発してきます。自分を理解しようとしない自分勝手な人だと思います。しだいに敬遠するようになるでしょう。こんな人は森田理論学習をして、応用してもらいたいと思います。まずそんな人は価値判断や是非善悪の判定の前にする事があります。自分いいたいことを言う前にまず「一呼吸置く」ようにすることです。相手に対して、「今言ったのはこういうこと」「私はあなたのおっしゃったことをこうゆうふうに理解しました。これで間違いありませんか」と確認するということです。相手の言葉を翻訳してみるといってもいいでしょう。オオム返しに確認するという態度です。これをはさむことによって、子供や部下に「かくあるべし」を押し付けることをとりあえず回避することができます。相手は「そうだ」「それは違います」というでしょう。相手には自分の考えをさらにまとめる時間的余裕が与えられます。話が途切れずに次につながってゆきます。これがなぜいいのかというと、本来人間の主体的行動というのは、段階を踏んで初めて可能になるからです。まず事件に遭遇したり、体験したりして事実をよく確認します。すると感じが起きてきます。感じが高まると、次に「こうしたい」という意思が働いてきます。その意志が高まることによって、最終的に行動へと結びついてゆくのです。他の人が行動を強制するとどうなるか。状況を確認し、感情の発生や高まりというプロセスを無視して、いきなり行動を迫るということになります。つまり主体的、自主的な行動に結びついていかなくなります。「かくあるべし」を押し付けることの弊害はここにあるのです。これは意識すれば修正できることです。
2013.09.01
コメント(0)
全50件 (50件中 1-50件目)
1