2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2010年01月の記事
全52件 (52件中 1-50件目)
-

一触即発
安くて軽くて使い勝手が良かったけど少しでかいな、と思っていたマイネルのシェイカー。これをスネアケースの変なところに突っ込んでおいたらいつの間にかひしゃげてしまって、ちょっと振り辛くなってしまった。音には影響が無いから使っていたんだけど、最近ずっと買い替えようとは思っていて、今日も楽器店で物色していた。Tocaのシェイカーがサイズ、重さともに丁度良かったけど少し高価い。結局買わずに帰ってきた。 その帰り、近所のダイソーで、会社の研修で必要な文房具や電卓を見ていた。どうせならペンケースもいるかな、と思って見ていたら、金属製の円筒状のペンケースを見つける。これちょっといいな、と思っていたら急に神が降りてきた。 「お前、ソレにビーズとか入れてシェイカーにすればいいじゃん」聖書 ビーズを眺めたけど、手芸用のビーズの梱包形態はいくら振ってみても音が解るように出来ていない。とりあえずペンケース(と、その他必要なもの)だけ買ってそのまま帰宅。 家に帰るなり、ニッパーを取り出しおもむろにマイネルのを切り裂く。意外にプラモ用ニッパーで金属切れるもんだね(笑)。そして中身を取り出し、ペンケースにぶち込んで、あとは気持ちの問題でターゲットのステッカー貼って、完成!振ってみると普通のシェイカーの音がする。大成功だ。 以前同じダイソーで買ったタンバリンもなかなか侮れない楽器だったが、コレは(中身はマイネルだけあって?)それを遥かに超える素晴らしい楽器だ。軽くて、安くて(笑)、しかもコンパクト。コレは進化だ。 ちなみに現行のダイソータンバリンは以前とは比較にならないくらいショボい楽器になってしまった。がっかりだ。 唯一(?)の欠点は、コレ多分油断してると蓋が取れちゃうと思うんだよね。そうなったら、もうおしまいだ。だって俺は金ぴかの時計をもって喜ばなくちゃならないんだ。あぁ~ああ~空が~破けて~・・・ ・・・? すいません。間違えてうっかり「一触即発」歌ってしまいました。 なんだっけ、ああ、そうなったら、中身が楽器のケースとかの中でばらまかれて大変なことになっちゃう。大変、ってーか面倒くさい。もうおしまい、ってほどじゃねえよな。蓋を瞬着でくっつけちゃえばいいのか。でも折角中身入れ替えられるのになぁ。まあ、もう一個買ってきてもいいんだけどさ。100円だし。
2010.01.31
コメント(2)
-
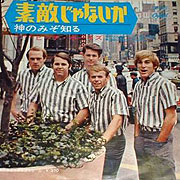
Wouldn't It Be Nice
プリティーズのライヴ~会社の呑み会~研修、って三連荘はキツい。 ビーチボーイズも来てたんだねぇ。見たいか見たくないか、という二択ならやっぱり見たい。だけど高額ってのもあるし、同じメンバー二人って条件ならプリティーズの方が魅力的だ。 フーも比較に入れようか。メンバーの不在を考える。プリティーズならポーヴィ、ウォーラー、スキッパー。フーはジョンとキース。それに比べ、ビーチボーイズはブライアン、デニス、カール、アル(流石にリッキー・ファターとブロンディ・チャップリンと言うつもりは無い)。 不在なのがシンガー、っていうのは大きいよな。中央に立つフロントマンが健在、ってのは3バンドに共通していて、そういう意味では充分楽しめるステージを見せてくれると思う。でもビーチボーイズの場合、やっぱりメインたるカールの不在、コレはあまりにも大きい。 ビーチボーイズの魅力にプライオリティを付ければ一にカールの歌声。次いでブライアンの曲、シンガー、フロントマンとしてのマイク、っていう順位になり、この三大要素に他のメンバーやサポートが肉付けをした上での素敵なビーチボーイズ、っていう感じだと思うんだ。 今のビーチボーイズには上位三要素の二つは揃っている。充分だ、とも言える。行ってみれば絶対楽しいだろう。それなりに満足すると思う。俺は全然マイク否定派(老害評論家中山康樹のような!)では無い。むしろマイクのいないビーチボーイズこそ最も「観る」価値のないものだと思う。ブライアンのソロなんか見ても、楽しいけどビーチボーイズの楽しさとは全然違うでしょ。ステージ、という意味に限定するなら「マイクの存在」って絶対だと思うんだ。多分一位。そういう意味では来日公演、見とくべきかな、とも思う。 やっぱり二の足運んでしまうのは、俺があまりにもカール・ウィルソンと言う美声が好きだからなんだな。多分ブライアンのバンドにマイク&ブルースが合体して「完璧なビーチボーイズサウンド」を聴かせてくれても、俺同じコト言ってると思う。
2010.01.31
コメント(0)
-
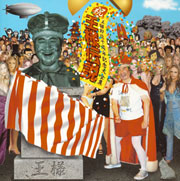
Kill The King
来日公演全日程が終わるまで特集は続くけど、とりあえず別のお話。 以前「マイケルがキング・オブ・ポップは言い得て妙」と言う話をしたけど、書店に行ったらボウイ(デイヴィッドにあらず)の「キング・オブ・ロック」と題された本が売っていて笑った。いや、いくら何でも(笑)ねえよ。 流石にね、一応「日本では」って断り付きだと思うよ、意味としては。世界って要素は一個も無いからね。でも、ちょっと「キング」はねえだろう。俺が全然好きじゃない、って言うのは置くとしたって、だよ。 80年代終盤以降の日本のロック(?ポップス、か?)に多大な影響を与えたのは認めるし、当時の人気の凄さも知ってるよ。でもどう考えても「キング」ってレベルの存在にはあまりにも遠いんじゃねえの。「器じゃない」って表現が非情にぴったりくる。 とは言っても、「じゃあ誰が(日本の)キングなのよ?」って言われたら少し困る。「器」ってレベルならボウイなんかより遥かに凄いのが山ほどいるんだけど、そこに「売り上げ」(マイケルを語る時にも無視出来ない要素)という要素を加えて考えた時に、あくまで「ロック」って枠で考えて当てはまる人がいるのか、と言われると難しいな。 ちょっとググったら真心ブラザーズに「キング・オブ・ロック」って作品があることが解った。もっと似合わない。 あえて言うならやっぱりYMOか。でもなんか佇まいがな。キングじゃない感じだよな。でもなんか細野さんが王様だったら少し嬉しい気がするけどね。なんか、いい国になりそうじゃん。全然ロック関係ないけど。王妃は森高千里(ネタが古いよ)。 要するにアレだね、マイケルの時書いたけど、日本にはああいうゴージャス感を持った人いないからさ。どうしたって貧乏臭いじゃん。似合わねえよ、日本人に「キング」なんて冠は。天皇とかで充分だろ。「天皇・オブ・ロック」うわーかっこわりー。 画像が出落ちであったことを深くおわびいたします。
2010.01.30
コメント(3)
-

The BBC Sessions
60年代のバンドのBBCライヴなんてーと60年代の音源しか入らないのだろう、なんて思ってたら60年代から70年代まで(二度目の解散まで)網羅されちゃってた、という衝撃、というか俺が勝手に思い込んでただけなんだけど、そんな嬉しい内容のCDがこれ。リリースされた瞬間に飛びついた(いや、タイムラグあった筈だな)。 多分このCDでほぼ全ラインナップのプリティーズが、しかもライヴで聴けるんじゃないかな。64年の音源はヴィヴだと思うし、スキッパーが入って、トゥインクが入って、ヴィクター・ユニットはいないかもな。70年の3曲がユニットかトルスンか微妙だ。 初期のライヴも荒っぽくていいんだけど、やっぱり俺が嬉しいのは70年以降。もっと言っちゃうと72~75年のライヴで、特にFreeway MadnessとSilk Torpedoの収録曲はコレと、オリジナルアルバムのボーナストラックでかなりの曲がライヴでも聴ける、という状態。コレは素敵だ。あとブートのLondon Live Torpedoを持ってればもっと嬉しいぞ。 72年、トルスン&ブルックスを擁するラインナップでのRosalynや75年のグリーン、エドワーズ在籍時のBig Cityなんてある意味珍品もあるのは楽しい。特に後者は64年のオリジナルラインナップでのライヴも入ってるから聴き比べると面白いぞ。メイ以外全員入れ替わってるからもう全然別物なんだけどさ、ソレでも通底する「プリティ・シングス」っていうものを感じるんだよな。俺が今までのレビューで散々言って来たこと、それを強く、端的に、お手軽に感じられる2テイク。 サイケ期のDefecting GreyやWalking Through My Dreams、そしてSorrowの楽曲群も嬉しい。まあ、BBCライヴっていうのはそれなりにスタジオのギミック(オーバーダブや編集)も使えるからこれらの曲をどの程度生で再現したかは不明だけど、それでも嬉しいことには変わりない。Defecting Greyは結構スタジオテイクの音使ってそうにも聴こえるけどな。 ちなみにLove is Good / Onion Soup / Another Bowlが1トラックになってる(しかもジャケにはLove Is Goodとしか書いていない)んだけど、これはメドレーじゃなくて、Love Is Goodの前に司会者のMCが入る(勿論Onion Soupはメドレー)。この後もう一回別の日のOnion Soupが入ってるからなんか混乱したのかな。曲順もさ、前述の3曲の後にRoute 66で、その次がまたOnion SoupとRoute 66って流れだから。まあ放送順なんだけど、少しどうにかならなかったのか。 あ、Route 66はスキッパーがヴォーカルじゃありません。 未発表曲が2曲。サイケ時代のちょっとポップな、なんか「悪いモンキーズ」って雰囲気もあるTurn My Headと、75年のポーヴィのピアノソロNot Only But Also。後者はアドリブかもな。 それにしてもディスク1が27曲、ディスク2が14曲、収録時間はほぼ同じ、っていうバランスの悪さは凄いな。
2010.01.29
コメント(0)
-

Old Man Still Going
ロシア料理を食いそびれた。 プリティーズ来日公演、開場18時と言うことなので、17時に高田馬場駅前のBECK'Sで同行者と待ち合わせ。先に飯でも食って行こうと誘ったら高田馬場にロシア料理屋さんがあるからそこにしようと言うのでそれに乗ったのだ。だが、その店は17:30開店。やむを得ず隣でピザを食う。ライヴ前にビール2杯も飲んでしまっていいのかソレで、と思うがまあ良しとしよう。名前と音楽の話をひとしきりしていたら18:30。丁度よさそうなので会場のAREAというライヴハウスへ向かう。 会場は「西友の下」と言うなかなか凄いロケーション。同行者が「こんなところにプリティ・シングスがいるんですね」とか言うのに思わずうなずく。 以下、何でもかんでも書いてしまうので、土曜日見に行く情報が欲しくない人は読まないことをお勧めする。ただ、一つだけ。前座は観た方がいい。最初に(現行メンバーのバンド)マルチックスが出るので、せめてそれは見た方がいい。驚く筈だ。 そんなマルチックスは予想より遥かに良い。基本ブルーズ(カヴァーが殆ど)なんで、定番曲ばかりで聴きやすいと思う。多分オリジナル曲ではアコギとヴォーカル、ドラムだけになるんだけど、それは少しホワイト・ストライプスっぽかった。 次は日本のバンド、パラシュートと言うバンドで、案の定プリティーズのアルバムから名前を取ったと言うが、パラシュートより前の時代が好きそうな音。まあ、所謂ガレージ系で、それ以上でも無ければそれ以下でも無い。全く予想から外れることのない普通の音楽を数十分垂れ流して、最後の長尺にすっかり飽きた頃にようやく終了。疲れた。俺は退屈だったね。 で、満を持してプリティーズ。ニコニコして登場するフィル、ディック、フランクと新メンバーの若いの二人、そしてどう見てもゲイのマーク・セント・ジョン。今回マネージャーは終始ステージでパーカッションとバックヴォーカルを担当。音に厚みを与えていた。 オープニングはやっぱりRoadrunner。もう初っぱなから会場も最高潮。続いてDon't Bring Me Down、そして最新作からBeat Goes On。若いのはともかく、ディックもフィルも全然衰えてねえ!6年前のDVDから、見た目はともかく老けてねえ!見た目は単なるご機嫌なおじいちゃんだけど。 続いて!俺狂喜の名曲Alexanderが登場!そしてコレを皮切りにサイケの時代へ・・・そう、S.F. Sorrowの登場だ!しかもS.F. Sorrow Was Born, She Says Good Morning, Balloon Burning, Baron SaturdayそしてLoneliest Personと、要するにアルバムをダイジェストで再現、という感じなのだ。Baron Saturdayのサビは新人ベーシストが歌ってたけど、コレが結構ウォーリーに声が似てて良かった。ってーか新人君達、全体に良い仕事。 フィルのMCで「63年が云々」というので「?」と思っていた。プリティーズは64年デビューだからね。キース・リチャーズだとかストーンズ、って名前が出てきて、ディックがアコギを持つので「なるほど」となるわけだが。他のメンバーが引っ込んでShe Just SatisfiedとCome on in My Kitchenを演奏(後者はフランクがハープで参加)。ああ、そう言えば今年も最初に見るアーティストがブルーズを演るのか。しかもロバート・ジョンソンを。しかし、求道的なエリックと違い、やっぱり(今でも)プリティーズはブルーズをぶち壊す気満々だ。フィルがもう、叫ぶこと。渋い、いや、渋くない。その狭間で、腹が出て白髪で剥げたおじいちゃんがあくまで荒々しく、ブルーズ、いや、ロックする。凄い。 後半戦は再び初期に戻ってBuzz The Jerk、そしてCome See Me, Midnight to Six Man。この辺もう会場大熱狂。この爺どもはこんなライヴハウスが似合う。似合いすぎる。ホールでは見たくない爺だな。終演後同行者が「大阪は凄いだろうな」って言ってたけど、確かに大阪向けかも。 次の曲はタイトル思い出せないんだけど、その次が待ってましたのCries From The Midnight Circus。俺の大好きな曲の一つで、同行者もParachute好きなので二人で狂喜。ヘヴィで格好良い!結局Parachuteからはコレしか演らなかったけど、いやもう嬉しいです。 そして続いてはL.S.D.。更にメドレーで(40周年ライヴと同じく)Old Man Going。前半のSorrowコーナーでやらなかったのはここに残しておいたから、ってのは解ってたんだけどね。ドラムが凄い!いや、全員凄い!「老人は行く」って、お前らのことだろ!? アンコールは勿論Rosalyn。ディックのギターから始まるんだけど、いきなりテンポが速くて吹いた。この老人いまだにパンキッシュなのだ。フーだってここまでパンクじゃなかったぜ。恐ろしい。 踊り狂ってたら久々に腰が痛くなった。結局終演は10時近く。そりゃあ7時開演で前座二組じゃそうなるよな。でも、満足。疲れたけど満足。すげー楽しかった。ありがとうおじいちゃん達。
2010.01.28
コメント(3)
-

Pretty Things初来日公演!
妄ステ番外編。完全に俺の希望で今日の来日セットリストを考えてみるぞ。 ってもね、ポーヴィがいなくて、代役キーボードもいないってなるとどうしても60年代中心の選曲になってしまうだろう。ウォーラー不在でヴォーカルパートをどう埋めるかもわからない。でもまあ、あまりその辺は考えず、俺の趣味で多少無茶でも選んでしまったぞ。選曲は40周年ライヴを参考にした。(追記:正解した曲を太字にした。もっと40周年ライヴ参考にして良かったんだな。エンディングのメドレーとか)1.Get The Picture2.Mamma Keep Your Big Mouth Shut3.Midnight To Six Man4.Balloon Burning5.Barron Saturday6.The Beat Goes On7.Havana Bound8.Passion Of Love9.Big City10.She's A Lover11.Cries From The Midnight Circus12.Come Home Momma13.Pretty Beat14.Come See Me15.Judgement day16.Alexander17.Old Man Goingencore18.Rosalyn19.L.S.D.20.Roadrunner さぁ、どの程度当たるかな・・・?俺にはとても予想が付かないような選曲大歓迎だ。期待してるぜプリティーズ!いよいよ!
2010.01.28
コメント(0)
-

Rocker's Rollin'
困った。明日プリティーズだと言うのにネットでQuoのブート音源、しかも70年代のを二つばかり入手してしまってそっちにハマっている。だって片方はむかぁ~~~し従弟が買って、カセットには録音したけどそれがどこにあるのかも記憶に無いような音源だからな。多分アレと同じもののはず。 78年、Rockin' All Over The Worldの頃のライヴで、同アルバムからの曲を大量にやっている。Hold You BackやDirty Waterはその後も残ったけど、Rocker's Rollin'とか先日パイレーツの話題でも触れたYou Don't Own meなんて素晴らしい選曲もあるんだからな。この辺の曲はコレ以降演ってないから音源欲しかったんだよ。ちなみに前者はBackwaterからのメドレー。音質は良くないけど、昔からブート聴いてる人なら途中から慣れてくるレベル。演奏のディテールは充分にわかる(特に後半)から文句無いぞ。 もう一つは75年のスウェーデン。こっちはOn The Levelの頃で、何が凄いってDown Downを演っていない(笑)。初の全英No.1ヒットを、ヒット真っ最中にツアーで演らないと言うこの無神経。On The Levelからは結局I Saw The Light(レア!)と、Little Lady / Most of the Timeのメドレーだけ(Bye Bye Johnnyは以前から演ってるからね)。前者はツアー序盤で落ちるから、後者メドレー以外は新曲が無いと言う、結構凄い選曲だったワケだな。全盛期だぜ?ナツメロバンドじゃないんだよ?それでこの選曲。いくら「現状維持」ったって・・・。ツアー後半では演ったのかな、Down Down。ちなみに同年マドリードのライヴDVDも持ってるけど、そっちでも演ってません。 明日はプリティーズだってばッ!!
2010.01.27
コメント(0)
-
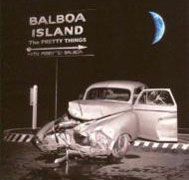
Balboa Island
最新作まで来たぞ。実はCross Talkと前作の間の怪しげなアルバムがあって、発注中なんだけどどうも間に合いそうにない。とりあえずライヴ前のアルバム紹介はコレがラストになる。 このアルバムについては出た時に書いた。考えてみれば俺が最初に買った「リアルタイムの」プリティーズのアルバムなんだな。前作は間に合わなかった(ってーか間に合わせなかった)からな。 メンバーは前作と同じ。ちなみにゲストで参加の女性シンガー、スカーレット・レンチは今回来日時のメンバー(ベースかな?)、ジョージ・ペレスとマルティックスってバンドをやってる人で、このバンドがプリティーズの前座も勤めるらしい。プリティーズのステージでこの人も出てくるみたいだぞ。タイトル曲のBalboa Islandでは大々的にフィーチャーされてるけど、この曲やってくれないかな。好きなんだよな、コレ(ってーかコレ、リードヴォーカル、ウォーラーか?)。 今のプリティーズ(99年以降)は写真を見ると不安になっちゃうくらいのおじいちゃんぶりなんだけど、前作に続いて1曲目のThe Beat Goes On(頼もしいタイトルだ!)でその不安を取り除いてくれるんだよね。それが嬉しい。99年以降ガレージ時代ノリに戻りつつある感じなんだけど、このアルバムはブルーズ色が強くなっていて、更に荒っぽさが増している感も。Buried Aliveとかもガリガリしてて最高だぜ? Livin' In My SkinやBlues for Robert Johnson, Feel Like Goin' Home, The Ballad of Hollis Brown(勿論ディランのカヴァー!)あたりはアコースティックギターを前面に出したブルーズで、渋い、明らかに渋いんだけど、なんか60年代の、まだ渋くなくってブルーズをぶっ壊してた頃のアティテュードってーか、そういうのがしっかり残っちゃってて。全然スタンスが変わってないんだよね。最高だ。多分コレ聴いてもアレクシス・コーナーは怒るんじゃないかな(笑)。 ちなみにPretty BeatとAll Light Upは前作リリース後に出たシングルからの曲で、このアルバム用の新曲では無い。ちょっと浮いてるけど、All Light Upのメロトロンはたまらないものがある。同じようなメロトロンはDearly Belovedにも出てくる。この曲のしゃがれたヴォーカルはウォーラーかと思ってたけど、クレジット見るとゲストの人みたいだな。サビとかウォーラーっぽいんだけどな。 ところでMimi(ディックの単独作!)で最後カウントしてるのはディックかな?だとするとBalon Saturday以来の「ヴォーカル」じゃないか? しかしこの画像、このブログで使うのって3回目くらいになるんだよな。リリース情報の時と、レビューの時と、今回か。そんないいジャケでも無いけどね。それよりジャケを広げると裏面がメイによるイラストになってて、それがS.F. Sorrowの時と同じセンスで良いんだよ。 いよいよ明日!さあ、あとはライヴを待つのみだ。
2010.01.27
コメント(0)
-

40th Anniversary - Live In Brighton
このDVDも以前紹介したんだけど。まあ、おおまかな感想は前回と同じかな。 2004年のライヴってコトで、前回の98年から既に6年が経過。メンバーのルックスには(98年に既におじいちゃんだったのに)更に老いを感じるのはまあ、仕方がない。今週のライヴは更に6年が経過しており、ここに写っているメンバーの半分はステージを引退(スタジオでは参加するらしい。ってコトは更にスタジオ盤出るのか?)。つまり俺がポーヴィ、ウォーラー。スキッパーの雄姿を見るのはここでのものが永遠に最新、と言うことになるのか。少し寂しい。 生きているピートとロジャーを見て、エリックやクリス・ステイントンを見てあれだけ感動したんだ。メイやディックの姿にも感動するに違いないさ。 前作より嬉しいのはディックがヴォックスの、しかもファントムってレアなギターを弾いてるところ。格好いいんだよこのギター。それから選曲の幅が広がって、初期から70年代、そしてRage Before Beautyまでの曲をほぼ網羅しているところ。Havana Boundをディックが、しかも60年代ノリのソロを弾いてるのはかなり不思議な光景だけど。 Parachuteからの選曲も嬉しいよね。Cries from Midnight Circus、In The Square / The Letter / Rainのメドレー。それから同時期のシングルからCircus Mind。個人的にはこのDVDの見どころはS.F. Sorrowからの曲を挟むこの中盤の流れ。中盤っても3曲目から11曲目まで(途中Come See Meとアーサー・ブラウンの歌うHoochee Coochieを挟むが)だから結構メインの流れだな。本編エンディングもOld Man Goingだし。この辺はディックが関わってなかった時期の曲も多いし、アレンジの変化(まあ、以前より強化されてるわけではないけど)も楽しめる。 Sorrowのパートは98年のほど再現には拘ってなくて、ホーンのパートをオリジナル通りシンセでやってたのがオルガンにさし変わってたり、Balloon Burningのコーラスがウォラーになってたりするんで、サイケ度は後退、そのかわりガレージ臭さがこの辺にも加わっちゃって、結局楽曲の骨格は変わってないのね、って言う確認にもなる。 Baron Saturdayは相変わらず楽しいな。98年版と同じくらい楽しい。パーカッション大会はメンバーが減ったけど、ポーヴィが目立つ(ボンゴだけど)から良しとしよう。俺はミーハーですか。今回ポーヴィが目立つ場面も多いんだけど、ピアノじゃなくて殆どハープなんだよ。それは残念なんだけど。 Baronもそうだし、The Rainでウォーラーのヴォーカルが聴けるのも嬉しい。今回の来日では彼の歌が聴けない、って思うとそれが一番寂しいかも知れないな。うん、ポーヴィの不在より残念かも知れない。最近こうやってプリティーズを見て、聴いてると凄く思うな。今回の来日メンバーがどれだけ歌えるのかは知らないけど、彼らとホランド、それから多分ゲスト参加するスカーレットさんに頑張ってもらおう。
2010.01.27
コメント(0)
-
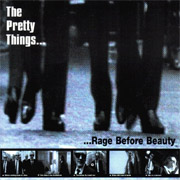
Rage Before Beauty
80年のアルバムの次が(公式には)99年。いや、勿論扱いは再結成。でもプリティーズの再結成は3回目なんだよね。71年の次が72年、76年の次が80年で、その次が99年。次回作がデルのが07年だけど、この間解散はしていない。最初の2回の解散よりブランク長いのに。 まあ、それはいいや。再結成とは言っても、このアルバム用の新曲は3曲だけだそうだ。つまりそれ以外の曲は結構「解散中」の曲だったりもするわけだな。古いのは81年で、Goodbye, GoodbyeとGoin' DownhillがCross Talkの時期、つまりピーター・トルスン在籍中「最強」時代の録音だ。まあ、そんな最強な曲じゃないんだけど(笑)。前者は同時期のShe Don'tにちょっと似てるし、後者はあまりにも80年代な音だし・・・。いや、曲は好きなんだけどね。 最強なのは新曲だ。特に好きなのはVivian Prince。勿論初代ドラマーのことを歌った曲で、ビートは名前の元になったボ・ディドリー調。ルーツ回帰!って感じの要素ながら全然60年代の要素じゃないところで出来てるってのが。スキッパーがヴィヴやトゥインクにも負けないドラミングしてるのが最高だね。 新曲の多くには新メンバーのフランク・ホランド(G)が作曲に関わっている。この人、元イングランドなんだそうで・・・新人にしちゃあ若くないな、と思ってたら。そのホランドとメイ、マネージャー(ホモっぽい)のマーク・セント・ジョン(亡くなった元キッスのメンバーとは無関係)の共作がEverlasting Love(ラヴ・アフェアーの曲とは無関係)。やたらにPaint It, Blackに似てるんだけど、このアルバム、Play with Fireやってたりとかして、すっかり「ストーンズ・コンプレックス」は払拭したと見える(ってーか開き直ったか)。God Give Me Sterngthもちょっとキースの歌うバラードっぽいところあるでしょ。メイの方が遥かに上手いけど。 音は結構ガレージ時代に戻ってる感じも強くて、特にオープニングのPassion of Love(しかし相変わらずタイトルのセンスはアレだな)や前述Everlasting Loveの荒っぽさは絶品。Passion of Loveは大好きだなぁ。プリティーズの1曲目は(I'm Callingも含めて)外れないからね。 かと思うと70年代HR期っぽいバラードのLove Keeps Hanging Onがあったりもする。ちなみにこの曲のギターソロはデイヴ・ギルモア、って書かなくってもギルモアにしか聴こえないギターを弾いている。でもポーヴィのオルガンも最高なんだぜ。 カヴァーが3曲入ってるのも60年代(ってーか2nd)以来だけど、これは色々録りためた中に結果としてカヴァーが含まれた、ってコトだろうね。前述のPlay with Fireはストーンズのよりアーシーになってて好き。Eve of Destruction(89年のシングル)と、Mony Mony(ロニー・スペクター参加)はプリティーズにはぴったりのR&Rだけど逆にあんまり面白くないかな。そこはもう通過したところだろ?荒さも足りないし。 アコースティックな曲が目立つのは特徴の一つで、この要素は次作(っても8年後・・・)にも受け継がれて行くんだけど、今作ではVivian Prince, Not Givin' In, Pure Cold Stone, Blue Turns To red, Fly Awayあたりがそういう要素が強い曲になっている。Pure Cold Stoneのクールさは大好きだな。俺はこの手の音づくりには弱いんだよねぇ。 ジャケの話・・・は今回はいいや(笑)。
2010.01.26
コメント(0)
-
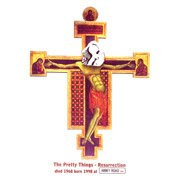
Resurrection
3回目の再結成したプリティーズの最初の仕事。ライヴそのものは98年で、Rage Before Beautyのリリースより先になるわけだ。CDがどっちが先に出たかは知らん。こっちなのかな?メンバーは黄金期の5人(レコーディングメンバー-トゥインク+スキッパー)に加え、ここから現在に至るまで中心メンバーの一人となるフランク・ホランド(元イングランド)。更にサポートドラマー(パーカッショニスト)としてスキッパーの息子、ドーヴ・スキッパーが全編で参加。曲によってマネージャーのマーク・セント・ジョンがパーカッションで参加。そしてゲストとしてはデイヴ・ギルモアがギター、アーサー・ブラウンがナレーションを担当。 これは映像版があるからそっちで確認しながら書こうか。 S.F. Sorrow Was Bornでディックのメインリフがいきなり危なっかしい、というかはっきり言って弾けてない(簡略化しちゃってる)ところから一抹の寂しさを覚えつつスタート。ソロは結構達者なんだけどなぁ。簡略化は狙いがあるのかな。それ以降は結構冴えてるしなぁ。 ヴォーカルパートは充実。メイ、ウォーラー、ポーヴィの3人を中心に、ホランドやセント・ジョンも加わって重厚で奇麗なコーラスを聴かせる。メイのヴォーカルも勿論、ウォーラーのしわがれ声も往年のままで、この声が出てくると結構「これこれ!」って気分になる。She Says Good Morningとか実は相当に重要な存在感を持ってたんだなぁ、と実感。ほぼデュエットだもんね。 そのShe Says~では前述フルメンバーが共演。パーカッションの量が凄い!セント・ジョンがマラカスとシンバル、名がタンバリン、ドーヴがシェイカーを担当。終始がちゃがちゃ言ってる上にギルモアを含んでギターが三本。なかなか凄いサウンドだけど、それがレコード通りなんだよね。 そう、音はかなり端正になったものの(60年代のあの空気の再現は不可能だ)、演奏としての再現度は極めて高い。エフェクティヴな部分はポーヴィが大活躍し、当時色んな楽器を使った部分をシンセで再現。パーカッションの多さも、当時はトゥインクに加えてドラムも叩けるポーヴィがだいぶ担当してたんじゃないかな、と考えると面白い。ギターはアコギの使用がかなり目立っていることに気付く。 そんなワケでポーヴィの活躍が見たい俺みたいな人には40周年ライヴのDVDより遥かに楽しめるんだけど、カメラは彼を追ってくれないのが残念。Deathでしっかりシタール弾いてるのにちょっとしか写らねえ。Blloon Burningなんかメイとデュエットなんだけどそれもあんまり写らないし。ピアノをあんまり弾かないのはまあ、しょうがないとしてもさ。I See Youでリードヴォーカルとるのを見て溜飲を下げるか(ギルモアもいるし)。 楽しいのはやっぱりBaron Saturdayだよね。ディックのレアなヴォーカル+サビはウォーラー。すっかりおじいちゃんのディックはなんか本物の「バロン・サタデイ」みたいだ。そして中間部。オリジナルではサイケデリックなノイズだったけど、ここではウォーラー以外全員が打楽器を担当してのアドリブ(って程でもないか)大会。ここでもキーボードから移動したポーヴィが写んなくなっちゃうんだけどな(ボンゴやってるのかな?)。 Well of Destinyの渾沌をライヴでやる、ってのも凄いけどな。サウンドは勿論だけど、何故かこの曲でディックがギブソンのダブルネック、ホランドがギターを弓弾きする、ってのが面白い。プリティーズは70年代にスワンソングにいたけど、その当時この二人のギタリストはバンドにいなかった。 しかしDVDは全体に映像処理が鬱陶しいんだよな。なんか編集ソフトいじくりながら面白そうなエフェクト場当たり的にかけてってるだけ、って感じでさ。センスなんか一個もねえ。
2010.01.25
コメント(0)
-

Cross Talk
普通の反応から。 「黄金期のメンバー+ピーター・トルスンって最強の布陣なのに・・・?」 「ヒプノシスなのに・・・?」 「・・・?」 まあ、そんな感じだろうねぇ。いきなりXTCみたいなヴォーカルでびっくりするもんねぇ。サウンドは明らかにNニューウェーヴの影響大。なんとなくQuoのAin't Complainingみたいなサウンドに感じる瞬間があったりするから、そういう意味では8年早い(笑)。Quoと比べて早くても何の自慢にもならない。 1曲目は名刺代わり、と考えればまあこれは明らかに「俺達はコレがやりたくて戻ってきたんだぜ!」という宣言だ。実際ディックは「パンクを聴いて音楽界に戻ってきた」とはっきり言ってるわけで、今更ハードロックやる理由は無い。勿論プリティーズのここまでのスタンスからも決して間違っているわけでは無い。 実は相変わらずほとんどの曲がメイ/トルスンの共作で、そういう意味ではFreeway Madness以来の制作体制。他の曲もウォーラー、ポーヴィとメイの共作であり、何か外部から新しい要素を取り込んだ、というワケでは無い。 さて、じゃあ「パンクを聴いて」シーンに戻ってきた彼らが何でこの音か。時代だ、と言ってしまえば簡単だけど、実は元々パンキッシュなプリティーズには「パンク」って既に通過したところなんじゃないだろうか。ここであえてパンクをやる必要は無い。そもそもパンクだって79年にはほぼ終わってるんだから、80年にプリティーズがやる理由も無い。じゃあ、このアプローチだ。 例えばEdge of the Nightとか、スワンソング時代に録ってれば多分ああいう音になったと思う。変わってないところは変わってないんだよね。I'm Callingは確かに衝撃的な変化に聴こえるんだけど、実はコレとFalling Againくらいで、それほど変化球は無かったりもする。It's So HardはヴォーカルはNW風だけどサウンドはプリティーズらしいものだからね。 ただ、特にキャッチーな部分に変化が見えるから「えっ!?」って思うんだよね。ちなみにI'm CallingとFalling Againはドラマーがスキッパーでは無くて、もしかしたら少し録音時期も違うのかもね。 Lost That Girlなんて普通のR&R(っていうかロカビリー)だし、一番パンキッシュなBitter End(高速Moneyって感じ)も然り。でも考えてみりゃあパンクなんてその「普通」のR&Rをあんまり上手くない(実は上手かったりもするんだけど)奴らが高速でやっただけで、そういう意味じゃあ適度にブランクのあるディックやウォーラーには丁度良い。 個人的にはOffice Love(ヒドいタイトル・・・)で聴こえるウォーラーのだみ声コーラスが嬉しい。ヒドいタイトルと言えばラストのNo Futureも「おいおいパンク通過したからってそれかよ・・・」っていう苦笑タイトル。 ジャケは・・・駄目だねぇ(笑)。でもデザインよりね、ブックレット、長髪じゃ無いメイの似合わないこと。この人基本的におっさん面で、髪短くすると途端に老けて見えちゃうんだよな・・・。トルスン&ポーヴィの若々しさと比べてみよう。
2010.01.24
コメント(0)
-

Savage Eye
もう一週間を切ってるからね、ピッチを上げて紹介だ。楽しみだなー。 スワンソング時代=ハードロック期、と思ってる向きもあるかも知れないけど、それは結構間違ってるんだよね。このアルバムはポップだったりバラードだったり、と言うあたりも充実してて、サウンドもエドワーズ、ポーヴィと言う二人のキーボーディストの存在でギター主体と言うわけでも無くなってきている。シンセサイザーも入って、印象はQuoのIf You Can't Stand The Heatあたりとも近いかもな。 とにかくこのアルバムを聴いて一番思うのは「ポップ化」ということ。前作と同じメンバーだけど、明らかにこっちの方がポップだ。エドワーズ、グリーンの発言権が増してきたか。実際、契約の関係でクレジットがメイやトルスンのものになっているが実際はエドワーズやグリーンの曲、ってのは幾つかある様だ。例えばSad Eyeはアコギ弾き語り曲で、しかも明らかにメイの声では無く、作曲はトルスンになってるが彼は歌わない。実はグリーンの曲で、ギターもヴォーカルも彼だと言う。My Songも10ccみたいな作風で、やっぱりメイの声じゃない(後半にシャウトが聴こえるけど)。コレも本当はグリーン/エドワーズの共作らしい。多分メイの単独作になってる曲はグリーンかエドワーズ、またはその両方が絡んでるんじゃないかな。I'm Keepingなんかも同じ系統の方向性感じるもん。 ハードで格好良いのはUnder the VolcanoとRemember That Boy。70年代のプリティーズの基本スタイルって感じのポップなR&Rの後者、ヘヴィに迫る前者。結局俺もこういう曲を彼らに求めてる部分はあるんで、やっぱり圧倒的に楽しい。前者が個人的にはベストトラック。 ポーヴィの(多分本当に彼だと思う)It Isn't Rock 'n' Rollも好きだ。ピアニストらしい発想の曲だと思うけどどうかな。ヴァースはメイじゃなくてポーヴィが歌ってるのかな?サビでメイがシャウトする流れが最高。 新しい要素、ってのは今回はむしろ全体的な、ポップと言う意味を含めての「洗練」で、本来の意味での新機軸は余り見当たらない。どの曲も以前のどれかで代用が効くような、微妙なインパクトの弱さがあるのは非常に残念。ポップなのは事実だけど、単純に「いい曲」は前2作の方が多いし。通して聴いてると明らかに好きなんだけど、聴いたあとにあんまり強い印象が残らないんだよな。
2010.01.23
コメント(0)
-
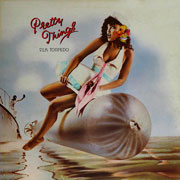
Silk Torpedo
プリティーズはジャケもいいよな。Emotionsまでの3枚は意識的なデザインは感じないけど統一感があるし、やたらクールな感じだ。Sorrowのフィル・メイ自身によるイラストも凄くいい。そしてParachuteからはヒプノシスが登場。ヒプノシスなら何でもいいというつもりも無いけど、少なくともプリティーズのデザインは基本的にはいいよな。 Freeway Madnessのジャケが好きなのは前回も触れたけど、俺が一番好きなのはこのすっとぼけたジャケ。「絹魚雷姉さん」は俺の中では一種のぬるキャラで、一時期はこのブログのマスコットキャラ的に使ってたのを覚えてるでしょ? アルバムの内容とジャケが見事に正比例するのがプリティーズの良いところで、つまり(以前も触れたけど)俺にとってはやっぱりSorrowからこのアルバムまでの4枚(+同時期のエレクトリック・バナナ作品)が最高。ジャケも内容もね。 メンバーはまた代わって、ブルックスが早くも抜けてゴードン・エドワーズとジャック・グリーンが加入。エドワーズは主にキーボードとギター、グリーンはベース(ジャケには契約の関係でヴォーカルとして記載)を担当している。二人とも歌えるので、コーラスはまた厚みが出た。 で、前回は新加入のトルスンが張り切ってたんだけど、今回はトルスンに加えて、既に古参メンバーのポーヴィが大活躍。エドワーズというもう一人のキーボーディストもいるため、キーボードがバッキングの印象を決定づける曲が多くなった。 そういう意味ではやっぱりオープニングのDream/JoeyとSingapore Silk Torpedoが白眉。前者は「合体パターン」というより「Joey's in the Dream」が正しいタイトル?って感じで、2パートに分かれているようには聴こえない。ピアノがダブルで入っていて、ポーヴィが重ねてるのかエドワーズが弾いてるのかは解らないけど、コレがメインなのは言うまでも無いだろう。 後者はポーヴィがピアノを弾き倒すロックンロールなんだけど、シーケンサーより凄いイントロのピアノが最高に格好良い。俺のプリティーズベスト3に絶対入る曲で、勿論★★★★★。トルスンとメイの共作でギターも凄い格好良いのだけど、やっぱピアノが強いなぁ。 「合体パターン」はむしろAtrantaとL.A.N.T.A.なんだけど、後者はむしろジャムって感じ。パープルのThis Time Around / Owed to "G"みたいな感じかな。一応後者も作曲されたモノにはなってる(メンバー全員共作扱いとかじゃなくて、メイ/ポーヴィ/ノーマン・スミスの作)。なんとなくトラフィックとかあの辺の、アーシーな感じもあるね。 あとBelfast CowboysとBruise in The Skyもね。曲調が変わるところから Bruise in the Skyだよ、と言っても「どこ?」って感じでしょ。ギターソロからテンポが落ちて、そこ。2分弱しかないからアウトロだよなぁ。 R&Rが好き?プリティーズはR&Rバンドだとおっしゃる。勿論Singapore~が最高なのは言うまでも無いけど、Maybe You TriedやCome Home Mamaならそういうファンだって100%満足だろう。Bride of Godは少し変化球だけどこれもスピード感があって良いですよ。どの曲もParachute以降凄い勢いでポップになってくメロディも良いから、聴きやすいのに熱い、という素敵なアンビバレンツ。 あとはバラードね。Is It Only Loveってタイトルがベタ過ぎて、オーケストラまで入ってるから甘くなりそうな気がするんだけど生涯やさぐれ男、フィル・メイが歌うので全然甘くならない。中間部の展開が凄くビートルズっぽいねぇ。サイケ時代のレノンじゃなくてポールっぽいってのがいいんだよな。 ほらな、名盤だから全部紹介しちゃったじゃん。みんな買え。俺も紙ジャケに買い替える。
2010.01.22
コメント(4)
-

Freeway Madness
プリティーズって名前の呼び方に困る人が多い。特にウォーラー、俺は良くウォーラーって書くけど、この人「ウォーリー・アレン」だったり「ウォーリー・ウォーラー」だったり「アラン・ウォーラー」だったりするので非常に困る。しかもドラマーがスキップ・アランで、混乱に拍車をかけつつこの人もスキッパーと呼ばれたりする。前任ドラマーのジョン・アルダーはトゥインクだけどコレは混乱しない。ジョン・ポヴェイかポーヴィか、は発音の問題で、コレはBBCライヴとか聴くとはっきり「ポーヴィ」と発音してるので問題ない。 このアルバムからヴィクター・ユニットに代わって参加するピート・トルスンも時々綴りがTolsen/トルセンになっていて困る。代わりに混乱の元であったウォーラーがプロデューサーに転向するため脱退(後任はスチュアート・ブルックス)。だがこのアルバムを彼がエイサ・ジョーンズという変名でプロデュースしたため混乱は増しているのだ。厄介者め! へぇ、ブルックスって元Black Cat Bones/Leaf Houndなんだぁ・・・また繋がっちゃった。 このアルバムからは再結成、と言うより「再編成」プリティーズで、実際には70年の前作リリース後一旦バンドは解散している(その間にウォーラーはベーシストからプロデューサーになったというわけだろうね)。 とは言えブランクはたったの2年。いや、実際には71年にStone Hearted Mamaが出ている(この時既にギターはトルスン)ので、特に今の目で見ると解散してたようには全然見えないよね。 ここからをHR期とする向きも多いようだけど、前回錯乱してわめき散らした通り、サウンドは前作から完全に連続している。事実上のセカンド・ヴォーカリストだったウォーラーが抜けて歌えないブルックスが入ったことでコーラスという面では一歩後退しているんだけど、そのかわりバラードが充実。相変わらずやさぐれているメイのおかげで絶対甘くならないのがポイント。 その手のバラード系はオープニングのLove is GoodやPeter/Rip Off Trainなどが代表格。前者はHRバラードっぽくもありつつメロディックで、コーラスも効いてるし、後者(2曲合体パターン!)もフォーキーな感覚があって前作からの流れを感じる。 バラードといえばOver the Moonではエイサ・ジョーンズがプロデューサーなのにリードヴォーカルをとっている。脱退しなきゃ良かったのに。セカンドギタリストにでもなってれば良かったのに。ウォーラーとトルスン、両方がソングライターとして活躍するプリティーズはCross Talkまで待たなければならない。 2曲合体パターンといえばラストのOnion Soup / Another Bowl?もそうで、一番ハードロックっぽい曲だろうね、コレが。大好き。でもライヴではAnother Bowl?のパートが無くなって代わりに長いアドリブ大会になってんだよね。アレはアレで好きだけど。ってーかあっちの方が好きかも。 それよりこのアルバムの白眉はHavana Boundで、各メンバーのソロパートも含みつつ疾走するR&R。後期を代表する曲の一つでしょ、絶対。Religion's Deadもそうだけどちょっとアメリカンな感じも強くなってきた。それはこの時期からアメリカのマーケットを狙い始めたから。そういう意味ではカントリー調のContry Road(有名曲とは無関係)とかAllnight Sailorも「そっち狙い」っぽいけど、どれ聴いても結局どうしようもなく英国人、なんだか妙にウェット、全然カラッとしない、ってトコがまた大好きで・・・。 このアルバムのジャケって、表に現行メンバー、裏に過去のメンバーが顔を揃える、と言うもので、そういえば99年のレココレでのインタビューでメイが「メンバーチェンジは多かったけど喧嘩別れしたヤツは一人もいなかった」って発言してて、それを裏付けるものだね。こういうのってちょっと嬉しいんだよな。 やっぱ好きなアルバムの紹介は熱が入るな。
2010.01.22
コメント(3)
-

minoradio新曲
minoradio新曲をアップ。まあ、新曲といっても今まで公開してた曲とほぼ同時に作ってたヤツなんだけど。Way to the Higherという曲で、詳しくはこっちに書いたけど、まあアバンギャルド風の世界を狙ってみました・・・的な曲。いや、あんまりアバンギャルドじゃないけど。 minoradioの曲(EP)を一応簡単に紹介。minoradio preview Trident Barrr Deep One 「プレビュー」と言うだけあって、GarageBandの実験として作った曲を中心に構成。ほぼデフォルトのアップルループだけで出来ている。多分、次の新曲アップ時にこの3曲は消すと思うけど、そのうち全てリミックスして再公開しようと思っている。Walk On EP Walking Nowhere The Machine Walk (Like a Lucky Guy) Way to the Higher もう少し凝り始めた楽曲群。「歩く」というコンセプトのEPで、なんとなくどこかへ歩いて行く、向かって行く、と言うイメージで作っている。まあ、コンセプトが出来てからそっちに持ってった曲もあるけど。minoradio2(仮) What's Love?(仮) Winter Lake Take 3 次回公開予定。ミックスをもう少し煮詰めてからだけど。アップルループやサンプルの自作の割合が増えてきた・・。コンセプトは無し。
2010.01.21
コメント(1)
-

Parachute
折角VINYL JAPAN招聘なのにその告知ページに、ディックのことを「元ローリング・ストーンズ」って書くのはヒドいと思う。プリティズ見たいってヤツにその肩書きで動くヤツなんかいねえよ。かなり失望。 そのディックが脱退、トゥインクも気まぐれっぷりを遺憾なく発揮して予想通りやら予定通りやらの脱退。後任にはヴィクター・ユニット(G)と、ドラマーの座にはスキッパーが復帰。イエスばりに「出たり入ったり」なプリティーズの歴史が変な方向に動き出す。 歴史は変な方に動いても音楽まで変な方へは動かない。ちょっとした金字塔を作り上げてしまったことでディックこそ満足し切ってしまったようだが、他のメンバーは全然そんなコト思ってなかった。まだ凄いコト出来るはずだよな?と思った(ハズ)のメイ、ウォーラー、ポーヴィは態勢を立て直し、案の定凄いコトをやり遂げる。紛れも無くエラい。 S.F. SorrowやDefecting Greyが「作曲」の枷を取り払い、これ以降プリティーズの楽曲には「曲名クレジットは2曲(以上)、でも実は一曲」というのが増えて行く。例えばこのアルバムだとまさしく前半の流れがそうで、勿論トータルアルバム、組曲的な意味(ストーリーは無い)もあるだろうけど、そういう曲作りがSorrow以上に強調されている。 序曲的なScene Oneはともかくとして、The Good Mr.SquareとShe Was Tall, She Was Highは一つの曲の二つのパート、と考えても差し支えない。実際、シングルはGood Mr. Squareと言うタイトルだけど、She Was Tall~まで含まれた形でカットされている。Scene Oneが無いので少し始まりが唐突に感じる(いや、元々繋ぎが唐突なんだけど、ソレ込みで場面転換の意味だからさ)。 この次の流れ(In The Square / The Letter / Rain)も組曲だけど、ここまでの流れは全体にフォーキー、アコースティックな雰囲気が全体を包む。前作から繋がる美しいハーモニーを生かした楽曲が多く、そこにやさぐれたメイとだみ声のウォーラーという、どっちも「美しいハーモニー」にもう一つ馴染まない要素を何故か見事に馴染ませている、ってのが不思議で、面白くて、しかも格好良い。 コレがこのアルバムの新路線か、と思ってるとその後の流れでびっくりする。今度は「やさぐれたメイとだみ声のウォーラー」をストレートに生かしたハードロックが炸裂するのだ。いや、Scene OneやRain(CDでは18秒の雨音のみになってるけど、実際にはThe Letterの1:50くらいからこの曲)にその要素は見えてるんだけどさ。 Cries from the Midnight Circus, Sickle Clowns, She's A Loverあたりのヘヴィな曲と序盤の楽曲群が同居するのがこのアルバムの面白さ。何となくフーのSell Outみたいに途中でコンセプトが終わっちゃったようにも聴こえちゃうけど、まあ曲がいいからオッケーでしょ。この辺の曲死ぬほど格好良いもん。1stのガレージ野郎が1970年になったらこんなことやってるって、凄く自然じゃん。それこそフーだってそうだしね。 要するにさ、俺は1st~Sorrowまでのファンと70年代以降のファンが分かれちゃってるのが理解出来ないんだよ。こうやって連続して聴いてると、プリティーズが一貫してるのって凄くよく解るハズだし、実際どっちのファンもSorrowとParachuteは好きじゃん。じゃあどうしてそれ以前/それ以後が好きになれないのよ。同じじゃん。同じくらい格好いいじゃん。お前らフィルの歌本当に聴いてるのか?ホントはフィルのヴォーカルなんか好きじゃねえんだろう。「モッズでーす」とか「ガレージ好きでーす」とか「ハードロックさいこー」とか脳みその表面でしゃべってるだけだろう。「ディックがいないプリティーズなんて・・・」馬鹿じゃねえの!来んな!そんなヤツプリティーズ見に来んな!
2010.01.21
コメント(4)
-

S.F. Sorrow
昔宝島かな、投稿で「キンキンケロンパ地獄行き」というヒドいのがあったんだけど、デイヴィッド・ボウイのPretty Things are Going To Hellを聴くとどうしてもこの投稿を思い出す。 S.F. Sorrowについても以前書いた。 今回久々に読み返したけど、俺の「サイケデリック」というものに対する意見ってのは一貫してここで書いた通りだ。いいコト言うじゃん、俺。とにかく俺が求めるのはその「いかがわしさ」であり、ビートルズ(ジョージを除く)の高級サイケはサイケとしては物足りない。ロックとしては最高だが。 そんなワケで、このアルバムに関する意見はリンク先の文章を読んでもらえれば全て書いてある。全く異論は無い。だから今回は少し違うことを書く。 トータル・アルバム、ロック・オペラとしてのS.F. Sorrowは、実は非常に出来が良い。「んなコトぁ解ってンよ」と言われるだろうけど、俺が言いたいのは少し違う。 これも以前の文章でも触れたけど、はっきり言ってストーリーは陳腐だ。でも陳腐じゃないロック・オペラってのも殆ど無いので、それはこのアルバムの欠点には成り得ない。歌詞だけで語り切れなかった部分の補足が歌詞カードに乗ってる、ってのもまあ、アリだろう。むしろ他のアーティストにもそうして欲しかったくらいだ。 このアルバムの何がいいかって、要するに曲なんだよね。 例えばフーは、ストーリーを補足するために小曲をいくつも挟み込んでいる。それはあくまでストーリーのための曲であって、楽曲本意で出来たものでは無い。つまり、曲としてのクォリティはどうしても低くなる。Miracle Cureを名曲って呼ぶ人はいないでしょ? S.F. Sorrowは、そういう部分を歌詞カードに書いちゃって、アルバムにはいい曲だけを入れて、しかもコンパクトなシングルアルバムに仕立てた。捨て曲は無い。「Well of Destinyは?」って意見は却下。アレはトミーで言うところのSparksだ。音楽で映像表現をするためには時に歌詞の無い曲も必要なんだよ。 音楽的にも、過去の3枚で積み上げてきたものが全部入っている。メイのシャウトこそ抑制されたものの、暴力的なサウンドは決してスポイルされていないし、2ndで見え始めた良いメロディ、3rdでのサイケデリックの実験、フォーキーな方向性など、全てがここに結実。しかも新しい要素もある。70年代のも一つのウリだったハーモニーが前面に出るのはここからだし、幾つかの曲で垣間見れるハードロック的な方向性も新しい要素だ。 前作までの紹介でも「S.F. Sorrowへ向かう要素が」などと書いてきたけど、実はここも必ずしも到達点では無かったのがプリティーズのエラいところ。ここには更に次のアルバムParachuteや、70年代の諸作へ繋がって行く要素がちりばめられているのだ。凄いな、ビートルズみてえだ。 でもやっぱコレ凄いワ。そのうちもう一回コレ再挑戦する。まだ言いたいこといっぱいある。
2010.01.21
コメント(2)
-
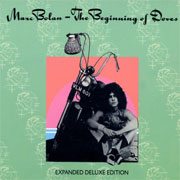
Pictuers Of Purple People
年末に薄暗い古着屋で、臙脂ってーかマルーンっぽい色と思って買ったら思いっきり赤紫だったリーヴァイス、思いの外カーキ色のモッズパーカに合うことが解ってちょっと嬉しい。俺の顔がもう少し小さければいいのに、とは思ったが。 ところがこいつの色落ちが凄い。腰からぶら下げてるiPod nanoのイヤフォンが物凄い勢いで赤紫に染まり、白いTシャツでも着ようものなら結果は言わずもがなである。こいつを履く時は薄色のTシャツ着れねえなあ。ってーか、例えばコレ履いて友達の車とか乗ったら怒られそうだよな。黒とかのシートならいいけど、グレーとか薄目の色だったりしたらさ。 ちなみに簡単につくだけあって、イヤフォンに付いた色はウェットティッシュで拭いたら簡単に落ちた。 もうちょっと渋めの赤系のズボンが欲しいんだけどな。
2010.01.20
コメント(0)
-
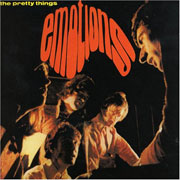
Emotions
シングル曲について触れてなかったって?Rosalynとか、Midnight to Six Manとか、Come See Meとか・・・って話だろ?そんなもんいちいち触れなくたって最高に決まってるじゃないか。シングルB面のGet a Buzzとか?.S.D.だってね。皆まで言うな、って話だよ。いいからレコード聴けよ。 と言っておきながら、俺は語るしプリティーズはガレージ時代を通過する。 Emotionsについては以前Soul Deepで書いている。今でもあの時書いたイメージとそれほどかけ離れてはいないかな。そう、俺はこのアルバムを「悪い」とは思っていない。 Death Of A Socialiteには★★★★ついてるんだよ。だって、いい曲じゃん?しかもこの曲はプリティーズとレグ・ティルセイ楽団が噛み合っている。メンバーは気に入らなかったかも知れないが、最高のサイケポップに仕上がっている。歯切れのいいアコギにアクセントとして入ってくるストリングスがいい感じじゃないか。 ところでこのアルバムはメンバーの相次ぐ脱退を挟みながら録音されてるんだけど、ギターが一本で、ベースも聴こえないこの曲はペンドルトン、スタックス両名の脱退後、ウォーラー、ポーヴィ参加前の録音かも知れない。まあ、余談だけど。 そう、ここから俺的黄金期のメンバーが顔を揃える、と言うのは重要なポイント。スキップ・アランも全曲に参加(一部レグ・ティルセイ楽団でドラムも担当してる曲もあるのかも・・・?)し、まだ独自の存在感は見せないまでもウォーリー・アレンとジョン・ポーヴィが遂に加入したことで一気に「次」へ向かう道が見え始める・・・。 「存在感は・・・云々」と書いたけど、実際にはウォーラーはThere Will Never Be Another DayやMy Timeといった重要な曲をメイ/テイラーと共作しているし、ポーヴィも俺の大好きな格好良いピアノをPhotographerで聴かせてくれる。充分、かな。 ジャケはちょっとRubber Soulっぽい、ってーかRubber SoulとRevolverの裏ジャケを足して2で割った感じだけど、まあ位置づけもそんな感じだよね。ステレオ盤とモノ盤でジャケの写真が逆(裏焼き)ってのは意味不明なコンセプトだけど(これもフォンタナが勝手にやったのかな?)。 Children(ちょっとスモール・フェイシズの曲にフーがコーラス付けたって感じ)とか、One Long Glanceといった従来の雰囲気を残すビートバンド的な曲とDeath Of A SocialiteやMy Timeの様なサイケに足を突っ込んだ曲(それが勝手に加えられたストリングスに起因するとしても!)が奇妙な同居するのがこのアルバムの魅力。で、その中間にThere Will Never Be Another DayやPhotographerみたいな曲があって、外側に「やり過ぎちゃった」バラードのThe SunとかHouse of Tenみたいのもある、っていう、まあトータルで見て、作品としては駄目なのかも知れないけどなんだかどうしても見捨てられないB級感、これがまた逆にプリティーズっぽいと言うか・・・不思議といとおしいアルバムなんだよな。
2010.01.20
コメント(0)
-
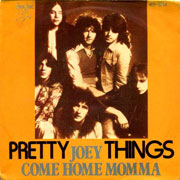
Dream/Joey
変な夢を見た。 ライヴをやるのだけど、俺の参加しているバンド(マードックスでは無いようだった)のメンバーが集まらない。俺以外のメンバーが来ないのだ。かなり苛々しつつ、何故か殆ど諦めてぼんやりしていたら今度は別のバンドのメンバーが泣いているという。そのメンバーは俺の友達なんだけど、どうも「自信が無い、ステージに出れない」と言っているらしい。とりあえず楽屋に向かって、励ますことにする。「ここまで来ちまえば一緒じゃん。出ないなんて勿体ないぜ。」こんな励まし方あるだろうか。気の利かない言葉をかけている。時間は過ぎる。別の対バンは妙に楽しそうだ。それがまた苛々する。 目が覚めた。 なんとなく嫌な夢だな、と思っていたんだけど、実はこの夢、あとから考えたら俺が漠然と気にかけていたコトが片っ端から出てきただけなのだ(ここに書けないけど夢に出てきた幾つかのことも含めてね)。 「俺の参加しているバンド」ってのは実際にはマードックスであり、BCWでもあるんだろう。どっちもライヴが出来ない状態で、それが「メンバーが来ない」という形で夢に出てきた。ステージに自信を持てない友人も実在して、そういう話を聞いてたからストレートに出てきただけ。 でも、この励ましの言葉は別の友人にかけたものだった。そっちはバンドでも何でもない。資格取得の試験に「自信が無い、無理だ、受けれない」という友人に対して「(金は会社が出すんだし)受けないなんて勿体ないぜ」って、全く同じ言葉をかけてたんだな。まあ、現実にはどっちも自信が無いとかの理由で泣くような人じゃないけどね。 いや、バンドも二人の友人も大事だけどさ、なんか、ちょっと変な気分だよ。仲間思いの俺、って?ホントかな。でもそういえば、人間関係でちょっと苦しんでる友人は出てこなかったな。悪りぃな。
2010.01.19
コメント(2)
-
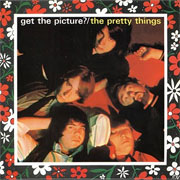
Get The Picture
俺ははっきり言ってプリティーズに「ブルーズ、R&Bを解体して云々」というコンセプトが本当にあったとは思わない。乱暴者が勝手に怒り狂ってブルーズやR&Bを力任せにぶちかましてただけなのだ。出てきた結果は「コンセプト」と合致するだろうが、狙ってねえだろう。せいぜい「思いっきり派手にやろうぜ」って程度の「コンセプト」だ。 1stでは元になるものがあって、それをぶち壊して見せたんだけど、この2ndの何が凄いかって、オリジナル曲を増やしつつも1stの勢いを決してスポイルせず、洗練はさせてるんだけど乱暴さも殺していない、と言うところだ。更に、フィル/ディックのコンビで作ったBuzz The Jerk, Get The Pictureが明らかにカヴァー曲より出来がいい、と言うところも素晴らしい。さあ、ビートルズやフー、キンクスを追撃する準備は出来た。 前述の2曲は本当に格好良くて、前者の荒々しさ、後者のクールさともに甲乙つけ難いのだけど、他に3曲、バンド全員や、テイラー/メイが外部の人間と共作した曲も含まれる。ちょっと興味深いのがWe'll Play Houseで、この曲の共作者として、また、ドラマーとしてジョン・アルダーが参加しているらしいのだ。つまりトゥインクである。俺の持ってるCDの裏ジャケだとAldoって書いてあるから別人の可能性も感じるんだけど・・・真相は? そう、このアルバムではヴィヴは既に数曲にしか参加していない。レコーディングの途中で彼は解雇され、アルバムの大半はセッションマンのボビー・グレアムが叩いていると言う(ヴィヴの後任として正式参加したスキップ・アランは不参加と思われる)。ちなみに彼はYou Don't Believe MeとCan't Stand The Painで共作者としてもクレジット。更に前者ではジミー・ペイジも共作&ギターを弾いてる・・・。 それでもヴィヴは特にYou'll Never Do It BabyとCry To Meで充分に存在感を見せてるんだからたいしたものだけどね。ボビー・グレアムの端正な(いや、素晴らしいプレイしてるけどね!)ドラムと聴き比べてみよう。やさぐれ感は明確だ。 要するにヴィヴの解雇を挟み、結構混乱した制作体制だったと思われるんだけど、そんな状況と考えればこの完成度は奇跡。一部ではコレこそプリティーズの最高傑作との声もあり、まあ確かにガレージ期としては明らかに完成形だ。 ただ、もう完成を見てしまったせいなのか、既に次への指針が垣間見れるところが面白い。London Townでは既にサウンドが次作Emotions、そしてS.F. Sorrowに向かおうとしている・・・。そういえばジャケにもサイケの片鱗が・・・?
2010.01.19
コメント(4)
-
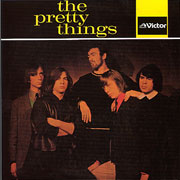
The Pretty Things
プリティーズ来日も目前に迫ったから特別企画をやるぞ。1stから最新作まで、全アルバムのレビューをやってしまおう、と言う企み。来日までに全部出来るかな。 最初は勿論この1stアルバムから。あ、ちなみに(当然だけど)スナッパー・ミュージック盤を基準で解説するからね。 デビューが64年のシングルでしょ。アルバムは65年だけど、それを踏まえてまずジャケを見る。とりあえずこの頃、ビートルズはアイドル時代真っ盛り、Whoはデビューしたばかりで、まあ他の連中も含め、こんなルックスした奴らはこの時代いなかったでしょ。いや、目つきとか存在感はWhoやストーンズも相当ふてぶてしかったけど、それでも(売り方も含め)アイドル性は持ってたワケだよ。 でもプリティーズには「アイドル性」なんか一個もない。いや、マジで怖かったんじゃないかな、こいつら。ストーンズより絶対悪そうだもん。フィルの長髪、ディックの髭面、ヴィヴの明らかにヤバい目つき。他の二人は明らかに存在感は薄いんだけど(笑)。 で、オープニングがいきなりRoadrunnerでしょ。この曲をここまで乱暴にやったヤツはいないと思うがどうか。アメリカのガレージバンドにだっていなかったんじゃないかな。 アルバムの大半はカヴァーで、オリジナルと言ってる曲も実はブルーズの改作が殆どだったりして、65年と言う時代には既に方向性と言う意味では遅れ気味だったと思うんだけど、とにかく演奏、そしてヴォーカルに「それがどうした五月蝿えぞ糞野郎」という勢いがある。 アルバム(ボーナストラックを除く)のベストトラックはRoadrunnerとMama, Keep Your Big Mouth Shutだと思う(あ、どっちもボ・ディドリーの曲だ)んだけど、後者で「とりあえず吠えとけ」的なフィルのシャウトには特にしびれる。なんか凄いタイミングで叫んだりするんだけどな(いや、他の曲でもそうだけど)。 あとディックが作者に名を連ねるHoney I Needでは既に後に見せるポップな感覚を感じさせるところに注目したい。3rdの頃になるとこの辺がどんどん洗練されて行く。 地味だ、と書いたけど、実は全体で結構サウンド面で存在感を発揮してるのがジョン・スタックス(ベース)の吹くハープだ。特にUnknown Bluesではメインのバッキングパートを担っている。ライヴではどうしてたのか解らない(ディックか、ブライアン・ペンドルトンがベース弾いてたのかな)んだけど、シンガーがハープ吹かずに専属ハープ奏者を立てる、ってスタイルはやっぱり「ブルーズバンド」って言うスタンスから来てるのかな、と思う。ストーンズでのブライアンみたいな感じかな。 でもプリティーズの場合、何故か全然違うものになっちゃうんだよねえ。多分ソレって、フィルの資質だと思うんだけど。この人ってちっとも黒っぽくない。シャウトしてもマリオットみたいには絶対ならなくて、下手するとロジャー・ダルトリーよりもっと黒くなくって、結局パンクっぽいんだよね。このやさぐれた感じはね。吐き捨てるように歌うからね。
2010.01.18
コメント(5)
-

One After 909
【情報募集】One after 909のカヴァーヴァージョン。ドラムパートにホントにTR-909使ったベタなアレンジした馬鹿っていないのかな。誰もいなけりゃ俺がやるけど。本物の909持ってないけど。 909欲しいなぁ。 いや、ホントはそれほど欲しくない。909にしろ303にしろ、俺が持ってたって宝の持ち腐れだ。コレクションとして欲しいだけなんだ、どうせ。俺にはMIDIも無い時代の機材を自分のシステムに同期させる技術なんかないし、ましてやソレで、ヴィンテージ機材に出した金額に見合うほどの音楽を作る自信もない。俺にはソフト音源に入ってるサンプリング音で充分だ。 ソフト音源、と言うかプラグインのエフェクターなんだけど、2~4000円くらいでテープエコーとか、スプリングリバーブのシミュレーターのいいヤツがあったんだよね。買おうかと思ってたんだけど、思いとどまっている。 一つの理由として、Logicに入ってるエフェクトでも結構使えるのを見つけちゃった、ってのがあるんだけど、それを使っててもう一つ気付いたのが、俺のクリエイターとしての駄目な資質、つまり、それらしい素材があるとその素材に縛られてしまう、と言うことだ。その音がそれっぽければそれっぽいほど縛りはキツくなり、音色の呪縛から逃れられなくなる。つまり、オリジナルな音楽が作れなくなる、ってコト。簡単に言えば、メロトロンのフルートがあると延々Strawberry Fieldsのイントロばっかり弾いてる、みたいな感じ・・・。 そういうワケで先週まで「どーにかならないか」と延々いじくってたダブを破棄することを決意した。前回アップした似非ダブが(一部で)評判良かったのはむしろレゲエの呪縛から離れざるを得なかったからなんじゃないか、と気付いたんだ。ただでさえレゲエの引き出し無いんだから、無理にレゲエっぽいコトやろうとすれば典型的な方に引きずられるに決まってるんだよね。それで「ぱしゃーん」ってスプリングリバーブでもかけた日にゃあ。それはその時は楽しいけど、全然俺の音楽じゃないよね。 とは言ってもいちからアイデア出すのも大変なんだよねぇ・・・(駄目じゃん)。
2010.01.17
コメント(0)
-

Pain In My Heart
今日の午後、昼飯をびっくりドンキーで食べ(何年ぶりだ?昔はKo-Ryuとしょっちゅう行ってた・・・)、午後の研修中に短時間だが謎の腹痛に襲われる。我慢してたらいつの間にか治っていたので忘れていたのだけど、帰宅後Yahooニュース見たら「宮城のびっくりドンキーで13人食中毒」の記事が。無関係だけど、タイムリー。 俺の師匠、ってもウェラー先生でも無く、ホワイティでも無く、本当の意味で、ってーか実際に習ったって意味での師匠、アースシェイカーの工藤さんが緊急手術、と言う記事を見て驚く。ラウドネスの樋口の訃報もいまだ記憶に新しいので一瞬ドキッとするが、虫垂炎と知って安心。師匠も腹痛ですか。 研修の帰り道、職場の友人O(旧姓)に近年の色々を話してすっきりする。やっぱりため込んでた部分が気分に悪影響及ぼしてたんだなぁ。気分が変わったわけでもないが、少しは軽くなった。この数日何故か妙に不安定だったからなぁ。勝手に語ってすまんな、ありがとうO。まあ、ヤツぁ読んでないんだけどな、このブログ。 痛いのは腹ばっかりでもない、って話だよ。
2010.01.16
コメント(0)
-

There No More
フラッシュの「40周年エディション」が出ると言うのだけど、未発表テイクとか入るのかと思えばコレがなんと、SHMCD+「オリジナル盤おこしリマスター」というワケの解らん2枚組。なんだか物凄く無意味な気がするのだけど、コレってもしかして「宮殿」40周年仕様のパクり企画?いくらオリジナル盤が音が良くたって、盤おこしにどれだけの需要があるのだろう。そして(多分主にプログレ業界では)この悪徳商法が流行って行きそうな気がして怖い。 それよりCDジャーナルのサイトで、これに関連して自動で入っただけだと思うんだけど、挿入された広告に笑った。カプセルの「Flash Best」、矢沢永吉の「Flash In Japan」、、知らないDVDの「Flash」、そして電気グルーヴの「Flash Papa」という絶妙に的外れなセレクト。素晴らしい。あ、再読み込みしたら別のになっちゃった。でも電気は入ってる(今度はFlasj Papa Mentholeまで・・・)。 どっかの馬鹿が1stと2ndを合体させた究極のエロジャケを作ってたからソレ載せときますね。
2010.01.16
コメント(0)
-
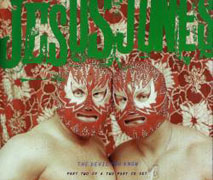
Behind The Mask
【マスカラ・コントラ・マスカラ】女子プロレスの試合形式の一つ。選手がギャル系の場合に行われ、敗者はマスカラを取られる。「マスカラ・コントラ・カベジェラ」の場合、ギャルじゃない方の選手は髪を切られるので何となく理不尽。 いや、プロレス系のサイトで「マスカラ戦」って表記を見て思いついただけ。あ、言うまでも無いけど「マスカラ」の本当の意味は「マスク剥ぎ」のことだからね。カベジェラは髪切り。 でもギャルの人の場合マスクマンのマスクと同じくらいつけまつげが大事な人もいるだろうなぁ。それに同じくらい取られたら誰だか解らないだろうしね。 あ~・・・普通の男のプロレスで敗者につけまつげを「付けちゃう」って方が面白いような気がしてきたなぁ。どこかの団体でやらないかな。
2010.01.15
コメント(0)
-
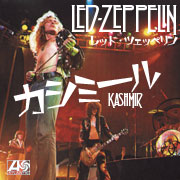
Kashmir
今更ではあるけど、カレーとZepを見間違える人は非常に多い。特にこのページの一番下を見ると「カシミール」というカレー粉を使って調理している素敵な馬鹿がいらっしゃって笑える。俺も喰いたい。 カレーは大好きなのだけど、それほどグルメじゃないし、カレーに高い金を払うという行為が許せないのであまりお気に入りのカレー屋さんは多くない。ココイチは時々行くけど、そんな美味しいとは思わない。しょっぱいんだよな、アレ。結構好きなのは松屋のカレー。アレは意外にコクがある。 で、特に好きなのが茅ヶ崎のブータンという店。ここは味も好きだし、量もあって(最近は昔ほど食えないから少し多く感じることもあるんだけど)値段が安い。カツカレーが700円を切るってのは魅力だ。 ただここには一つ難点がある。そもそも俺は「カレーに味噌汁」ってのは今一つ納得が行かないのだけど、この店も味噌汁が付く。まあ、それは納得しないまま許してる(何様だ)んだけど、ただもっと納得いかないのは、ここ箸って無いのよ。スプーンなんだ。カレーの大きなスプーンで味噌汁を飲まざるを得ない。カレー味のする大きなスプーンですくうか、直接飲むかの二択。結構「う~む」なのだけど。アレさえ無ければもう最高なんだけどな。
2010.01.14
コメント(3)
-

橙
そーか、チャットモンチーのあの複雑なドラムの良い曲は橙というタイトルだったのか。素晴らしい。 アルバム3枚(+1)を一気に通して聴いてみた。約3時間。 この人たちって、いい曲+聴きやすいサウンド+がっつりロック+実はテクニカル、というかなり理想的な音楽づくりしてるんだよね。あといい声ね。好みは分かれる声だと思うけど俺は好きだな。 テクニックもね、それが目的じゃないじゃない。曲が求めるテクニックが入ってる感じ。プログレっぽくは絶対ならない。曲短いし。「一人だけ」の6分ちょっとが最長だって?でも2分台まで短い曲もないのね。歌詞をじっくり聴かせたいのかな。 しかしこの声(声域/声量)が出るシンガーはどのバンドも欲しいだろうなぁ。 アルバム3枚通して聴くとやっぱりメロディに癖、というかパターンがあるのが解っちゃうけど、まあそれはそういうもんだし、ワンパターンってワケでもないから全然オッケー。アレンジには幅もあるし。 ただやっぱり、いい声が逆に仇、というか、結構強い声だから通して聴いてると疲れちゃうって一面はあるかな。 ところでジャケ、「イラレで描いた赤と青3部作」が完結したわけで、次回作がどういうデザインになってるかが素人デザイナーとしては楽しみだね。ミニアルバムの「おざなりPhotoshop使い」はヒドかったのであの路線に戻らないことを祈る。
2010.01.13
コメント(3)
-

You Don't Own Me
えぇ~ッ!?ミック・グリーン亡くなったの!?コレは結構ショックだな・・・何もアベフトシの後を追うように死ななくても・・・アベも本望・・・じゃねぇよな。アベ「こっち来ないでくださいよ!」ミック「いやお前の方が早すぎるんだよ」。そんな会話を妄想しつつ。R.I.P. 俺がミック・グリーンの名を知ったのは元を辿れば実はQuoからだ。You Don't Own Meをはじめとした数曲がLancaster / Greenってクレジットされていたんだけど、その段階ではミックのことは全然知らない。その後、モーターヘッド+ガールスクールのPlease Don't Touchを聴いて、この曲がジョニー・キッド&パイレーツのだ、と言うことを知る。そういえばShakin' All Overもそうじゃん、と思って少し気になりだす。 でも当時レコード屋に行ってもジョニー・キッドなんて売ってないんだよな。で、どんなタイミングだったかな、調べたのかな。そのバックバンドがパイレーツで、パンク/ガレージ系に人気、で、しかも復活後パンキッシュな音楽でそいつらと同レベルで渡り合ってる・・・云々、と言った情報。 そしたらギターがミック・グリーンって人。あれ?この人ポールのレコードとか参加してたよね、ってコレ、Run Devil RunじゃなくてCHOBA B CCCPの話ね。なんか縁がありそうだな、って思ってレコード屋でCD見たら、You Don't Own Meが入ってた。「えーっ!同名異曲?まさかね。あ!そういえば、この曲Lancaster / Greenじゃん!・・・Greenって、ミック・グリーンかよ!」ここではじめて繋がった。半信半疑でよく見るともう一曲、Hard Rideって曲もある。コレもQuoの曲。勿論Lancaster / Green。 俺はミッシェルガンは通ってないんだけど、音楽ってこうやって繋がるから面白いんだよね。そうかぁ・・・逝っちゃったかぁ・・・残念だなぁ・・・。
2010.01.12
コメント(5)
-

Sing The Changes
ポールのプロジェクト、Firemanの最新作(2008年)がキカイダーに見えるのは俺だけじゃないと思う。 ポールの話をしようか迷ったがDVDはまだ見てない(CDは聴いた)のでキカイダーの話にする(えぇっ!?)。 石ノ森章太郎のエラいところって、こういう「明らかにおかしいだろう」的なデザインを格好良く見せてしまう、ってコトだと思う。ゴレンジャーとか、アクマイザー3なんかもそうじゃん。いや、仮面ライダーだってそうだよな。基本は「異形」。そしてキカイダーやライダーに共通する「垂れ目」は悲しみ(異形であること、戦うこと)の表現なんだそうだ。 思想は置くとしても、「明らかに変=格好良い」ってのは良く考えてみると偉大なアートの重要条件なのかも知れない。その「明らかに変」はイコール見る(聴く)側への「引っ掛かり」になるんだよね。 ただ変なだけじゃあ「変なの」で引っかかったものは外れてしまう。それ以降(以降じゃないんだけど)の表現、ってーか、要するに一回引っかかった針(針なのか)をつい飲み込ませてしまうだけのアートの力。そこだよね、差は。 年末年始に従弟や妹とも話してたけど、ビートルズってそうじゃん。アレンジとか、コード進行とか、メロディとか、明らかに変がいっぱいあるじゃん。でもそれが変だけど違和感じゃなくて、気持ち悪いってコトは全く無くてその変なポイントこそ大事、って言うか。妹が「西瓜に塩かけるようなもの」っていったけど、それかな。 あ~・・・キカイダーの話のつもりがこっちに来ちゃったか。しかもビートルズ(ポール)に戻ってきたな。たいしたもんだな、俺も。
2010.01.12
コメント(2)
-

Is It In My Head?
どうも昨日から色んなことが微妙に噛み合わない。なんだか上手くいってない気がして、何が上手くいかないのか解らずに苛々する。苛々してる時には特にガキが邪魔に見えて、よりによってこういう時に成人式終わったばかりのガキどもがゴミのようにうろついていて更に苛つく。成人を18歳から、とか言う議論があるみたいだけど、俺に言わせりゃ25くらいにすべきだと思うね。30過ぎるくらいまではガキだよ。自分の経験から言ってもね。 噛み合わない時は買い物も失敗する。 昨日新調した眼鏡は、最初良かったんだけどかけてるうちに痛くなってきて再調整。忙しさにかまけてか、ZOFF町田店手ェ抜きやがった。「丁度いいみたいですね」って、今日藤沢店持って行ったら「全然合ってない」って言われたぞ。もうあそこじゃ買わねえ。 iPod用のイヤフォンを新調した。理由は以下のうちどれでしょう。1)AKGのイヤフォンが安かった。2)AKGでしかもカナル型じゃないイヤフォンが安かった。3)AKGでカナル型じゃなくてしかもオレンジのイヤフォンが安かった。4)オレンジだった。 サウンドもかけ心地も見た目も気に入ったんだけど、音漏れが激しい。ちょっと電車では使い辛いかな、ってレベルに・・・。でも気に入ったからネットで予備も注文した。歩きや自転車の時はコレ、電車用にカナル型をもう一個用意しようかな。幸いクリアに聴こえるから音量は上げなくても結構聴きやすいしね。自転車乗ってる時音大きくすると危ないからさ。そういう理由で「耳栓型」も避けてるんだけどね。 AKGって、赤城音響っていう日本のメーカーのブランドだって知ってた? DAW用にKorgのnano Kontrolを買おうと思っていたら、丁度良く中古品があってしかも更に10% offだった。喜んで買ったらどうもLogicで上手く動かない。調べたら専用のドライバがいるみたい。DLして、なんとか動くようになったけど、俺がやりたいようにするために少しカスタマイズしようとしたら何故か設定中にやたらLogicが落ちる。デフォルトで使えというのか。でもそれではダブ向きじゃないんだよ。 大失敗はしてないんだけどな。どうにもガッツリハマらないんだよな。 あ、赤城音響の話は嘘です。でも今ググったら赤城音響研究所ってのが実在して焦った。
2010.01.11
コメント(2)
-
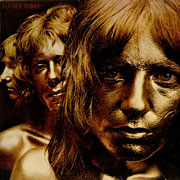
Bossa Jump
おかしな夢を見た。「奇妙な」といえば奇妙なんだけどむしろおかしな夢。夢の中に出てきたあるグッズ、というか玩具?置物?とにかくそれがあまりにくだらなくて爆笑して目が覚めた。こんな経験無い。目覚めて呆然。 Judas Jumpを聴いた。 Quo関連、アンディ・ボウンのいたバンド、と言うことで得意のB級HRというイメージで聴いたんだけど、それは違うということはすぐに解った。金色なのに貧乏臭いジャケがQuoの12 Gold Barsを思い出させたせいかも知れない。でもこのデザインはなんとなくヴァーティゴっぽい(実際にはパーロフォンからリリース)様な気がする。 良く考えるとアンディというのも今一つ実態の掴み難い人で、まああんまり派手では無いキーボーディスト、しかもマルチプレイヤーで器用貧乏的というか。ソロをガンガン弾くタイプでも無いので目立たないせいかも知れないけど。まあ、Quoでの楽曲やHerdを聴けばポップ的なセンスを強く持った人だ、と言うことは解るんだけど。 何が言いたいかというと、アンディ→Quoって流れを意識するQAJ的聴き方ではこのバンドは捉えられないんじゃないか、と。そもそもアンディがQuoに参加するのこの後だし。むしろヘンリー・スピネッティが在籍したバンド、と考えた方がスムーズなんじゃないかな。 だからちょっとスワンプ的な感じを持った曲もあって、ギターの響き方なんかも湿度低めだし。かと思うとボンゾズかポールか、っていうおふざけっぽい、でも英国臭さ満載の小曲があったりとか。メロディがポップだったり、結構ハーモニーが重要な位置を占めてたりとか、そういう意味ではたまたまハマってる同時期のプリティズなんかとも通じるところもあって、この時代のミュージシャンがサイケデリックから抜け出してルーツ時代へ・・・っていう過程がかいま見れるアルバムとも感じたな。しかもビートルズやストーンズが68年後半くらいで済ませてるところを70年にやってるその遅さもB級っぽいんだけど。 ヘンリー・スピネッティはまさかアンディをクリス・ステイントンと見間違えてバンド組んだんじゃないよね(似てないって)。
2010.01.11
コメント(0)
-

Alexander
チケットを取ってしまってからmixiに貼ってあった昨年一月(丁度一年前か)のプリティズのライヴ、しかも曲はAlexander、という嬉しいものを見る。これが予想した以上に格好良くて、がぜん来日への期待が盛り上がってきた。 60年代の映像もあって、こっちの格好良さも筆舌に尽くし難いんだけど。映画のワンシーンらしいけど、トゥインクもいるし、近年のライヴ(今回の来日には不参加)では紳士然としていたジョン・ポーヴィが上半身裸で熱演してるのとか、ディックとフィルは結局いつまでも悪そうだ!とか、なんだか物凄い格好良い。映像のサイケデリックに妖しい感じも良いんだけどね。 この曲はプリティーズがElectric Banana名義でリリースした曲の一つ。この名義では断続的に、こういうサントラ仕事などの作品を出してるんだけど、実は本体作品を凌ぐ名曲がこうやって潜んでいるから油断出来ないのだ。 映像を見て解る通り、この曲はS.F.Sorrowと同時期の曲で、メンバーもほぼ同一。フィル、ディック、ポーヴィ、トゥインク、ウォーリーという最強ラインナップの一つだ。俺にとって真の最強はドラムがスキッパーに戻ってからなんだけど、でもトゥインクの荒々しいドラミングも最高だ。トゥインクは好きなんだよ。プリティーズという塊としてはスキッパーがいる方が嬉しいだけで。 そんなワケで、プリティーズ名義では無いにも関わらず俺が一番好きなプリティーズの曲、来日公演でもやってくれたら最高なんだけどな。楽しみだな。
2010.01.11
コメント(0)
-
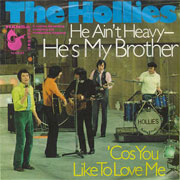
He Ain't Heavy, He's My Brother
そういえば年明けてからすっかり報告が途絶えていたな。別に知りたくない人も多いだろうけど。ってーか書くようなことは無いんだけど。あんまり増えてないしあんまり減ってない。 変動はあって、やっぱり年末呑んで、それからあんまり家から出ない正月休みってコトで若干増えて78kg台後半平均って感じだったんだけど、先週アタマにはまた77kg台半ばまで戻ってたんで安心、してたら二日前くらいかな、いきなり79kgを上回って焦った。でも昨日の朝にはまた77.1kgまで戻って。更に呑んで帰って今朝、76.3kgだった。変動幅3kg時代に復帰か(笑)。 まあ呑む時、特に相手が女性だとあんまり量食わないから、水分が出ればそれだけ減るんだろうな、とは思ってるんだけど。今夜カレーだったから明日はもう少し多いだろう(笑)。 カレーについての話題はまた後日。 今度の目標は腹周りもそうだけど、俺は結局足が太い(自転車毎日こぐ関係もあるんじゃないかな)んでこれ以上小さいズボンは多分履けない。だからソレはサイズダウンというより腹が出たみっともなさの解消、という意味として、体重ももう少しだけ、一年かけてもいいから75kgをわずかに切るかどうか、くらいまでは持って行きたいと思っている。日々の変動はあるから、上限を今の77kgくらいにする感じかな。それで充分だと思うんだけど。 年末に会った友人達が165cm/65kgとか165cm/70kgとか言ってたので少しだけ勝った感じだ。でもあいつ(70kgのほう)は筋肉も結構あるんだけどね。何せフルマラソン完走する男だからな。負けてるじゃん。
2010.01.10
コメント(0)
-

Money-Go-Round
今日(昨日か)は酔っぱらった感強いなぁ。 先月中止になった呑みの代替で池袋。結局ゆっくり呑めた分延期になって良かった気がする。先月の段階では翌日早いから軽くで、って言われてたからね。店が混んでてカウンター席で、あんまりゆっくり出来なさそうだしある程度呑んだら移動しようか、とか言ってた割に結局11時まで居座る。しかも二人だし、そんなに量呑まないんだから嫌な客だろうな。四時間半居座って一人3000円。 その前に新宿に寄ってVINYLへ。勿論プリティーズのチケットを買うためである。ついでにセールで2割引だというのでTSCの7インチ、Money-Go-Roundも購入。ちょっと高くてもヤフオクより状態がいいのが手に入るなぁ。やっぱ時々新宿行った方がいいか。 チケットをわざわざVINYLまで買いに行ったのは店頭特典のバッジが欲しいから、と言っても過言では無い。画像ではよく見えないと思うけど、Parachuteの時のロゴがデザイン。同行者に連絡を取ったら「S.F.SorrowやParachuteからいっぱい演って欲しいな」とのご意見。俺も結構同意見なんだけど。いや、出来れば70年代の曲も聴きたいけど、今回のメンバーでは期待薄。だがコレは期待を煽るグッズだ。 その後池袋で呑んでたら別のライヴにお誘い頂く。四月だから読めないけど、読めない時には先に予定を入れてしまうに限るのだ。楽しそうなことには乗っからない手は無い。 その前に西新宿を久しぶりに歩き回る。まあVINYLに行くまでの暇つぶしで、結局ブート屋さんにも全然寄らず済ませる。「あの界隈」の雰囲気を感じたかっただけ。柏木公園の写真撮れば良かったな。懐かしいディスクロードもキニーもエアーズも無くって少し寂しい。 その後池袋で呑んで、たいした量でも無いのに酔っぱらって結局東海道線終電で帰宅。家に着いたらディスクユニオンからJudus JumpのCD(祝・再発!)が届いていた。 その前に新大久保で中古楽器店に行ったらちょっと欲しいシンバルが・・・ その後、風呂に入って寝る。 その前に家で寝ていた。 今日は(昨日か)雨は降らなかったな。
2010.01.10
コメント(5)
-

Led Zeppelin 1980 U.S. Tour
忘れた頃に(俺が)やってくる妄ステ。誰も楽しい人がいない妄ステ。でもやります。 これははっきり言って誰もが悲しみとともに妄想したと思う。そう、レッド・ゼッペリン1980年全米ツアーを、実はこのツアー用の選曲やアレンジが考えられていた、という情報が幾つかあったりもするんだけど、あくまで俺の趣味を最優先して考えてみた。 80年のヨーロッパツアーは13~5曲くらいのコンパクトなセットだったけど、USツアーってコトになればもう少し曲を増やしてくるに違いない!ってコトで、77年のLAフォーラムや79年コペンハーゲンを参考に(ネブワースはスペシャルだからね)18曲で選んでみました。1.The Train Kept A Rollin'2.Sick Again3.Nobody's Fault But Mine4.Black Dog5.For Your Life6.In The Evening7.All My Love8.Carouselambra9.SInce I've Been Loving You10.Trumpled Underfoot11.Kashmir12.Ten Years Gone13.Warering And Tearing14.Hot Dog15.Achiles's Last Stand16.Stairway To Heaven(encore)17.Rock and Roll18.Whole Lotta Love(Knebworth Special) incl. Let That Boy Boogie ・・・長いか?まあ、Zepだからいいだろう。長尺ナンバーは多いが冗長なギターソロ、ドラムソロは無し。White Summer~Black Mountain Sideも無し。他にはヨーロッパツアーからRain Songが落ちて、ライヴ初登場のFor Your LifeとWarering and Tearingが。後者は当然ツアー記念にEPとして出るわけだね。日によっては例によってアンコールでCommunication Break DownやHeartbreakerも登場しただろうね。
2010.01.09
コメント(0)
-
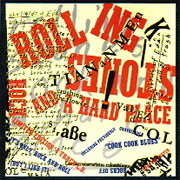
Rock And A Hard Place
ストーンズのアルバムで一番好きなのはBlack and Blue。一番聴き込んだのは多分Tatto You(最初に買ったアルバムだからね)だけど、一番思い入れが強いのはSteel Wheelsだ。 そりゃあそうだ。だって俺は初来日を見てるんだから。このアルバムを聴いて心待ちにしたんだよ。ネットがない当時、雑誌とかで必死で情報を集めてツアーのセットリストを入手して、同行する友達にテープ(懐かしいな)作って。Angieが好きな女の子。俺は(高校生の分際で)あのツアー3回行ってるんだけど、その日だけAngie演ったんだよな。行く前はライヴ後に食事でも誘おうと思ってたのにストーンズに興奮してすっかりそんなこと忘れてジュースさえ飲まずに普通に帰ってきたのも思い出だ(特別に好きな子だったワケでもないんだけどね。可愛かったけど)。 俺はAngieよりAlmost Hear You Sigh演った日の方が嬉しかったんだけどね。 でも今日の本題はそっちじゃなく、この曲だ。 Steel Wheelsからは2曲目のシングルカットでヒットはしなかったけど、当時来日公演のCMとかにも使われてて結構浸透度は高かったんじゃないかな。俺はアルバムもシングルも持ってたけど、特にシングルでは変なリミックスヴァージョンが山積みで逆に印象が薄れてしまっていたんだよね。 それが一気に晴れて、俺の中で超名曲、★★★★★の扱いになったのは実はもう少しあと、テレビでVoodoo Rougeツアーの映像を見た時だ。 Steel Wheelsツアーではチャック・リヴェールのオルガンのグリッサンドからチャーリーのタムでのフィル、って始まり方で、これが今一つインパクトが薄い。アルバムではスネアなんだけど何故か変更(気まぐれ?)されているんだよね。 それがVoodoo~ではスネアのフィルに戻って、しかもフィルを埋めがちだったオルガンも小さめのバランスになった。そして、それ以上に演奏全体がソリッドになっていて、格好良さが3割増しくらいにまで跳ね上がってしまったのだ。ベースが変わった効果かも知れないな。ブレイクのベースはダリルの方が向いてるしね。あとホーンの使い方も少し違うし、ギターもラフになってる感じがする。マット・クリフォードのクラビみたいな音が余分なのかも知れない。 そうやってライヴを堪能してからスタジオヴァージョンに戻ると今度はその良く出来たサウンドプロダクションに感動したりもする。要するに曲がいいんだよ。どうやって聴いたって格好良いんだ。
2010.01.08
コメント(0)
-

Funky Junk
amazonから届いたCDがラヴィ・シャンカールとディランとM/A/R/R/S。何を考えてるのか全く解らない(俺か)。「ディランとシャンカールまでは・・・」っていう人もいるかも知れないけど、キリスト教時代のディランだからね。 サバスとマッカートニーおじさんのDVDは後から届くってさ。 レアドロの福箱も届いた。スティーヴィー・ワンダーとジミー・マクグリフのTシャツが含まれていたのでそれだけで7000円分、充分元を取った。加えて長袖2枚、半袖もう一枚(ピンク。コレもデザインはともかく欲しかった色)とニットキャップ。5000円でコレなら全く文句はない。大満足だが欲しかったヤツ(買い替えようと思ってたヤツ)は入ってなかったので後日購入予定。 ヘッドフォンはまだ届かない。 CDはもう少し積極的にレンタルしようかと思う。買うのはレンタルしてないヤツと凄く好きなヤツ、それからレンタルして凄く気に入ったヤツと中古屋で一期一会だったヤツだけにしよう、ってそれのどこが「だけ」だ。それにこれだけ決めても「衝動買い」という魔物は誰にも止めることが出来ないのだ。
2010.01.07
コメント(2)
-

ハナノユメ
薄い紙で指を切って 赤い赤い血がにじむ これっぽっちの刃で痛い痛い指の先 チャットモンチー/ハナノユメ 以前もその現象には触れたことがあって、あの時は元同僚がコメントをくれたけど、この曲の歌詞を一番本気で実感出来る職場ってのはやっぱりうちの会社、というよりうちの部署だと思う。厚い紙でも切るけどな。 しかしこのデビューミニアルバムのジャケのあかぬけ無さと、画像処理のおざなりさ加減ってのはやっぱり(アマチュア時代から評判が高かったとは言え)「海のものとも山のものとも知れない小娘3人がキューンからデビュー」っていう条件とリンクしてるんだろうなぁ。 しかしキューンみたいなレーベルの所属バンドこそ、iTunes StoreからDL販売みたいなフットワークの軽さが似合いそうなんだけどソニーが馬鹿だからそれはままならない。電気なんかまさしくそうなんだけどな。 逆に一番似合わないのは人間椅子。しかし実は売ってるのだな。
2010.01.07
コメント(3)
-
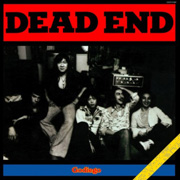
Dead End~Love Flowers Prophecy
俺と同世代近辺の人たちだったらゴダイゴを知らないと言うことはまずない。あの当時はまさに一世を風靡していて、あらゆるところで彼らの曲が流れていた。特に国際児童年のテーマ曲「ビューティフル・ネーム」、日本テレビのドラマ「西遊記」のオープニングとエンディングだった「モンキー・マジック」と「ガンダーラ」、そして映画「銀河鉄道999」のテーマ曲・・・ それらの曲は幼い俺にはいつの間にか刻み込まれていたんだけど、高校で同じクラスになったある男によりその記憶が突如呼び戻されることになる。 彼は「ゴダイゴのファンだ」と言っていた。俺は上記の曲は当然よく知っていたが、既にロックを聴きまくるようになっていたけど当時は邦楽を聴くと言う発想自体なかったし、それ以上にゴダイゴをある種「ロック」って言うか、うん、音楽とさえ捉えていなかったんじゃないか。なんか懐かしいあの時代の空気、とは思っていても。 でもその男と話すうちに、確かに俺はゴダイゴの音楽が好きだったことに気付く。そうだ、俺は間違いなくモンキー・マジックが大好きだった。アレはもしかして俺の「ロック」の原体験じゃないのか。そこまで言ったら言い過ぎか。 そいつの家でゴダイゴのLPを聴くにつれ、ロックバンドとしてゴダイゴが素晴らしいことにすぐに気付いた。当時中二病真っ盛りの俺だが、メンバーに外国人2名、歌詞は殆ど英語、と言うのは素晴らしい言い訳となり、「邦楽」を聴くことにたいする抵抗感はゴダイゴに対してはなかった。 本題までが長くなっちゃったな。ヤツの家で聴いた曲の中で特に好きだったのがこのDead End~Love Flowers ProphecyとProgress and Harmony。特に前者の格好良さは格別だった。 アルバム全体がダークなムードに包まれてて、俺の思っていた、明るく安全なゴダイゴ、と言う感じとは全く違っていたんだけど、特にタイトル曲のコレは、実際アルバムの他の曲よりキャッチーなんだけど、凄くクールに感じた。 とにかくイントロのピアノのリフから凄く格好良くて、これだけで引き込まれないほうが嘘。そこからの盛り上げ方も、徐々に楽器が増える、まあお決まりのスタイルなんだけど、ドラムの入りがミソで、ありがちに「ガツン!」と入るんじゃなくて入りは抑えてるんだよね。で、そこから得意の手数の多いドラミングに徐々に持って行く、って言う、いや、凄く巧みに出来てると思う。 でまあ、当然最高なのが後半のヴォーカルの掛け合い。前半に登場する2種類のサビに当たるメロディが対位法になって登場するんだ。これはもう俺の大好きなパターンで。レコードでは女性コーラスとタケカワなんだけど、やっぱりここはライヴでのトミーとタケカワでやってるほうが最高ね。ライヴはテンポも速くて(ファイナルライヴのは速すぎるけど)ロック度も更に上がってて最高!(一段落に3回も最高って書くのは文章としてどうかと思います)。 で、高校で知りあった「その男」とは1999年には横浜で、2006年には奈良まで行ってゴダイゴの再結成ライヴを見ることになるわけだ。長い付き合いになったものだよ。当時はまさか一緒にバンドまでやるとは思ってなかったけどな。
2010.01.06
コメント(2)
-

Listen To The Band
音楽始めました。 もう少し前から一部(主にmixi絡みの音楽仲間)には公開していたのだけど、思い切って、って言うのもアレだけど一般公開に踏み切ろうと思う。 minoradio - My Space minoradio (マイノレディオ、と読む。みのではない)と言うのは、以前SIN Creationと言うバンドをやっていた時代に平行して活動していた、と言うか活動しようとしていた零細エレクトロミュージック・プロジェクト。当時の俺なりのダブや、アンビエントっぽい曲を作っていたんだけど活動の場がないままフェイドアウト。結局ドラムに戻ってからはテクノへの熱が薄れていたので長らく封印されていた。 でも、いつかは新たな形で活動をしたいと思っていた。で、最近バンドがライヴを休止中と言うことも相まって、この際だから自分の音楽を形にしてみるか、と言う気になったわけだ。 旧minoradioはKorg 01/Wで作ってたけど、今回は主にmacの付属ソフト、GarageBandで作った音源を公開して行くと言う形になる。 このソフトは、ループを組み合わせて音楽を構築するという、初心者でも遊んでれば音楽っぽいものが作れるお手軽ソフトであり、付属のループを組み合わせるだけでもこの手の音楽が簡単に作れる。今現在公開している5曲は大半の音源をこの付属ループに因っており、そういう意味では純粋に俺の自作曲とは言えない。だから今回どこにも「作曲」と言う言葉は使ってないのだけど、そういう中からどれだけ俺の世界を表現出来るか、ってのもある意味挑戦、ある意味手抜きだ。 でも既にそれだけでは飽き足らなくなっていて、並んでるうち上の方の2曲ではごく一部だが自分で打ち込んだループが使われている。最近作ったヤツにはスタジオで録音した俺の生ドラムをサンプリングしたものもあったりするし、前回書いたようにフル自作の曲も進行中だ。そうやってこれから徐々に「オリジナル曲」に近づけて行こうかな、と思っている。新兵器も既に導入してるしね。 さて、このMy Spaceを使った活動だけど、マードックスの曲もこっちで(minoradioとは別ね)公開する準備もしている。それは今月中にでも正式に公開出来るんじゃないかと思ってるんだけど。そっちもお楽しみに。なんとマードックスのメンバーのブログも・・・いや、やる可能性は薄いな。 写真ブログはもうちょっと待ってね。ってーか俺、手ぇ広げすぎじゃないか。どれか息切れするでしょう。
2010.01.05
コメント(2)
-

Dub To The Rescue
休み最終日。minoradio用の曲と戯れていたら半日終わった。 作曲してた、というより戯れてた感じ。リズムセクションの打ち込みを一時間くらいで済ませて(2~4小節のループを5パートくらい作っただけ)、あとはシンセでアドリブ弾きまくっていた。年末に画像のブツを入手したのでリアルタイムで打ち込み可能になったのだ。ピアニカに見えるけどUSBキーボードである。大きさはピアニカとおんなじ。 メロディらしきものが出来たら打ち込んで、ソロっぽいのをでっち上げて・・・あんまり面白くないレゲエが出来た。どうもアップルループで作ってた時の方がオリジナリティのある曲になってた気がするのは気のせいか。 要するに引き出しの問題だよな。他人のループを俺が構築する、って行為は、自分の引き出しに無い音を選んで使うことが出来るわけで、それだけで実は幅が広がる。それをどう構成するか、何を加えるか、ってのが俺のセンスの出しどころで、まあリミキサーに近い作業なんだろうな。でもそれはそれで充分「音楽製作」だ。 今回はダブに再挑戦を目標に据えたんだけど、最初にオーソドックスなレゲエのビートを作ってしまったからそこから抜け出せなくなってしまった。何か一個や二個、全然違うものをぶつけないと面白くも何ともないんだよな。まあ、これはあくまで習作、プロトタイプとして、ここから何か広げて行こうかな。やっぱりアップルループは上手く使って、混在させた方が面白くなりそうだな、俺の場合。
2010.01.04
コメント(2)
-
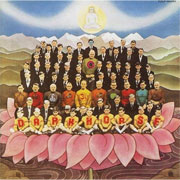
Far East Man
名曲というのはどうやっても良い、という話。 例えばDon't Let Me Downのカヴァーには外れが少ないんだけど、アレは要するに、原曲が良過ぎてどうやっても悪くなりようがない、という仕組みなのだ。 Far East Manはジョージとロニーの共作で、存在が地味な人同士が共作したおかげで非常に地味で、素晴らしいミュージシャン同士が共作したおかげで非常に素晴らしい曲として完成した。極端に良い曲なので二人のヴァージョンを交互にリピートしていてもどんどん心地よくなる一方で全然飽きる気配がない。 どちらのヴァージョンもそれほどアレンジは違わなくて、特にリズムセクションはアンディ・ニューマーク&ウィリー・ウィークスで共通。このコンビ(元ファミリー・ストーン+元ダニー・ハザウェイ・バンド)を開発したのはロニーで、それだけでノーベル賞モノなのだが、ファンキーな曲でなくてもこういう気持ちよいグルーヴを打ち出してくれるのでもうそれだけでもオッケー。あとはジョージとロニーがあんまり上手じゃない素晴らしいヴォーカルを乗せるだけである。 他のメンバーも両者共に豪華。ジョージはこの後のツアーメンバーとの録音で、ビリー・プレストン、トム・スコットが参加。彼らの演奏を軸にしたちょっとフュージョンっぽいサウンドで渋めに決める。ソロやオブリガートは主にサックスで、ギターは控えめなのね。コーラスはプレストンかな?ちょっとロニーっぽい声も聴こえる気がするんだけどクレジット上は参加してないことになってる。 対するロニーのヴァージョンはジョージがギターとバッキング・ヴォーカルで参加。キーボードはマック(イアン・マクレガン)で、ジョージのヴァージョンよりシンプルな、ギター中心のサウンドになっている。音からすると多分ギターは2本、キースは参加してないんじゃないかな。ギターソロはロニーだよな、コレは。ニューマークのドラムが微妙にニュアンスが違うんだよな。それが面白い。 どっちのヴァージョンがいいか、と訊かれると物凄く困る。俺はロニーよりジョージのファンだけど、この曲はどっちのヴァージョンも最高にいいんだよね。似てるようで微妙に違って、その違い方がどっちもいい方に違う。ロニーらしく、ジョージらしく、この地味でいい曲を丁寧にアレンジして、いい演奏とあんまり上手くない(しつこいな)けど素敵な歌で俺達に聴かせてくれてる。結局、こうやって2ヴァージョンを延々リピートしてるのが最高なんだよ。
2010.01.04
コメント(0)
-

Idiot Box
レアドロの福箱を買うのは今年で3回目になるのかな。実際には正月だけ売ってるわけじゃないから、正月に買うのは2回目か。今年は例年よりお得で、2万円分のアイテム(例年は半袖Tシャツ3枚+長袖1枚で約15000円分)が入って5000円だと言うのでいつもより早く予約した。ここのTシャツはたいてい好きだからそう滅多には外れない。逆言えばそのくらい安心感がなければ福袋とかの類いは買えないよな。 例年は勿論XLを買っていたんだけど、今年はMサイズにした。早く予約したのはその辺にも理由がある。普通サイズであるM、Lはレギュラーアイテムでも売り切れが多い。特にセール品は軒並み売り切れている。だから早くしないとな、と思ったんだ。大正解だった。年明ける前に完売。メルマガが来てすぐに予約して良かったよ。XLはまだ残ってるから、今までだったら油断してても平気だったんだな。 今回はサイズが違うから、今まで持ってるのとかぶっても大丈夫、ってのがポイントかも知れない。同じデザインが入ってたら買い替えって考えてもいいんだ。実際気に入ってるヤツをMに買い替えようと思ってて、それなら運良くそれが福箱に入ってればラッキーじゃん。まあ、福箱らしく運試しだよね。入ってなければ、別に買うさ。 発送は1/5以降だと言うから、楽しみに待っていよう。
2010.01.03
コメント(0)
-
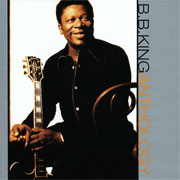
Why I Sing The Blues
ブルーズを一番聴いたのは高校生の頃。Zepやストーンズのルーツとしてマディ・ウォーターズやハウリン・ウルフ、ロバート・ジョンソン等のレコードを買ってきて、カセットで登下校中に聴くと言う嫌なガキだった。ジョンソンなんかは最初は面食らったけど、そのうち結構馴染んでしまって愛聴していた。 愛聴したとはいっても、良く聴くのは上記アーティスト達の原曲ばかりで、例えばLove In Vainは聴いてもKind Hearted Woman Bluesは聴かなかったりとかそういう程度なのでそのうちP-Vineが便利なClassicsシリーズを出すとそれで充分、と言う感じになり、ブルーズ方面は結局現在に至るまでそれほど掘り下げずに来ている。 そんなワケで、60~70年代ブルーズ~ハードロックバンドによる直接カヴァーがあまり思い当たらないB.B. Kingは実は現在に至るまで縁の薄い存在だ。一応ベストを持ってはいるけど、あまり熱心に聴くわけでは無い。 だから例によってこの人の印象の多くの部分はライヴ・エイド、オランダのステージに立っていた時のこの曲、と言うことになる。 実際にそこで演奏されたのはWhy I Sing The Blues~Don't Answer The Door~Rock Me Babyというメドレーだが、日本での放送はDon't Answer The Doorの途中までだった。でもスローな同曲より初っぱなの、ある意味ファンキーでさえあるWhy I Sing The Bluesの方が中学生の耳(まだ高校でブルーズを聴く前である)には解りやすくて、また、少しコミカルなルックスの出っ腹のおじさんの親しみやすい印象(ブラック・サバスの真逆だ!)と相まって、結構好きな曲になっていた。 ところがこの曲を「ちゃんと」聴いたのは実は去年だったりするのだ。しかもiTunes StoreでのDLで。入手したのは(多分)76年のヴァージョンで、8分を超えるロングヴァージョンだ。これがライヴ・エイドよりはるかに格好良い。よりファンキーで、ギターもヴォーカルも冴え渡っている。 そしたら先日、ご存知の通りGet Yer Ya-Ya's Out!のデラックス盤が出たわけだけど、そこにもこの曲の70年ヴァージョンが入っていた。これもメドレーになっていて、Why I~からスローなブルーズへメドレーにつなぐパターンはこの頃には既に出来ていたことが解る。繋ぎのフレーズも同じだ。 何が凄いって、やっぱり70年でも85年でも渋さが全然変わってない、ってトコだろうな。完成しちゃったら一個もぶれやしねえ。脱帽だよな。
2010.01.03
コメント(0)
-

E.S.P.
20100102ってシンメトリーだねぇ。 近所の子供がバットで一生懸命タイヤ(木の棒に括りつけてあるヤツ)を叩いていたので「痛ッ!」と叫んで逃げてきた。リアクションは不明だが十数秒間バットの音が止んだ。 写真を撮るのに少しずつ色々考えてみた。最近夕日や夕焼けを良く撮るのだけど、奇麗に撮るのにはどうすりゃいいのか?とか考えても解らないのでメニューとかに入って適当に機能をいじくる。 「測光」という言葉の意味は何となくわかる。光を測るのだから、明るさをカメラがチェックしているわけだ。どうやらこれを「ESP」じゃなくて「スポット」という方を選んだ方が俺の欲しい感じに撮れる場合が多いことが解ってきた。 「ESP」とは勿論超能力のことである。このカメラはどういう仕組みかわからないが超能力を利用して測光する機能を持っているようなのだ。残念ながら俺には超能力はないので、この機能は上手く働かないようだ。つまりそれがそのまま写真の出来に繋がってきた、というワケなのだな。念写とかする時もこのモードを使うのだろうか。カメラに詳しい超能力者がいたら教えてください。 ISOと言うのもよくわからない。数字が大きい方が暗いところでも撮れる(ノイズは乗る)と教えてもらったのだが、この数字が更に大きくなると環境がどうこうって話になって偉い人に怒られたりするのだ。ISOは小さめの方が面倒が起こり辛い、ということはだいたい理解した。 まだまだ俺には難しい分野だな。
2010.01.02
コメント(0)
-
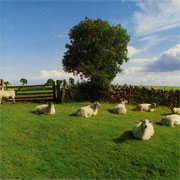
3AM Somewhere Out Of Beaumont
正月は暇なのでだいたいこんな更新ペースです。スタジオ営業して欲しいなぁ。 年末に買ったCDとかツタヤで借りてきたCD(俺だってたまにはレンタルするんだよ)が結構たまっているのに何故かKLFを聴いている。理由は無いのだけど、天気の良い冬の朝、何となくまどろみながらのChill Outは心地よい。 借りてきたのはフィッシュマンズ、ジョニ・ミッチェル、スプリングスティーンという脈絡の無いセット+最近出たLove Love Loveっていう国産ビートルズカヴァー集。最近俺のiTunesには安室奈美恵とかグレイが入ってしまっていて気持ち悪い。 グレイはMother Natures Sonをカヴァーしていてあんまり良くなかったんだけど(どうにも歌い方、ってーか声の出し方がね)、安室奈美恵はなんか変に評判が良いので興味を持って職場で借りた。確かになんかアーティスティックな方向で良いのは解るんだけど、どうにも俺は声が好きになれない、と言う意見で終了。マドンナになろうとしてるんだろうなぁ、とは思った。頑張れ。 カヴァー集には図らずも(実は聴いたことの全く無かった)フジファブリックが入っていた。他には布袋、椎名林檎、吉井和哉など、なんか俺のブログ読んでくれてる皆さんの方が興味ありそうなメンツ。個人的には原田知世が良かった。あ、ジェイムズ・イハが参加してる曲もあった。 フィシュマンズは途中まで聴いたんだけど、サウンドは大好き。これも声があんまり好きになれない気もするんだけど、曲によっては好きだったりするからもう少しゆっくり聴く予定。欣ちゃんのドラムはいつ聴いても最高。
2010.01.02
コメント(2)
-

Uh-Huh Oh-Yeh
2010年になって最初にちゃんと聴いたのがこの曲。なんか景気付けが欲しくてね。ちょっとそういう気分だったんだ。 ウェラーの1stソロの一発目、ってコトで、こういう「景気付け」気分の時には結構聴きたくなる曲だ。From the Floorboards Upと双璧、ってコトかな。今回もあっちを聴こうかと思って急遽チェンジしたんだけど。 初期のライヴではWhat's Going Onと二枚看板のオープニング定番曲だった。だからブートでもライヴ音源が大量に残されてて、俺も7ヴァージョンくらい持ってるかな。でもスタジオヴァージョンが一番好き。 ライヴは勿論アレはアレでいいんだ。ライヴならではのドライヴ感があって、熱くてファンキーなロックナンバー、って感じは替え難い。今でも演ってくれないかな、って気はする(あ、ピルグリムクビにしてからね)んだけど。だけどね、俺はあのスタジオ版のアシッドジャズからの流れを強く感じるヴァージョンが好きなんだよ。 イントロのフランジングされたフィルから既にノックアウトなんだけど、とにかくこの曲はドラムとホーンだ。ホーンもね、ジャコ・ピークが生で吹くサックスとサンプリングのリフが組み合わさってるんだけど、これは両方入ってるが故の格好良さ、ってところがあって。ライヴでは全部ジャコが吹いてるんで、それだけでノリが変わってるんだ。 それにファンキーなベース、ブレンダン・リンチの名刺代わりのサウンド・エフェクト、そしてクールなヴォーカル。ソロでのポール・ウェラーって言う方向性が(IntoTomorrowと並んで)きっちり詰まってる曲だと思うな。 シングルにはAlways There To Fool Youっていう、この曲のダブっぽいヴァージョンが入っていてこれも格好いい。でも構成とか違うな、と思ってたら、先日出たデラックス・エディションで元々はデモ・ヴァージョン(タイトルもHot Rodになっている)のバッキングだと言うことが判明して驚き。
2010.01.02
コメント(0)
-
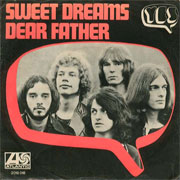
Dear Father
昨年は色々なことがあって、個人的には殆ど状況に振り回されっぱなしで終わってしまった感がある。辛いこともあったし楽しいこともあった。でも辛いことは全部それほど悪くない方向へ向かってるし、総じて良い年だったんじゃないかな。悩みまくったから心理状態は不安定だったけど。 辛いことの一つとして、春ごろにかけて父が大病を患った、と言うものがあった。正直、色々と覚悟もせざるを得ないような状況もあったけど、結果として今父は結構元気だ。体力は落ちてるようだけど、昨夜、夕食の席で09年を締めくくるに相応しい素晴らしく含蓄のある、力強い言葉が彼の口から出て、俺も妹もいたく感動したのでここに紹介したい。「俺はこの脂身が一番好きだ!」 だいたいこの糞親父は腎臓悪い、ってのにまあ塩まみれの鮭は買ってくるわ、ポテチはばりばりかっ喰らうわ、ケンタッキー3ピース平らげるわ、どうしてくれよう、って程の。まあ、好きなように長生きするがいいさ。尊敬するよ、悪い意味で。
2010.01.01
コメント(0)
全52件 (52件中 1-50件目)
-
-

- 楽器について♪
- 2025年冬のハープコンサートのお知ら…
- (2025-11-13 00:50:21)
-
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-
-
-

- 洋楽
- ブルース・スプリングスティーン 「…
- (2025-11-17 06:03:53)
-








