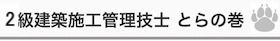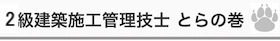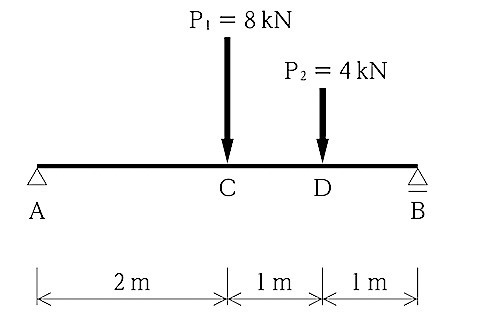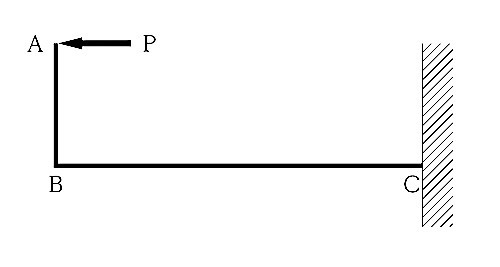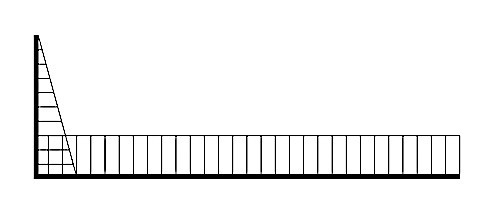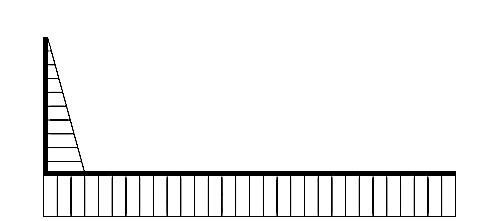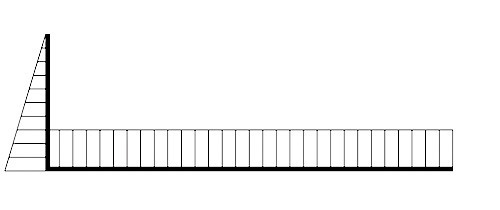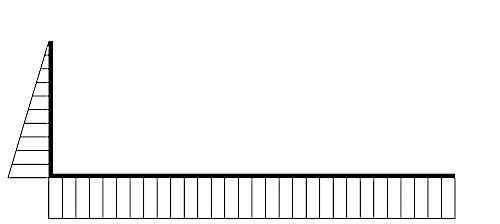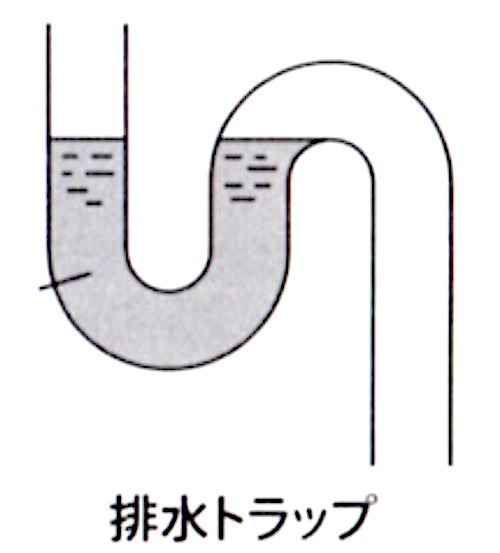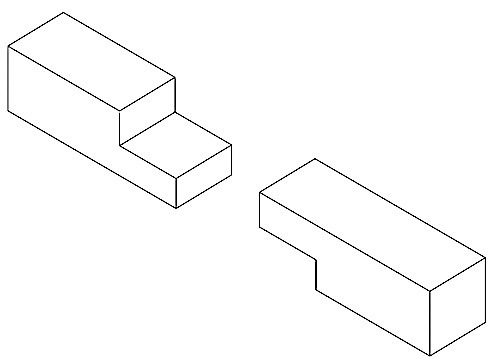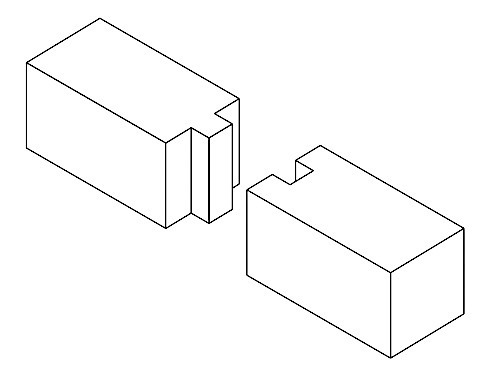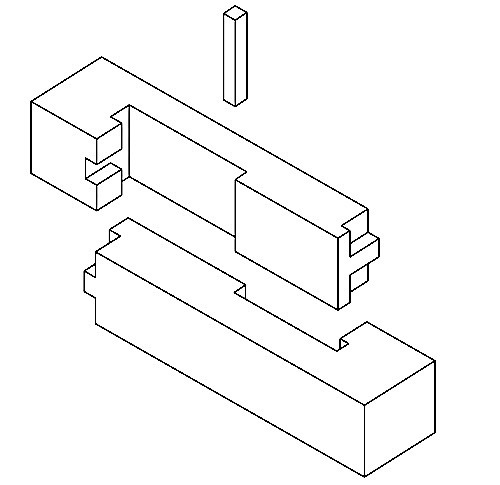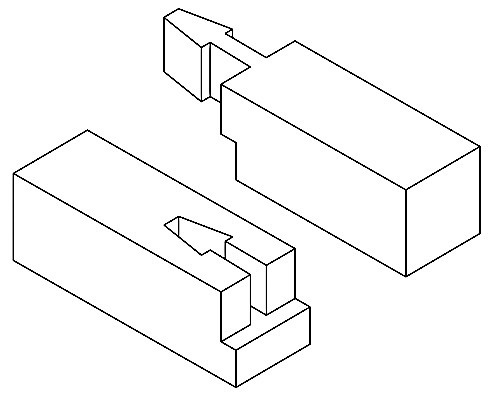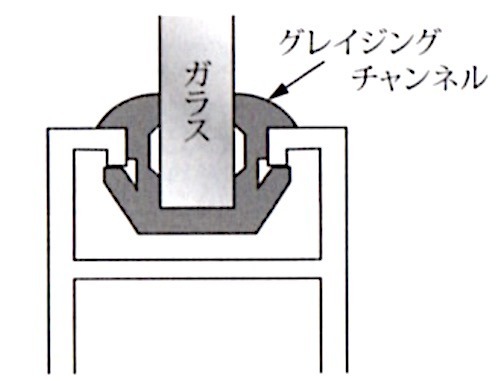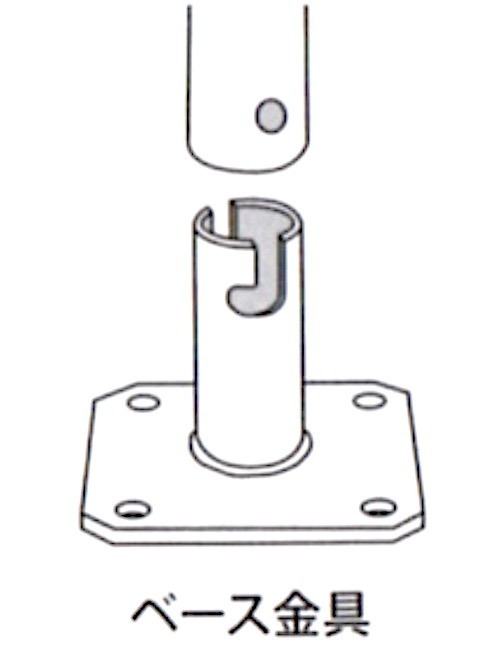2級建築施工管理技士 とらの巻
ながらくのご愛顧、ありがとうございました。
この度、ファンブログ様が平成7年4月22日をもちましてサービスを終了されるので、
つきまして、ブログの引越しを行いました。
★ 2級建築施工管理技士 とらの巻 ★
↑ ↑ ↑ こちら
新規登録のし直しをお願いします 。
まだ、内容は不十分で、見にくいところも多々あると思いますが、
今後、調整していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらのブログは 4/22 23:59 に削除されると思いますので、ご注意願います。
今後ともよろしくお願いいたします。
- no image
- no image
- no image
- no image