2015年10月の記事
全164件 (164件中 1-50件目)
-

分散した九条ネギ 起き上がりつつある 東日本大震災4年と7か月と20日後に
ねぎの根っこ12月31日 初の九条ねぎ 収穫をした 根っこも庭のブランターに植え付けをしておいた01月03日 2回目の収穫をしておいた 根っこは庭にて 植え付けをしておいた01月10日 3回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた01月17日 5回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた01月24日 6回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた02月01日 7回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた庭にブランター 6個に ネギのねっこ 植え付けをしている これで もうすこし大きくなったら 畑に移動する予定あと 3-4個 追加していく予定なり ネギは根っこから 育てていこう03月01日 ネギの根っこ まあまあ 生育してきている 03月12日 ネギの坊主のちいさいのがついてきている03月22日 かなり生育してきている そろそろ 畑に移動させよう03月29日 M-08の畑の畝に移動してうえつけをしておいた04月04日 その後も ネギさん 根っこも 元気そうだ 無事なり04月12日 ネギのねっこ ネギ坊主が でているので 全部をカットしておいた04月19日 ネギのねっこ その後もネギ坊主をカットしている04月26日 その後も 様子見をしている 05月26日 その後も まあまあ 無事なり06月20日 数はそのまま あまり 大きくはなっていないが 無事なり07月04日 ヤマノイモの日陰になっているが ちいさいが 数は無事にそだっている07月11日 2月からのねぎの根っこ 無事にそだっている まあまあかな九条ネギの在庫 m-08 10本 ネギの根っこ 60本 m-06 20本 m-07 20本 g-01 10本 g-03 20本 合計 140本くらいは まだある ネギ坊主をカットして そのままブンケツさせていこう06月20日 在庫のネギさん ネギ坊主が まだまだ 出てきている06月27日 在庫のネギさん ネギ坊主も まだまだ 出てきている でも 新しいブンケツのネギさんも そろそろ 出てきている07月04日 まだ ネギ坊主でできている07月11日 そろそろ 止まりでしている 青々としているのと 枯れているのが半々くらいになっている ネギ坊主をカット カット カット しているので ネギさんも あきらめて ブンケツしてみようかなと 考えているようだ残っている九条ねぎ 無事に生き残っている07月20日 九条ねぎ 大量にのこっている 新しい畝に分散させて植えなおしをあとでやろう07月21日 根っこの分のネギは ちいさいので そのまま 大きいのは植えなおそう08月01日 九条ねぎ 残っているのも 8月になって 元気になってきている09月05日 g-3の九条ネギ 9月になって この状態なり まあ 順調なり09月12日 m-07の九条ネギ これも元気になってきている09月23日 m-07の九条ねぎ 元気なり10月04日 m-07の九条ネギ 追肥をしておいた 九条ネギの在庫 m-08 10本 m-06 20本 m-07 20本 g-01 10本 g-03 20本 合計 80本くらい まあ たくさんある10月11日 m-06/07の在庫のネギ バラバラにして 分散して植えなおしておいた10月18日 m-07の在庫のネギにもみがらをかけておいた10月25日 分散したネギ すこしづつ 起き上がりつつある 追肥をしておいた みずやりをしておいた在庫のねきの土 カチカチになっていた土を耕して ネギさん ばらばらにして 植えなおしたが しばらく元気になるまで時間がかかりそう東日本1震災 3月11日発生10月31日は既に4年と7か月と20日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------ここなっつ オイルは 安全かこのブログで取り上げているのは 健康な人に 限定しています日本食としうのは 魚 煮物 おひたし 香の物などで 魚の油以外はほとんどとらないヨーロッパや中国は牛やブロの油を食べ 植物油も使う植物油が危険なのは その成分そのものの時(飽和と炭素数)と少量の毒物を含むときがあるラットなどの実験データは 基礎的なもので 人間とは同一ではないヨーロッパのデータは 参考にはなるが 日本人とは違う私たちの食生活になじみのないものは注意ビジネスと健康がつながっている場合が多い武田の調査では 日本人とココナッツオイルのデータは不足しているふむふむはた坊
2015.10.31
コメント(2)
-

らっきょう 眺めも良い 順調なり オリーブ おべんきょうその01
昨年hcでの売り物が出ていたので かっておいた植え付けは9月から09月07日 らっきょう m-08の畑の畝に植え付けた09月14日 発芽はまだ 2週間くらいしてから 発芽してくる見込み09月21日 やっと 発芽してきている 09月28日 いつも 花の蕾みたいのが 出てきている もうすぐ 花が咲くようだな10月29日 花が咲いてきている11月08日 その後 生育して大きくなってきている11月30日 雑草とりをした らっきょうらしくなってきている12月13日 追肥をしておいた 12月23日 雑草がまた 増えてきている01月03日 その後も らっきょう 元気なり01月24日 まあまあ 元気である01月08日 それなりに 元気なり 雑草もすくないな02月15日 そろそろ 雑草とりもしないとねえ03月01日 やっと 雑草取りをしておいた03月08日 春らしくなり 生育が始まってきている03月14日 らっきょう いい感じになってきている03月22日 らっきょう 雑草もなくなって すっきり04月04日 らっきょう まあまあ 生育している 良し04月12日 らっきょう 青々としてきている06月06日 らっきょう 収穫をした らっきょう 今年の根っこは かなり大きくなっている今年また hcでのらっきょう 買ってきている08月29日 hcで らっきょう 買ってきた08月30日 m-07の畑で 植え付けをしておいた09月12日 発芽している09月19日 花つぼみ 大きくなってきつつある09月22日 葉もつづけて でてきている09月27日 花つぼみ まだ 花は咲いていない 10月04日 葉も伸びてきている らっきょうの花 咲くのは10月の下旬なので まだ2週間ぐらい 後となる10月10日 花らしくなってきている 色はまだうすい 10月18日 花の色 すこしついてきている 開花も近いなあ10月25日 花が開花した 下の分が開花してきている10月28日 らっきょう 眺めも良くなっている まあまあだなあオリーブ おべんきょうその01Olea europaea subsp europaeaOliveTree.jpg オリーブの樹 分類界 : 植物界 Plantae 門 : 被子植物門 Magnoliophyta 綱 : 双子葉植物綱 Magnoliopsida 目 : シソ目 Lamiales 科 : モクセイ科 Oleaceae 属 : オリーブ属 Olea 種 : オリーブ O. europaea 学名 Olea europaea 和名 オリーブ 英名 Olive オリーブ(橄欖、英: Olive、学名:Olea europaea)モクセイ科の常緑高木。果実がオリーブ・オイルやピクルスを作るときに利用されている。種子の油は、オリーブ核油 olive kernel oil といい、オリーブ油よりも品質が劣る。はた坊
2015.10.31
コメント(0)
-

にんにく その後の生育は良い マルチの方が良いようだな おうむ おべんきょうその15
昨年hcでの種をうっていたので 購入した08月09日 芽にんにく 500gのもの 中国産かな ??? 08月17日 宮崎のニンニクが売っていない で 博多のニンニクを買っておいた9月になったら 植え付けをしよう09月07日 にんにく m-08の畑の畝に植え付けた09月14日 発芽はまだ 2週間くらいしてから 発芽してくる見込み09月21日 やっと 発芽してきている 芽にんにくは発芽した 博多のニンニクはまだ10月05日 やっと 博多のニンニクも 発芽してきている これで ニンニクの発芽は okとなった10月18日 芽ニンニクの畝の雑草とりをしておいた 10月19日 こちらの博多のにんにく 草取りをしておいた 11月16日 その後 芽ニンニクは元気になっている11月16日 その後 博多のニンニクもそれなりに 数はすくないが 育っている11月16日 芽ニンニク これは良く育っている 42本ある11月22日 博多のニンニクも元気なり 14本ある 合計であわせて56本なり12月06日 芽ニンニク 雑草とりしたので見栄えもよくなってきている12月13日 雨の前なので 鶏糞をばらまいておいた これで 良し 雨がふれば 効くぞーーーー12月23日 その後も 芽にんにくは 元気なり01月03日 博多のニンニク これは 数がすくないが それなりに生育している 良し01月18日 雑草がまた ふえてきているなあ あとで 雑草とりをしておこう02月01日 その後も まあまあ 元気なり02月08日 雑草とり まだ やっていないなあ あとでやろう02月22日 芽にんにく かなり 大きくなってきているぞ03月01日 芽にんにく 雑草取りをしておいた すっきりとした03月01日 博多のにんにく 数は10本くらいしかない 雑草とりして すっきり03月08日 芽ニンニク これも 雑草とりしてみると 大きくなってきている03月14日 博多のニンニク まあまあ 大きくなってきている03月15日 芽にんにく 元気になっている イキイキとしているなあ03月22日 芽にんにく かなり 大きくなってきている03月23日 博多のニンニク 数えてみると 15本ある まあまあかな04月04日 博多のにんにく これも 大きくなってきつつある04月05日 芽にんにく これも成長してきている 50本はある04月12日 博多のにんにく まあまあ なり04月19日 芽にんにく その後も 元気なり05月02日 芽にんにく トウができてきている05月03日 芽ニンニクのトウ 一回目の収穫をしておいた05月06日 芽ニンニクのトウ 2回目の収穫をしておいた05月17日 その後も 肥大してきている感じ05月17日 芽にんにくのトウ 3回目の収穫をしておいた05月24日 博多のニンニク 収穫をしておいた05月30日 芽にんにくのトウ 4回目の収穫をしておいた05月31日 芽ニンニク 収穫をした これにて 終了なり ニンニク 博多が15本と芽ニンニクは50本 合計65本 今年 hcでのニンニクの種をみてきて ついでに 買ってきて植え付けた08月29日 にんにくの種1kgをかってきて ついでに m-07の畑に植え付けた09月12日 発芽してきてような感じだけど まだまだ 3週間すくらいはかかりそう09月20日 1つだけ 発芽 残りはまだだなあ09月21日 追肥をしておいた 鶏糞をかけておいた これで びっくりして発芽するだろう10月04日 やっと46本くらいが 発芽してきている まだ 半分だな10月10日 にんにく 88本くらいに発芽したのが増えてきている10月25日 にんにく 発芽するのは土が早いが 成長はその後はマルチが早いなあ半分はマルチに植えて 半分は 土の畝に植えている これで 差はつくかな ???マルチは差がどれだけつくか 様子をみておこうおうむ おべんきょうその15形態学テリクロオウム インコの強靭な嘴、鉤爪のある脚そして側面を向いた目が見られるインコは時に"hookbill"(鉤状の嘴)と呼ばれることがある。これは彼らの最も顕著な身体的特徴、すなわち強力な湾曲した幅の広い嘴のことをさしている。上側の嘴は張り出しており、下向きにカーブし、先がとがっている。この嘴は頭骨とは癒合しておらず、これにより嘴を独立して動かすことができ、このことがこれらの鳥が噛む際に発揮することのできる驚異的な圧力に貢献している。下側の嘴は短く、上向きの鋭い先端をもっている。これが上嘴の平坦な部分に対して、鉄床に対するハンマーのような動きをする。種子を食べるインコは強靭な舌をもっており、これが嘴の中で種子を扱ったり、ナッツの位置決めを助けたりする。これによって嘴は殻を割るために適切な力を加えることができる。頭は大きく目は横向きについている。これは双眼視による展望を制限するが、周辺視野を大いに強化する。彼らは直立した姿勢で、強力な脚と鉤爪をもった趾(あしゆび)をしており、二つの趾は前方を向き、二つの趾が後方を向いている(対趾足)。オウムはその頭頂部に可動する羽根でできた冠(冠羽)をもっており、ディスプレイのために起立させたり、畳んだりすることができる。はた坊
2015.10.31
コメント(0)
-

にら まだまだ 元気である 大豆 おべんきようその11
にらまたまだ 元気である昨年は12月15日まで 収穫をしているということで11月と12月 まだ 収穫できるにらまだ これから これからどんどん 収穫していこう昨年もニラさん 元気だった3月に 2回 4月も 3回 5月も 3回 6月も 2回の収穫をした 7月も 4回 8月も 4回 9月も 6回 10月 4回 11月5回 12月2回のの収穫をした大豆 おべんきょうその11大豆油ダイズから得られる大豆油は、パーム油に次ぐ代表的な食用油であり、大豆需要の87%を占めている。主要な生産国は、中国、アメリカ、ブラジル、アルゼンチンで、上位5カ国で8割を占める。日本では菜種油が好まれるため、大豆油の生産量は40万トン前後と菜種油の半分以下に留まる。 近年では環境配慮型の素材とされる大豆インキの原料としての需要も拡大している。残渣の油粕は醤油の原料や家畜の飼料、大豆ミートとして粗タンパク質源に利用されていたが、最近は『ヘルシー』を売りにした小麦粉代替食品としても拡販が進んでいる。はた坊
2015.10.31
コメント(0)
-

かぶら もう かなり大きくなっている 収穫もまじかに 東日本大震災4年と7か月と19日後に
昨年のかぶらhcでの カブラの種をかってきた いつもとおりの 聖護院のかぶら9月より 種まきする予定08月31日 庭で種まきをした09月04日 発芽してきている09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた第二弾の種まき09月07日 庭でまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-09などに植え付けわしておいた第三弾の種まき09月15日 庭で種まきわしておいた09月18日 発芽した09月20日 畑に移動した m-07などに植え付けた弾四弾の種まき09月21日 庭での種まき また やっておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した10月12日 かぶら 第一弾のもの かなり 大きくなってきている10月19日 その後も かぶら 大きいものはおおきくなっている カブラもみえてきている10月26日 その後 かぶら 大きいのが出てきている 収穫できそうだなあ収穫できるのは 来月くらいかな まあまあ 順調なり11月02日 初のかぶら 収穫をした 2個11月09日 2回目の収穫をした 2個11月16日 3回目の収穫をした 4個11月17日 4回目の収穫をした 2個11月22日 5回目の収穫をした 2個11月29日 6回目の収穫をした 4個12月06日 7回目の収穫をした 3個12月13日 8回目の収穫をした 3個12月23日 9回目の収穫をした 4個12月31日 10回目の収穫をした 3個01月03日 11回目の収穫をした 3個01月10日 12回目の収穫をした 4個01月12日 13回目の収穫をした 2個01月18日 14回目の収穫をした 3個01月24日 15回目の収穫をした 3個02月01日 16回目の収穫をした 4個02月08日 17回目の収穫をした 8個02月15日 18回目の収穫をした 4個02月22日 19回目の収穫をした 4個02月28日 20回目の収穫をした 4個これで かぶら 御終いに今年また 聖護院蕪の種 買ってきた08月29日 hcで種を買ってきて08月30日 庭で 種まきをしておいた09月03日 発芽してきている09月05日 畑に移動した g-3/g-1の畑の畝に植え付けた09月12日 その後 無事なり 雨がよく降ったので 育っている09月19日 g-1の畝の蕪 まあまあ元気に育っている09月27日 g-1の畝のかぶら その後も順調なり10月04日 g-3の畝のかぶら 元気なり10月18日 g-3の畝のかぶら かなり大きくなってきている10月25日 ねっこも だいぶ 大きくなってきている もう 収穫してもよさそうになっているかな東日本1震災 3月11日発生10月30日は既に4年と7か月と19日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------「バックツーザフューチャー」考(1) 科学と未来予測 「バックツーザフューチャー」という映画が30年ほど前にはやって、それがちょうど2015年の状態を予想しているというのでにわかにテレビの話題になった。日本のテレビは横並びが原則だから、NHKをはじめとして各局が同じ内容を流していた。ニュースなら各局が同じ事件を流すのは良いが、このような茶の間の話題のようなものも各局の横並びというのは考えさせられる。この話題を多方面から考えてみたい。第一に、「科学と予測」という問題、つまり「未来を描く」ということが科学でも政治でも可能かという問題だ。未来を予測するというのは、「現在の自分の頭の中にあるもの以外は 未来に起こりえない」と仮定することだが、そうすると、まずノーベル賞は生まれない、これまでの人間の発達の歴史を無視しなければならない、さらには多くの予測の間違いの理由が分からなくなるなどのことが起こる。人間が未来を見たいという欲求を持っていることはわかるし、あるときにはそれは恐れであり、あるときは希望だが、事実とは違うと言う点で大きな損害になることをよく知っておく必要があるだろう。またテレビ放送などでは、よく「選挙に行きなさい」や最近の「避難をしてください」という上から目線が見られるが、それよりこのような時に「未来は予測できない」ということを全面に出した方が良いとおもう。(平成27年10月27日)ふむふむnetをみると正確には2045年に人類全てが考えた事よりもコンピューターの方が凄いことできるんで、人では予想できない と書かれていたはた坊
2015.10.30
コメント(0)
-

家庭菜園するにも バイクと自転車は必需品 それと スコップも 茶 おべんきょうその42
家庭菜園用のバイク家から2kmの場所であるのでバイクで往復しても4kmだけで 2か月と半で やって112kmくらいであるガソリンもまだ 1回だけ まだまだ走れるこの調子でいけば 3回月で120kmくらいで ガソリン代も500円くらい1年で480km ガソリン代金も 2000円くらいかな土曜はバイクで家庭菜園にいって 肥料や土の購入や収穫物を運搬している 荷物は100kgくらいまで運べる日曜は 自転車で家庭菜園にいっている 水やりして耕作と雑草とりなどをしている2km離れている家庭菜園 バイクでは5分でつく 通勤前でもバイクで10分で往復できる 帰宅後もバイクだと簡単にいける自転車では10分くらい 時間のゆとりがある日曜に使用している2kmは近いようで遠い 往復で4kmなので一時間かかる歩いてはいけない距離なので 家庭菜園するにも バイクと自転車は必需品茶 おべんきょうその42茶の音楽邦楽『宇治巡り』(地歌・箏曲) 文化文政の頃、京都で活躍した盲人音楽家・松浦検校が作曲した手事(てごと)もの地歌曲。箏の手付は八重崎検校。「喜撰」「雁が音」など、多数の茶の銘を詠み込み四季の順に配列しつつ、春夏秋冬の茶の名産地宇治を巡り歩くという風流な趣向の曲。大曲で二箇所の手事(楽器だけで奏される器楽間奏部)も音楽的に凝ったもので、転調も頻繁に現れ、技術的にもなかなか難しい曲。「松浦の四つ物(四大名曲)」のひとつとされている。『茶音頭』(地歌・箏曲) 文化文政時代、京都で活躍した盲人音楽家・菊岡検校が作曲、八重崎検校が箏の手付をした手事もの地歌曲。俳人横井也有の「女手前」から抜粋した歌詞で、多数の茶道具を詠み込みつつ男女の仲がいつまでも続くよう願った内容。三味線の調弦が「六下り」という非常に特殊なもので、独特な響きがこの曲独自の雰囲気を作り出しており、歌の節も凝っている一方で手事が長く、八重崎検校の箏手付も巧みで合奏音楽としてもよくできているので、現代でも演奏会でよく採り上げられる曲である。「音頭」という語が付いているが、民謡ではなく、れっきとした芸術音楽。お点前の伴奏として演奏されることもある。『宇治茶』(上方歌・端唄・うた沢)『茶摘み』(文部省唱歌・作詞作曲者不詳)『ちゃっきり節』(新民謡。静岡県の民謡。作詞:北原白秋、作曲:町田嘉章)クラシック音楽チャイコフスキー :バレエ音楽「くるみ割り人形」より、お茶(中国の踊り)。レハール :オペレッタ「微笑みの国」より、二重唱曲「お茶を飲みつつ語らえば」。ショスタコーヴィチ :タヒチ・トロット(「二人でお茶を」という流行歌の編曲)。その他、茶製造に関する労働歌、民謡として「茶摘み歌」「茶揉み歌」などが各地にある。またこれらに、茶に関する童謡や歌謡曲を含めて「茶歌」と言われることがある。はた坊
2015.10.30
コメント(0)
-

らっきょうの花 開花したあ おうむ おべんきょうその14
昨年hcでの売り物が出ていたので かっておいた植え付けは9月から09月07日 らっきょう m-08の畑の畝に植え付けた09月14日 発芽はまだ 2週間くらいしてから 発芽してくる見込み09月21日 やっと 発芽してきている 09月28日 いつも 花の蕾みたいのが 出てきている もうすぐ 花が咲くようだな10月29日 花が咲いてきている11月08日 その後 生育して大きくなってきている11月30日 雑草とりをした らっきょうらしくなってきている12月13日 追肥をしておいた 12月23日 雑草がまた 増えてきている01月03日 その後も らっきょう 元気なり01月24日 まあまあ 元気である01月08日 それなりに 元気なり 雑草もすくないな02月15日 そろそろ 雑草とりもしないとねえ03月01日 やっと 雑草取りをしておいた03月08日 春らしくなり 生育が始まってきている03月14日 らっきょう いい感じになってきている03月22日 らっきょう 雑草もなくなって すっきり04月04日 らっきょう まあまあ 生育している 良し04月12日 らっきょう 青々としてきている06月06日 らっきょう 収穫をした らっきょう 今年の根っこは かなり大きくなっている今年また hcでのらっきょう 買ってきている08月29日 hcで らっきょう 買ってきた08月30日 m-07の畑で 植え付けをしておいた09月12日 発芽している09月19日 花つぼみ 大きくなってきつつある09月22日 葉もつづけて でてきている09月27日 花つぼみ まだ 花は咲いていない 10月04日 葉も伸びてきている らっきょうの花 咲くのは10月の下旬なので まだ2週間ぐらい 後となる10月10日 花らしくなってきている 色はまだうすい 10月18日 花の色 すこしついてきている 開花も近いなあ10月25日 花が開花した 下の分が開花してきているおうむ おべんきょうその14生息範囲と分布ほとんどのインコは熱帯に分布するが、コイミドリインコのように温帯に深く進出している種もいくつかあるインコはオーストラリアや太平洋の島嶼、インド、東南アジア、北アメリカの南部地域、南アメリカおよびアフリカを含むすべての熱帯および亜熱帯の大陸で見ることができる。一部のカリブ海と太平洋の島々には固有種が存在する。圧倒的多数のインコの種がオーストラレーシアと南アメリカに由来する。複数の種類のインコが南アメリカとニュージーランドの冷涼な温帯地方に進出している一種類、カロライナインコが北アメリカの温帯に生息していたが20世紀の初期に狩り尽くされて絶滅した。数多くの種が温暖な気候の地域に移入されて安定個体群を確立している。オキナインコ(Monk Parakeet)は現在では合衆国の15の州で繁殖している。いくつかのインコの種はまったくの定着性であったり、また完全な渡り鳥であったりするが、大多数はその二つの間のどこかに落ち着いて、十分には解明されていない地域間の移動を行ったり、また種類によっては完全に非定着な生活様式を採用したりしている。はた坊
2015.10.29
コメント(0)
-

隣の畑のにら もう 枯れてしまっている 大豆 おべんきょうその10
隣の畑のにら花芽が伸びて 種もできて 種も半分くらい落ちてしまっているで韮も枯れてしまっている放置していると こうなっているはた坊のは 花芽をカットしているので まだまだ青々としているやはり 野菜の花は咲かしてしまうと枯れてしまう花をカットしていると いつまでも 若々しいこれ 植物も 動物もおなじなのかな人間も 老化するとだめ気を若くしていると いつも 元気になるいつでも 若い 若いいつでも 元気 元気これが 一番なり いつまでも 若い 元気でいるのが一番だなあ大豆 おべんきょうその10生薬蒸した黒豆(黒大豆)を発酵させてから乾燥させたものは、香豉(こうし、別名:豆豉(ずし))という生薬であり[25][26]、陶弘景校定による『名医別録』には「豉」として収載されている[25]。香豉には発汗作用、健胃作用があるとされ、香豉を含有する漢方薬には梔子豉湯、瓜蔕散などがある[25][26]。本来、黒豆の発酵・乾燥品を用いるが、現在では納豆を乾燥させたものを代用する[26]。はた坊
2015.10.29
コメント(0)
-

にら 27回目の収穫をしておいた 東日本大震災4年と7か月と18日後に
在庫 m-08 たくさんあるg-01 4つ 植えている そのた 種からのにらが生えている庭 結構と生えている韮 たくさんあるので 今年も 収穫する分は たくさんある在庫だけで 今年も たくさん 収穫できる楽しみだあーーーーーーーーーーあ01月12日 にら 冬なので 半分は枯れているが まあ こんなもの02月14日 にら 庭のにら 青々としている まあ 元気なもの02月14日 にら 畑のは枯れているが 風があたらない場所のは 青々としている02月22日 にら ブラの横のは 収穫できそうだなあ03月01日 にら 庭のにらは 青々としている 新しい葉も出てきている03月01日 にら 畑のも すこし 新芽も出てきそうな感じになりつつある03月22日 にら 庭のは もう 大きくなっている04月12日 にら 庭のも 大きくなっている 収穫はokである にら 風があたると枯れるが 風があたらない場所では 青々としている気候では 風は 馬鹿にならない 結構と影響をあたえているものだなあ1月と2月と3月は 収穫はなし03月08日 畑のにら そろそろ 新芽もすこし03月15日 畑のにら 新芽になりつつある03月22日 畑のにら 雑草を取り除いておいた 結構とあるものだなあ初のにらの収穫も そろそろ できそうになってきている03月29日 G-01のにら これも 成長してきている03月29日 M-08のにら 若々しくなってきている04月12日 g-01/m-08ともに 収穫できる もう 大きくなっている04月19日 g-01のにら もう 大きくなっている 04月26日 m-08のにら もう 収穫できる にら 今週より 収穫を開始しよう04月29日 今年も韮の収穫を開始 1回目の収穫をした05月06日 にら 2回目の収穫をした05月10日 にら あちこちに 若い韮が どんどん 増えてきている05月10日 にら 3回目の収穫をした05月16日 にら m-08のにら 十分に大きくなっている 雑草とりをして追肥しておいた05月23日 にら 4回目の収穫をした05月30日 にら 5回目の収穫をした06月06日 にら 6回目の収穫をした06月13日 にら 7回目の収穫をした06月14日 にら 8回目の収穫をした06月20日 にら 9回目の収穫をした06月27日 にら 10回目の収穫をした07月04日 にら 11回目の収穫をした07月11日 にら 12回目の収穫をした07月12日 にら g-01の韮は 元気になっている07月18日 にら m-08のにらに 花蕾がついてきている カットしておく07月19日 にら m-08のにら 雑草とりして 花蕾もカットして 追肥もしておいた07月20日 にら 13回目の収穫をした07月26日 にら 14回目の収穫をした08月01日 にら 15回目の収穫をした08月02日 にら m-08のにら しっかりとしてきている08月08日 にら 16回目の収穫をした08月15日 にら 17回目の収穫をした08月22日 にら 追肥をしておいた サトイモの日陰になっているが まあまあ良く育っている08月23日 にら 18回目の収穫しておいた08月29日 にら 19回目の収穫をしておいた09月05日 にら 20回目の収穫をしておいた09月12日 にら 21回目の収穫をしておいた09月20日 にら g-01のにら まだまだ 収穫はできる たくさんある09月20日 にら 22回目の収穫をしておいた09月27日 にら 23回目の収穫をしておいた10月03日 にら 24回目の収穫をしておいた10月04日 g-1のにら まあまあ 元気である10月10日 にら 25回目の収穫をしておいた10月18日 にら 26回目の収穫をしておいた10月25日 にら 27回目の収穫をしておいた畑で一番に元気なのは にら である東日本1震災 3月11日発生10月29日は既に4年と7か月と18日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------不適切な新聞用語 「放射線防護服」と「子会社、下請け、契約社員」 不適切な新聞用語 「放射線防護服」と「子会社、下請け、契約社員」「放射線防護服」は放射線を防護しない。でも、東電が言ったから新聞もテレビもそのまま使う。東芝の会計の違反は「不適正会計」ではなく「粉飾決算」であった。それも専門家の判定ではたちの悪い粉飾決算とされている。欠陥マンションは「子会社が、3次下請けで、契約社員」が行ったというのは正しく言えば、「大会社が、契約して、社員」が担当した。でも、会社が言ったので、そのまま報道する。新聞用語は正しく使わなければならない。しかし、相手が個人なら「糾弾するためにきびしい用語」を使うマスコミも、相手が東電とか東芝のような大会社になると「会社が使った用語」をそのまま使う。悪いことをした会社がなんとか表面でも取り繕おうとするのは人間の性であるが、新聞やテレビは読者や視聴者に向いている必要がある。(平成27年10月25日)ふむふむはた坊
2015.10.29
コメント(0)
-

ほしねぎ vs 在庫のネギ 判定はまだ 先だなあ 茶 おべんきょうその41
ほしねぎhcで 売っていたので 1つ 買ってきている08月23日 hcで1つ 買ってきて 畑に植え付けをしておいた これで 在庫のネギさんと ホシネギさんの成長に どれくらいの差があるか実験してみよう在庫のネギも ばらばらにして うえつけてみて比較して 様子をみていこう ほしねぎさん どれくらい効果があるか どうか調べてみよう9月05日 植えたホシネギ 発芽しているが まだ 横の九条ネギよりは ちいさいな9月12日 ホシネギ 横のネギくらいになってきている 生育は良いな9月22日 ホシネギ 横のネギより 大きくなっている さすが ホシネギさんだなあ もう しばらく 様子見をしておこう10月04日 ホシネギ 頑張っていたが 在庫の九条ネギが 成長を始めている で どちらが大きいかというと 在庫の方が大きくなってきている ほしねぎと 在庫の九条ねぎ最初は ホシネギが大きかっただ いまでは 在庫のネギが大きくなっている今回は在庫のネギが大きくなったので ほしねぎのほうが 良いともいえないみたい だな ????10月12日 ホシネギはそのまま 在庫の九条ネギ 分散しておいた今 見てみると ホシネギ 頑張っている在庫の九条ネギ 分散させておいた これから 成長するかどうかなで ホシネギ 在庫ねぎ バトルは延長戦となった しばらく 様子をみておこう10月25日 ただいま ホシネギが大きくなっている 分散した在庫ねネギは横になっているまだまだ わからないさて もうしばらく 待ってみよう茶 おべんきょうその41パッケージングティーバッグ1907年に、アメリカのお茶商トーマス・サリヴァンは、絹の小さなバッグの中にお茶を入れ、配布したのが始まり。 再利用することができる点が便利である。はた坊
2015.10.29
コメント(0)
-

たんぽぽの綿毛 どこまで飛ぶか 答え 判らない おうむ おべんきょうその13
たんぽぽの綿毛タンポポの綿毛の飛行距離は どれくらいかnetで 調べたみたこたえ回答は、わからないというのが正確でしょう。綿毛(たね)が飛ぶ距離を正確に測った人はいないでしょう。 種類による違いを、一定の高さのガラス管の中を落ちる綿毛の時間の比較で表すことは行われています。その差は数倍といったものではなく、1.3倍とかの違いです。その飛行距離は、風(気流)次第なので、予測できません。綿毛の落下時間の差は、この予測できない気流に乗る可能性の違いと思ってください。滞空時間が長いほど、風に乗るチャンスが多いということです。たねを含めた綿毛は、風に飛ぶ形をしていますので、上昇気流に乗れば、かなり遠くに飛ぶと考えることができます。しかし、セイヨウタンポポが綿毛をヨーロッパから日本まで飛ばしたということはなかったようです。山奥にも外来種のセイヨウタンポポが生育していることがあるので、もっとも近い生育地まで数キロメートル あるだろうと見られます。もっとも、人や動物の体について移動したとの可能性を否定はできません。また、山奥で見つけたというのも、結果であって、過去に途中の地点まで来ていた時期があったかもしれません。もちろん氷河を避けてもっと長距離を移動したと推測される種類もありますが、それは1年や5年ではない、長い時間をかけて少しずつ移動したのでしょう。一つ一つの綿毛が同じ距離を飛ぶこともほとんどあり得ないので、平均値を求めるのは、さらに難しい質問です。一つ一つの綿毛の飛ぶ距離がわからなければ、平均値は出せません。ちなみに最小値は親の直下に落ちた、飛行距離0mの綿毛です。広い室内で扇風機の前に綿毛を置いたとき、10m以上移動したのを 見たことがありますが、これも野外の風とは異なる条件でしょう。というわけで、お問い合わせに対して、数値での解答はできません。 小川 潔(東京学芸大学)まあ こんなことを調べる人はいないということらしいおうむ おべんきょうその13分類和名Psittaciformes の和名は一定しておらず、「オウム目」と「インコ目」が使用されている。ただし最近では鳥類学術関連でもペット関連でもオウム目の方を使われる例が多い。インターネット上でも検索するとオウム目がはるかに浸透していることが分かる。また国語辞典でも、例えば広辞苑は第4版まではインコ目だったが第6版ではオウム目を説明記述に使用している。また、系統学の項に述べられているような差異を重視して2科に分ける場合は、主に小型の種からなるインコ科(Psittacidae)、大型の種からなるオウム科(Cacatuidae) と2つの科に分ける。複数の科からなるという説では、さらにヒオウム科(ヒインコ科:Loriidae) を立てる。しかしこれらの差異を同じ科内での変異として考える説ではPsittacidae 1科とされ、Sibley分類でもその立場を取っている。この場合もPsittacidae の和名は一定しておらず、「オウム科」と「インコ科」とがある。このグループを1目1科の Psittaciformes - Psittacidae とする場合も、この分類和名には、「オウム目オウム科」あるいは「インコ目インコ科」と表記される他に「インコ目オウム科」や「オウム目インコ科」などと交差した用例まである。このようにオウム類の分類和名には現状やや混乱があるが、何れも同じ分類対象をさしていることに注意すること。はた坊
2015.10.29
コメント(0)
-

ブロッコリーの葉に 水が ころころと 朝には湿度が高いので水がたまる 大豆 おべんきょうその09
ブロッコリーの葉朝には 葉に水摘がついている葉の上に水がたまるくらいある朝露だなあ朝の湿度が高いと水滴が 葉に どんどんついてくる雑草の葉などにも水滴がついているので歩くと水が落ちてくる雨が降らなくても 水やりしているみたいなものnetで湿度について 調べてみた相対湿度 : 空気中の水蒸気の分量の、同温で飽和している空気が含む水蒸気量に対する割合を相対湿度という。一般に、単に湿度といえば相対湿度のことを指す。これは水蒸気圧で考えても同じなので、通常は空気中の蒸気圧の、同温の飽和蒸気圧に対する比を、百分率 (%)で表わす。空気中の水蒸気量( 圧)が同じでも、気温が高くなると飽和水蒸気量 (圧)が高くなるので、相対湿度は下がる。露点 : 水蒸気を含んでいる大気を冷やしていくと、いつかは必ず飽和する。このときの温度を、露点 (または露点温度)という。湿球が凍っている場合など氷に対して求めた飽和する温度は、霜点または霜点温度ともいう。 ℃(摂氏)を用い、 0.1℃ を最小単位とする。露点が高いほど含まれている水蒸気量が多く、気温と露点の差(露点差または湿数) が大きいほど相対湿度が小さい湿度計の設置場所や環境条件は、前節の気温観測の場合とほぼ同じである。とくに、建物の冷暖房のための排気口や自動車の排気ガスなどの影響を受けにくい場所で観測するよう配慮する必要がある。低温、低湿時における湿度を精度よく測定することは、長い間の懸案であった。観測時刻には乾湿計 (1950 年から通風乾湿計)が、自記記録用には毛髪湿度計が古くから用いられていたが、電気信号を出せる湿度計として塩化リチウム露点計が、 1961 年から航空気象観測で、また 1971 年から地上気象観測で使用されるようになった。 1996 年からは静電容量型の電気式湿度計が順次導入されている。日平均湿度のほか日最小湿度も求めている。これは明け方気温が下がると湿度が 100 % 近くになることは珍しくないので、日最大湿度というものにはあまり意味がないが、一方日中どこまで湿度が下がるかはその日の気象状態を反映しており、また乾燥は火災に結びつくので監視する必要があるためである。都市化に伴って乾燥化が進むといわれている。湿度の統計例として東京における年平均湿度の経年変化を図に示す。年 湿度1880 781900 751920 751940 701960 651980 632000 57大豆 おべんきょうその09食用ダイズの栄養価の代表値 日本では色々な形に加工され、利用されている。まず、大豆を暗所で発芽させるとモヤシ、未熟大豆を枝ごと収穫し茹でると枝豆、さらに育てて完熟したら大豆となる。大豆を搾ると大豆油、油を絞った粕は大豆粕として食用・醤油製造や飼料へ、煎って粉にするときな粉、蒸した大豆を麹菌と耐塩性酵母で発酵させると醬油・味噌、また蒸した大豆を納豆菌で発酵させると納豆となる。熟した大豆を加水・浸漬・破砕・加熱したものを搾ると液体は豆乳、その残りはおから、豆乳を温めてラムスデン現象によって液面に形成される膜を湯葉、にがりを入れて塩析でタンパク質を固めると豆腐、豆腐を揚げると「油揚げ」「厚揚げ」、焼くと「焼き豆腐」、凍らせて「凍み(高野)豆腐」となる。大豆にはサポニン等水溶性の低分子化合物やタンパク質性のプロテアーゼ・インヒビターやアミラーゼ・インヒビターやレクチンなどの有毒成分が含まれており、これらの加工には有毒成分の除去や解毒の意味もある。はた坊
2015.10.29
コメント(0)
-

勝手に生えている じゃがいも 収穫をしておいた 東日本大震災4年と7か月と17日後に
じゃがいもタマネギの畝つくりをしていたらじゃがいも 勝手に生えているのが じゃまなので抜いておいた結構とイモがついていたので収穫をしておいたこれは 前につくったじゃがいもの 残り物が勝手に生えていたものじゃまだなあと 思っていたが イモがついてるので栽培せずに 収穫できているまあ 小さいのが多いが それなりに収穫できているありがたいというのか ありがた迷惑なのかわがらないけど 収穫できるのは ありがたいもの東日本1震災 3月11日発生10月28日は既に4年と7か月と17日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------難民を引き受けるべきか(2) 生活の安全から考える 日本の社会、特にNHKなどを中心とする現在のマスコミに左右される社会は、どんなことでも「良い子」の方向を選び、「なぜ、それで良いのか」という問いはない。難民問題が起こると「可哀想だ」、「日本だけは・・」という直感的な議論が横行している。しかし、私たちが大人、もしくは親としての責任は、あることが日本のためにどういう影響があるか、問題は無いかを冷静に考えなければならない。第一回は戦争と難民の関係を整理し、難民を引き受けるのは戦争とのペアーであることを示した。その国の安全性はその国にとって基本的な要件だ。だから、難民や外国人労働者を含めて「生活の安全を保つ」というのが最も大切である。生活の安全、つまり犯罪とかテロというものは、その民族や国で常識が異なる。日本の場合、伝統的に犯罪はほとんどなく、それが日本の特徴である。まず第一に明治の初めに日本に来た貝塚のモースの著述を表紙に示した。(真ん中はモースの本、右がモースの肖像)「鍵を掛けぬ部屋の机の上に、私は小銭を置いたままにするのだが、日本人の子供や召使いは一日に数十回出入りをしても、触っていけないものは決して手を触れぬ。」当時のアジアで、子供や貧困層がお金を見て盗まないはずはないが、日本ではまったくその気配すらないことにビックリしている。次に、現代の世界の犯罪率(人口10万人あたりの殺人件数)を示す。図1世界広しといえども日本はこの表の国の中では世界でもっとも犯罪率が低い。この文化を守るためには難民や外国人労働者を基本的には受け入れることはできない。(平成27年10月17日)ふむふむはた坊
2015.10.28
コメント(0)
-

エンドウ その後も 無事なり 茶 おべんきようその40
昨年まず すなっぶエンドウをかってきた エンドウもかってきている秋は9月から 種まきしていこう スナップエンドウ09月28日 庭での種まきをしておいた10月10日 発芽してきている10月13日 畑に移動した m-20のマルチの畝に植え付けしておいた10月20日 その後 残っているスナップの苗がすくなくなってきている 追加の種まきをしておいた10月27日 まだ 発芽していない11月03日 まだ 発芽していない11月09日 すこし 発芽してきている11月16日 発芽した苗をまたm-20の畑の畝に再度 植えなおしておいた11月22日 もみがらをかけておいた11月23日 支柱をつけておいた12月06日 苗は無事に生育している もみがらのおかけなり12月13日 苗は小さいまま これで 越冬中 二回目の苗は 全部ともに 無事なり12月23日 苗はちいさいまま これで良し 無事なり普通のエンドウ豆09月28日 庭での種まきをしておいた10月10日 発芽してきている10月13日 畑に移動した m-20のマルチの畝に植え付けしておいた11月09日 エンドウ かなり大きくなっている11月16日 支柱をつけておいた11月22日 もみがらをかけておいた12月06日 エンドウは大きくなりすぎている こまったものだなあ12月13日 紐で固定していこう すこし ふらふら している感じ12月23日 ぜんぶの豆さん 無事なり これで 安心だなあ12月28日 すなっぶ えんどう いい感じ01月15日 その後も 無事なり 02月08日 雑草もなし もみがらとマルチで無事なり02月14日 支柱に紐で固定をしておいた 風がつよいので 紐が必要なり スナップエンドウにも もみ殻と支柱をつけた エンドウは大きくなり過ぎ もみがら 支柱もつけた これで あとは 大きくなるまで 放置だなあ01月03日 すなっぶえんどう その後も 無事なり01月03日 えんどう こちらも デカいが なんとか 無事に育っている01月12日 えんどう なんとか もちそう でかいが なんとかなるだろう01月12日 すなっぶえんどう その後も小さいままで 無事なり02月01日 その後もすなっぶえんどう 無事なり12月02日 エンドウ こちらも 雑草はなし 無事なり01月15日 その後も 無事なり 02月08日 雑草もなし もみがらとマルチで無事なり02月14日 支柱に紐で固定をしておいた 風がつよいので 紐が必要なり02月22日 紐で固定したので 安定した これから 成長してくれるはず03月01日 えんどう これから 成長するはずだけど まだ そんなに伸びていないな03月01日 スナップ エンドウ まだ 小さい 支柱もつけたが 生育は これからだな03月01日 エンドウは 大きくなっている これから どんどん 伸びてくれるはず03月07日 スナップ エンドウ すこし 生育して 伸びてきている03月14日 スナップ エンドウ その後もすこし 伸びてきている03月22日 スナップ エンドウ それ後も もう すこし 伸びてきている03月29日 エンドウ 花が咲いてきている04月04日 えんどう 花がたくさん 咲いてきている04月12日 えんどう 実がどんどんついてきている04月19日 スナップ こちらにも 実がどんどんとついてきている04月26日 エンドう そろそろ 収穫してもよさそうになってきている今年はマルチをしているので 雑草はまったく なし昨年は雑草にかなり負けていたが 今年は 無事なり5月になったら 収穫できる見込みなり05月02日 スナップエンドウ 収穫できそうになってきている こちらはこまめに収穫をしていこう05月03日 エンドウ かなり実がついている こちらは 昨年は5月17日に収穫した あと2週間後なり05月04日 すなっぶ えんどう 初の収穫をした05月05日 えんどう 初の収穫をした05月06日 スナップ えんどう 2回目の収穫をした05月09日 えんどう 2回目の収穫をした05月16日 えんどう 3回目の収穫をした05月17日 すなっぶ えんどう 3回目の収穫をした05月23日 えんどう 4回目の収穫をした今年エンドウ 種をかってきた植え付けは9月27日くらいにやってみよう来月に植え付ける予定なり えんどう10月04日 庭での種まきをしておいた10月10日 発芽してきている 来週に畑に移動しよう10月17日 g-09の畑の畝に移動した 10月24日 その後 無事に生育しているスナップエンドウ10月04日 庭での種まきをしておいた10月10日 まだ 発芽していない10月14日 やっと 発芽してきている やや 遅いが okだなあ10月18日 g-07の畑の畝に移動した茶 おべんきょうその40茶ではない「茶」詳細は「茶外茶」を参照茶葉を使用しない嗜好性飲料も総じて「茶」と呼ばれることがある。こういった茶ではない「茶」の多くはチャノキ以外の植物に由来するものであり、葉や茎、果実、花びらなどを乾燥させたものを煎じて使用する。 また、それら「茶ではない茶」を中国語では「茶外茶」と呼び、本来の茶を「茶葉茶」と呼んで区別することも行われている。[119][120]ほかにも、真菌類・動物に由来するものがわずかながら存在し、さらに中国の華中地区では、白湯(さゆ)さえも「茶」と呼ぶことがある。植物由来麦茶 ハトムギ茶 熊笹茶 竹茶 そば茶 ハブ茶 甜茶 甘茶 甘茶蔓茶 杜仲茶 苦丁茶 ドクダミ茶 コーヒー生豆茶紫蘇茶 緑甘茶(緑天茶) ゴーヤー茶 マタタビ茶 柚子茶陳皮茶(蜜柑の皮茶) 韓国伝統茶 ハーブティー マテ茶 羅漢果茶 コカ茶 ルイボス茶 ハニーブッシュティー 桜漬葉茶 昆布茶 梅昆布茶ほか、多数 真菌類由来 椎茸茶 動物由来虫糞茶(虫屎茶) :茶の材料とする茶葉(チャノキの葉に限らず)を蛾の幼虫に食べさせる。その結果として得られ る物は糞であるが、分解が進み、動物性の旨みも加わった自然加工物である。象糞茶 :アフリカ東部に暮らすマサイ族などが乾期のゾウの糞を元に作る飲み物。別名・サバンナティー。 無機物 湯(中国のスープ) はた坊
2015.10.27
コメント(0)
-

となりの畑 もみ殻を大量にいれて マルチをしているだけ でも 野菜は上出来になっている 不思議だなあ おうむ おべんきょうその12
隣の畑ここは いつも もみがらを大量にいれているそして 手入れはあまりしていないマルチをひいて 何かをうえたら 放置しているが 結構と野菜はできている不思議な 不思議な 隣の畑であるただいま 小豆と 大豆と ネギとサトイモなどをつくっているサトイモ 水が大量に必要のはずなのだけどみたところ 水やりもあまりしていないが サトイモ ちゃんと育っている不思議だなあ ??????サトイモ 水が不足すると 生育が貧弱になるがここのは ちゃんと 育っている?????不思議だな もみがらのせいなのかなあ ????もみがらと燻炭にしたものをたぶん30cmくらいはいれているはずここの野菜は普通の野菜の倍くらいのサイズになっている じつに不思議な畑だ????おうむ おべんきょうその12種名のリストオウム目の種名リスト (英文)一般的な英名と学名でそれぞれソートできる約350種のリスト オウム科の分類学的種名リスト 7属21種。インコ科の分類学的種名リスト(英文)分類学的なシーケンスを冒頭の taxobox のように、二つの亜科の下に属名 と種名が連なる古典的なアプローチにより列挙したリストオウム科 (Sibley)はオウム目を単一の科として分類したリストはた坊
2015.10.27
コメント(0)
-
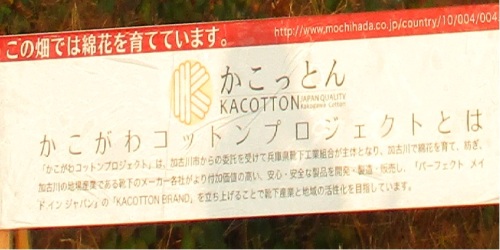
加古川で 綿つくりをやっているらしい 大豆 おべんきょうその08
g-1/3/7/9の畑を借りているがここの地主さん今年は綿をつくっているいつもは 米をつくっているが今年は綿をつくっている加古川は綿の産地であったらしいで 加古川の綿をつくろうとの運動らしい豆知識 + 加古川で綿花栽培が盛んになったきっかけ。 清流加古川をはさんで広がる播州平野。江戸時代は、全国屈指の綿の産地でした。 江戸末期には、多くの藩が負債を抱えていたのと同様、姫路藩も収入の四倍強に及ぶ73万両もの累積債務を抱えており、日常生活に支障を来すほどの困窮ぶりだったといいます。 この債務に悩んだ藩主忠以(ただざね)は、藩政改革に、河合道臣を家老として登用しました。 河合道臣は、加古川流域で早くから栽培されていた綿花を素材とした姫路木綿が、極めて良質であることに目を付けていました。 布を織る技術に優れ、薄地で柔らか、しかも白さが目立って特筆に値するものでしたが、問題は流通にありました。 大坂の問屋が介在することで、仕入れ時の買い叩きや、かなりの中間利益が吸い取られていることを知った彼は、大坂市場に見切りをつけて、藩が独占して江戸直送。江戸表で売り捌く専売権獲得を思いつきました。これは先例が無かったため事前に入念な市場調査をし、幕府役人や江戸の問屋と折衝を重ねた上、文政6年(1823年)から江戸での木綿専売に成功します。 色が白く薄地で柔らかい姫路木綿は「姫玉」「玉川晒」として、江戸で好評を博しました。また、木綿と同様に塩・皮革・竜山石・鉄製品なども専売としました。これによって藩は莫大な利益を得、道臣は27年かけて藩の負債完済を成し遂げました。(※参考 河合道臣 - Wikipedia 大豆 おべんきょうその08利用ダイズ種子(大豆)はタンパク質や脂肪、鉄分、カルシウムなど、ミネラルを多く含む。はた坊
2015.10.27
コメント(0)
-

やまのいも 4回目の収穫をしておいた 東日本大震災4年と7か月と16日後に
2014今年もヤマノイモの植え付けをしよう04月27日 家の保管しているヤマノイモの種イモをみてみたが 発芽しているのはすくないな04月29日 3月にhcで買っていた種イモをm-08に植え付けておく05月03日 畑のあちこちに 残っていたヤマノイモの分が どんどん 発芽してきている05月11日 支柱を乗り越えて どんどん 蔓がのびてきている05月18日 植え付けた種イモからの発芽 やっと 1本目が出てきている なんとかなりそう05月25日 支柱をどんどんつけている 全部のイモに支柱をつけた たくさんある06月01日 支柱から伸びる蔓をひもで固定をしている 輪をつくって どんどん葉が茂るようにしておいた06月08日 庭でもむかごからのヤマノイモがででいる m-08のはかなり増えてきている またまだ発芽中06月15日 発芽してくるのが まだまだある あちこちで どんどん 発芽してきている今年もヤマノイモをあちこちでそだてていこうg-01 2-3本をうえつけている すこし発芽してきているg-03 2本のヤマノイモをうえつけている 発芽している 1mは超しているm-08 2-3本の発芽している 2mくらいになっている 8本くらいはあるm-08 植え付けをしたのは5本 1本が5月18日に発芽した 残りも5月25日に発芽したm-20 2-3本の発芽がある 2mくらいになっている 5本くらいはあるm-06 2-3本の発芽している 2mくらいになっている3本はあるm-07 2-3本の発芽してきている 2mくらいになっている3本はある あちこちに 18-24本くらい 発芽している植え付けたのは 5本 5月18日にやっと 1本目の発芽 残りも発芽した放置しているのは どんどん発芽して 2mを超えてきている わき目もどんどん出てきている発芽したのには 支柱をどんどんつけていこう葉が茂るように どんどん支柱をつけよう 全部が29本くらいになった 写真の記録など5-6----は m-08の写真 あちこち 伸びている5-9----は m-20の畑の分 これも 良く伸びている5-11---は m-08の写真 もう 支柱を追い越していいる 2mはある5-18---は m-08の種イモからの 発芽 やっと 1本目5-25---は m-06の写真 かなり長くのびて脇芽もたっぶりとでてきている6-01---は m-07の写真 支柱から蔓が輪をつくってぐるぐるとまわっている6-08---は m-07の写真 支柱からどんどん伸びている6-14---は m-08の写真 にぎやかになってきている6-15---は m-20の写真 ここも 蔓はどんどんのびてにぎやかになっている6-28---は m-20の写真 また どんどん 新しく発芽してきている ヤマノイモには 全部に支柱をつけている はみ出した蔓を紐で固定して ぐるぐる回らせている今年のヤマノイモは元気が良い 全部で29本くらいある支柱をつけているので ヤマノイモの蔓は無事に葉が茂ってくれている06月15日 畑をみると その後も またまだ 発芽してくるのがある5月3日くらいから 発芽してきているが 29本を超えている その後も 発芽してきているので 面白い まだまだ 増えてきている支柱さえあれば 雑草に負けることなく 成長してくれている 今年のヤマノイモ 元気が良い07-20---は m-08の写真 まあまあ 元気である08-31---は m-06の写真 秋の雰囲気になってきている 黄色の葉になってきている夏は過ぎた もう 秋だなあ 色ずいてきている09月06日 やまのいも むかごも たくさんついてきている10月05日 m-7のやまのいも 1個を掘り出してみた バラバラになってしまった10月19日 g-03のやまのいも 1個を掘り出しておいた まあまあ だな10月26日 m-20のやまのいも 1個を掘り出しておいた まあまあ11月04日 m-08のやまのいも 3個を掘り出しておいた まあまあ なり12月31日 m-08のやまのいも 3個を掘り出しておいた まあまあ なり2015 今年04月19日 昨年の残っている分からの発芽 どんどん 出てきている m-08にも数本04月20日 庭にも 発芽してきている04月25日 g-1/3にも 発芽してきている04月26日 m-20にも 発芽してきている04月29日 m-06/07にも 発芽してきている05月03日 それぞれに 支柱をつけてまわっている05月05日 まあ 大きくなってきている 上に上に どんどん 伸びている 凄いなあ05月30日 支柱をこえて どんどん 伸びてきている g-07のやまのいも05月31日 こちらも にぎやかになってきている m-20のやまのいも06月20日 あちこちの やまのいも どんどん 茂ってきている06月21日 m-08のやまのいも ここが メインのヤマノイモの場所06月27日 m-20のやまのいも 雑草取りをしていたら2-3本の蔓を切ってしまった あらあら きをつけよう07月04日 m-08のやまのいも こちらは 鬱蒼と茂ってきている 元気である07月19日 m-06のやまのいも こちらも 元気なり08月01日 やまのいも むかご たくさんついてきている08月22日 やまのいも やや 勢いがなくなってきている 夕顔にからまれている09月06日 やまのいも 支柱も倒れつつある ななめになっているのが 多いなあ在庫 g-1 2本 g-3 2本 m08 10本 m20 10本 m06 4本 m07 10本 庭 4本 合計で 42本も生えてきている すごいなあ やまのいも 10月には収穫できる 今年は雑草とりしてイモの蔓をきったりはあまりしていない たくさん 残っているので 掘り出すのが楽しみだなあ 収穫まで あと1か月となった09月22日 雑草とりをしていたら ヤマノイモがでてきた ついでなので 収穫をしておいた10月04日 m-20のやまのいも すこし掘り出しておいた 2回目の収穫なり10月10日 m-08のやまのいも 3本を収穫をしておいた まあまあ かな 3回目の収穫なり10月18日 m-08のやまのいも すこし収穫をしておいた 4回目なり東日本1震災 3月11日発生10月27日は既に4年と7か月と16日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------難民を引き受けるべきか(1) 民族性から考える 「難民」という点で、世界の民族には大きく二つに分けることができる。一つが、アーリア人でインド西方からアメリカまで分布するいわゆる、ヨーロッパ、ロシア、中東、アメリカ合衆国の人で、彼らは「力があれば他国への侵略は良いことである」ということで、その主人公、たとえばローマ帝国のシーザーのように「英雄」として尊敬される。このような地域では、「侵略」が日常的なので、それに伴って追い出される「難民」が常に発生してきた。その結果、「侵略」と「難民」はペアーになっているので、難民が発生した時にはそれを受け入れる伝統もある。一方、アジア海洋民族やアメリカのインディアンなどは、「自分の土地は自分の土地、他人の土地は他人の土地」という意識があり、侵略はほとんどしない。このような国は、他国への侵略の主人公はむしろ悪人か失敗ととらえる。豊臣秀吉の朝鮮征伐が日本人にとってあまり歓迎されない民族性が影響している。このようにアジア海洋民族系の場合、侵略がないので難民がでない。むしろ難民を引き受けるということは侵略を是とすることになるので受け入れない。今回のシリア難民の場合、その発生原因は1920年代にヨーロッパが中東を適当に地図上で線引きして分割したことに端を発している。つまりアーリア人的な発想で難民が発生しているのだから、難民がヨーロッパに向かえばヨーロッパ、ロシアに向かえばロシアが収容するべきで、日本は関係ない。(平成27年10月17日)ふむふむはた坊
2015.10.27
コメント(2)
-

なすび 寒くなってきて 元気はない 茶 おべんきょうその39
なすびそろそろ 御終いになりつつあるで毎週 追肥をして みずをやってはっぱをかけているが 実はすこししかならない葉も元気はなししかしながら 実はすこしはつくあと1-2回で 御終いの予定茶 おべきょうその39食用以外での利用日本では平安時代より江戸時代まで、茶は染料として利用されており「茶色」は正しく茶の色だった。時代とともに、茶そのものよりも茶色が出しやすい別の染料に置き換わる形で次第に利用されなくなった。元禄時代には茶色ブームが起き、当時の「茶」の付く色の和名は80種を超える[117]。 茶の葉を噛みつぶし、水虫の患部に塗る伝統治療法が、長野県秋山郷にて行われる[118]。はた坊
2015.10.27
コメント(0)
-

もみがら 大量にでるのは11月の半ばの予定 競争して手に入れる予定 おうむ おべんきょうその11
g-1-3-7-9の畑の横にも もみがらでも これは地主さんのものらしいいつも どうぞ 使ってくださいとかかれているが今回はそれがないので 様子見をしている大量のもみ殻はいつも11月に出てくるこれは 貸農園さん用として 畑に山盛りになるくらいをだしてくれるで 貸農園の人が 競争して 勝手にもっていって良いもの昨年は11月25日くらいだったバイクで 袋につめて20回くらい うろうろとして畑に運ぶもみがら ネギさんにかける土のすくない畑にどんどん いれておく粘土の土がおおいので もみがらいれて 柔らかくしている今年も 大量のもみがら 畑にいれる予定おうむ おべんきょうその11分類学以下の分類は複数の亜科を認めるバージョンである。分子配列データ(上記参照)によれば複数の亜科による分類が実際に確実かもしれず、おそらく科に昇格するものもあるかもしれない。しかしこの中での族の配置については現時点ではあまりよく解明されていない。インコ科(Psittacidae):true parrotsArinae 亜科:新熱帯区のインコ、おおよそ160種、約30属からなる。おそらくは二つの異なる系統からなる[11][12]ヒインコ亜科 Loriinaeケラインコ亜科 Micropsittinaeミヤマオウム亜科 Nestorinaeフクロウオウム亜科 Srigopinaeインコ亜科 Psittacinae Cyclopsitticini 族:イチジクインコ、3属、 すべてニューギニアかその近傍産Polytelini 族:オーストラリアおよびWallacea産の3属 - アオハシインコの仲間に属するのかもしれないPsittrichadini 族: アラゲインコ 1種のみPsittacini 族:アフリカの熱帯産インコ、約10種前後、3属Psittaculini 族: 旧熱帯産の Psittaculine 族のインコ、約70の現存種、12属からなりインドからオーストラレーシアにかけて分布Platycercinae 亜科:アオハシインコの仲間、約30種が約12の属に分類される Melopsittacini 族:1属、1種、セキセイインコNeophemini 族:キキョウインコ、アキクサインコの仲間。二つの小さな属からなるPezoporini 族:ヒメフクロウインコ、キジインコの非常に異なった2種、1属からなるPlatycercini 族:クサインコの仲間、おおよそ20種、8属はた坊
2015.10.27
コメント(0)
-
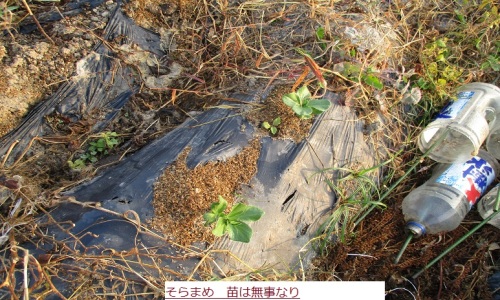
そらまめ 元気なり 大豆 おべんきようその07
昨年09月23日 hcでそらまめの種をかってきた09月29日 すこし早いけど 庭で種まきをしておいた 20個の豆さんの植え付け10月13日 まだ 2個だけ 発芽 残りはまだまだ ゆっくりとしている10月19日 発芽している で すぐに 畑に移動した m-06とm-07に植え付けた10月27日 その後 畑でも 苗は無事なり11月04日 m-06の苗も 無事なり まあまあ11月17日 よくみると 苗は みんな ひょろひょろとしている やや 伸びすぎているな11月24日 横からみると やっぱり ひょろひょろ 伸びすぎ12月08日 その後は 成長はしていない 寒くなったので stopだなあ12月15日 寒くなってきているが そらまめさん 無事なり まあまあ 伸びすぎだけど12月22日 その後も 元気なり今年01月05日 風でふらふらしている01月11日 支柱をつけて 紐で軽く固定をしておいた02月02日 まだまだ小さいまま03月02日 すこし起き上がりつある03月08日 花芽がすこしついてきている やや おおきくなってきている03月22日 支柱を追加しておいた 大きくなりだしている まあまあ なり04月06日 そらまめ その後も 順調なり04月21日 実がつきだした05月03日 あちこち 実が大量につきだした05月18日 そろそろ 収穫できそうなので 全部を収穫をした結構とたくさん 実が 収穫できた 今年は 良し今年 秋になったので そらまるの種を買ってきている種まきは9月から10月12日 種まきをした10月19日 まだ 発芽しない10月25日 まだ 1本しか 発芽していない 遅いなあ11月08日 やっと 8本のみ発芽している まだ 半分11月09日 発芽していないのは m-08の畝にうえておいた すこし 遅いので 追加の種まきをしておいた10月26日 追加のそらまめ 種まきをしておいた11月08日 発芽してきている こちらは順調なり11月09日 発芽したのは g-1/g-3のさつまいものあとに植え付けておいた これで そらまめの植え付けをした 予定の倍の数になっている11月16日 m08のは まだ 発芽していない が g-1/g-3のは無事に生育している11月22日 そらまめにも もみがらをかけておいた これで 保温にもなるし 雑草よけにもなる11月30日 そらまめ もみ殻をかけているので 元気になっている やはり もみ殻 有効だなあ12月06日 そらまめ そり後も元気なり もみがら 土の代わりになっている12月13日 そらまめ 元気なのは もみがら さんのおかげなり もみがら 風を防いでいる01月18日 そのご そらまめ やや 生育してきているなあ02月08日 その後 そらまめ 見た目にも 生育が進んできている02月15日 そろそろ 支柱もつけてみようかな02月22日 支柱つけようとおもっていたが やる時間がなくちゃった 次回としよう03月08日 そのごも 生育している 支柱 まだ03月15日 そらまめ 花が咲いてきている03月22日 そらまめ まあまあ 元気なり03月29日 そらまめ 花もとんどん 咲生きている04月19日 そろそろ 実もつきだす雰囲気になっている04月26日 そらまめ 実もつきだした あちこちに05月09日 そらまめ 実の収穫をした05月17日 そらまめ 収穫をした そらまめ 実も大きくなってきたので 収穫をしておいた秋のそらまめ 種をかってきた08月29日 hcで種をかってきた植え付けは来月の10月の予定なり10月04日 庭で 種まきをしておいた10月14日 発芽してきている10月18日 畑に移動した g-07の畝に植え付けた10月25日 その後 そらまめ 無事に生育しているだいず おべんきょうその07原産地・世界への伝来説が各種あり、定かではないが、原産地は中国東北部からシベリアとの説が有力で、日本にも自生しているツルマメが原種と考えられている。栽培の歴史も諸説あるが、約4,000年前に中国でツルマメの栽培が始められ、ダイズとして作物化されたと考えられている。日本には朝鮮半島を経由して、縄文時代後期中頃[18][19]に伝来したと考えられている。日本列島においては縄文時代においてアズキやリョクトウなどの炭化種実が検出されているためマメ類の利用が行われていた可能性が考えられており、縄文農耕論の観点からも注目されている。近年はダイズに関して九州地方や中部地方においてを土器内部の植物圧痕として確認された例があり、縄文中期から後期にかけては日本列島における存在が確認されている[20]。これらの発見により日本列島においては縄文中期中葉段階で栽培種ダイズが存在し、この時期以前に大陸から栽培種ダイズがもたらされたか、あるいは日本列島において独自にツルマメからの栽培化が起こった可能性が考えられている。また、山梨県の酒呑場遺跡から出土した土器のダイズ圧痕は蛇体装飾の把手部分から検出されており、これは偶然混入したものではなく意図的に練りこまれた可能性が想定されており、その祭祀的意図をめぐっても注目されている。ヨーロッパやアメリカに伝わったのは意外にも新しく、ヨーロッパには18世紀、アメリカには19世紀のことである。ヨーロッパにダイズの存在を伝えたのはエンゲルベルト・ケンペルだといわれており、彼が長崎から帰国した後、1712年に出版した『廻国奇観』において、ダイズ種子を醬油の原料として紹介した。故にダイズの英名はshoyu(醬油)bean(豆)からSoybeanとなっている。ヨーロッパでは1739年にフランスでの試作、アメリカでは1804年にペンシルベニア州での試作が最初の栽培とされている。ベンジャミン・フランクリンの手紙の中に、1770年にイギリスにダイズ種子を送る旨が記してある。ヨーロッパでそれ以前にダイズの存在を知られていなかった理由として、既に他の豆類が栽培されていた事や、土壌が合わなかったこと、根粒菌が土壌にない場合があったことなどが挙げられている。ダイズが伝播した後も、専ら搾油用やプラスチックの原料など、ダイズ種子の工業用途が主な栽培理由であった。1910年代以前は、ダイズはアジア圏以外では重要な作物とはみなされていなかった。ヘンリー・フォードもプラスチックの原料を安く調達するために大豆農園を作っていた。食料として注目されるようになったのは1920年代以降の事であり、ヨーロッパで食料として初めて収穫されたのは1929年の事とされる。アメリカで本格的にダイズが栽培されるようになったのは、1915年にワタミハナゾウムシ(英語版)の侵入によってアメリカ南部の綿花が大打撃を受け、それまでアメリカの製油業の中心であった綿実油が不足してからである。ワタに代わる新たな製油材料として、それまでも徐々に栽培を拡大させてきたダイズは一気に脚光を浴びることとなった。1920年代には製油用や飼料用としての需要の高まりにより、さらに大規模に栽培されるようになった[21]。タンパク質含有量の高いダイズ種子は用途が広く、様々な食品の製造に加工されている。そのタンパク質以外の成分である脂質からは食用油以外にもレシチンなどが抽出され、利用されている。日本では非常に重用され、米・麦・粟・稗(ひえ)・豆(大豆)を五穀とし、節分には大豆を用いた豆まきが行なわれるほどである。はた坊
2015.10.27
コメント(0)
-

さといも 2回目の収穫をしておいた 東日本大震災4年と7か月と15日後に
さといも昨年01月19日 サトイモ 2回目の収穫をしておいた03月09日 hcで サトイモの白目大吉を買ってきた04月17日 昨年の残りのサトイモの発芽 2本の芽が出てきている04月30日 白芽大吉の種イモ m-08の同じばしょに植え付けをしておいた05月03日 納屋に残っていた種イモがあったので これも畑に移動して植え付けた植え付けた種イモからの発芽はまだない しかし 昨年の残りのサトイモが どんどん 発芽してきている ブロックのまわりにも3本が発芽してきている同じ場所だけど まあ なんとか なるだろう今年もサトイモ 水路の横の溝の場所で 育ててみよう06月02日 水路の水がながれるようになった これで 安心なり06月08日 サトイモがたくさん発芽している 今年も無事に育ってくれそう06月22日 その後 発芽したのは かなり多くなっている 見た目もにぎやかになってきている サトイモ 今年も昨年と同じ場所だけど 今の所は良く育ってくれている07月20日 その後も順調なり 大きくなって 背も高くなってきている 見事なものだなあ08月02日 その後も 大きくそだっている みずの心配はいらないようだ08月17日 その後も さといも 元気なり 茎はあまり太くないけど 無事なり08月24日 その後も さといも 元気だ 虫がいた 黒いの1匹 逮捕しておいた08月31日 雑草とりして 追肥した となりのヤマノイモよりも背が高くなった雑草とりをしておく追肥もした09月21日 その後 秋になってきたので 勢いもやや弱くなってきている10月05日 その後 秋になって 涼しくなってきている 葉もすこし枯れだしてきている10月19日 その後 葉も スキスキになってきつつある さといも ゆっくりと 収穫する予定11月になってから 掘り起こそう11-12-01-02月と ゆっくり 収穫する予定11月02日 さといも 初の収穫をした まあまあ たくさん出てきた11月16日 さといも 2回目の収穫をした これも まあまあ12月01日 さといも もみがらがもうないので サトイモには もみがらは なし12月06日 さといも その後も葉は枯れてきている 12月23日 サトイモ 完全に葉は枯れた葉もかれつつある サトイモの横には ヤマノイモもあるので サトイモと ヤマノイモ 12月には 2回ずつ 収穫していこう12月28日 さといも 3回目の収穫をした今年01月12日 さといも 収穫しようかな と 思いながら 結局 寒いので やめた寒くなると 外にでるのが どうも おっくうになるなあ 01月24日 さといも またもや 収穫しようかなと思いながらも外は寒い また あとにしよう とうとう 芽が出てきている04月04日 残りのサトイモ 芽が出てきている そのまま サトイモ 今年も育てていこう04月12日 その後も どんどん 芽が大きくなりつつある04月19日 サトイモ 発芽が どんどん 続いていて かなり増えている サトイモだらけになりそう04月26日 さといも 芽も はっきりとわかるくらい 大きくなってきつつある 元気なもの05月16日 発芽したサトイモ かなり大きくなってきている 混雑しすぎている05月23日 さといも 密集したまま 茂ってきている密集しているての゛ すこし 分散させよう05月31日 さといも 分割して すこし間隔をあけて植えなおしをやっておいた06月06日 そのご 雨がふって 元気になってきている06月13日 さといも 生育がよくなってきている 水路に水が流れるようになり 元気なり06月20日 さといも 回りのサトイモと比べると とんでもなく 大きくなっている これはすごいなあ06月21日 それにしても 今年のサトイモは育ち具合は良い サトイモ 小芋を植えるよりも 親イモを植えたほうが 育ち具合は良い サトイモは 親イモをうえたら 成長も収穫も良いということだなあ これは すごいわ06月27日 さといも 元気に どんどん 大きくなってきている07月11日 さといも 葉が とんでくなく 大きくなっきているなあ07月18日 横の水路にも 葉がかかってきている 良し07月25日 さといも まだまだ 伸びてきている昨年は発芽したのが6月08日だった が 今年は 発芽が 4月04日だった と いうことは 今年のサトイモ 昨年より 2か月も早く成長しているわけで大きいはずである 残りもののサトイモが発芽したので 発芽も早い 生育も早い08月01日 サトイモの葉 デカい デカい 猛暑でも水路の水が横を流れているので元気なり08月08日 さといも 茎をみてみた 細いが 数はすごいもの 密集しすぎているかな???08月22日 さといも 追肥をしておいた これで もっともっと 大きくなるぞ09月06日 さといも 葉が倒れているのがおおいので 紐で固定してじゃまにならないようにした09月12日 さといも 葉を紐で固定して まわりにじゃまにならないようにした これで 見やすくなった09月20日 さといも 今は葉をみているだけ 虫もいないし 絶好調みたい収穫は11月から まだ 先だなあ育ち具合は これまでで 最高の出来である が イモは収穫してみないと 判らない10月10日 雑草とりしていて さといも 1つ抜いてしまった10月12日 サトイモ 葉もやや元気がなくなりつつある 冬になってきているのかな10月18日 さといも 土をかけて イモが太りやすくなるようにしておいた10月25日 さといも 2回目の収穫をしておいた東日本1震災 3月11日発生10月26日は既に4年と7か月と15日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------少子化とメタボ・・・利権が作り出した無目的の政策は無視しよう! 少子化対策とメタボ対策という二つの政策は「天下りと利権を狙った似たような政策」だ。それは、表紙のグラフを見ると分かる。左のグラフは主要国の人口密度でよく知られているように日本の人口密度はもっとも大きい。右のグラフは先進国の肥満度を示していて、日本はもっとも痩せている国である。日本の人口密度がもっとも高いのに「人口が減ると大変だ」と言い、日本人がもっとも痩せているのに「太ると大変だ」と危険を煽る。政府がそういうとNHKが追従して日本の空気を作る。テレビや新聞もそれに追従して、少子化は問題か?これ以上、痩せても良いのか?も考える思考力がない。「言われたとおりの羊の群れ」という感じだ。私はまず山野を除いた可住地域の人口密度をヨーロッパ並みにすると、今の減少率で200年ぐらいかかるので、むしろ少子化は歓迎だ。また、女性の痩せ率が危険な領域にあり、もう少し「ポッチャリ型」を推奨して肥満度を示すBMIを28ぐらいにした方が良いと思っている。みなさんはどのぐらいが適当と考えておられるのだろうか?(平成27年10月18日)ふむふむはた坊
2015.10.26
コメント(0)
-

芽きゃべつ 差がついたまま 生育中 お茶 おべんきょうその38
昨年の秋hcで 芽キャベツの種が売っていたので 買ってきた今年は 芽キャベツ 種まきをしてみよう08月31日 庭で 種まきをした09月04日 発芽した09月06日 M-01の畑の畝に移動した第二弾の種まき09月07日 庭にて 第二弾の種まきをしておいた09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-01の畑に移動した苗の半分くらいは 残っているが まあ そこそこ 育っている10月26日 残っている芽キャベツをみてみたが 残っているのは 4本くらい種まきしたのは32本だったけど 残っているのは 4本のみ まあ 4本のこれば 良しとしよう これは 昨年と同じ4本となっている11月02日 そのご 4本のめきゃべつ それなりに 成長している大きいのと 中くらいのと 小さいの2本 それぞれ サイズは ばらばら まあ なんとか なるだろう11月09月 追肥をしておいた 肥料はたくさん必要らしい11月23日 葉をカットしておいた ちいさい芽はできてきつつある12月06日 追加で 葉をカットしておいた葉をカットしてたら 4本ではなくて もう すこし 小さいのもある4-8本くらいはあるみたい 追肥をしておいた12月13日 追肥をしておいた12月23日 雨がふったので いい感じになっている01月02日 まあまあ 成長もすこしづつ してきている01月18日 その後 あまり変化はない まあ そんなものかな01月25日 いい感じになってきている02月08日 第一弾 1本を収穫をした02月22日 次の芽キャベツが収穫できそうになってきている03月08日 残りの4本 芽キャベツの収穫をした03月22日 最後の芽キャベツ 収穫をしておいた これでお仕舞いに今年hcで苗が売っていたので 4本をかってきた09月06日 ローヤルで芽キャベツの苗が売られていた 4本を買ってきた09月13日 g-07の畑のはしっこに植え付けた09月20日 その後の芽キャベツ ちいさいまま 植え付けたままのサイズだなあ09月22日 追肥をしておいた09月27日 あまり大きくならないなあ まあ それなりの生育である10月04日 すこし 背が伸びてきている10月10日 もう すこし 背が伸びてきているが サイズは バラバラだなあ10月18日 2個は大きくなりつつあるが 2個は小さいままだなあ10月25日 2個の差はそのまま すこしづつ 大きくなりつつはある が 差はおおきいな もっと 背が高くなってほしいが 低いままだなあ茶 おべんきょうその38茶葉を用いた料理、菓子など食茶 :茶がらをそのまま食べること、また、その食材としての利用。茶漬け、ひつまぶし :ご飯に魚、塩辛、梅干、海苔、三つ葉などを乗せ、煎茶をかけて食べる。茶粥 :日本の奈良県と和歌山県では、茶葉を入れて粥を作る伝統がある(主にほうじ茶を使用)。茶そば :抹茶を練りこんだ蕎麦切り。龍井蝦仁 :中国浙江省杭州市の名物料理で、川エビの殻を剥いて、龍井茶の若葉と炒めたもの。樟茶鴨 :四川料理の一つで、下味をつけたアヒルをクスの葉とジャスミン茶でいぶして香り付けした後、蒸し、さらに表面を油で揚げる料理。茶卵(茶鶏蛋) :中国で一般的な、茶や醤油などで味付けしたゆで卵。ラペソー :ミャンマー料理の一種。後発酵させた茶葉をナッツ・干蝦・生野菜などと和え、サラダのように調理する。茶団子 :団子に抹茶を加えて風味を添えたもの。大正初期に京都府宇治市の「大茶万(おちゃまん)本店」で作られた物が発祥。はったい粉、ツァンパ :大麦の粉を使う練り菓子の一つで、茶を用いる場合もある。ほか、抹茶ソフトクリーム、抹茶ババロア、抹茶ケーキなど、緑茶の風味を添えた菓子類が日本には多い。また、チョコレート菓子(※「準」扱い含む)の製品は特に多い。また、北タイのラーンナー地方では茶葉をチューインガムのようにして噛むという[115]。これら以外にも、茶葉を使った料理は日本や中国を中心に様々なものがある[116]。はた坊
2015.10.26
コメント(0)
-

野菜つくりには 素人には シートは必要なり おうむ おべんきょうその10
専門家の農家は農薬を使うが素人の家庭菜園はまずシートなどをつかうまあ シート シート シートである野菜は虫さんのエサになるのでシートがないと 収穫するのは まず むつかしい野菜つくりむつかしい土つくり肥料農薬みずやり雑草とりなかなか いそがしいものシートこれは 全部が石油製品石油がないと 農業もできないしかし シート これがなかなか良くできてるそれでもシートしていても 虫さんも ときどき 中にはいりこむ虫さんとの戦いも なかなか むつかしいものおうむ おべんきょうその10系統学少なくとも nestorine [14]の特異性に関するケースは、さしあたりほぼ決着しているようである。その位置(フクロウオウムの有無に関わらず)と、分子分析による年代測定から示唆されるその古代の年齢が化石記録と食い違っているのに関わらず、またそれが不合理に高度な成因的相同と、現存のインコに対して明らかに最大節約法に反する分布特性を要求することになるにも関わらず、である。これらの研究は、物的証拠による校正を経ていない旧式な分子時計モデルに依存しているため、その結果は非常に疑わしい。ミヤキらによるシナリオ(1998)[11]は不完全であり、またフクロウオウムが含まれていないが、物的証拠とは完全ではないにせよ、よく一致している。しかしこれにもまた信頼のおけない分子時計モデルが使われている。後者二種(ミヤマオウム、カカ)がいかにも独立した系統を構成するように見えるのに、これらの種のなかにフクロウオウムを位置づけることはミトコンドリアDNA シトクロームb 配列データによって否定される[11]。どんな場合でも、インコの主要な系統がいかにもそれぞれの分岐群を代表しているように見えるが、しかしその相互関係は現存する分子配列データからは十分に解明されてはいない。明らかに彼らの適応放散はおおよそ始新世のあいだの非常に限られたタイムスパンのなかで起きている。ある一つの重要な発見はオウムもヒインコも、それ以外の主要なインコの系統から、従来考えられていたほどには隔たってはいないということである。はた坊
2015.10.26
コメント(0)
-

お米つくりの後の水田 これから 何もせず 来年まで 放置 大豆 おべんきょうその06
10月すぎて 米の収穫を完了しているあとの水田の様子ハトとすずめなど 鳥がうろうろしているその後は 放置うーーーん 一年のうち6-7-8-9-10月と5か月はお米つくりその後は 何もなし 家庭菜園は 1月からずーーーとー ずーーーと一年中 何かを作っている土地がたらない もっと 野菜をつくりたいくらいだけど????お米つくり vs 家庭菜園まあ 中身が違うけどこの 差はすごいなあイスラエルなどでは 砂漠でも 野菜をつくって 輸出をしているオランダなどの小さい土地の国でも 野菜を輸出しているお米 輸出もしないけど 輸入もさせないようにしているお米を作れとも 作るなとも どっちでもないような ??????何もしないまま 放置されたまま だなあ????????????大豆 おべんきょうその06有害なトリプシン・インヒビターなど多くのマメ科植物の種子と同様に、ダイズ種子中には有毒なタンパク質性のプロテアーゼ・インヒビター(トリプシン・インヒビター、セリンプロテアーゼ・インヒビター)やアミラーゼ・インヒビターやレクチンが含まれて消化を阻害するため、生食はできない。トリプシン・インヒビターを含むものを摂食すると消化不良を起こし下痢することがある[9]。そのため、加熱してプロテアーゼ・インヒビターやアミラーゼ・インヒビターを変性・失活させて消化吸収効率を上げている。なお、加熱してもプロテアーゼ・インヒビターの失活は十分ではないので、納豆菌などを繁殖させて納豆菌の分泌するプロテアーゼによってダイズ種子中のタンパク質とともにタンパク質性のトリプシン・インヒビターを分解させると、分解されたタンパク質と相まって消化酵素であるトリプシンが正常に機能してタンパク質の消化吸収効率が増大する。トリプシンインヒビター活性の高い生大豆を飼料としてラットに摂取させると成長阻害や膵臓肥大などの有害作用が引き起こされることが報告されている[10]。この膵臓肥大は、腸内で阻害されるトリプシンを補うための膵臓の機能亢進の結果として生じると考えられる[11]。生大豆粉はラットの膵臓癌と相関することが知られているが[12]、加熱調理済みの大豆粉の発ガン性は認められていない[13][14]。大豆がヒトの膵臓癌を促進する可能性があるかどうかの研究はまだ十分でないため不明である。ラットに与えられている大豆の量は、人間が通常摂食する量に比べてはるかに大きい[15]。大豆乳の加熱処理について、100℃10分間の加熱処理した大豆乳には加熱未処理試料のトリプシン・インヒビター活性の約34%が残存し、また100℃20分間では約30%、120℃10分間では約10%、120℃20分間でも約5%のトリプシン・インヒビター活性が残存した[16]。黒大豆を95℃で加熱した場合のトリプシン・インヒビターの活性変化について、1%のNaCl(食塩)溶液中、16%のショ糖溶液中では、いずれも60分の加熱でトリプシン・インヒビターの70%の活性が残存していたが、0.1%の重曹溶液中の45分の加熱でトリプシン・インヒビターの活性は完全に失われた[17]。はた坊
2015.10.26
コメント(0)
-

わけぎ 分散をしておいた 結構とあるものだなあ
昨年01月02日 初の収穫したあ01月06日 九条ネギがたくさんあるので 収穫はなし02月10日 そのご 雑草も生えているので すこし雑草を取り除いた やや 黄色に02月11日 2回目の収穫をした03月10日 3回目の収穫をした03月20日 4回目の収穫をした03月24日 5回目の収穫をした03月31日 6回目の収穫をした04月08日 7回目の収穫をした04月14日 8回目の収穫をした04月21日 9回目の収穫をした これで おしまいに残っているわけぎは 黄色くなりつつある そろそろ 抜き取ってしまい 納屋で乾燥して 保管しよう8月の後半くらいに 再度の植え付けをする 予定05月03日 引っこ抜いておく 畑ですこし 乾燥する05月04日 家に持って帰る 乾燥させて 納屋で保管する植え付け用の根っこ 大量に収穫した いい感じ秋には 大量のわけぎ どんどん 植え付けよう07月15日 干している分葱 状態も良い やや青みがついてきている08月22日 その後も 無事で 保存の状態も良いなあ やはり 外で保存が良い わけぎ今年は納屋でなくて 外の壁の横に干している保存の状態はこちらのほうが 風通しが良いので 元気に見える09月07日 在庫のわけぎの在庫を全部 畑に植え付けた m-20 m-07に分散した わけぎの在庫は 畑に2つに植え付け 残りは会社でも植え付けた これで 今年も大量にわけぎを育てよう09月17日 発芽した すこしだけどokだなあ09月22日 全部が発芽している その後 すくすく 育っている わけぎ 今年の畑も わけぎ だらけ もう わけぎで いっぱいになっている10月05日 その後も わけぎは 元気になっている すくすく 育っている10月27日 全部のわけぎ 元気にすくすくと育っている 結構と大きくなっている11月17日 わけぎ 全部が大きくなって 収穫はokになっている今週より わけぎの収穫を開始しよう11月24日 わけぎ 収穫を開始 まずは 試しで これだけ12月01日 わけぎ 2回目の収穫をした12月08日 わけぎ 3回目の収穫をした12月15日 わけぎ 4回目の収穫をした12月22日 わけぎ 5回目の収穫をした今年01月05日 わけぎ 6回目の収穫をした01月12日 わけぎ 7回目の収穫をした05月03日 ためしに すこしを収穫してみた もう 撤収してもよさそう今年はネギがたくさんあったので あまり収穫をしていない で たくさん 残っている そろそろ 掘りあげてしまおう全部 残っているわけぎを掘り起こして 乾燥させて休眠とする05月03日 わけぎ 残っているのを全部を引き上げた 納屋にて保管して しばらく お休みとする納屋で保管して 8月後半になったら また 畑に植え付けるとする09月07日 わけぎ 畑に移動した m-07の畑に植え付けをしておいた09月14日 発芽はまだかな ゆっくりとしている09月21日 やっと 発芽してきている これで 安心なり10月12日 わけぎ かなり大きくなってきている もう 収穫できそうになってきている2つの畝にうえつけているか゜ まだ すこし残っている たくさん あるので 楽しみだ すくすく 生育してきている11月09日 わけぎ 初の収穫をしておいた たくさんあるので どんどん 収穫していこう11月16日 わけぎ 2回目の収穫をした11月22日 わけぎ 3回目の収穫をした11月29日 わけぎ 4回目の収穫をした12月06日 わけぎ 5回目の収穫をした12月13日 わけぎ 6回目の収穫をした5 12月23日 わけぎ 7回目の収穫をした01月03日 わけぎ 8回目の収穫をした01月10日 わけぎ 9回目の収穫をした01月12日 わけぎ 10回の収穫をした01月18日 わけぎ 11回目の収穫をした01月24日 わけぎ 12回目の収穫をした02月01日 わけぎ 13回目の収穫をした02月08日 わけぎ 14回目の収穫をした02月14日 わけぎ 15回目の収穫をした02月21日 わけぎ 16回目の収穫をした03月01日 わけぎ 17回目の収穫をした03月08日 わけぎ 18回目の収穫をした03月15日 わけぎ 19回目の収穫をした03月22日 わけぎ 20回目の収穫をした03月29日 わけぎ 21回目の収穫をした04月04日 わけぎ 22回目の収穫をした04月12日 わけぎ 23回目の収穫をした4月まで 収穫できる予定 5月に 引き抜いて9月に 再度 植え付けをする予定なり05月04日 そろそろ 引っこ抜いてしまうかな05月10日 引っこ抜いておいた 畑においておく 乾燥したら 家の納屋に保管しよう05月17日 畑のわけぎ 家に持ち帰る 庭の横においておく05月24日 庭の横で 乾燥中 いい感じになってきている07月18日 その後も 庭の横で 放置している すこし 芽がでてきているなあ08月01日 その後も 無事なり 在庫は たっぶりとある 9月になったら 植え付けしよう08月22日 在庫のわけぎ 畑のm-07に発芽したのをばらまいておいた 台風の雨で発芽するだろう09月05日 わけぎ 発芽してきている しかし 数がすくないな あとで 分散させよう09月12日 わけぎ 発芽して やや おおきくなっている 分散してしまおう09月22日 わけぎ 大きくなって 密集している もうすこし バラバラにしないとねえ 混み過ぎだな10月04日 わけぎ そろそろ 分散させないとねえ10月18日 わけぎ 分散をさせておいた これで 生育は良くなる予定なりはた坊
2015.10.25
コメント(0)
-

m-07のネギさんに もみがらをがけておいた もみ殻 これから 大変に役に立つ
ねぎの根っこ12月31日 初の九条ねぎ 収穫をした 根っこも庭のブランターに植え付けをしておいた01月03日 2回目の収穫をしておいた 根っこは庭にて 植え付けをしておいた01月10日 3回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた01月17日 5回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた01月24日 6回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた02月01日 7回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた庭にブランター 6個に ネギのねっこ 植え付けをしている これで もうすこし大きくなったら 畑に移動する予定あと 3-4個 追加していく予定なり ネギは根っこから 育てていこう03月01日 ネギの根っこ まあまあ 生育してきている 03月12日 ネギの坊主のちいさいのがついてきている03月22日 かなり生育してきている そろそろ 畑に移動させよう03月29日 M-08の畑の畝に移動してうえつけをしておいた04月04日 その後も ネギさん 根っこも 元気そうだ 無事なり04月12日 ネギのねっこ ネギ坊主が でているので 全部をカットしておいた04月19日 ネギのねっこ その後もネギ坊主をカットしている04月26日 その後も 様子見をしている 05月26日 その後も まあまあ 無事なり06月20日 数はそのまま あまり 大きくはなっていないが 無事なり07月04日 ヤマノイモの日陰になっているが ちいさいが 数は無事にそだっている07月11日 2月からのねぎの根っこ 無事にそだっている まあまあかな九条ネギの在庫 m-08 10本 ネギの根っこ 60本 m-06 20本 m-07 20本 g-01 10本 g-03 20本 合計 140本くらいは まだある ネギ坊主をカットして そのままブンケツさせていこう06月20日 在庫のネギさん ネギ坊主が まだまだ 出てきている06月27日 在庫のネギさん ネギ坊主も まだまだ 出てきている でも 新しいブンケツのネギさんも そろそろ 出てきている07月04日 まだ ネギ坊主でできている07月11日 そろそろ 止まりでしている 青々としているのと 枯れているのが半々くらいになっている ネギ坊主をカット カット カット しているので ネギさんも あきらめて ブンケツしてみようかなと 考えているようだ残っている九条ねぎ 無事に生き残っている07月20日 九条ねぎ 大量にのこっている 新しい畝に分散させて植えなおしをあとでやろう07月21日 根っこの分のネギは ちいさいので そのまま 大きいのは植えなおそう08月01日 九条ねぎ 残っているのも 8月になって 元気になってきている09月05日 g-3の九条ネギ 9月になって この状態なり まあ 順調なり09月12日 m-07の九条ネギ これも元気になってきている09月23日 m-07の九条ねぎ 元気なり10月04日 m-07の九条ネギ 追肥をしておいた 九条ネギの在庫 m-08 10本 m-06 20本 m-07 20本 g-01 10本 g-03 20本 合計 80本くらい まあ たくさんある10月11日 m-06/07の在庫のネギ バラバラにして 分散して植えなおしておいた10月18日 m-07の在庫のネギにもみがらをかけておいた在庫のねきの土 カチカチになっていた土を耕して ネギさん ばらばらにして 植えなおしたが しばらく元気になるまで時間がかかりそうもみ殻 第一弾を確保しているが第二弾 じゃんし゜やん もみ殻を確保しておこうもみ殻 大変に役に立つもみ殻さん ばんざーーーーーーーい だなはた坊
2015.10.25
コメント(0)
-

コスモス 野生種は3mにもなるらしい すごいなあ 10月24日は 霜降
コスモスなかなか 綺麗な花である園芸品種には一定の気温があれば日長に関係なく開花する早咲き系があります。早咲き系は春早めにまくと初夏には開花します。また、早咲き系に対して従来通り秋に咲く系統を遅咲き系と呼ぶこともあります。ちなみに、主力で広く普及しているのは早咲き系の品種です。 野生種は草丈2~3mになりますが、園芸品種は矮性種で40cm、高性種で1.5mほどです。葉は細かく枝分かれして羽状になります。花径は大輪種で10cmを超します。色は白、ピンク、赤、黄色などがあります。白地に紅色の縁取りが入るピコティ咲きなど可愛らしいものもあります。一重のほか、花びらの付け根に小さな花びらが付くコラレット咲きや花びらが筒状になるユニークな品種もあります。*C・ピピンナツス(コスモス)-高さ2~3mにもらる一年草。葉は羽状に細かく切れ込んで、糸のような状態。茎は分枝し、それぞれの先端に直径6~10cmの花をつける。早咲き系と遅咲き系があり、早咲き系の大輪種で白、淡紅、濃紅の3色がそろった「センセイション」をよく見掛けるコスモス野生種は2-3mになるらしいすごい 背の高い花なんだなあ3mのコスモス すごいなあ10月24日は 霜降霜降(そうこう)は、二十四節気の第18。九月中(通常旧暦9月内)。現在広まっている定気法では太陽黄経が210度のときで10月23日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から10/12年(約304.37日)後で10月22日ごろ。期間としての意味もあり、この日から、次の節気の立冬前日までである。西洋占星術では、霜降を天蠍宮(さそり座)の始まりとする。露が冷気によって霜となって降り始めるころ。『暦便覧』では「露が陰気に結ばれて霜となりて降るゆゑ也」と説明している。楓や蔦が紅葉し始めるころ。この日から立冬までの間に吹く寒い北風を木枯らしと呼ぶ。七十二候[編集]霜降の期間の七十二候は以下のとおり。初候霜始降(しも はじめて ふる):霜が降り始める(日本)豺乃祭獣(さい すなわち けものをまつる):山犬が捕らえた獣を並べて食べる(中国)豺は{豸才}次候霎時施(こさめ ときどき ふる):小雨がしとしと降る(日本)草木黄落(そうもく こうらくす):草木の葉が黄ばんで落ち始める(中国)末候楓蔦黄(もみじ つた きばむ):もみじや蔦が黄葉する(日本)蟄虫咸俯(ちっちゅう ことごとく ふす):虫がみな穴に潜って動かなくなる(中国)次は立冬 11月08日はた坊
2015.10.25
コメント(0)
-
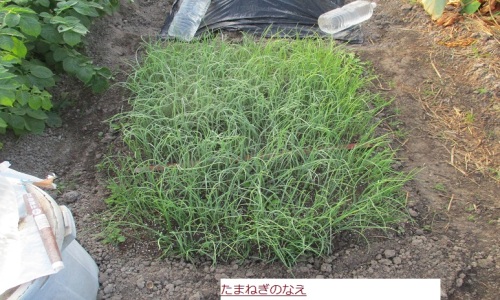
となりは タマネギの苗つくりしている はた坊はhcの苗を購入する予定なりne
昨年のたまねぎの注文10月25日 hcで玉ねぎの苗を注文した 11月の苗を予約しておいた10月26日 予約したら すぐに苗がきましたとの事 で 26日に苗をとりにいった予約なのに すぐに苗がとどいたとのこと 仕方がなく 植え付けるとしよう10月26日 早生の苗を g-09の畝に植え付けをしておこう10月26日 中生の苗を g-07の畝に植え付けをしておこう10月26日 赤玉ねぎを g-07の畝に植え付けておこう11月02日 マルチの畝の姿 中生の苗 50本11月02日 マルチの畝の苗 赤たまねぎ 100本11月02日 マルチの畝の苗 早生のたまねぎ 50本11月08日 晩生50本の植え付けをした11月09日 晩生100本の植え付けをした11月16日 その後 タマネギ 全部 無事に育っている これで 安心なり 合計で350本の植え付けをしている11月17日 もみがらをかけようと 探しに行ったが まだ でていない もみがらがでたら タマネギさんにもみがらをかけておこう もみがら でた11月22日 もみがらがでたあ 赤玉ねぎにもかけておいた これで 安心なり11月22日 中早にも もみがらをかけておいた タマネギもこれで 土をかけるよりしっかりとする11月22日 晩生にも もみがら 早生にも もみがら ばっちり12月06日 全部のたまねぎ 元気になっている もみがら 役に立つものだなあ12月07日 赤たまねぎ もみがらをかぶって 元気である 今年は順調である12月23日 その後も 赤たまねぎ 見た目も良い 良く育っている12月31日 晩生のたまねぎも 元気なり土寄せのかわりにもみ殻寄せすると 簡単であるし マルチにもなる昨年の雑草とりは12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ01月05日 雑草とりをしておいた02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月24日 雑草とりして すっきり昨年は4回の雑草とりをしたが 今年はまだ0回マルチともみ殻だと 雑草も生えてこないなあ やっぱし マルチは役に立つなあ01月18日 晩生のたまねぎ 150本 元気なり 雑草もなし01月24日 中生の苗 50本も 元気なり02月08日 早生 やや すこし 大きくなってきつつあるなあ02月08日 赤たまねぎ げんきになってきている02月15日 晩生のたまねぎ やや おおきく なってきている02月22日 赤のたまねぎも やや おおきくなってきている03月07日 赤のたまねぎ 下の方が赤くなってきている さすが 赤玉だなあ03月08日 おくてのたまねぎも まあまあ 育ってきている03月14日 早生のたまねぎ まだ 太ってはきていない まだまだ 時間がかかりそう03月15日 赤のたまねぎ これも いい感じになってきている03月22日 赤のたまねぎ あまり 変わりはなし03月22日 おくて これは 一番生育が遅いな03月29日 なかて これは まあまあ それなりに成長してきている03月29日 わせ すこし大きくなってきている もう すこしかかりそう04月19日 赤たまねぎ まだ まだ 小さいかな もうすこし時間がかかりそう04月19日 早生のたまねき すこし 玉ができてきている04月26日 早生のたまねぎ もう 収穫してもよさそうになってきている04月29日 早生のたまねぎ 初の収穫をした05月03日 2回目の収穫をしておいた05月10日 赤たまねぎ トウ立ちをしてきている05月16日 早生のたまねぎ 3回目の収穫をしておいた05月17日 晩生のたまねぎ トウ立ちしてしまった05月17日 早生のたまねぎ 4回目の収穫をしておいた05月23日 赤たまねぎ 収穫をした05月23日 中生たまねぎ 収穫をした たまねぎ トウ立ちしたので どんどん 収穫していこう05月30日 晩生のたまねぎ のこりも収穫しておいた05月31日 中生のたまねぎ 残りも収穫をしておいた05月31日 赤のたまねぎ これも 残りを収穫しておいた今年のたまねぎ まだ 苗はうっていない が 畑の場所は決定マルチをつけて 用意をしている タマネギの苗はhcでの販売される苗を買う予定 良い苗がうられていたら 即 植え付けできる体制になっている まあ 来月なので ゆっくりとしよう今年の最後の植え付けのたまねぎ まだまだ 時間がある ゆっくり しようもう 隣の畑では 種まきをしている発芽して 自分で苗つくりしているはた坊は hcの苗が予約すると 貧弱なものがくるのでhcの良い苗を探して それを買うことしよう昨年の苗は良くなかった今年は良い苗をかってこよう売り出しされれば 買い物しにいこう早生中生晩生と 3つ 植え付ける予定なり今年の作業は タマネギの苗の植え付けもみがら 拾いが 残っている今年の作業の予定は あと2つのみnetでの タマネギのコツをみておいたタマネギの育て方のコツ◾長期保存するには、貯蔵性に優れた品種を選択する。◾必ず適した時期(11月中旬)に植え付けを行う。◾苗は、長さは20~25cmくらい、太さは4mmか5mmくらい、根が良く伸びているものが良い。◾苗の植え付けた後、株元を押さえて鎮圧する。◾4月以降の追肥は行わない。◾霜が降りる前までに、もみ殻やくん炭、バーク堆肥などを株元に敷いておく。◾霜で持ち上がってしまった場合、株元を押さえて鎮圧する。◾全体の株の7割~8割の葉が倒れたら収穫する。◾晴天が続いて土が乾いた時に抜き、そのまま畑に2日~3日置いて乾燥させる。◾雨の当たらない風通しの良い場所に束ねて吊るすか、またはネットに入れて吊るして保存する。なるほどねえ はた坊
2015.10.25
コメント(0)
-

たかな g-01の残りの物 なんとか残っている 東日本大震災4年と7か月と14日後に
昨年また hcで 高菜の種をかってきた9月から 種まきをしよう08月31日 庭で種まきをした09月04日 発芽してきている09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた弾四弾の種まき09月21日 また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した第五弾の種まき09月28日 またまた 種まきをしておいた10月05日 発芽した10月12日 畑に移動した M-06の畑に植え付けをした第一陣のタカナ 4株 g-03 まあまあ 大きくなってきている 収穫しても よさそうになってきている第二弾の 15株 g-07/09も そろそろ 成長してきている第三弾の 0株 m-20のも ちいさいが 無事だったが なくなってしまった第四弾の 10株 m-06のも ちいさいが まあまあ 無事 第五弾の 4株 m-07のも ちいさい すこしだけ 無事 合計で33株がある 大きいのは4株で そろそろ 収穫できそう11月09日 大きいのは収穫できるサイズになりつつある 追肥をしておいた11月22日 初の収穫をしておいた まあまあ なり11月29日 2回目の収穫をしておいた12月06日 3回目の収穫をしておいた12月13日 4回目の収穫をしておいた12月23日 5回目の収穫をしておいた12月31日 6回目の収穫をしておいた01月12日 7回目の収穫をしたおいた01月18日 8回目の収穫をしておいた01月24日 9回目の収穫をしておいた02月01日 10回目の収穫をしておいた02月08日 11回目の収穫をしておいた02月15日 12回目の収穫をしておいた02月22日 13回目の収穫をしておいた03月01日 14回目の収穫をしておいた03月08日 15回目の収穫をしておいた03月14日 16回目の収穫をしておいた03月22日 17回目の収穫をしておいた03月29日 18回目の収穫をしておいた04月04日 19回目の収穫をしておいた04月12日 20回目の収穫をしておいた04月19日 21回目の収穫をした そろそろ 御終いになりそう今年08月29日 hcで種をかってきた 庭て種まきをしておいた今年もタカナ たくさん 育てよう09月05日 発芽したので 畑に移動した g-1/3に植え付けた第二弾09月05日 庭での種まきをしておいた09月12日 発芽したので畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた第三弾09月12日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽したので m-06の畑の畝に移動した第四弾09月20日 庭での種まきをしておいた09月27日 発芽した m-06の畑に移動しておいた在庫g-01 3本m-20 10本m-06 2本10月18日 g-01のたかな 残りは3本だけなり 追肥をしておいた東日本1震災 3月11日発生10月25日は既に4年と7か月と14日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------少子化と性欲 生物が子孫を作るのは、個別の個体(たとえば一組の夫婦とか一人の女性など)の意識ではなく、集団としてその生物が数を増やすべきかどうかという意識が本能に働きかけて決まるものである。このような「集団性の意識」は、誕生と死の両方に強く働く。たとえば、死の方では、哺乳動物のメスが生理が終わったらすぐ死んだり、一夫多妻制のオスでボス争いにまけた「はぐれ」が短命であることから分かる。誕生の方では、もともと人間の男性の性欲は女性からの働きかけ(誘導型性欲)なので、女性が産む気にならないと男性に働きかけず、従って男性の性欲がわかないので出生率は落ちる。戦争などの人口を損失する状態では女性は多くの子供を産まなければならないと感じて、寝化粧をする。「すっぴんでいる」というのは女性が男性に送るサインとしては「産みたくない」というものだ。動物では一般的にはオスに性欲があるので、オスが出生率を決めるので、オスの方が一般的に立派で美しい。しかし、人間は頭脳の大きさが大きくなるにつれて男性の性欲が失われたのが大きな要因となっている。また、女性の体内に入った精子が卵子に到達するか、その時に遺伝的に女性か男性かという問題も解明されていないところが多い。たとえば、男児の方が着床率、胎児の生育、出生時の事故、出生から成人までの事故死などがおおいので、現在の社会では、着床率は男児の方がかなり多く、出生時の男女比は1.03と言われる。一ヶ一ヶの精子が胎児の健康状態や日本の交通事故死の割合などを理解しているわけではないので、集団的な力が精子の運動性を決めていると考えられる。現代の日本は戦争がなく、長寿化し、人口密度が経済発展段階から見ると高い。従って、社会全体に「子供はいらない」という共通概念が生じているのは確実である。社会の発展段階から見ると、少し前までは、「食糧があるだけ子供を生む」(西アフリカタイプ、一人の女性でだいたい5.2人)、「バランスをとりながら人口増加へ向かう」(かつての日本タイプ、一人あたりの女性で3人程度)、それにフランスなどの成熟国(1.5人程度)がある。これらについては社会学的には、女性の教育程度や育児環境ということが問題になるが、自然科学的には当然のことで、「産む必要がなければ産まない。それができないぐらいなら男女の産み分けなどできるはずもない」と言うことになる。国の施策は生物学、統計学、社会学、哲学、などを総合して作るべきで、現在のように密室である特定の人が利権を背景に政策を議論していると日本の発展にはつながらない。(平成27年10月17日)ふむふむはた坊
2015.10.25
コメント(0)
-

秋のせろり また2本 育てている お茶 おべんきょうその37
今年のセロリ01月03日 その後も 生育は良し02月01日 その後も 生育している いい感じ02月02日 3回目の収穫をした02月15日 4回目の収穫をした03月01日 5回目の収穫をした03月08日 6回目の収穫をした03月15日 7回目の収穫をした これで 御終いになった今年04月29日 せろり 2本をかってきた m-06に植え付けた05月17日 その後も 生育してきている 無事なり06月20日 せろり しっかりと 大きくなってきている そろそろ 収穫できそうになってきている せろり 今年の植え付けた分も そろそろ 収穫できそうになってきている06月27日 せろり そろそろ 収穫できる 来週には 収穫しよう07月04日 収穫をしておいた秋のセロリ09月27日 hcで また2本のセロリ 買ってきてうえた10月10日 その後 無事なり10月18日 まだ 小さいが 無事なり追肥をしておいたお茶 おべんきょうその37他の材料と混合した茶花茶 ジャスミン茶(茉莉花茶、さんぴん茶)菊洱(ジュアル): プーアル茶に菊茶を加える。蓮茶:茶葉に蓮の花の香りをつける。ベトナムでポピュラーな飲み方。バター茶 :茶以外にバター、塩を含む。ミルクティー: 紅茶に牛乳、砂糖などを加える。 チャーイェン :タイではポピュラーな茶の飲み方であり、茶に加糖練乳(コンデンスミルク)を加える。果実茶 レモンティー: 紅茶にレモン、砂糖などを加える。アップルティー: 紅茶にリンゴ、砂糖などを加える。但し、レモンティーとは少し手順が異なり、果肉の代わりに果汁やジュースを加えることもある。鴛鴦茶 : 茶とコーヒーを混合する。マサーラー・チャイ :インドや東南アジア諸国にて広く普及している茶の飲み方。カルダモン、クローブなどの香辛料、牛乳を含む。前述のミルクティーと要素は近いものの香辛料を加える点では大いに異なる。玄米茶ぶくぶく茶 :炒米を煎じてさんぴん茶に加え、泡立てた後にピーナッツ粉末を振りかけて供することが代表的。日本の沖縄県。擂茶 :客家の伝統茶で、落花生、ゴマ、玄米などを入れる。八宝茶(三泡台) :回族の伝統茶で、砂糖やナツメなどを入れる。三道茶 :ペー族の伝統茶で、砂糖やルーシャンなどを入れるものもある。はた坊
2015.10.25
コメント(0)
-

となりの水田 雑草だらけで 展示会のようになってきている おうむ おべんきょうその09
となりの水田おやじさん入院してお米つくりやめている息子さんも忙しいので 米つくりやめているで 雑草どんどん 増えて どんどん はピッこっているすごいなあ雑草のパラダイスになってきている雑草とりもしていないので 自然にもどりつつあるなあ荒れ放題だと 何か住み着きそうになってきている鳥が住処にしてしまいそうだなあいろんな 雑草の展示会みたいになっているおうむ おべんきょうその09系統学ヒインコは従来オウム目第三の科であるヒインコ科(Loriidae) と見なされていたが[9]、現在ではほとんどの場合インコ科(Psittacidae)の亜科と考えられている[10] 。またヒインコを含むすべてのオウム目の鳥を巨大な単一の科の範疇に収める考え方もある。現在主流となっている見方は、ヒインコが亜科としての位置を正当化するに足るだけの差異をもっているとするものである。しかしこのきわめて顕著な差異が一意的な深い分岐の証拠ではなく、むしろもっと近縁の系統との差異と量的には違っていないと考えている者もある。生物地理学によればヒインコは明瞭に区別できる系統と考えるのが最良であり、おそらくオウムほど分岐した種ではなく、しかしそれでも他のインコの種からは隔たっていることが示唆される。1998年のミトコンドリアDNAや[11]、2005年のZ染色体の spindlin 遺伝子の分析[12] などのような最近の分子生物学的研究から、どんな証拠からも現存しているインコの系統相互の関係がほとんどの場合解決不能であることがわかった。予想外の結果は、spindlin 遺伝子の配列データから計算系統学により信頼性のある位置決定が可能な、現存しているインコの間での唯一の主要な分岐が起きたのがニュージーランド産インコ - フクロウオウム、ミヤマオウム、カカ - のいずれかとその他のインコの間であったことである[13]。はた坊
2015.10.25
コメント(0)
-

もみがら 出回りだしている 大豆 おべんきょうその05
先週より もみがら 出回りだしたとなりの畑の人も もみ殻 畝にいれて 耕作をしているいいなあもみがら たくさんほしいものもみがら 結構とやくにたつ 11月には もみがら 大量にでるので それを待っている 来月が 楽しみである大豆 おべんきょうその05根粒菌との共生ダイズを含む一部のマメ科植物は根に根粒もしくは茎に茎粒を持ち、根粒菌という細菌が共生している。根粒菌は植物からリンゴ酸などの効率のいい栄養分をもらって生活の場を提供して貰う代わりに、大気中の窒素を植物にとって使いやすいアンモニアに転換(窒素固定)する。窒素は植物にとって必須元素であり、肥料として取り入れる成分の一つであるが、自然界では一部の細菌と雷などでしか使用可能形態に転換できない。特に根粒ではその能力が高いため、それを持つ植物は自ら窒素肥料を作ることが出来ることになり、そのような植物はやせている土地でもよく育つものが多い[5]。このダイズの窒素固定能を有する根粒菌との共生により十分な量の窒素分を吸収し、豊富なアミノ酸を産生でき、ダイズはその種子に他の植物には見られないような豊富なタンパク質を含有させている。共生成立までの過程に於いて、Nodファクターと受容体による経路[6][7]とIII型分泌系による経路[8]の複数の経路が有ることが解明されている。はた坊
2015.10.25
コメント(0)
-

あかまんま いぬたで tpp と農業
あかまんまいぬたでイヌタデ(犬蓼、学名: Persicaria longiseta)タデ科イヌタデ属の一年草。道端に普通に見られる雑草である。和名はヤナギタデに対し、葉に辛味がなくて役に立たないために「イヌタデ」と名付けられた。赤い小さな果実を赤飯に見立て、アカマンマとも呼ばれる。tppと農業TPP成立でも、日本の農家は変わらない大前研一の日本のカラクリ 「フードバレー」と呼ばれる産業クラスターオランダ農業の3つ目のシフトが「イノベーション」である。現在のオランダの農業は大規模なガラスハウスなどを活用した施設園芸が中心で、オランダ国内の5カ所に生産者、研究機関、関連企業が集積した、「グリーンポート」と呼ばれるクラスター(集団)が形成されている。そこで展開されているのがITを活用したスマートアグリだ。たとえば大規模施設園芸では天然ガスで発電して、排出される「熱」はハウス内の暖房に、「CO2(二酸化炭素)」はハウス内の植物の光合成に利用されている。もちろん「電力」は施設の動力として活用されるが、余剰分は売電する。火力発電中心のオランダでは全発電量の10%が農業事業者による発電で、売電は農業経営を支える重要な事業であり、「半農半電」といわれるほどだ。オランダには温室環境制御システム開発や温室設備の世界的なメーカーが揃っていて、農作物ばかりではなく、各種の農業生産技術やシステムなどスマートアグリ設備を世界に輸出している。オランダ農業のイノベーションの推進役を果たしてきたのは、ワーヘニンゲン大学を中核とした、「フードバレー」と呼ばれる農業と食品の産業クラスター。フードバレーには食品関連企業約1400社、科学関連企業約70社、そして約20の食品関連の研究機関が集結、約1万人の研究者によって多様な研究・事業化プロジェクトが行われている。日本からはキッコーマンや日本水産、アサヒビールやサントリーなどが参画。また種苗分野の研究開発も強く、種子クラスターの「シードバレー」もあって、フードバレーとも綿密に連携している。こうした最先端の研究開発と農業関連企業、現場の生産者をつなぐ存在が「農業コンサルタント」で、技術指導などでイノベーションを現場の成果に結びつける重要な役割を果たしている。自由化、集中と選択、そしてイノベーションの結果、オランダ農業は劇的に変わった。穀物生産から脱却して、付加価値の高い農産物に特化したのだ。結果、広大な農地を活用して小麦やトウモロコシ、大豆などの穀物を大規模生産するボリューム型の農業大国とは対極的な、クオリティ型の農業先進国に生まれ変わったのだ。次回、日本の農業はオランダモデルから何を学ぶべきなのか、考えてみたい。ふむふむはた坊
2015.10.24
コメント(0)
-

じゃがいも 抜いても 抜いても 生えてくる tppと農業
じゃがいも植えていないじやがいも残っていたイモのちいさいのがどんどん発芽してくるかなりカットして抜いていたがそれでも かなり 生えてくるもう 大きくなっているのもあるのでイモがあれば 収穫できそうだなあtppと農業TPP成立でも、日本の農家は変わらない大前研一の日本のカラクリオランダは九州程度の面積しかない オランダの農業関連施設を視察する安倍晋三首相(2014年3月)。(写真=AP/AFLO)安倍政権は成長戦略に農業改革を掲げ、今後10年で農業所得を倍にするという。しかし、時間と補助金をかけて小出しに市場開放しても、再生できないことは実証済み。やるなら2年なり3年なり猶予期間を決めて、一気呵成に進めるしかないと私は考える。市場開放の結果、国際競争に敗れて一時は壊滅的な打撃を受けながら復活を果たした産業といえば、(セイコーとシチズンにやられた)スイスの時計、(日本の繊維産業にやられた)イタリアのアパレル、フランスのブランド品などを思い浮かべやすいが、農業にも好例がある。オランダである。九州程度の国土しかないオランダが世界第2位(11年)の農業輸出国であることは案外知られていない。農業輸出額1位はアメリカで、3位がドイツ、以下、ブラジル、フランス、アルゼンチンと上位は国土の大きい農業大国ばかりで、農地面積が限られたオランダの奮闘ぶりが際立つ。ちなみに日本は57位で、輸出額は10兆円を誇るオランダの30分の1ほどしかない。実は30年ほど前の86年にポルトガルとスペインがEC(欧州共同体)に加盟した際、オランダ農業は危機的状況に陥った。安価な輸入農産物が国内に流入するようになったからだ。そこからいかにしてオランダ農業は再生し、世界最強の農業輸出国へ変貌を遂げたか。同じく農地面積が狭く、TPP前夜を迎えている日本にとっては大いに参考になるはずだ。オランダは農業の競争力を強化するために3つのシフトを断行した。まず1つは「自由化」だ。農業保護をやめるとともに、日本の農林水産省に当たる農業・自然・食品安全省を解体して経済省(日本でいえば経済産業省)に統合して、農業部、酪農部、水産部という3つの部局に編成し直した。農業も産業だというなら考えてみれば当たり前のことだが、これまた今の日本では想像することさえ難しい英断だ。さらに公的機関(DLV Plant社)による農業指導事業を民営化している。要するに農業を産業の1つととらえて、「競争力のある強いものだけが生き残るべし」という方針を打ち出したわけだ。2つ目が「選択と集中」である。生産品目を高付加価値品目にシフトして、農地を集約化。現在ではトマト、パプリカ、キュウリの3品目で施設野菜の栽培面積の8割を占めている。農家のサバイバルと大規模化が進み、農業の経営体数は80年には15700社あったものが、10年時点では7100社に半減しているふむふむはた坊
2015.10.24
コメント(0)
-

野菊 いろいろあって350もあるので 何が何やら tppと農業
野菊菊といっても いろいろとあるらしいnetでみると菊と野生種一般に栽培されている菊は、和名をキク(キク科キク属 Dendranthema grandiflorum (Ramatuelle) Kitam.)と言い、野生のものは存在せず、中国で作出されたものが伝来したと考えられている。したがって、菊の野生種というものはない。しかしながら、日本にはキクに似た花を咲かせるものは多数あり、野菊というのはそのような植物の総称として使われている。辞典などにはヨメナの別称と記している場合もあるが、植物図鑑等ではノギクをヨメナの別名とは見なしていない。現在では最も身近に見られる野菊のひとつがヨメナであるが、近似種と区別するのは簡単ではなく、一般には複数種が混同されている。キク科の植物は日本に約350種の野生種があり、帰化種、栽培種も多い。多くのものが何々ギクの名を持ち、その中で菊らしく見えるものもかなりの属にわたって存在する。tppと農業TPP成立でも、日本の農家は変わらない大前研一の日本のカラクリ 大幅な生産過剰になったために71年度から始まったのが減反による生産調整。かつて減反政策に参加した農家に10アール当たり15000円の補助金を一律に払ってきたのだ。半世紀も続いてきた減反政策は2018年度にようやく撤廃される予定だが、当然至極。米価を高止まりさせるために補助金を払って生産調整するほうがおかしい。余るなら生産をやめればいいし、価格が下がるなら消費者に還元すべきなのだ。70年には1000万人以上いた農業就業人口は今や226万人(全就業人口の2~3%)まで減っている。しかも、そのうちの3分の2は65歳以上。すでに年金をもらっているわけで、日本のコメ農家の平均所得の構成比を見てみると、年金所得は農業所得の3倍以上だ。年金をもらって片手間でやっている人たちがTPPを奇貨として農業改革をするかといえば、するはずがない。しかも農地を持つ農民である限りは相続税がかからないから、農民であることをギブアップしない。代替わりしても補助金だけはもらい続けるわけだ。耕作放棄地は年々増えている。しかし、企業が参入しやすいように政府が買い上げて農地を集約しようとしても、これがなかなか進まない。農民が手放さないからだ。農業も産業である。産業である以上、競争力がなければ潰れるのは当たり前。戦後のひもじい時代に胃袋を満たしてくれたとはいえ、とうに崩壊している農業を助け続けるのは納税者にとって永遠の重荷に、消費者にとっては大きな負担に、なるだけだふむふむはた坊
2015.10.24
コメント(1)
-

ノイチゴ へびいちご 拡大すると まあまあ 綺麗な実だなあ tppと農業
野いちごへびいちごともまあ 小さいが 実がよくなっているヘビイチゴ(蛇苺、学名:Potentilla hebiichigo)バラ科キジムシロ属の多年草。語源については実が食用にならずヘビが食べるイチゴ[1]、ヘビがいそうな所に生育する[2]、イチゴを食べに来る小動物をヘビが狙うことからなど諸説がある。毒があるという俗説があり、ドクイチゴとも呼ばれるが、無毒。以前はヘビイチゴ属に分類されDuchesnea chrysanthaと呼ばれていた。特徴畦道や野原などの湿った草地に自生し、アジア南東部と日本全土に広く分布する[1][2]。茎は短く、葉を根出状につけるが、よく匍匐茎を出して地面を這って伸びる。葉は三出複葉、楕円形の小葉には細かい鋸歯があって深緑。初夏より葉のわきから顔を出すように黄色い花を付ける。花は直径1.5cmほどで、花弁の数は5つと決まっている。花期は4月から6月[1][2]。花のあとに花床が膨らんで光沢のない薄紅色の花床となる[1]。果実の表面には多数の痩果が付き[1]、赤色で球形、イチゴに多少似たものがなる。毒は含まれないので食用可能だが、あまり味が無いため食用(特に生食)には好まれない[1][2][3]。ジャムに加工可能。全草や果実を乾燥させたものは漢方の生薬として利用される。TPP成立でも、日本の農家は変わらない大前研一の日本のカラクリ穀物にすぎないコメを聖域化してきた日本TPP(環太平洋経済連携協定)交渉を巡る日米協議。日本はコメ、アメリカは自動車分野という互いの聖域で激しい攻防を繰り広げてきたが、落とし処が見えつつある。コメの市場開放についていえば、関税を維持して米国産米の特別輸入枠を設けるとか、関税を引き下げるにしても10年かけて1%ずつ下げる、といったレベルの最終合意になりそうだ。アメリカは議会対策もあるので日本側と生温い妥協点を見出すだろうが、TPPの交渉結果が日本の農業に危機感を与えて改革を促すようなインパクトをもたらすことはないだろう。かつてのGATT(関税貿易の一般協定)ウルグアイ・ラウンドでコメの市場開放を迫られたとき、日本は778%というコメの関税を維持する代わりに毎年一定量の外米を無税で輸入するミニマムアクセスを義務付けられて、関税も毎年100%ずつ下げて最終的にゼロにすると約束させられた。しかし最終的にはコメの関税は1%も下がっていない。また購入したコメの有効利用方法も見出されていない。当時の自民党政権はウルグアイ・ラウンド対策として20年間で42兆円という巨費を投じて農業基盤整備事業を行ってきた。しかし日本の農業の生産性も国際競争力もまったく向上しなかった。世界の相場ではコメは完全にコモディティ化していてトン単位で取り扱われている。キログラム当たりの産地価格は20円程度。日本のコメはキログラム200円以上する。日本のコメの競争力は底の底で、778%というバカ高い関税と減反政策にかろうじて守られてきたのだ。日本の農業政策の最大の問題点は穀物にすぎない、すなわち付加価値の少ないコメを中心に置いて、聖域化してきたことだ。戦後直後は農業就業人口の割合は50%を超えていたし、コメ農家も多かった。日本全体が飢えていたから、それでもよかった。しかし食の多様化が進んで、コメの消費量は1963年の約1300万トンをピークに年々減少、今や800万トンほどしかないふむふむはた坊
2015.10.24
コメント(0)
-

夏の残り物のブロッコリー まだ 収穫している 東日本大震災4年と7か月と13日後に
ブロッコリー やはり 夏のブロッコリーは花蕾が貧弱である春ののこりのブロッコリーが育っていたが収穫は2-3回のみ貧弱なものしかできないなあ やはり ブロッコリーは 秋に植えて冬から春に 収穫するのが 一番だなあ夏はだめだなあ09月20日 そのブロッコリー 秋になって 収穫できるものがある とりあえず 収穫をしておいた秋になると 涼しくなるので 花をすぐにさかせずに 大きくなってきている いい傾向だなあ収穫できるのは 収穫しておこう09月27日 すこし収穫をしておいた これで 御終いだな10月11日 また すこし収穫できた まだ いけるかも10月18日 また すこし収穫をした 花だらけだなあ ぶろっこりーの残り物 まだ 収穫できそうだなあ東日本1震災 3月11日発生10月24日は既に4年と7か月と13日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------「少子化」という問題は存在しない 出生率を上げなければならないという理由は、「年金」、「労働力」、「経済力」などと思われるが、多くの国民はむしろ「なぜ、少子化が問題か」という疑問を持っている。おそらくマスコミが政府に追従しているだけと考えられる。またその原因は「結婚のしにくさ」、「育児のしにくさ」にあると言われているが、子供を産むというのはそのような社会的制約で決まるわけではなく、より生物的な原因と考えられる。 日本の人口密度は先進国の中でトップで、大都市にすむ人の割合もトップである。しかも森林面積率は日本は70%近いので、実際的な人口密度はさらに高い。日本の可住面積率は34%で、ドイツが69%だから、可住面積あたりの人口密度では日本が平方kmあたり1027人、ドイツが334人で、その比率は3倍程度になる。だからもし日本がドイツ並みの可住地域人口密度にするには、現在の1億2千700万人を4100万人程度にすることを意味している。現在のままでも日本の人口が4000万に近づくには100年程度かかると推定されているが、それでもドイツと同じになるということだ。それではなぜ、日本では少子化が問題になるのだろうか? それはマスコミや専門家も含めた日本人全体が「政府に単純に追従する」からだ。まず労働力不足は起こらない。それは、1)電子化、2)女性の就労率の上昇、3)定年制度の撤廃、が予想されるからだ。武田が名古屋大学の時代に学生と、この3つで推定されている労働生産性や家族構成などから計算してみたが、「人口減少より実質勤務者の増加が大きく、当面、産業に影響を与えない」という結果が得られた。つまり、少子化、電子化、女性就労率、定年延長の4つを総合的に考慮した国家の計画は存在しないで、情緒的に「少子化はダメ」と言っているに過ぎない。また、年金制度は現在の積立ー賦課型では少子化の有無にかかわらず破綻するので、年金の廃止と生活保護(年齢や性別によらないネット方式)に変えなければいけないので、これも少子化は問題ではなくなる。いずれにしても、生活の質、子供を産むという生物学的、また日本社会の発展から言って少子化は問題ではない。日本社会の野蛮性が残っているだけ。(平成27年10月17日)ふむふむはた坊
2015.10.24
コメント(0)
-

彼岸花 昔はやくにたつものだったが 今は見てるだけ 茶 おべんきょうその36
彼岸花の葉 たくさん でてきている普通の植物は 春に種から発芽して 成長して 花を咲かせて 実をつくり 種をばらまいてしまうが彼岸花の球根のものは 根っこに養分があるので最初から 一気に花を咲かせてしまうそして 葉もどんどん出してくるこれで 葉が出たので これから 養分をため込むことになる今 葉が出てくると 回りの植物は枯れてしまっているので太陽の光をひとりじめなかなか 賢いやり方であるおまけに 球根を食べられないように毒をもつなんてねえすごい賢いやつであるこの彼岸花を薬にしたり 毒があるので米の水田の畔にうえてヒガンバナの有毒性や悪臭を利用して、モグラやネズミなどから田んぼのあぜ道を守る目的で植えたとも利用している人間は もっと 賢いということだなあnetをみるとヒガンバナは日本の本州以南、中国の温帯に広く分布するヒガンバナ科の多年草で、ヒガンバナの鱗茎を用いる。石蒜(セキサン)ともいう。 9月下旬、秋の彼岸頃に鮮やかな赤い花をつけるので彼岸花と呼ばれ、赤い花を意味する曼珠沙華(マンジュシャゲ)という別名もある。 有毒植物であり、かっては鱗茎をすりつぶして水にさらし、毒抜きをすると食べられるため救荒食物として利用されてきた。ヒガンバナの鱗茎にはリコリン、ホモリコリン、ガランタミンなどのアルカロイドが含まれ、誤って食べると、 嘔吐、下痢、流涎、神経麻痺などが起こる。 石蒜は民間では生の鱗茎をすりおろし、足の裏に貼って用いた。 成分のうちリコリンはジヒドロリコリンの製造原料となり、ガランタミンも利用されている。リコリンは強い嘔吐作用があり、、ジヒドロリコリンは催吐作用があるので、毒性が強い。 何か他の毒物を飲み込んでしまった時に救急的に吐き出させる必要があるときに新鮮な鱗茎1~3gを使うほかは家庭ではむやみに用いてはならない。彼岸花 すごい役に立つものだったらしいが 今は見てるだけ茶 おべんきょうその36成分と効能テアニンにはリラックス効果[107]、抗ストレス作用[108]、睡眠の質の改善[109]月経前症候群(PMS)の軽減[110]、認知活動や気分の改善[111]の作用がある(詳細はテアニンを参照のこと)。モンゴルなど野菜が不足する地域では、茶を飲む習慣があり、1日に10杯程度飲むと言われてているが、遊牧民が愛飲するレンガ状に固められた茶葉を分析するとビタミンはほとんど存在しなかった[112]。むしろ、遊牧民が夏場に愛飲する馬乳酒中の乳酸菌がビタミンCを生成するため、野菜や果物を摂れない遊牧民のビタミンC補給源となっていると言われている[113][114]。はた坊
2015.10.24
コメント(0)
-

さといも 土をかけて 保護をしておいた おうむ おべんきょうその08
さといも昨年01月19日 サトイモ 2回目の収穫をしておいた03月09日 hcで サトイモの白目大吉を買ってきた04月17日 昨年の残りのサトイモの発芽 2本の芽が出てきている04月30日 白芽大吉の種イモ m-08の同じばしょに植え付けをしておいた05月03日 納屋に残っていた種イモがあったので これも畑に移動して植え付けた植え付けた種イモからの発芽はまだない しかし 昨年の残りのサトイモが どんどん 発芽してきている ブロックのまわりにも3本が発芽してきている同じ場所だけど まあ なんとか なるだろう今年もサトイモ 水路の横の溝の場所で 育ててみよう06月02日 水路の水がながれるようになった これで 安心なり06月08日 サトイモがたくさん発芽している 今年も無事に育ってくれそう06月22日 その後 発芽したのは かなり多くなっている 見た目もにぎやかになってきている サトイモ 今年も昨年と同じ場所だけど 今の所は良く育ってくれている07月20日 その後も順調なり 大きくなって 背も高くなってきている 見事なものだなあ08月02日 その後も 大きくそだっている みずの心配はいらないようだ08月17日 その後も さといも 元気なり 茎はあまり太くないけど 無事なり08月24日 その後も さといも 元気だ 虫がいた 黒いの1匹 逮捕しておいた08月31日 雑草とりして 追肥した となりのヤマノイモよりも背が高くなった雑草とりをしておく追肥もした09月21日 その後 秋になってきたので 勢いもやや弱くなってきている10月05日 その後 秋になって 涼しくなってきている 葉もすこし枯れだしてきている10月19日 その後 葉も スキスキになってきつつある さといも ゆっくりと 収穫する予定11月になってから 掘り起こそう11-12-01-02月と ゆっくり 収穫する予定11月02日 さといも 初の収穫をした まあまあ たくさん出てきた11月16日 さといも 2回目の収穫をした これも まあまあ12月01日 さといも もみがらがもうないので サトイモには もみがらは なし12月06日 さといも その後も葉は枯れてきている 12月23日 サトイモ 完全に葉は枯れた葉もかれつつある サトイモの横には ヤマノイモもあるので サトイモと ヤマノイモ 12月には 2回ずつ 収穫していこう12月28日 さといも 3回目の収穫をした今年01月12日 さといも 収穫しようかな と 思いながら 結局 寒いので やめた寒くなると 外にでるのが どうも おっくうになるなあ 01月24日 さといも またもや 収穫しようかなと思いながらも外は寒い また あとにしよう とうとう 芽が出てきている04月04日 残りのサトイモ 芽が出てきている そのまま サトイモ 今年も育てていこう04月12日 その後も どんどん 芽が大きくなりつつある04月19日 サトイモ 発芽が どんどん 続いていて かなり増えている サトイモだらけになりそう04月26日 さといも 芽も はっきりとわかるくらい 大きくなってきつつある 元気なもの05月16日 発芽したサトイモ かなり大きくなってきている 混雑しすぎている05月23日 さといも 密集したまま 茂ってきている密集しているての゛ すこし 分散させよう05月31日 さといも 分割して すこし間隔をあけて植えなおしをやっておいた06月06日 そのご 雨がふって 元気になってきている06月13日 さといも 生育がよくなってきている 水路に水が流れるようになり 元気なり06月20日 さといも 回りのサトイモと比べると とんでもなく 大きくなっている これはすごいなあ06月21日 それにしても 今年のサトイモは育ち具合は良い サトイモ 小芋を植えるよりも 親イモを植えたほうが 育ち具合は良い サトイモは 親イモをうえたら 成長も収穫も良いということだなあ これは すごいわ06月27日 さといも 元気に どんどん 大きくなってきている07月11日 さといも 葉が とんでくなく 大きくなっきているなあ07月18日 横の水路にも 葉がかかってきている 良し07月25日 さといも まだまだ 伸びてきている昨年は発芽したのが6月08日だった が 今年は 発芽が 4月04日だった と いうことは 今年のサトイモ 昨年より 2か月も早く成長しているわけで大きいはずである 残りもののサトイモが発芽したので 発芽も早い 生育も早い08月01日 サトイモの葉 デカい デカい 猛暑でも水路の水が横を流れているので元気なり08月08日 さといも 茎をみてみた 細いが 数はすごいもの 密集しすぎているかな???08月22日 さといも 追肥をしておいた これで もっともっと 大きくなるぞ09月06日 さといも 葉が倒れているのがおおいので 紐で固定してじゃまにならないようにした09月12日 さといも 葉を紐で固定して まわりにじゃまにならないようにした これで 見やすくなった09月20日 さといも 今は葉をみているだけ 虫もいないし 絶好調みたい収穫は11月から まだ 先だなあ育ち具合は これまでで 最高の出来である が イモは収穫してみないと 判らない10月10日 雑草とりしていて さといも 1つ抜いてしまった10月12日 サトイモ 葉もやや元気がなくなりつつある 冬になってきているのかな10月18日 さといも 土をかけて イモが太りやすくなるようにしておいたおうむ おべんきょうその08系統学インコ科の下位分類群(たとえばヨウムを含むグループに対するセキセイインコの仲間の関係、といった)相互の関係についての理解はかなり確固としたものになってきているし、種相互の関係についての知見はここ数年で非常に改善されてきている。しかしインコ科における異なる系統を亜科と考えるべきなのか、それとも族と考えるべきなのかについてはいまだに論争が続いている。インコの化石や分子分岐学による年代決定では、その進化における主要な多様化と分岐の起きた時期を正確に決定するための十分なデータが得られず、このためさまざまな系統が実際には互いにどれくらい異なっているのか、そして進化によってどれほど素早く、また根本的に変化したのかを断定することは困難なのである。はた坊
2015.10.24
コメント(0)
-

m-06の青梗菜 ちいさい 大豆 おべんきょうその04
昨年01月05日 4回目の収穫 また 1個01月12日 5回目の収穫 こんかいも1個02月11日 6回目の収穫 また 1個だけ02月16日 7回目の収穫 3個02月23日 8回目の収穫 3個 これで おしまいに昨年08月10日 また hcで 種をかっきてた08月31日 追加で また hcて 種を買ってきた種まきは 9月より 今年はたくさん 収穫できるようにしよう苗の植え付け 水をしっかりと確保しておこう昨年は 栽培に失敗したので 今年は たくさんの青梗菜を つくるぞーーー08月31日 庭で 種まきを開始した09月5日 発芽してきている09月06日 G-03の畑の畝に植え付けをしておいた第二弾の種まき09月07日 庭で 第二弾の種まきをしておいた09月11日 発芽してきている09月14日 畑に移動した g-03などに植え付けをしておいた第三弾の種まき09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた第四弾の種まき09月21日 また 庭で 種まきをしておいた09月28日 発芽してきている10月05日 畑に移動した m-06の畑に植え付け これにて 種まきは終了10月12日 青梗菜 すこし生育してきている が まだまだ 小さいなあ まあ ゆっくりと成長していく予定 虫に強い 結構と大きくなってくれるので 楽しみである10月19日 その後 まあまあ大きくなってきつつある10月26日 その後 青梗菜は それなりに 成長してきている 見事なり11月09日 その後 青梗菜は かなり大きくなってきている 追肥をしておいた他の野菜もそれなりに成長してきている青梗菜 高菜 大根 カブラ ぶろっこりー 菊菜 ネギ 芽キャベツ そこそこ 大きくなってきている 11月12日 ちんげんさい もう 収穫してもいい 大きなサイズになっている 日曜には 収穫していこう11月15日 今年は青梗菜は良く育っている まずは 初の収穫 4個なり11月16日 2回目の収穫をした11月22日 3回目の収穫をした11月29日 4回目の収穫をした12月06日 5回目の収穫をした12月13日 6回目の収穫をした12月23日 7回目の収穫をした12月30日 8回目の収穫をした12月31日 9回目の収穫をした01月03日 10回目の収穫をした01月05日 11回目の収穫をした01月12日 12回目の収穫をした01月18日 13回目の収穫をした01月24日 14回目の収穫をした02月01日 15回目の収穫をした02月08日 16回目の収穫をした02月15日 17回目の収穫をした青梗菜の在庫 g-03 0個 m-20 0個 m-06 4個 合計 4個くらい まだ ある02月21日 残りの青梗菜 6個 大きく育っていた分 全部 ひよどりが 食べてしまっていた あらあら 6個ともに 残骸となってしまっていた02月22日 まだm-06に青梗菜があった すこし収穫をした 18回目の収穫03月01日 19回目の収穫をした これにて終了となった今年08月29日 hcで種をかってきた ついてに庭で種まきをしておいた09月05日 発芽したので 畑に移動した g-01に植え付けをしておいた09月20日 g-01のその後 ちいさいけど なんとか無事かな10月11日 ここのは まあまあ 生育してきている第二弾09月06日 庭での種まきをしておいた09月12日 発芽したので 畑に移動した m-20に植え付け第三弾09月13日 庭での種まきをやっておいた09月19日 発芽したので m-08の畑の畝に移動した09月27日 その後も 無事なり 小さいがこれから これから第四弾09月20日 庭での種まきをしておいた09月27日 発芽した m-06の畑の畝に移動した4回目の種まきをして畑に移動した これから 大きくなるのを待つのみ在庫g-01 8本m-20 4本m-08 7本m-06 8本すくないが すこし生育している10月17日 m-20のちんげんさい 残っている分の生育は良い10月18日 m-06のちんげんさい わずかしか 残っていない 少ないな大豆 おべんきょうその04特徴古くからの在来種、固定種が多く現存しており、マメ科の特性もあり、両性花で自家受粉可能であるため自家採種のしやすい植物である。その反面、連作障害を起こしやすいため、次の年は輪作を行ない、違う作物を作付けし、連作を避けるか、連作を行なうために消毒や土壌改善を行う等の対策を練らねばならず、日本国内においては、この事が栽培規模拡大への障害のひとつとなっている。ダイズは遺伝子組換え品種の割合が高く、2014年現在、世界におけるダイズの栽培面積の82%を組換え品種が占めている(ISAAA調査)[4]。はた坊
2015.10.24
コメント(0)
-

にら 26回目の収穫をしておいた 東日本大震災4年と7か月と12日後に
在庫 m-08 たくさんあるg-01 4つ 植えている そのた 種からのにらが生えている庭 結構と生えている韮 たくさんあるので 今年も 収穫する分は たくさんある在庫だけで 今年も たくさん 収穫できる楽しみだあーーーーーーーーーーあ01月12日 にら 冬なので 半分は枯れているが まあ こんなもの02月14日 にら 庭のにら 青々としている まあ 元気なもの02月14日 にら 畑のは枯れているが 風があたらない場所のは 青々としている02月22日 にら ブラの横のは 収穫できそうだなあ03月01日 にら 庭のにらは 青々としている 新しい葉も出てきている03月01日 にら 畑のも すこし 新芽も出てきそうな感じになりつつある03月22日 にら 庭のは もう 大きくなっている04月12日 にら 庭のも 大きくなっている 収穫はokである にら 風があたると枯れるが 風があたらない場所では 青々としている気候では 風は 馬鹿にならない 結構と影響をあたえているものだなあ1月と2月と3月は 収穫はなし03月08日 畑のにら そろそろ 新芽もすこし03月15日 畑のにら 新芽になりつつある03月22日 畑のにら 雑草を取り除いておいた 結構とあるものだなあ初のにらの収穫も そろそろ できそうになってきている03月29日 G-01のにら これも 成長してきている03月29日 M-08のにら 若々しくなってきている04月12日 g-01/m-08ともに 収穫できる もう 大きくなっている04月19日 g-01のにら もう 大きくなっている 04月26日 m-08のにら もう 収穫できる にら 今週より 収穫を開始しよう04月29日 今年も韮の収穫を開始 1回目の収穫をした05月06日 にら 2回目の収穫をした05月10日 にら あちこちに 若い韮が どんどん 増えてきている05月10日 にら 3回目の収穫をした05月16日 にら m-08のにら 十分に大きくなっている 雑草とりをして追肥しておいた05月23日 にら 4回目の収穫をした05月30日 にら 5回目の収穫をした06月06日 にら 6回目の収穫をした06月13日 にら 7回目の収穫をした06月14日 にら 8回目の収穫をした06月20日 にら 9回目の収穫をした06月27日 にら 10回目の収穫をした07月04日 にら 11回目の収穫をした07月11日 にら 12回目の収穫をした07月12日 にら g-01の韮は 元気になっている07月18日 にら m-08のにらに 花蕾がついてきている カットしておく07月19日 にら m-08のにら 雑草とりして 花蕾もカットして 追肥もしておいた07月20日 にら 13回目の収穫をした07月26日 にら 14回目の収穫をした08月01日 にら 15回目の収穫をした08月02日 にら m-08のにら しっかりとしてきている08月08日 にら 16回目の収穫をした08月15日 にら 17回目の収穫をした08月22日 にら 追肥をしておいた サトイモの日陰になっているが まあまあ良く育っている08月23日 にら 18回目の収穫しておいた08月29日 にら 19回目の収穫をしておいた09月05日 にら 20回目の収穫をしておいた09月12日 にら 21回目の収穫をしておいた09月20日 にら g-01のにら まだまだ 収穫はできる たくさんある09月20日 にら 22回目の収穫をしておいた09月27日 にら 23回目の収穫をしておいた10月03日 にら 24回目の収穫をしておいた10月04日 g-1のにら まあまあ 元気である10月10日 にら 25回目の収穫をしておいた10月18日 にら 26回目の収穫をしておいた畑で一番に元気なのは にら である東日本1震災 3月11日発生10月23日は既に4年と7か月と12日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------不幸になりたがる(2) 親子 親子の間には小さなケンカや諍いがあるけれど、それは大したことは無い。時々、深刻な言い争いになり、それが決定的な親子の断裂になることがある。特に小学校のころはさほどでなくても、思春期に入ると深刻になる。親子の意見が合うはずもなく、もし合えば子供は時代遅れになる。親子は意見を合わせる必要は無く、愛情があれば良い。小さい頃に「意見を合わせる教育」をするのではなく、「相手の考えを尊重して、相手の気持ちをくみ取る」という教育をすることが大切。どうしても譲れないという時を1,2回にするように計画しておく。両親の役割分担を作ることができれば、たとえば「頑固な親父」と「優しい母」として子供に接する。(平成27年10月14日)ふむふむはた坊
2015.10.23
コメント(0)
-

m-08の菊菜 8本が残っている 茶 おべんきょうその35
昨年 秋の菊菜hcでの種は 中葉くらいの菊菜をかってきておいた9月より 植え付けをしよう09月07日 種まきをした09月12日 発芽した09月13日 畑に移動した g-07の畑の畝に植え付けた第二弾09月14日 庭で種まきわした09月18日 発芽した09月20日 畑に移動した g-01-03の畝のとこに 植え付けをしておいた第三弾09月21日 庭で また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した g-07-09などに植え付けた第四弾09月28日 庭で追加の種まきをしておいた10月05日 発芽してきている10月12日 畑に移動した m-06の畑に植え付けた これにて 植え付けはお仕舞い11月09月 菊菜 生育はゆっくりとしている まあ こんなものかな11月30日 きくな かなり 大きくなってきている そろそろ 収穫もできそうだなあ12月23日 きくな 収穫はokとなっている そろそろ 収穫しよう01月12日 菊菜 初の収穫をした02月14日 そのご 様子見 あまり生育していない02月15日 様子見をしているが そろそろ 収穫しよう もう2-3回くらいは収穫できそう02月22日 菊菜 収穫しようと畑にいくと ひよどりに葉が食われていた あらあら葉がない ひよどりは 菊菜の葉も食べるのだなあ ありゃあまあ 参ったなあ03月08日 その後 菊菜 葉はまた 出てきている03月22日 収穫をしておいた もう 2-3回 できるかも05月17日 残っていた菊菜 花だらけなので 撤去とした これで 菊菜は畑になし今年 菊菜 今年も種まきの予定08月30日 hcで種をかってきた来週くらいから 種まきしていこう09月05日 庭で種まきをしておいた09月12日 発芽した 畑に移動して植え付けた g-07に移動した09月22日 その後も小さいながらも 無事なり第二弾09月12日 庭で種まきをしておいた09月19日 発芽したので m-08の畑の畝に植え付けた10月04日 その後も 無事なり在庫g-07 14本m-08 08本10月18日 m-08の菊菜は8本 残っている茶 おべんきょうその35成分と効能カテキンには実に多様な生理活性があることが報告されており、それらを列挙すると、血圧上昇抑制作用[100][101]、血中コレステロール調節作用、血糖値調節作用(詳細は以下を参照のこと)、抗酸化作用[102][103][101]、老化抑制作用[104]、抗突然変異、抗癌[100][101]、抗菌、抗う蝕[100][101]などとなる[98](詳細はカテキンを参照のこと。)。チャの葉や種子のテアサポニン(theasaponin)類、アッサムサポニン(assamsaponin)類には小腸でのグルコースの吸収抑制等による血糖値上昇抑制活性が認められた[105](詳細はサポニンを参照のこと)。動物実験で日本茶、特に番茶、中でも多糖類(ポリサッカライド)を有効成分とする番茶冷浸エキスでの血糖降下作用が認められた[106]。はた坊
2015.10.23
コメント(0)
-

m-20の大根 これも まあまあ 順調に生育中 おうむ おべんきょうその07
昨年度09月01日 hcで 大根の種をかってきた ついでに 庭で種まきをしておいた09月01日 間違って 聖護院蕪でなくて 大根の方を買ってしまった まあ ええか今年も大根の種まきを開始 まずは16potsx2=32potsで育ててみよう09月01日 大根 聖護院大根 ともに 庭で 弾ねきをしておいた09月04日 発芽 畑に移動 ともに32potsづつ m-08の畑に移動した09月08日 その後も無事 生育中 okだ ついでに 苦土石灰をまいておした大根 第二弾の種まきも開始09月08日 大根の第二弾の種まきを開始 16x2=32potsを種まきした09月13日 発芽している これも 畑に移動しよう09月15日 畑に移動した g-22の畝に植え付けた大根 第三弾の種まきもしておいた09月16日 庭で種まきをしておいた 16potsx2 09月22日 畑に移動した m-06に16pots m-07に16pots 分散して植え付けた大根は no1-32pot no2-32pots no3-32pots total 96pots聖護院大根は no1-32potの種まきをした これだけうえたらokだ育ち具合は これからだ 今のところは 無事に育っている まあ これだけ種まきしたら かなり育つだろう10月05日 一か月が過ぎた 聖護院大根 いい感じに育ってきている10月05日 大根の方も 一か月が過ぎている こちらも いい 感じ10月06日 2番目の大根 g-10の分も まあまあ 生育中10月13日 m08の畑の大根のねっこ かなり見えるようになってきた10月20日 m008の畑の大根のねっこ 50日でこれくらい10月27日 1本 ためしで 収穫した まあまあ初の収穫なり これから どんどん 収穫しよう11月02日 2回目の収穫をした 5本なり12月29日 17回目の収穫をした 丸の5本 やや小さくなってきている今年01月04日 18回目の収穫をした 2本 曲がっているなあ01月05日 19回目の収穫をした 丸4個01月12日 20回目の収穫をした 4本01月13日 21回目の収穫をした 丸7本01月18日 22回目の収穫をした 5本01月19日 23回目の収穫をした 丸7本01月26日 24回目の収穫をした 11本01月27日 25回目の収穫をした 丸7本02月01日 26回目の収穫をした 6本02月02日 27回目の収穫をした 小物の10本02月09日 28回目の収穫をした 6本02月11日 29回目の収穫をした 小物の丸の大根も おしまいかな02月16日 30回目の収穫をした 5本02月22日 31回目の収穫をした 6本03月02日 32回目の収穫をした 6本03月09日 33回目の収穫をした 4本03月16日 34回目の収穫をした 6本03月22日 35回目の収穫をした 6本03月30日 36回目の収穫をした 9本そろそろ おしまいになりそう今年の秋の大根また 種をかってきておいた今年も9月より種まきを開始しよう大根の種まき 第一弾だ08月31日 庭で種まきをした09月03日 発芽してきている09月07日 畑に移動するぞ 本日は大根の種まき 第二弾をやろう09月07日 種まきをするぞ09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-9などに植え付けをしておいた種まき 第三弾09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた種まき 第四弾09月21日 ついでに また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に植え付けた種まき 第五弾09月28日 また 種まきをしておいた10月01日 発芽した10月04日 畑に移動した m-07の畑に植え付けた種まき 第六弾10月05日 また 種まきをしておいた10月09月 発芽した10月12日 畑に移動した g-07などに植え付け これで 大根の種まきも終了した種まきした大根 かなり 大きくなってきている在庫もかなりある あちこち 植え付けてたので 大根だらけ10月19日 その後 大根 大きくなっているのもあり 収穫できそうになってきている10月26日 これくらいになっている もう 収穫できる11月01日 初の大根の収穫をした 曲がりもすごい が まあまあ 大きくなっている11月02日 2回目の収穫をした11月07日 3回目の収穫をした11月15日 4回目の収穫をした11月16日 5回目の収穫をした11月22日 6回目の収穫をした11月29日 7回目の収穫をした12月06日 8回目の収穫をした12月13日 9回目の収穫をした12月23日 10回目の収穫をした12月28日 11回目の収穫をした01月03日 12回目の収穫をした01月10日 13回目の収穫をした01月12日 14回目の収穫をした01月18日 15回目の収穫をした01月24日 16回目の収穫をした01月25日 17回目の収穫をした02月01日 18回目の収穫をした02月08日 19回目の収穫をした02月15日 20回目の収穫をした02月22日 21回目の収穫をした03月01日 22回目の収穫をした03月08日 23回目の収穫をした03月14日 24回目の収穫をした03月22日 25回目の収穫をした03月29日 26回目の収穫をした04月04日 27回目の収穫をした04月11日 28回目の収穫をした04月19日 29回目の収穫をした04月26日 30回目の収穫をした05月03日 31回目の収穫をした05月06日 32回目の収穫をした05月23日 33回目の収穫をした だいこん これにて 終了となった秋の大根の種を買ってきた08月29日 hcで大根の種をかってきて 庭で種まきをしておいた09月03日 発芽してきている09月05日 畑に移動した g-1-3の畑の畝に植え付けをしておいた09月21日 畑の大根の発芽したもの まあまあ 育ってきている09月23日 g-3のだいこん まあまあ 生育してきている09月27日 g-3の大根 これが 一番 生育は良い はやく大きくなれーーー10月11日 いちばん育っている第二弾09月05日 庭で種まきをした09月12日 畑に移動した m-20に植え付けた09月22日 まあまあ 生育してきている10月04日 それなりに 生育してきている10月11日 まあまあ育っている第三弾の種まき09月12日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽したので 畑に移動 m-07の畝に植え付けた09月22日 ちいさいが 無事なり10月11日 それなりに育っている第四弾の種まき09月21日 庭に種まきをしておいた09月23日 発芽はまだ みずやりをしておいた09月27日 発芽したので m-06の畑の畝に移動しておいた10月11日 ちいさいままだなあ在庫g-03 28本m-20 16本m-07 16本m-06 16本10月18日 m-06の大根 これも 小さいながら順調に育ってきている10月19日 m-20の大根 これも まあまあ 順調に育ってきているおうむ おべんきょうその07系統学インコに関する系統学は現在も研究途上である。以下に述べる分類は現時点での状況を反映したものであり、現在も議論が続いている。したがって未解決の問題が新たに究明された場合には変更される可能性がある。このためこの分類は暫定的なものと見なすべきである。一般にオウム目は二つの現存する主要な系統から構成されていると考えられており、それぞれ科として分類される。すなわちインコ科(Psittacidae)とオウム科(Cacatuidae)である。オウム科はインコ科とは明白に異なっており、頭部に可動する冠羽をもち、インコ科とは異なる配置の頚動脈をもち、胆嚢があり、頭蓋骨に相違があり、そして羽毛のダイクテクスチャー組織(さまざまなインコに見られる鮮やかな色彩を作り出すように光を散乱させる羽根の構造)を欠いている。しかしながら実際の状況はおそらくもっと複雑である(下記参照)。はた坊
2015.10.23
コメント(0)
-

m-20の青梗菜 残っている分は生育は良い 大豆 おべんきょうその03
昨年01月05日 4回目の収穫 また 1個01月12日 5回目の収穫 こんかいも1個02月11日 6回目の収穫 また 1個だけ02月16日 7回目の収穫 3個02月23日 8回目の収穫 3個 これで おしまいに昨年08月10日 また hcで 種をかっきてた08月31日 追加で また hcて 種を買ってきた種まきは 9月より 今年はたくさん 収穫できるようにしよう苗の植え付け 水をしっかりと確保しておこう昨年は 栽培に失敗したので 今年は たくさんの青梗菜を つくるぞーーー08月31日 庭で 種まきを開始した09月5日 発芽してきている09月06日 G-03の畑の畝に植え付けをしておいた第二弾の種まき09月07日 庭で 第二弾の種まきをしておいた09月11日 発芽してきている09月14日 畑に移動した g-03などに植え付けをしておいた第三弾の種まき09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた第四弾の種まき09月21日 また 庭で 種まきをしておいた09月28日 発芽してきている10月05日 畑に移動した m-06の畑に植え付け これにて 種まきは終了10月12日 青梗菜 すこし生育してきている が まだまだ 小さいなあ まあ ゆっくりと成長していく予定 虫に強い 結構と大きくなってくれるので 楽しみである10月19日 その後 まあまあ大きくなってきつつある10月26日 その後 青梗菜は それなりに 成長してきている 見事なり11月09日 その後 青梗菜は かなり大きくなってきている 追肥をしておいた他の野菜もそれなりに成長してきている青梗菜 高菜 大根 カブラ ぶろっこりー 菊菜 ネギ 芽キャベツ そこそこ 大きくなってきている 11月12日 ちんげんさい もう 収穫してもいい 大きなサイズになっている 日曜には 収穫していこう11月15日 今年は青梗菜は良く育っている まずは 初の収穫 4個なり11月16日 2回目の収穫をした11月22日 3回目の収穫をした11月29日 4回目の収穫をした12月06日 5回目の収穫をした12月13日 6回目の収穫をした12月23日 7回目の収穫をした12月30日 8回目の収穫をした12月31日 9回目の収穫をした01月03日 10回目の収穫をした01月05日 11回目の収穫をした01月12日 12回目の収穫をした01月18日 13回目の収穫をした01月24日 14回目の収穫をした02月01日 15回目の収穫をした02月08日 16回目の収穫をした02月15日 17回目の収穫をした青梗菜の在庫 g-03 0個 m-20 0個 m-06 4個 合計 4個くらい まだ ある02月21日 残りの青梗菜 6個 大きく育っていた分 全部 ひよどりが 食べてしまっていた あらあら 6個ともに 残骸となってしまっていた02月22日 まだm-06に青梗菜があった すこし収穫をした 18回目の収穫03月01日 19回目の収穫をした これにて終了となった今年08月29日 hcで種をかってきた ついてに庭で種まきをしておいた09月05日 発芽したので 畑に移動した g-01に植え付けをしておいた09月20日 g-01のその後 ちいさいけど なんとか無事かな10月11日 ここのは まあまあ 生育してきている第二弾09月06日 庭での種まきをしておいた09月12日 発芽したので 畑に移動した m-20に植え付け第三弾09月13日 庭での種まきをやっておいた09月19日 発芽したので m-08の畑の畝に移動した09月27日 その後も 無事なり 小さいがこれから これから第四弾09月20日 庭での種まきをしておいた09月27日 発芽した m-06の畑の畝に移動した4回目の種まきをして畑に移動した これから 大きくなるのを待つのみ在庫g-01 8本m-20 4本m-08 7本m-06 8本すくないが すこし生育している10月17日 m-20のちんげんさい 残っている分の生育は良い大豆 おべんきょうその03特徴ダイズ種子貯蔵タンパク質のアミノ酸残基組成において、含硫アミノ酸であるメチオニンとシステイン残基が少なく、それらは制限アミノ酸となっていると言われたことがある。そのため、タンパク質の有効利用効率を示すアミノ酸スコアやプロテインスコアを下げていると言われていた。しかし、これらは成長期のラットに基づく数値であり、その後、ヒトに基づく数値に置き換えられ、具体的には、大豆のアミノ酸スコアが1973年には86点だったものが、1985年には100点と変更された。大豆は、牛乳や卵と同等の良質なタンパク質であるとの評価を得ている[3]。はた坊
2015.10.23
コメント(1)
-

おくら 16回目の収穫をした これにて おくらも終了なり 東日本大震災4年と7か月と11日後に
昨年hcで丸のオクラの種をかってきた植え付けは4月の予定 27日くらいでいい感じ まだ 1か月先になる種まきは 暖かくなってからで ok買うのは 早くでもok 04月20日 種まきをしておいた04月27日 まだ 発芽していない05月03日 発芽したのは まだ数本 まだまだ全部を発芽させたら 畑に移動する予定 今週の日曜くらいには 移動できるかも05月11日 全部が発芽したので 畑に移動した m-06の畑に植え付けた06月01日 雑草に囲まれていたので 除草しておいた まだ 苗は小さい なんとか 苗も残っている雨がふってきているので なんとかなるだろう06月18日 その後 雑草とりをしておいた なんとか すこし成長をしてきている06月29日 再度 雑草とりをしておいた これで また すこし成長をしてきている07月06日 初の収穫をしておいた 小さいうちは 早目に収穫しておこう07月13日 2回目の収穫をした07月16日 3回目の収穫をした07月20日 4回目の収穫をした07月27日 5回目の収穫をした08月02日 6回目の収穫をした08月06日 7回目の収穫をした08月09日 8回目の収穫をした08月13日 9回目の収穫をした08月20日 10回目の収穫をした08月27日 11回目の収穫をした08月31日 12回目の収穫をした09月07日 13回目の収穫をした09月14日 14回目の収穫をした09月21日 15回目の収穫をした09月28日 16回目の収穫をした10月05日 17回目の収穫をした10月13日 18回目の収穫をした台風19号で やや 勢いがなくなってきているので これで 撤去として 次の野菜に この場所をゆずるとしよう今年は18回の収穫をもって 終了 今年 また おくら 丸いタイブの種を買ってきた04月12日 hcでのまるオクラの種をかってきた種まきは4月19日くらいにやっておこう04月26日 庭で種まきをしておく05月06日 発芽したので畑に移動 g-07の畑の畝に植え付けをしておく05月10日 これにも ペットをかけている まあまあである05月23日 それなりに生育してきつつある 無事なり06月06日 その後も 無事に生育してきている06月13日 残っている苗も 結構とたくさんある 支柱もむつけておいた06月20日 その後も 生育は良く だんだん 大きくなりつつある06月27日 無事に大きくなりつつある そろそろ 実もついてくるかな07月04日 ちいさい実がつきだした おくら 今年も たくさん 苗が育ちつつある07月11日 初の収穫をしておいた07月12日 2回目の収穫をしておいた07月12日 おくら 勢いがある 実もたくさんついてきている07月19日 3回目の収穫をしておいた07月26日 4回目の収穫をしておいた08月01日 5回目の収穫をしておいた08月08日 6回目の収穫をしておいた08月15日 7回目の収穫をしておいた08月22日 8回目の収穫をしておいた08月29日 9回目の収穫をしておいた09月06日 10回目の収穫をしておいた09月12日 11回目の収穫をしておいた09月19日 12回目の収穫をしておいた09月27日 13回目の収穫をしておいた10月04日 14回目の収穫をしておいた10月10日 15回目の収穫をしておいた10月18日 16回目の収穫をしておいたこれにて オクラも 終了なり東日本1震災 3月11日発生10月22日は既に4年と7か月と11日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------マスコミの選び方(4) どういう報道が政治判断を狂わせるか? 「政党が抗議しそうなこと」を報道する覚悟も力もすでにテレビも新聞もない。その典型的な例が2014年(昨年)の12月の選挙だ。この時、自民党はマスコミに対して3つの作戦を組んだ。民主主義下の政党としてやるべきだったかどうかは別にして、実際に自民党がやったことは確かだ。1) 消費税の減免措置に「報道」を入れるとくことで、日本新聞協会(テレビも含む)に打診する(会合がもたれた)。・・・アメ2) 選挙前に「選挙の前は報道の中立性に特に留意すること」という申し入れを行う。・・・ムチ3) 公約で本当の争点であった「安保法案」を掲げず、アベノミクスと消費税を選挙の争点にした(経済選挙の見かけを作る戦術)。選挙に戦術があってもかまわないので、3)は普通なら認められる範囲だ。でも、1)のアメと2)のムチとの総合作戦で、マスコミは金縛りに遭った。2014年の総選挙の前には「政治報道、政治討論」などは極めて少なくなったので、私はあるテレビ局の人に聞いたら、「やりにくいんですよ」と言っていた。安保法案、消費税、アベノミクスのいずれも大きな選挙の争点だったが、もともと安保法案は、民主党、公明党、維新の会、みんなの党が自分の党の政策にもしていたので、自民党としては無理矢理、公約として出す必要は無く、また憲法論争、集団的自衛権などは戦争と関わり、議論が紛糾すると考えた。これは戦術としては正しく、2015年の安保法案の騒動を見れば納得できる。しかし、これではマスコミは何のためにあるのだろうか? ある政党が選挙戦術としてある政策に議論が及ばないようにしても、それが国民にとって大きな関心事なら、特に意識して取り上げる必要がある。2015年に衆議院で可決された後、マスコミの多くは「安保法制反対」の立場をとって紙面を作った。特に朝日新聞などの「煽り新聞」はそれが目立った。それではなぜ、朝日新聞は2014年の選挙の前に安保法案を争点にしなかったのだろうか?すでに2014年7月1日には閣議で「憲法を改正せずに集団的自衛権の法案を次の国会に出す」と言うことが決まっていたのだから、選挙の時こそ争点にすべきなのである。朝日新聞の考えは次のようだったと考えられる。1) 自民党が勝つ情勢だったから、消費税の減免措置を認めてもらうには自民党が不利になる報道はできない。2) 安保法案は国会に上程され、可決までに世論が反対に傾いたら、それを煽れば良い。その方が部数が伸びる。3) 民主主義的に言えば、選挙の争点にすべきだが、日本の新聞は「正当な役割」を果たすと必ず国民から目を背けられる(国際連盟脱退などの例がある)。「報道の自由を実現する」という理想に燃えたテレビや新聞を期待することはできない。それは日本人が「煽りに弱い国民」である限り、仕方が無いので、自分で政党の方向を考えることだ。ネットの一部は役に立つ。(平成27年10月6日)ふむふむはた坊
2015.10.22
コメント(0)
-

m-06の大根 まあまあ 育ってきている 茶 おべんきょうその34
昨年度09月01日 hcで 大根の種をかってきた ついでに 庭で種まきをしておいた09月01日 間違って 聖護院蕪でなくて 大根の方を買ってしまった まあ ええか今年も大根の種まきを開始 まずは16potsx2=32potsで育ててみよう09月01日 大根 聖護院大根 ともに 庭で 弾ねきをしておいた09月04日 発芽 畑に移動 ともに32potsづつ m-08の畑に移動した09月08日 その後も無事 生育中 okだ ついでに 苦土石灰をまいておした大根 第二弾の種まきも開始09月08日 大根の第二弾の種まきを開始 16x2=32potsを種まきした09月13日 発芽している これも 畑に移動しよう09月15日 畑に移動した g-22の畝に植え付けた大根 第三弾の種まきもしておいた09月16日 庭で種まきをしておいた 16potsx2 09月22日 畑に移動した m-06に16pots m-07に16pots 分散して植え付けた大根は no1-32pot no2-32pots no3-32pots total 96pots聖護院大根は no1-32potの種まきをした これだけうえたらokだ育ち具合は これからだ 今のところは 無事に育っている まあ これだけ種まきしたら かなり育つだろう10月05日 一か月が過ぎた 聖護院大根 いい感じに育ってきている10月05日 大根の方も 一か月が過ぎている こちらも いい 感じ10月06日 2番目の大根 g-10の分も まあまあ 生育中10月13日 m08の畑の大根のねっこ かなり見えるようになってきた10月20日 m008の畑の大根のねっこ 50日でこれくらい10月27日 1本 ためしで 収穫した まあまあ初の収穫なり これから どんどん 収穫しよう11月02日 2回目の収穫をした 5本なり12月29日 17回目の収穫をした 丸の5本 やや小さくなってきている今年01月04日 18回目の収穫をした 2本 曲がっているなあ01月05日 19回目の収穫をした 丸4個01月12日 20回目の収穫をした 4本01月13日 21回目の収穫をした 丸7本01月18日 22回目の収穫をした 5本01月19日 23回目の収穫をした 丸7本01月26日 24回目の収穫をした 11本01月27日 25回目の収穫をした 丸7本02月01日 26回目の収穫をした 6本02月02日 27回目の収穫をした 小物の10本02月09日 28回目の収穫をした 6本02月11日 29回目の収穫をした 小物の丸の大根も おしまいかな02月16日 30回目の収穫をした 5本02月22日 31回目の収穫をした 6本03月02日 32回目の収穫をした 6本03月09日 33回目の収穫をした 4本03月16日 34回目の収穫をした 6本03月22日 35回目の収穫をした 6本03月30日 36回目の収穫をした 9本そろそろ おしまいになりそう今年の秋の大根また 種をかってきておいた今年も9月より種まきを開始しよう大根の種まき 第一弾だ08月31日 庭で種まきをした09月03日 発芽してきている09月07日 畑に移動するぞ 本日は大根の種まき 第二弾をやろう09月07日 種まきをするぞ09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-9などに植え付けをしておいた種まき 第三弾09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた種まき 第四弾09月21日 ついでに また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に植え付けた種まき 第五弾09月28日 また 種まきをしておいた10月01日 発芽した10月04日 畑に移動した m-07の畑に植え付けた種まき 第六弾10月05日 また 種まきをしておいた10月09月 発芽した10月12日 畑に移動した g-07などに植え付け これで 大根の種まきも終了した種まきした大根 かなり 大きくなってきている在庫もかなりある あちこち 植え付けてたので 大根だらけ10月19日 その後 大根 大きくなっているのもあり 収穫できそうになってきている10月26日 これくらいになっている もう 収穫できる11月01日 初の大根の収穫をした 曲がりもすごい が まあまあ 大きくなっている11月02日 2回目の収穫をした11月07日 3回目の収穫をした11月15日 4回目の収穫をした11月16日 5回目の収穫をした11月22日 6回目の収穫をした11月29日 7回目の収穫をした12月06日 8回目の収穫をした12月13日 9回目の収穫をした12月23日 10回目の収穫をした12月28日 11回目の収穫をした01月03日 12回目の収穫をした01月10日 13回目の収穫をした01月12日 14回目の収穫をした01月18日 15回目の収穫をした01月24日 16回目の収穫をした01月25日 17回目の収穫をした02月01日 18回目の収穫をした02月08日 19回目の収穫をした02月15日 20回目の収穫をした02月22日 21回目の収穫をした03月01日 22回目の収穫をした03月08日 23回目の収穫をした03月14日 24回目の収穫をした03月22日 25回目の収穫をした03月29日 26回目の収穫をした04月04日 27回目の収穫をした04月11日 28回目の収穫をした04月19日 29回目の収穫をした04月26日 30回目の収穫をした05月03日 31回目の収穫をした05月06日 32回目の収穫をした05月23日 33回目の収穫をした だいこん これにて 終了となった秋の大根の種を買ってきた08月29日 hcで大根の種をかってきて 庭で種まきをしておいた09月03日 発芽してきている09月05日 畑に移動した g-1-3の畑の畝に植え付けをしておいた09月21日 畑の大根の発芽したもの まあまあ 育ってきている09月23日 g-3のだいこん まあまあ 生育してきている09月27日 g-3の大根 これが 一番 生育は良い はやく大きくなれーーー10月11日 いちばん育っている第二弾09月05日 庭で種まきをした09月12日 畑に移動した m-20に植え付けた09月22日 まあまあ 生育してきている10月04日 それなりに 生育してきている10月11日 まあまあ育っている第三弾の種まき09月12日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽したので 畑に移動 m-07の畝に植え付けた09月22日 ちいさいが 無事なり10月11日 それなりに育っている第四弾の種まき09月21日 庭に種まきをしておいた09月23日 発芽はまだ みずやりをしておいた09月27日 発芽したので m-06の畑の畝に移動しておいた10月11日 ちいさいままだなあ在庫g-03 28本m-20 16本m-07 16本m-06 16本10月18日 m-06の大根 これも 小さいながら順調に育ってきている茶 おべんきょうその34成分と効能茶を嗜好品として特別視せしめたのはカフェインが含有されている事であるが、茶には他にも次のような各種有効成分があると言われている。タンニン(カテキン類)テアニンビタミンCカフェインの主な作用は、中枢神経を興奮させることによる覚醒作用及び強心作用、脂肪酸増加作用による呼吸量と熱発生作用の増加による皮下脂肪燃焼効果[98]、脳細動脈収縮作用、利尿作用などがある[99]。はた坊
2015.10.22
コメント(0)
-

m-06のブロッコリーの苗 生育は順調なり おうむ おべんきょうその06
昨年ブロッコリーの種 買ってきている これも 秋になって 9月からの種まきの予定なり08月15日 種をかってきている今年も ブロッコリーの栽培を開始した種まきも 苗からも 同時に開始 種まき 第一弾08月31日 庭にて 種まきを開始09月04日 発芽した09月06日 畑に移動 G-01の畑の畝に植え付け第二弾の種まき09月07日 庭にまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月13日 畑に移動した g-03の畑に植え付けた第三弾の種まき09月14日 庭にまたまた 種まきをしておいた09月19日 発芽した09月21日 畑に移動した m-06の畑の畝に植え付けた苗からも 栽培しておこう08月31日 hcでの苗がうられていたので 4本の苗を買っておいた m-08の畑の畝にうえておいた09月13日 その後 1本が虫にかじられている のこりの3本は無事なり09月14日 追加で 4本の苗をかってきた g-07の畑の畝に植えておいた09月21日 その後 苗からのブロッコリーの成長は良い どんどん 大きくなってきている10月05日 その後も いい感じ どんどん 成長している10月13日 その後 7本は無事 おおきくなりつつあるHCからの苗は 無事なのは7本 苗からのは 生育が早いし 大きい 早期の収穫には もってこい種からのは まだ小さいままで 生育はかなり遅くなるが まあまあ 長く長く収穫できるので これも良い苗と種まきの組み合わせ これで 良し苗からの本数は7本 種からの本数は まだ わからない 何本残るかはあとで 調べよう10月19日 畑の残っている種からの苗を数えてみたG-01 8本G-07 1本G-09 4本 合計で13本くらいHCからの苗は7本と 種からの苗は13本なので 総本数は20本なり10月26日 苗からのブロッコリー 花蕾がしっかりとついてきている11月01日 その後も 成長してきている そろそろ 苗からのブロッコリーも 収穫をできそうになってきている11月02日 初の収穫をしておいた まあまあ なり ブロッコリー春からの分も収穫できている苗からの分も収穫できている種からの分は まだだけと 良く成長してきている今年は 成績は良いようだなあ先週に収穫したあと また 次のができてきているg-09の4本のブロッコリの花蕾も大きくなってきている収穫しても 良さそうになってきている11月09日 2回目の収穫をした11月17日 3回目の収穫をした11月22日 4回目の収穫をした11月23日 再度 在庫の確認をしてみた苗からのものm-08 4本g-07 4本 合計08本 春の残り物m-20 04本 種からの分g-09 2本g-01 8本 合計10本 全部で 08-04-10=22本 たくさんあるなあ11月23日 5回目の収穫をした11月30日 ブロッコリー 6回目の収穫をした12月06日 その後も ブロッコリー 元気に育っている今年はうまくいっている 苗からの育ち具合は 特に良し12月07日 7回目の収穫をしておいた12月13日 8回目の収穫をしておいた12月21日 先週に大量に収穫したので 今週はなし12月28日 追肥をしておいた すこし息切れしているなあ 追肥だ 追肥だなあ12月31日 なんとか 花蕾が成長をしてきている 追肥が効いている01月03日 9回目の収穫をしておいた01月04日 10回目の収穫をしておいた01月12日 11回目の収穫をしておいた01月18日 12回目の収穫をしておいた01月24日 13回目の収穫をしておいた02月01日 14回目の収穫をしておいた02月08日 15回目の収穫をしておいた02月15日 16回目の収穫をしておいた02月22日 17回目の収穫をしておいた03月01日 18回目の収穫をしておいた03月08日 19回目の収穫をしておいた03月15日 20回目の収穫をしておいた03月22日 21回目の収穫をしておいた03月29日 22回目の収穫をしておいた04月04日 23回目の収穫をしておいた04月12日 24回目の収穫をしておいた04月19日 もう 収穫できるものはなし ブロッコリー 収穫は終了した これにて ブロッコリー 収穫するものは なくなった今年hcで 種がうっていない他のhcにいって 探したら なんとか 1つあった ブロッコリーのふつうのは売っているが茎のスティックのタイブはあまり 売っていないなあ とりあえず 1つ見つけて買ってきて 種の植え付けを開始した08月30日 ブロッコリ 植え付けを忘れていた09月05日 種を探したらない 苗は打っていたので 12本をかっておいた09月06日 他のhcにいって 種をさがす なんとか 1つだけあったての゛ かって植え付けた09月07日 苗は6本をg-9に植えて 6本をm-06に植え付けた09月12日 発芽した苗を畑に移動した g-07に植え付けた09月19日 m-06の苗のもの 無事なり 追肥をしておいた09月20日 g-09の苗も 無事なり 追肥をしておいた09月27日 g-09のなえ すこし 追肥が効いてきた すこし成長を開始10月04日 g-09のなえ まあまあ 見た目も安定してきている10月11日 g-09の苗 まあまあ 生育も良くなっている10月18日 m-06の苗 これも 生育は順調なり在庫m-07 種まきした分 何本育つか未定なり 残っているのは8本のみm-06 苗の5本g-09 苗の6本おうむ おべんきょうその06現代のインコの最も古い記録はおよそ2,300万年から2,000万年前にまでさかのぼり、これらもすべてヨーロッパで出土している。これに続く化石記録は - これもまた主にヨーロッパからであるが - 明瞭に現代のタイプのものであると識別できる骨格からなっている。南半球には北半球に匹敵するような興味深い時代に関する化石記録が存在せず、また2,000万年前の中新世より古い時期の既知のインコ様の鳥の遺物も含まれていない。しかしながら、この点に関しては(インコ様のものとは対照的に)最初の明白なインコの化石が発見されており、その上嘴は現代のオウムのそれと見分けがつかない。いくつかの現代の属は暫定的に中新世起源とされているが、その明確な記録はたかだか500万年程度さかのぼったものに過ぎない。命名されている化石のオウム目の属はおそらくすべてインコ科ないしその祖先の近縁である:Archaeopsittacus(後期漸新世/初期中新世)Xenopsitta(チェコの初期中新世)Psittacidae gen. et spp. indet. (オタゴ地方バサンズの初期/中期中新世 ニュージーランド)- 複数の種類Bavaripsitta(スタインバーグの中期中新世 ドイツ)Psittacidae gen. et sp. indet.(中期中新世 フランス) - 誤って"Psittacus" lartetianusと ともにPararallus disparにおかれていた。いくつかの古第三紀の化石はオウム目の化石であると明確には認められていない:Palaeopsittacus(初期-中期始新世 北西ヨーロッパ) - caprimulgiform (podargid?) あるいは quercypsittid?"Precursor"(初期始新世 - 明らかにキメラであるこの化石の部分はpseudasturid か psittacid であろう。Pulchrapollia(初期始新世)— "Primobucco" olsoniを含む -オウム目 (pseudasturid か psittacid)?はた坊
2015.10.22
コメント(0)
-

九条ねぎ 在庫の分を ばらばらにして 植え直しをしておいた 大豆 おべんきょうその02
ねぎの根っこ12月31日 初の九条ねぎ 収穫をした 根っこも庭のブランターに植え付けをしておいた01月03日 2回目の収穫をしておいた 根っこは庭にて 植え付けをしておいた01月10日 3回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた01月17日 5回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた01月24日 6回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた02月01日 7回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた庭にブランター 6個に ネギのねっこ 植え付けをしている これで もうすこし大きくなったら 畑に移動する予定あと 3-4個 追加していく予定なり ネギは根っこから 育てていこう03月01日 ネギの根っこ まあまあ 生育してきている 03月12日 ネギの坊主のちいさいのがついてきている03月22日 かなり生育してきている そろそろ 畑に移動させよう03月29日 M-08の畑の畝に移動してうえつけをしておいた04月04日 その後も ネギさん 根っこも 元気そうだ 無事なり04月12日 ネギのねっこ ネギ坊主が でているので 全部をカットしておいた04月19日 ネギのねっこ その後もネギ坊主をカットしている04月26日 その後も 様子見をしている 05月26日 その後も まあまあ 無事なり06月20日 数はそのまま あまり 大きくはなっていないが 無事なり07月04日 ヤマノイモの日陰になっているが ちいさいが 数は無事にそだっている07月11日 2月からのねぎの根っこ 無事にそだっている まあまあかな九条ネギの在庫 m-08 10本 ネギの根っこ 60本 m-06 20本 m-07 20本 g-01 10本 g-03 20本 合計 140本くらいは まだある ネギ坊主をカットして そのままブンケツさせていこう06月20日 在庫のネギさん ネギ坊主が まだまだ 出てきている06月27日 在庫のネギさん ネギ坊主も まだまだ 出てきている でも 新しいブンケツのネギさんも そろそろ 出てきている07月04日 まだ ネギ坊主でできている07月11日 そろそろ 止まりでしている 青々としているのと 枯れているのが半々くらいになっている ネギ坊主をカット カット カット しているので ネギさんも あきらめて ブンケツしてみようかなと 考えているようだ残っている九条ねぎ 無事に生き残っている07月20日 九条ねぎ 大量にのこっている 新しい畝に分散させて植えなおしをあとでやろう07月21日 根っこの分のネギは ちいさいので そのまま 大きいのは植えなおそう08月01日 九条ねぎ 残っているのも 8月になって 元気になってきている09月05日 g-3の九条ネギ 9月になって この状態なり まあ 順調なり09月12日 m-07の九条ネギ これも元気になってきている09月23日 m-07の九条ねぎ 元気なり10月04日 m-07の九条ネギ 追肥をしておいた 九条ネギの在庫 m-08 10本 m-06 20本 m-07 20本 g-01 10本 g-03 20本 合計 80本くらい まあ たくさんある10月11日 m-06/07の在庫のネギ バラバラにして 分散して植えなおしておいた在庫のねきの土 カチカチになっていた土を耕して ネギさん ばらばらにして 植えなおしたが しばらく元気になるまで時間がかかりそう大豆 おべんきょうその02特徴農作物として世界中で広く栽培されている。日本には縄文時代に存在したと思われる大豆の出土例があり、『古事記』にも大豆の記録が記載されている。ダイズ種子には苦み成分であるサポニン (Saponin) (ダイズサポニン)が多く含まれており、人類の主食にまではなっていないが、植物の中では唯一肉に匹敵するだけのタンパク質を含有する特徴から、近年の世界的な健康志向の中で「ミラクルフード」として脚光を浴びている。日本・ドイツでは「畑の(牛)肉」、アメリカ合衆国では「大地の黄金」とも呼ばれている。また、日本料理やその調味料の原材料として中心的役割を果たしている(後述)。はた坊
2015.10.22
コメント(0)
-

なすび 33回目の収穫をしておいた 東日本大震災4年と7か月と10日後に
昨年ののなすび04月13日 6本の苗をhcで買ってきて 庭で保管している04月17日 g-09の畑に移動しておいた 追加が4本の苗も植え付けた04月20日 m-06の畑にも4本のなすびをうえつけた なすび m-06に4本 g-09に10本 合計で14本の苗を育てている 種まきも開始しておいた ことしも なすび 大量につくろう04月27日 畑で なすびさん 無事に生育中 追肥をしておいた05月03日 黒マルチをつけておいた 無事に生育している06月01日 花もさき実もつきだしている 06月03日 なすび 実もついてきている06月08日 収穫を開始だなあ 2本06月15日 2回目の収穫 10本くらい種まき第一弾04月20日 庭でなすびの種まきをしておいた05月03日 発芽 m-06の畑に移動した06月01日 その後 雑草に隠れて 見えなくなった06月08日 1本だけ 発見 なんとかなりそう06月22日 1本だけだけど なんとか 成長してきている種まき第二弾05月05日 庭での種まきをまた やっておいた05月19日 発芽したのでm-20に移動した06月01日 無事に生育している06月08日 10本くらいはありそう06月22日 これが 写真の分 なんとか ちいさいながらも成長しつつあるかな種まき第三弾05月11日 ついかで また 種まきをしておいた05月25日 発芽したのでm-08の畑に移動した06月08日 雑草だらけになっている さて どうなるかな06月15日 1本だけは残っている06月22日 1本だけだけど 支柱をつけておいた06月15日の 今年の茄の在庫は苗の物が14本 全部が 無事に育っている ただいま 収穫中 種からの物が 全部で 残っているのが 12本 これが時差で秋ナスとして育てている今年のなすび 苗も無事に 全部が育っている 順調なり06月18日 3回目のなすびを収穫しておいた06月21日 4回目のなすびの収穫をしておいた06月22日 5回目のなすびの収穫をしておいた06月25日 7回目のなすびの収穫をしておいた06月29日 8回目のなすびの収穫をしておいた07月02日 9回目のなすびの収穫をしておいた07月05日 10回目のなすびの収穫をしておいた07月06日 11回目のなすびの収穫をした07月09日 12回目のなすびの収穫をした07月13日 13回目のなすびの収穫をした07月16日 14回目のなすびの収穫をした07月19日 15回目のなすびの収穫をした07月23日 16回目のなすびの収穫をした07月26日 17回目のなすびの収穫をした07月30日 18回目のなすびの収穫をした08月02日 19回目のなすびの収穫をした08月03日 20回目のなすびの収穫をした08月06日 21回目のなすびの収穫をした08月09日 22回目のなすびの収穫をした08月10日 23回目のなすびの収穫をした08月13日 24回目のなすびの収穫をした08月16に 25回目のなすびの収穫をした08月23日 26回目のなすびの収穫をした08月30日 27回目のなすびの収穫をした08月31日 28回目のなすびの収穫をした09月07日 29回目のなすびの収穫をした09月13日 30回目のなすびの収穫をした09月20日 31回目のなすびの収穫をした09月21日 32回目のなすびの収穫をした09月27日 33回目のなすびの収穫をした09月28日 34回目のなすびの収穫をした10月04日 35回目のなすびの収穫をした10月05日 36回目のなすびの収穫をした10月12日 37回目のなすびの収穫をした10月19日 38回目のなすびの収穫をした10月25日 39回目のなすびの収穫をした10月26日 40回目のなすびの収穫をした11月02日 41回目の茄の収穫をした これで 御終いになった 終了なり今年04月12日 hcで なすびの 苗6本を買ってきて植え付けた g-0304月19日 追加で また なすびの苗 6本を畑に植え付けた m-06なすび 合計12本これだけあれば 良いのかな まあ 様子見としよう05月23日 g-03の6本は元気なり05月30日 ますび 初の収穫をしておいた06月06日 g-03のなすび これは 元気が良い06月07日 2回目の収穫をしておいた06月13日 3回目の収穫をしておいた06月14日 4回目の収穫をしておいた06月20日 5回目の収穫をしておいた06月21日 6回目の収穫をしておいた06月27日 7回目の収穫をしておいた06月28日 8回目の収穫をしておいた07月04日 9回目の収穫をしておいた07月05日 10回目の収穫をしておいた07月11日 11回目の収穫をしておいた07月18日 12回目の収穫をしておいた07月19日 13回目の収穫をしておいた07月26日 14回目の収穫をしておいた08月01日 15回目の収穫をしておいた08月02日 16回目の収穫をしておいた08月08日 17回目の収穫をしておいた08月09日 18回目の収穫をしておいた08月08日 19回目の収穫をしておいた08月15日 20回目の収穫をしておいた08月22日 21回目の収穫をしておいた08月29日 22回目の収穫をしておいた09月05日 23回目の収穫をしておいた09月12日 24回目の収穫をしておいた09月13日 25回目の収穫をしておいた09月14日 26回目の収穫をしておいた09月19日 追肥をしておいた すこし元気がなくなりつつある 秋だなあ09月20日 27回目の収穫をしておいた09月22日 28回目の収穫をしておいた09月26日 29回目の収穫をしておいた09月27日 30回目の収穫をしておいた10月04日 31回目の収穫をしておいた10月11日 32回目の収穫をしておいた10月18日 33回目の収穫をしておいた東日本1震災 3月11日発生10月21日は既に4年と7か月と10日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------ヘイトスピーチの原因 在日朝鮮人や沖縄の人に対して激しい街頭でのヘイトスピーチが行われ、一部で訴訟になって最高裁がヘイトスピーチをした方に「ヘイトスピーチをしたことによって損害が生じたとして1200万円の賠償を命じた」というところまできた。テレビなどでヘイトスピーチの解説が行われているが、私は次のように思う。1) 小保方さんのSTAP細胞事件はマスコミと科学者のヘイトスピーチだった。2) ネットで見られる個人へのバッシングもヘイトスピーチである。3) 安保法案で国会で乱闘や罵声が横行したがヘイトスピーチである。4) その他、日本にはこの種のヘイトスピーチは多い。5) 私も数多くのヘイトスピーチを受けた。学会でもそうだった。6) 韓国の朴大統領の発言も政治的なヘイトスピーチに近い。7) ヨーロッパのムハンマドに対する侮辱もヘイトスピーチに近い。ヘイトスピーチの定義と改善策1) 表現の自由の限界を知る(内的、精神的に限定)2) 表現の自由の限界を守る(回復せざることを批判する、弱いものを批判するのはダメ)3) 他人の意見や議論を尊重する。結局はその社会の品格、見識、常識、成熟などの問題で、恥ずかしい日本になったものだ。(平成27年10月11日)ふむふむはた坊
2015.10.21
コメント(0)
-

らっきょうの花 もうすぐ 開花してくれそう 色がつきだした 茶 おべんきょうその33
昨年hcでの売り物が出ていたので かっておいた植え付けは9月から09月07日 らっきょう m-08の畑の畝に植え付けた09月14日 発芽はまだ 2週間くらいしてから 発芽してくる見込み09月21日 やっと 発芽してきている 09月28日 いつも 花の蕾みたいのが 出てきている もうすぐ 花が咲くようだな10月29日 花が咲いてきている11月08日 その後 生育して大きくなってきている11月30日 雑草とりをした らっきょうらしくなってきている12月13日 追肥をしておいた 12月23日 雑草がまた 増えてきている01月03日 その後も らっきょう 元気なり01月24日 まあまあ 元気である01月08日 それなりに 元気なり 雑草もすくないな02月15日 そろそろ 雑草とりもしないとねえ03月01日 やっと 雑草取りをしておいた03月08日 春らしくなり 生育が始まってきている03月14日 らっきょう いい感じになってきている03月22日 らっきょう 雑草もなくなって すっきり04月04日 らっきょう まあまあ 生育している 良し04月12日 らっきょう 青々としてきている06月06日 らっきょう 収穫をした らっきょう 今年の根っこは かなり大きくなっている今年また hcでのらっきょう 買ってきている08月29日 hcで らっきょう 買ってきた08月30日 m-07の畑で 植え付けをしておいた09月12日 発芽している09月19日 花つぼみ 大きくなってきつつある09月22日 葉もつづけて でてきている09月27日 花つぼみ まだ 花は咲いていない 10月04日 葉も伸びてきている らっきょうの花 咲くのは10月の下旬なので まだ2週間ぐらい 後となる10月10日 花らしくなってきている 色はまだうすい 10月18日 花の色 すこしついてきている 開花も近いなあわけぎ あさつき にんにく ネギを育てているが花がきれいなのは らっきょう のみためして ガッテンにこんなのがあったらっきょうの魅力は「甘酢漬け」だけじゃない。実は旬の今だけ食べられる「生らっきょう」には、極ウマな味わい方があったんです。生のまま刻めば最高の香味野菜に。さらに加熱すると、なんとジャム並みの甘さにも大変身!らしい ?? 本当かいな茶 おべんきょうその33生産国連食糧農業機関 (FAO) の統計によれば、2010年における世界の茶葉生産量は、約452万トンである。地域別では、アジアが生産量の約84%、アフリカが約14%、南北アメリカが約2%を占める。上位5か国は中国、インド、ケニア、スリランカ、トルコであり、国別生産量は次表のとおり[96]。国 2008 2009 2010 中国 1,274,984 1,375,780 1,467,467 インド 987,000 972,700 991,180 ケニア 345,800 314,100 399,000 スリランカ 318,700 290,000 282,300 トルコ 198,046 198,601 235,000 ベトナム 173,500 185,700 198,466 イラン 165,717 165,717 165,717 インドネシア 150,851 146,440 150,000 アルゼンチン 80,142 71,715 88,574 日本 96,500 86,000 85,000 合計 4,211,397 4,242,280 4,518,060はた坊
2015.10.21
コメント(0)
全164件 (164件中 1-50件目)
-
-

- クリスマスローズについて
- クリスマスローズの種まきポットづく…
- (2025-11-15 18:30:05)
-
-
-

- フラワーアレンジメント
- 畑のコスモスはやっぱりキレイ♪
- (2025-11-18 17:10:04)
-
-
-

- やっぱり果樹栽培!
- 中の種を避けて柿を割る+今日の空間…
- (2025-11-17 21:35:05)
-








