2006年08月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
ふざけるな、人権擁護法!
あの悪名高い人権擁護法案をまたまた提出する動きがあるという。そしてマスコミは相変わらずマスコミ規制ばかりを問題として、この法案が持つネット言論規制などの大問題については相変わらずスルー・・・。何度でもいうが、犯罪、児童虐待、病気や障害、いじめ、職場でのセクハラやパワハラ、こうした人権侵害は、それぞれの類型毎に対策をとることが最も効果的なのであって、漠然と人権擁護自体を目的とした法案をつくったって意味はないのではないのだろうか。少なくともこの法案ができたところで、本当に日々人権を侵害されている弱い立場の人々がメリットを享受できるなんて全然思わない。う~む、せいぜい利益があるとしたら、先祖の誰かが賎民だったことを理由に「今も続く深刻な差別を受けている」と騒いでいる一部の人達くらいかな。アホらし。そんな「差別」などとっくになくなっているのに、きっと「差別」がないと困る輩がいるのだろう。人権擁護法ができ、「差別を助長する言論」などが規制されたら、ネット言論などたちどころに萎縮する。国民がもの言わぬ国民であり、大衆はあくまでも情報の受け手であった方が、政府やマスコミには都合がよい。人権擁護法案の動きをみていると、そんな政府とマスコミとの共同歩調をつい感じてしまうのである。この法案の問題はけっして「マスコミ規制」などではない。ネットの日記やブログで、ささやかながら意見を発信することを覚えた私達一人一人にとってこそ、人権擁護法案は大きな脅威なのである。※※皇太子ご夫妻帰国らしいのだが、なぜか映像はなし。本当に日本に戻ってきたのかしら…なんて思うのはかんぐりすぎかしら。
2006年08月31日
コメント(2)
-
若者の雇用対策こそ急務
少し前までの日本は「真面目にやればまあまあ自立できる社会」だった。ところが今ではワーキングプアとかフリーターとかよばれる、それすらかなわぬ若者が大勢いる。彼らはやむなく親と同居し、家賃、光熱費、場合によっては食費すら親負担のもとに暮らしている。親が元気なうちはまだよい。でも、親が高齢化し、彼らを庇護しきれなくなったら一体どうなるのだろう。当然彼らは年金を払うこともできない。ましてや結婚して家族を持つことなどは考えることも出来ない。普通の若者が自立して夢をおうこともできない社会はどうみても普通ではない。はっきりいってこんな状況になってきたのは、ここ数年のことだ。どうみても現政権の失政ではないのか。考えてもみてほしい。今の若者が生まれたのは1980年代。あの時代にフリーターとかニートなどという言葉はなかった。親の夢、次々壊して子は育ち・・・というように子供が親の期待どおりに育たないことはそりゃあるだろう。でもあの頃の親は、健康に育てば子供はいずれ自立できるのがあたりまえ、そんなつもりで子供を持ち、子供を育ててきたのではないのだろうか。※福祉や労働者保護などの国の関与を最少にしていこうとする「小さな政府論」がでてきたのは冷戦終結後のことである。社会主義の脅威が消えてから資本主義もまた弱肉強食の初期の形態に戻りつつあるのだろうか。政府中枢や政治家の中からは格差容認の意見すら聞こえてくる。たしかに格差というのは昔だってあった。でも昔の貧窮層の多くは、農村や血縁という共同体の中で最低限のセーフティネットだけは享受していた。今のように都市の核家族や単独世帯の中で孤立して暮らす貧窮層とは全然事情が違う。今でも生活保護申請は急増しているというが、これがさらに幾何級数的に増加し、行政が全く対処できなくなってきたとき何が起きるか・・・ちょっとそらおそろしいような気がする。※フリーター ニートという語も 聞かざりし 吾子の生まれし 夏の日の午後
2006年08月30日
コメント(8)
-
宮沢賢治資料館
この年になるまで行ったことのない県がいくつかある。岩手県もそのうちの一つだった。もちろん機会がなかったのだが、実はなんとなく避けていたというのもある。遠野物語も宮沢賢治もすごく好きで、その舞台となった岩手県には独特のイメージを抱いていたのだが、それだけに実際に訪れてイメージがこわれるとなんとなくいやだなと思っていたのである。そんなわけで今回、花巻の宮沢賢治記念館を訪れたのは、ようやく積年の想いを果たしたようなところがある。※岩手県に行くと宮沢賢治の存在というのは、東京で考えるよりもずっと大きい。花巻だけではなく、盛岡にも、宮沢賢治にちなんだ商品や通り名があるし、肥料会社の看板にはさりげなく宮沢賢治の写真のシルエット(あのートーベンのまねをして散歩をしているもの)が使われている。それにしても花巻駅の宮沢賢治弁当にはちょっとびっくりした。大河ドラマの主人公ではあるまいし、泉下の賢治もきっと苦笑していることだろう。よく考えると、今、東北の生んだ人物の中で一番人気があるのって宮沢賢治ではないか。賢治資料館はかなりのにぎわいだったが、たぶん近くの新渡戸資料館にはこれほど人は入っていないだろう。なぜ新渡戸や野口英世はお札のモデルになったのに、宮沢賢治をお札のモデルにするという案はでなかったのだろう。上昇志向の権化のような野口英世に比べると宮沢賢治の方がずっと時代の気分にあっているように思うのだが。※宮沢賢治資料館は山の中腹、バスをおりても20分ほどかかるのだが、大勢の人が訪れていた。残念ながら私が見たのは記念館だけだが、時間があれば童話の森周辺を散策するのもよいかもしれない。宮沢賢治の作品は外国にも紹介され、今ではここを訪れる外国人もいるそうである。文化というものは、やはりその国の資源であるといっても過言ではない。
2006年08月29日
コメント(6)
-
映画「博士の愛した数式」
この映画が公開されたときから、原作に描かれた世界をどのように映画化するかとても気になっていた。たぶんテーマは数学の美しさ・・・なのだが、これは言葉には表せても映像にするのは難しいのではないか。そんなふうに思っていたからである。※ところがDVD映画をみてみると、そうした原作の魅力はそのままで、しかも原作とは別の魅力のある映画になっているので感動をした。原作がよい場合、映画というのはどうしても原作のイメージを損なうか、まるで原作どおりで映画独自の魅力がない(映画「ダビンチコード」などこれに近い)かのどちらかである場合が多いのだが、この映画「博士の愛した数式」は原作も映画も両方よいという稀有な事例だろう。※まず主人公の子供ルートが数学教師となってから生徒に博士の思い出を語るという構成がよい。授業をまるごとドラマにするというのは「金八先生」でもあったが、これだと黒板に数式を書く場面も堅苦しくならない。そしてそのルートを演じる吉岡がすごくはまっている。映画「半落ち」では芸達者の中で彼の下手な演技がすごく浮き上がっていると思ったのだが、この人そんなに下手なわけではないのかもしれない。それにしても、あんな初々しい教師から、あんな授業を受けられたらよかったな。博士を演じた寺尾も、「半落ち」で見た暗く生活臭のある雰囲気からちょっと博士のイメージに違うと思っていたのだが、実際にみると純粋で優しい数学者のイメージによくはまっていた。若くまだ十分に美しい家政婦とそんな数学者との、友愛数のような性愛も利害も超えた「愛」を表現するのには、彼でなければ無理なのではなかったのかという気さえしてくる。※この映画の原作もきっかけとなって、出版界では、ちょっとした数学ブームだという。なんか数学というのは音楽と似ている。音楽の美しさは多くの人が感じることができるが、音楽を創り出す人間というのは限られている。数学もそれと同様、数学の才自体にはgiftとよぶしかない天の配剤が働くのだが、数学の美しさを感じ、人知を超えた天の摂理に驚嘆するのは万人のものだ。最近ブームの数学関連の本はそんな喜びを万人にとりもどさせたという意味で功績は大きいのかもしれない。
2006年08月27日
コメント(4)
-
次期総理に望むこと
5年半も続いた小泉政権もそろそろ終盤に近づいている。北朝鮮との国交締結が目的だったのだろうが、結果的に拉致事件を認めさせたことが、おそらくこの政権の唯一の功績であろう。もっとも、その背景には北の政権と同様、世論の読み違いがあったわけで厳密な意味で「功績」といえるかどうかはわからないのだが。※それ以外の分野では、全く惨憺たるものといわざるをえない。ちょっと5年半前、小泉総理登場前を思い出してほしい。中高年のリストラは社会問題になりはじめていたのかもしれないが、フリーター漂流、ワーキングプア、富裕層、格差…こんな言葉はまだなかった。富裕層や格差が問題なのではない。社会の下の方からじわじわと貧窮層が広がっていることが問題なのである。5年前に比べると30代、40代の男性就労率は確実に低下している。そしてそれと同時にこの年代の男性の未婚率は急上昇している。安定した生活も将来の展望も望めない層が拡大しているわけである。そして今の日本には様々な問題をつつみかくし、社会を安定させる機能を担っていた血縁共同体や農村コミュニティーももはやない。※自殺者は年間3万人。生活保護申請は役所窓口に殺到しているが、これに対して職員は申請用紙すらわたさないことが多いという。こうして申請を断られた50代男性が衰弱死し、抗議の自殺をした30代男性もいる。彼らの叫びや抗議の声は霧の中の木霊のように消えていくだけなのだろうか。フリーターやアルバイトでやっと生活する若者や最低限の暮しを続ける中年独身者。彼らが後戻りのできない年齢になったり、窮乏しはじめたとき、社会はそのコストに耐えられるのだろうか。彼らこそ、文字どおりの「鉄鎖の外に失うもののない」プロレタリアなのだから。※次期総理としての呼び声の高い安倍氏は、教育基本法と憲法改正を優先課題にするという。雇用不安、失業といった大きな社会問題に比べれば教育基本法などはどうでもよい話だ。経済や財政が、難しいのはわかるけど、教育論議をおもちゃにするのはやめてほしい。
2006年08月26日
コメント(6)
-
シュレッダー事故
最近、シュレッダーによる事故がマスコミをにぎわしている。エレベーター、湯沸し器、プールそしてシュレッダー。このうち湯沸し器とシュレッダーについては、なぜ過去の事故が今頃急に騒がれるのか、そしてその騒ぐ元がなぜ被害者ではなく某中央官庁なのか…ちょっと首をひねりたくもなるが、ともかく人命や子供の安全にかかわる事故が問題であることはいうまでもない。それにしても湯沸し器はともかくシュレッダー事故については根本的疑問が頭から離れない。そもそもなぜ家庭にシュレッダーが必要なのだろうか。事業所ならともかく家庭のくずかごにそんなにみられて困る情報があるとも思えないし、ゴミ出しの後でゴミをあさる人がいるわけもない。普通の家庭、それも幼児のいる家庭で、ゴミ箱のかわりにシュレッダーを置いておくこと自体ちょっと理解できない。だからメーカーを非難する前に、この件については、どうしてそんなものを家に置く必要があっったの…とつい聞いてみたくなる。※※共同通信がピョンヤンに支局を開設するという。以前にも、共同通信はマスコミ各社をひきつれて北朝鮮を訪れ歓迎を受けたりもしている。これによって共同通信の今後の北朝鮮報道はどう変わるのだろうか。マスコミの動静をマスコミが報じないのは不思議だ。情報の受けてにとっては重要なことなのに。参照 http://www.enpitu.ne.jp/usr4/45126/diary.html※※冥王星がついに惑星から降格する。といってもこれもしょせんは人間界、それも「天文学者」というごくごく一部の人達の話で本当はどうでもよことかもしれない。はるか遠くで冥王星と名づけられた岩の塊がカロンというもう一つの岩と一緒に長い時間をかけて太陽の周りを回っていることには変わりないのだから…。しょせんは定義の問題、つまり人間がそれをどうよぶかだけの問題。ちょっと話はとぶが、竹島も島から降格したらどうなのだろうか。あれはどうみても島というよりも大きな岩ではないか。そしたら韓国との紛争はなくなる?そういうわけにもいかないのか。
2006年08月25日
コメント(12)
-
冥王星
惑星の数を12個にするとか8個にするとか、天文学会ではもめているらしいけど門外漢レベルでは9個のままでよいのではと思う。あの水金地日木…もすっかりなじんでいるし、その中では冥王星だって不可欠である。そしてまた冥王星はさそり座の主護星で生と死を司る神秘の星として星占いでも定着しているし、SFでも冥王星のでてくるものがいくつかある。日本のSFでも、冥王星の基地にたまにやってくる地球からの連絡船を人々は「春」とよんで心待ちにする話などもあったっけ。そしてまた遠い将来恒星間飛行が不可能だと判明したら、人類は冥王星の基地から空を見上げて宇宙での絶対的孤独をかみしめるだろうというエッセイもあったが、これだってやはり海王星ではぴんとこない。
2006年08月24日
コメント(4)
-
アジアでも落ちこぼれゆく日本人の英語力
今朝の日経新聞にアジア圏における英語教育熱の記事があった。これによると中国、韓国、タイではすでに小学校からの英語教育が行われており、タイで小学生が習う単語は1000以上に上るそうである。これに対して日本では中学生(小学生ではない)が学ぶ単語は900。これではイソップ物語を読むくらいがせいぜいで、とても外国語を読む楽しさを体験するなどはできないであろう。日本の子供の英語力は欧米に比べてはもちろんアジアの中でも大きく遅れをとっている。小学生の英語教育導入の是非の議論でなぜこうした現実がもっと紹介されないのか不思議である。国語は日本人のアイデンティティーだとか、自国語が先だとかの議論を、英語を自由に操るエリート達がしている構図は愚民化政策をめざしているものとしか思えない。たしかにヨーロッパ人の中には自国語に強い誇りを持っている人もいるが、彼らとて英語ができないわけでは決してない。英語ができて使わないのと、初めから英語ができないのとでは天地ほどの開きがあることをよく認識すべきであろう。教育政策の目標は一にもニにも外国語を含めたたしかな学力の育成である。それに比べれば愛国心を書きこむための教育基本法の改正など、本当にどうでもよい話なのに、どうして誰もそういわないのだろうか。
2006年08月22日
コメント(16)
-
外国の名前
子供に人気の絵本で「うさ子ちゃん」シリーズというのがある。かわいらしいウサギの女の子を主人公にした本で、作者はドイツの作家のブルーナである。「うさ子」というのはもちろん翻訳で、もとの本ではミッフィーという。ミッフィーが「うさ子」となったのは、この本が最初にでた当初には、こんな発音のしにくい(フィなんていう音はもともとの日本語にはない)名前よりは、子供向けの本でうさぎの女の子の定番の名前になっている「うさ子」の方がよいと判断したからだろう。これが今だったら、外国の名前に子供でもずいぶんなじんでいるし、ミッフィーでもよいのかもしれない。※同じことは、ケストナーの児童文学「点子ちゃんとアントン」にもいえる。点子というのは、小さい女の子という意味のあだ名で原文では「ピュンクトヘン」である。この本の初訳が出た頃にはピュンクトヘンなんてのはそれこそ舌をかみそうな名前だったのだろうが、今だったら全然問題でない。これもそろそろピュンクトヘンに戻した方がよいのではないか。いくら小さいからといって「点子」なんて呼ぶのは、日本語の語感ではほとんどいじめである。※物語の登場人物の名前とかは、よほどのことがない限り、原文を極力活かした方がよい。「ロードオブリング」の翻訳で剣士アラゴルンの名前がなぜか「馳夫」と翻訳されていたがあれなどは最悪である。明治大正の昔ならいざ知らず、今は純和製ゲームでさえも外国風の名前の登場人物が活躍する時代になっている。変な和訳はイメージを損なうだけで百害あって一利なしではないか。※このようなことは物語や絵本の登場人物にかぎらない。新たな惑星の名前についてS新聞では「美しい和名を公募してはどうか」と主張していたが、セレスやカロンじゃなぜいけないのだろうか。この名前はすでに最大の小惑星の名、あるいは冥王星の衛星の名として日本の天文好きにも定着している。そしてその外側のUBなんとかについてもジェナという美しい名がある。世界中がセレスと呼び、カロンと呼んでいる星を、日本だけが別の名で呼ぶ理由などはない。そんな情報の孤島化は御免被りたいものである。
2006年08月21日
コメント(7)
-
チンギスハン~世界を創った男
今年はチンギスハン即位800年ということでモンゴルでは大々的に記念行事が行われているという。以前の日記にも書いたが、靖国を侵略の象徴というのなら、チンギスハンはそれこそ大侵略者の象徴である。侵略の被害を受けた国から批判の声があがってもよさそうなのにそれがないのは、800年という時の経過よりも、たぶん今のモンゴルが昔日のおもかげもない貧しい小国になっているからだろう。逆にいえば日本が豊かな大国であるかぎり、靖国参拝をやめようがなにしようが、侵略の謝罪を求められるに違いない。※チンギスハンといえば今、日経新聞に堺屋太一の「チンギスハン~世界を創った男」が連載されているがこれがけっこう面白い。よくある合戦ものや冒険ものではなく、大帝国を築くまでの組織運営や経済政策に焦点をあてた一種の企業小説となっている。たしかに企業小説としてみれば、13世紀初頭の漠北に生まれた人物が世界征服という最大のプロジェクトを行ったのだから、これ以上、スケールの大きい話はちょっとないだろう。興味深いのはこの小説の中でチンギスハンは「国にへだてなく人に差別のない社会をつくろう」と一種の理想を語っている点である。これは史実なのか、それとも独創なのか…。たとえ独創だったとしても、あれだけの大帝国の築くのだから、その基盤には、なんらかの理念はあったのではないか。ただ略奪のためだけに版図を広げたというのはちょっと考えにくい。サラセン帝国拡大の背景には宗教があったし、ヨーロッパによる植民地化も布教活動を伴っていた。※もし、堺屋太一の小説にあるようにチンギスハンの理想が「人に差別のない社会をつくる」ということだったら、それはそれで興味深い。そうした平等という理想こそ、社会主義や共産主義の思想のルーツというものではないか。そうだとしたら社会主義政権下のモンゴルでチンギスハンが批判的に語られていたのは皮肉というしかない。当時は、モンゴル人の前でチンギスハンのことを語るのはドイツ人の前でヒットラーの話をするようなものだと書いてある旅行書もあったくらいである。本当のところ、チンギスハンが版図を広げるにあたってどんなことを考えていたのかは想像するしかないのかもしれないが、やはりモンゴル支配化の統治政策には、かなりみるべきものがあったのではないか。単なる収奪や略奪だけが行われたのでは、少数のモンゴル人があれだけの地域を相当期間支配したことがどうしても理解できないからである。このあたり、今後、堺屋太一の小説ではどのように解説されていくのかも楽しみである。
2006年08月20日
コメント(6)
-
日本の戦争責任
日本の戦争責任についてどう考えるかと問われたら、わからないというのが正直なところである。一つはそもそもあの戦争で日本が責任を負わなければならない行為とは何だったのか。そしてもう一つは、そんな責任を問われるような行為について、誰が責任を負うのか。この二点である。※前者について考えてみる。日本軍の残虐行為は否定しないが、それと原爆投下やシベリア抑留、匪賊による襲撃の残虐さの程度においてどう違うのだろうか。戦勝国の行為は糾弾されずに敗戦国の行為のみが問われるのも理不尽なら、日本の行為がナチドイツの行為と並列されるのはもっと理不尽だ。だいたいホロコーストのように、敵でもない支配地域内の少数派の市民を組織的に抹殺するような行為は一般の戦争の残虐さとは異質なのではないか。南京で虐殺があったとしてもそれは市民にまぎれたゲリラが相手であって、収容所で抵抗の手段のない市民を殺害するのとは全く別の話である。※責任を負うべき人となるともっと分かりにくい。一番責任のありそうなのはA旧戦犯なのだろうが、彼らにしても、あの難局で誰かが総理や大臣を務めなければならず、たとえ彼らではない別の人達がその席にいたところで戦争を避け得たとも思えない。国民の多くもそれをわかっていて、だからこそ、A級戦犯遺族に恩給が支給されても、ほとんど反対の声がでなかったのではないか。あの戦争について、誰か少数の特定の人々の責任に帰すということ自体がどうも無理なのではないかと思う。 ※このように日本の戦争責任というのはつきつめていくとよくわからないのだが、じゃあ、日本が戦争責任をなにもとってこなかったかというとそんなことはない。敗戦国としての賠償責任は負ってきたし、その責任は果たしてきた。週刊新潮のコラムによるとスイスにまで日本からの賠償金が支払われたというので驚きである。そしてまた、戦後の世界秩序の中で敗戦国としてのハンディは負ってきたし今も負っている。国際連合はもともと連合国と訳すのが正しいし、その中では戦勝5カ国がP5として特権的地位を有している。従って日本が常任理事国の地位を求めたところで、それは第二次大戦の戦勝国クラブとして発足した国連の基本性格自体を変える話になり、とても無理であろう。※賠償責任と国連内での旧敵国としての扱い。これだけで戦争責任は十分で、これ以上、いったい何を謝罪しろというのだろうか。
2006年08月19日
コメント(4)
-
社会主義体験ツアーが人気?
おとといの朝日新聞国際面の記事にはびっくりした。ポーランドで「社会主義体験ツアー」というのがあって、観光客の人気を博しているらしい。東ドイツ製の自動車トラバントに乗り、労働者レストランで食事をし、ホテルに着くと秘密警察の踏み込みなどのどっきり企画もあるという。そのうち労働収容所の体験ツアーも企画するらしい。「社会主義体制」もすっかり歴史の遺物になったということなのだろうか。※記事では「現代史の一断面を感じることができた」というカナダ人観光客の言葉が紹介されていたが、当のポーランド人の反応はどうなのだろうか。秘密警察とか収容所とか思い出したくもない人もいるだろう。それとも当時の食事とかスローガンとかそうしたものにひたりたい客にうけているのだろうか。映画「グッバイ、レーニン」の中で消えた国東ドイツの宣伝歌を歌い、「まるで東ドイツの同窓会みたいね。」という場面があるが、案外そんな感じなのかもしれない。そういえば中国でも最近、紅衛兵スタイルのウェイトレスが給仕をする「文革レストラン」というのがあってけっこうな人気だという。※もっとも中には、こうした作り物ではなく、本物の「社会主義」を体験したい人もいるだろう。いわば一種の秘境探検ののりである。韓国では以前から北朝鮮への金剛山観光が行われており、多くの人がお金をおとしているのだが、数年前ごく普通の主婦が「脱北者は韓国で幸せに暮らしている。」とガイドに言ったということで、一週間も抑留されたことがあった。帰国の時には、担架にのった、まことに痛々しい姿だったのだが、この件については日本のマスコミではほとんど報道されていない。旧社会主義国のどっきり企画とは違って、実際の閉鎖的国家(北朝鮮の実態は「社会主義」とは何の関係もないと思うが)に行く際には、たとえ観光のつもりでもそれなりの覚悟が必要なようである。
2006年08月18日
コメント(4)
-
太陽系12惑星&侵略の謝罪
おなじみの水金地火水…の太陽系9惑星に3惑星が新たに加わることで12惑星になるかもしれないという。太陽の周りを回る天体には様々なものがあり、特に小惑星のようなものまでも考えると、結局はどこまでを「惑星」と定義するかが9個であるか12個であるかの分かれ道となる。冥王星の外の惑星などは冥王星よりも大きいので文句なしに入りそうだが、セレスやカロンを惑星とするかどうかは基準の問題でしかないように思う。最も高い山や最も大きい湖といえば誰でもわかるが、最も低い山や最も小さい湖となると答えるのが難しいという。結局それはどこまでを山というか、どこまでを湖というかという定義の問題に帰着するからだ。惑星もなにかそれと似ている。そしてまた惑星の定義には一定以上の大きさであることのほか、形状が球形である必要があるという。なぜ球形でなければならないのだろうか。そえこそ趣味の問題のようにも思えてしまう。最後にまた名前の問題もある。セレスとかカロンについても和名をつけるのだろうか。セレスは穀物の女神なので穀神星とか、カロンは地獄の番犬なので冥犬星とか…それはやめた方が良い。外国の人名に慣れていない昔とは違う。「指輪物語」の翻訳をみたとき、剣士アラゴルンをわざわざ「馳夫」と翻訳してあってげんなりしたけど、その愚をくりかえしてはならない。※靖国神社についてはなぜ侵略のシンボルに参拝するのかと近隣諸国からの批判がかまびすしい。いったい侵略の謝罪というものはいつまで続けなければならないのだろうか。モンゴルではチンギスハン即位800年ということで官民あげて盛大に記念行事を行っているという。軍国日本のやったことも侵略かもしれないが、チンギスハンこそ侵略も侵略、それも大侵略である。周辺国だけではなく、ロシア、ポーランド、ドイツからだって批判の声があったっておかしくない。でも、おそらくモンゴルではチンギスハンの侵略を謝罪するなどは、発想すらないのではないか。別に軍国日本のやったことを誇りに思えとはいわない。ただマスコミがマッチポンプのようにことさら靖国参拝を大報道するから、それに呼応して近隣諸国が問題視しているという面があるように思えてならないのである。
2006年08月17日
コメント(4)
-
ハウルの動く城
「ハウルの動く城」をみた。公開中の批評が芳しくなかったので、あまり期待してはいなかったのだが、すごくよかった。たぶん他のジブリ作品に比べると、絵のタッチがどことなく子供向けアニメのようにもみえるところがあり、それが評価の低かった原因なのだろうか。※これをみてあらためて思ったのは、極彩色の異世界ワールドはやはりアニメの本領だということ。極彩色という点では「千と千尋の神隠し」にも共通するのだが、個人的にはこちらの方がはるかに好みだ。「千と千尋の神隠し」ワールドが夜店や観光地の書割の極彩色なら、「ハウルの動く城」は純粋メルヘンの花園の極彩色といった感じだろうか。そしてなによりも、やはりハウルがすごく素敵で、最初の空中散歩の場面など、見るだけでうっとりする。こういうのって実写でやろうとしてもまず無理だろうな。※「自分をきれいだと思ったこともない」と言う主人公のソフィーだが、物語の中ではとにかくもてる。超美形魔法使いハウルは最初からソフィーの肩に手をかけ、空中に誘うし、物語の後半では「ソフィー、君を守るために、もう逃げるのはやめるよ。」と聞いただけで泣けるセリフをいう。それだけではない。彼の幼い弟子はソフィーを慕い、彼女が出ていきそうになると「ソフィー行かないで」と泣いてしがみつく。そして最後に登場する魔法で姿を変えられた王子はソフィーのキスで元の姿に戻り「愛する人のキスで魔法がとけた」とソフィーに礼をいう(ハウルの立場はどうなるんだ?)。しかもこの時のソフィーは魔法で90歳の老女になっていたという設定なのだから、愛は年の差を超えてということなのだろうか。現実世界では「自分をきれいだと思ったこともない」程度の容姿ならさしてもてるわけもないし、ましてや老女の姿だったら女性ともみなされないだろう。まあ、このあたりがメルヘンのメルヘンである所以なのかもしれない。※このアニメは魔法と近代兵器が同居する世界が舞台となっており、物語の背景には魔法使いもまきこんだ大戦争が描かれている。気の利いた評論家なら、このアニメのテーマを反戦にすえるのかもしれない。でも、実際には、戦争というのは単なる舞台装置で、テーマとしては愛の純粋さが強く印象に残る。特に、ソフィーがハウルに叫ぶ「私きれいでもないし掃除くらいしかできないわ。でも、あなたの役にたちたいの。」という言葉は、よく少女の気持を表しているように思う。メルヘンワールドならぬ現実世界のソフィーは、重い通学かばんをかかえながら、はるか前をさっそうと歩くハウルの姿をため息をつきながら眺めるばかりなのだけれど。
2006年08月16日
コメント(2)
-
首都圏停電
あの停電が起きたとき、まず思ったのはヒューズがとんだのではないかということだった。あわててチェックしたが異常なし。すぐ外にでてみたら何人もの人が廊下にでている。管理人への連絡方法を話しているうちに、どうやら停電はこのマンションだけではないらしいと気づく。さっそく様子見もかねて近くのコンビニに行ってみた。人通りはさしてないが、なんと信号が全部消えている。コンビニのある大通りまでいくと、交叉点の真中に警官がでて手と笛で交通整理をやっている。あの警官の動作の意味って、あのスタイルに慣れていた古い世代しかわからないのではないのだろうか。横断するのもちょっと怖い。コンビニは閉まっていたが、おじさんに頼むとつり銭なしを条件に新聞だけを売ってくれた。「私だってさっぱりわかりませんよ。」なんていいながら。思ったことその1:停電があると自宅だけ、マンションだけ…というように狭い地域内での可能性から考える。思ったことその2:信号機が消えるのは安全に直結する問題ではないか。警官の動作の見えない夜間やもっと交通量の多い時期だったら事故が起きてもおかしくない。※さいわい停電は短時間で終った。もしあれが2時間も3時間も続いたら夏場のことで冷蔵庫の食品などの損害は大変なものになっていただろう。送電線にぶらさがって修復をする人の様子、街頭で交通整理をする警察官の様子などもテレビに映っていた。この停電騒ぎで誰かを非難したり批判したりすることはたやすい。しかしまた停電が短時間で事故もなく終ったことの背景には、多くの人の地道な活動があったことも想像してみる必要があるのではないか。ことさらいうことではないのかもしれないが、停電のさなかに交通整理をしていた警察官やいち早く送電線の修理にあたっていた人々に、社会全体として静かな感謝と称賛をおくるべきであろう。
2006年08月15日
コメント(6)
-
あいまいな戦争責任
世の中で起きる森羅万象の中で、マスコミが騒げばニュースになるし、そうでないものは些事として忘れられて行く。アライグマが立ちあがったとか、アザラシ(どうなったのだろう?)が出没したなんてことも、マスコミが報道さえしなければ、ニュースですらなかったのかもしれない。※最近では総理の靖国参拝。これがどうして大ニュースになるのか、さっぱりわからないし、マスコミが騒ぐから近隣諸国も騒いでいるような感もある。問題は本当にA級戦犯だけなのだろうか?じゃあA級戦犯はだめだが、BC級戦犯ならよいのだろうか。戦犯のABCというのは、戦犯の等級と考えている人もいるが、これは等級というよりも種別である。捕虜虐待などの国際法違反がBC級で事後法としての「平和・人道に対する罪」違反がA級で、両者ともいわゆる「戦争犯罪」自体には変わりない。A級戦犯がまつられているから参拝するなというなら、BC級戦犯がまつられているから参拝するなということも、またいえるはずである。それとも、中国がA級戦犯がまつられている靖国神社参拝に反対しているから参拝するなというのだろうか。じゃあ、イギリスやオランダの旧軍人会が捕虜虐待をやったBC級戦犯への参拝に反対したらどうするのだろうか。戦争裁判では裁かれたがBC級戦犯は戦争の被害者…というのが多くの国民の実感ではないか。そして正直のところA級戦犯についても、被害者ともいえないし、指導者としての判断ミスは非難されるにしても、未来永劫石を投げつけられるような犯罪者であり極悪人だとおもっている人も少ないのではないか。だからこそ戦犯遺族への恩給支給が決まったときでも、国民の中に反対する声はほとんどなかった。※靖国の問題は結局のところ、日本が戦争責任をあいまいにしたところにはじまるように思う。ドイツのように一握りのナチス党幹部に責任をおしつけ、一般の国民はむしろ「被害者」としてしまえばわかりやすかったのだが、日本はそうはしなかった。天皇を守るために戦犯追及は中途半端におわり、戦争責任はまるで頂上近くまでいった石が土砂崩れとなって下に落下するように「一億総ザンゲ」と国民すべてに責任があるかのような形でなんとなくうやむやになってしまった。皆が悪ければ誰も悪くない。誰も悪くないからA級戦犯の遺族にも恩給は支給されたし、出所した者の中には要職についたものもいた。そしてまた、ドイツと違って、「あの戦争」を正当化する理屈が、戦後60年たっても次から次へとでてくる。戦争のせいで植民地が独立したなんていう理屈はドイツについてだっていえることなのに。※これからも戦争責任をあいまいにしたまま参拝を続けるのか。それともA級戦犯に責任をおわせる形にするのか。あいまいなままにすませるつもりなら、靖国参拝については、マスコミも大騒ぎせずに、夏の風物詩としてもっとひっそりやるようにしたらどうだろうか。
2006年08月15日
コメント(10)
-
最大の政治課題
昔は子供が無事に生まれれば一安心といわれたものだが、今日では子育ての心配はそれにとどまらない。非行にも登校拒否にもならずに、無事に高校や大学を卒業したとしても、実はその先が大変である。正社員として就職し、安定した正業につくというのが、入学試験などよりもよほど大きな関門になっているからである。いったいいつからこんな状況になってしまったのだろうか。かっては不本意な就職というのはあっても大抵の人が何らかの就職先をみつけ、これほど若者の失業や不就業が問題になっていなかったように思う。中高年のそうだが、特に若者にとっての安定した雇用の確保…これこそが今の日本における最大の政治課題であるように思う。これに比べれば教育基本法に愛国心を書きこむかどうかとか、総理が靖国を参拝するかどうかなんて、全くどうでもよい問題ではないか。今ならたぶん間に合うけど、後10年もしたらとりかえしのつかない事態になる。若年のワーキングプアとよばれる不安定就業者や失業者、ニートなどをみていると本当にそう思う。若者のフリーターやニートは決して自分探しの自発的なものや豊かな親が甘やかしているものばかりではない。むしろその逆の事例の方がずっと多いだろう。条件の悪い若者ほど正規雇用の場からはじかれているのである。就労率を男女別、年齢別にみると、男性の20代後半から50代までの就労率はのきなみ下がっている。20代後半は大学院進学率の上昇を反映して豊かさの証左という面もあるかもしれないが、男性の30代、40代、50代の就労率が低下してきている状況というのは、やはり問題なのではないか。
2006年08月14日
コメント(2)
-
格差で崩壊する社会
小泉政権もいよいよ終焉に向っている。終始支持率だけは高かったこの首相だけど、彼の執権中に世の中はどう変わっただろうか。思えば彼が総理になる前…「富裕層」なんていう言葉はあっただろうか。「ワーキングプア」とか「ニート」なんていう言葉はあっただろうか。急激に格差が拡大し、下のものが切り捨てられていったのがこの政権下で起きたことなのではないか。※格差といっても上が問題ではなく、下が問題である。そうしてみると、実際に起きている「貧困層激増」を「格差拡大」とよぶのも、問題の隠蔽なのかもしれない。こうした貧困層の中でも特に問題なのは、若年低所得者層だ。いまでこそ彼らの親が同居し、庇護することで、深刻な社会問題として噴出することを抑えている実態があるが、やがて親が高齢化し、彼らも中年となった頃にはどうなるのだろうか。※最近新聞でみた統計では、中年無職の一人暮し世帯で火災の発生源となる比率が非常に高いという。将来への希望があり、会社、家族など自分が属し自分が責任を負わなければならないものがあってこそ、人は自分の生活を律することができる。火災だけではなく、犯罪未満の小さな違法行為などもますます多くなっていくのではないか。駅員への暴行や、図書館の本の切り取り、自動販売機へのガムの塗りつけ…こんな行為が日常化すれば社会の負担も膨大となる。※それなのに政権中枢からきこえてくるのは、「再チャレンジ」とか「格差の何がわるい」といった、事態の深刻さを認識していない声ばかりだ。それこそ共産党でも大躍進しないと、あの人達はことの重大さに気づかないのかもしれない。
2006年08月13日
コメント(8)
-
核分裂家族の時代
木賃アパートに住む知人を訪問したときのことである。ちょうど知人が玄関のドアを開けたとき、下の階のドアから老女がでてきたので、なんとなく彼女の身の上についての噂話をしたことがある。なんでももともとは一戸建ての家で息子夫婦や孫と生活をしていたらしいのだが、息子が癌で亡くなってからは家を売却してアパートに越してきたのだという。ときどき同居している祖父母を「家族」と思っていない孫がいるという話をきくが、この老女と息子夫婦の子供も、たぶん家族ではなかったのだろう。たまたま息子を核とする二つの家族(母と息子、両親と子供)が同居していただけで、核となる息子がいなくなれば核分裂するしかないのである。※似たような話は最近の新聞の人生相談でも読んだ。母と弟夫婦、甥姪と暮していた中年独身女性が母の死後、弟夫婦に家を追い出されたというのである。これも、もともと母娘と母と息子夫婦、孫という二つの家族がたまたま同居していただけで、母が死亡すれば離れるしかなかったのだろう。この人生相談の回答子も頭を切り替えて自分の権利を守るようにとアドバイスしていた。※昔、といってもそんなに遠くない昔だが、夫の死後、その妻子と姑が同居しているのはごく普通のことだったし、配偶者のいない女性が兄(弟)一家と同居しているのも珍しくもなかった。今では、そういった変則的な親族世帯や三世代世帯はどんどん減って、かわりに一人暮しがどんどん増えている。いまや全世帯の2割は一人暮し世帯、これに二人暮し(老夫婦や老親と未婚の子供など一人暮らし予備軍世帯が多い)も加えると半数近くになる。家庭は社会の基盤だとか、夫婦と子供二人が標準世帯だとか、そんな時代ではないのである。
2006年08月12日
コメント(2)
-
老人介護職員の「暴言」
老人ホームで職員が入所者に「性的暴言」をはいたといって問題とされている。でも、これが老人ホームだからここまで問題とされたとも考えられないだろうか。家庭という密室の中では、数え切れないような暴言や虐待が行われているのではないか。この「性的暴言」をはいた職員に家族は怒っているという。じゃあ、この家族の方は90歳のその女性をふたたび家にひきとり、介護をするというのだろうか。たぶんそんなつもりはないだろう。さらにいえばこうした介護職員の「不祥事」は職員や施設を批判すればすむのだろうか。外国人を入れれば、問題は解決するのだろうか。たしかに言葉が通じなければ「暴言」の問題はなくなるのかもしれないが。※昔と今の大きな違いは、家族がもつ保障機能が大きく減退したことではないか。農村社会では家族が同時に経済基盤であり、それゆえ容易に解体することもなかった。皆が力を合わせていきるしかなかったし、家事も農作業も多くの人手が必要だった。でも今は違う。今の家庭は家族それぞれがめいめいの畑をもってそれぞれ無関係に耕しているようなものだ。だから妻が自分の預金名義をかってにかえたとか、義父母が自分の収入をあてにするのがいやだとかいってすぐに離婚にふみきる。誰も言わないが、中高年の離婚や家庭崩壊の背後には老親の介護や同居の問題のひそんでいるケースは多いと思う。※施設の職員の態度に問題があるからといって、いまさら老人を家族にもどすのは無理だ。ならば結局は解決のかぎは施設や職員を批判することではなく、施設ではたらく人々の待遇を改善していくことしかないのではないか。あの施設に録音テープをしかけ暴言を批判した方にしても、そんなヒマがあったら、ボランティアでもなんでも施設の仕事をやってみたらどうなのだろうか。施設が地域の中で孤立せず、ボランティアなどの多くの人の目にふれることが、密室での暴言や虐待をなくすなによりの近道であるように思う。
2006年08月11日
コメント(7)
-
「ラスコーリニコフの日」佐々木敏
K国のテロリストが日本の警察庁長官を狙撃するという内容の小説であり、もちろんこれは実在の事件をモデルとしている。あの事件で本当にK国は関係なかったのだろうか。何かまだ隠された真相があるのではないか。小説を読みながら、何度もそんな疑問を強く感じた。※以下、実際のあの事件を思い出してみる。あの時、事件現場にはK国のバッジが落ちていた。あのバッジはK国国民にとっては出身成分(階級)を意味する大切なものだという。すくなくとも土産物として買えるような代物ではない。ところがなぜか警察は現場に落ちていたK国のバッジについては、早々と偽装と判断してまともに捜査した形跡がない。たとえ偽装であったとしても、これほど入手しにくいものなら、入手経路をわりだすのが普通ではないのだろうか。狙撃事件だけでなく、あの教団が起こした一連の犯行全部にかかわることであるが、オウム幹部早川は何度もK国に行っていたという。彼が逮捕されてからの報道でもあるので、嘘ということはないだろう。ところが裁判が進むにつれて、彼のK国行きの話はほとんど報道されなくなった。いったい彼はなんの目的でK国に行っていたのだろうか。狙撃事件にかかわっていると疑われている信者を含め、何人かの信者はいまだに行方不明である。彼らは最高幹部というわけでもないし、さして組織の中枢にいたとも思えない。事件後次々と幹部信者が捕まったり自首しているなかで、なぜ彼らだけが完璧に姿を隠しているのだろうか。もしかしたら彼らこそが教団とK国の接点を知っているからだとみるのは考えすぎなのだろうか。そしてまた、もう一つの疑問、教団の最中枢にいた幹部がなんの刑事責任も問われていない、逮捕すらされていないということも、これと関係があるのだろうか。※警察庁長官狙撃事件のみならず一連のオウムの事件は、K国と深いかかわりがあるのだが、このことを政府は隠したがっており、警察もまた追求を控えているとみるのは陰謀論の読みすぎなのかもしれない。でも「ラスコーリニコフの日」を読むと、もしかしたらそんなとんでもない真相もあるのかもしれない…なんていう気もしてくる。
2006年08月09日
コメント(0)
-
神の数式
数学者であり天文学者であったガウスは天体観測をしているときにいつも測定誤差に悩まされていたという。そんな誤差をみているうちに次のようなことに気づいたらしい。・小さい誤差は大きい誤差よりも起こりやすい。・誤差にはプラスもあればマイナスもあり、ただしい測定値は誤差も含んだ測定値の真中辺にあるらしい。普通に考えればあたりまえのことなのだが、そこは天才でどこまでも凡人とは違う。この誤差の分布についてのグラフを書き、ついにこれが一定の式で表せる曲線であることを発見した。だから正規分布曲線のことをガウス曲線ともいう。※中学生の身長体重や同じ種類の植物の花や葉の大きさなど、自然界のたいていのものはこの正規分布曲線を描くというし、よくできた問題の点数分布もこの形になる。これに限らず、いくつもの要因が複雑にかさなりあってでてくるものは、ほとんどといってもよい。それだけではなく、ある集団からサンプルを選んで平均をとっていくとその平均の分布はかぎりなく正規分布に近づくし、2項分布といって両方の確率が同程度の二つのものを何度かくりかえしてでてきた結果をならべる(釘をいくつもうった板の上から多くの玉を落し、その玉がいくつもの釘にぶつかって落ちたところなど)とこれも正規分布曲線に近づくという。※この正規分布の数式こそは「神の愛した数式」なのかもしれない。ちなみにこんな数式である。f(x)=1/√2π*e^(-x^2/2)…どうもうまくできないが。こんなによくでてくる数式であり、曲線なのだが、目に見えるもので正規分布曲線を描いているものというのは不思議にないように思う。いくつもの要因がからみあってでてくる数値。もしかしたら火山噴火などのときに舞い上がった火山礫や溶岩が落ちて固まるところなどは数値で示せば正規分布を描くのかもしれない。そうだとしたら、正規分布曲線をみたときに、誰でもすぐに連想する火山の形というのも決してただ似ているだけではないのではないか。あの富士山の裾野の曲線…あれももしかしたら正規分布曲線の一部なのではないか?学のある人がいたら是非教えてほしい。
2006年08月08日
コメント(2)
-
たしかな野党は何してる?
格差拡大の深刻な中南米で次々と左派政権が誕生しているという。冷戦終結で社会主義があたかも終ったかのように言う人もいたが、貧困層の不満の受け皿としての社会主義は実はまだまだ健在なのではないか。※ここ数年間日本でも急速に格差が広がってきている。上が問題なのではない。問題は下の方、貧困層である。貧乏物語のような悲惨な労働者階級の実態なんて過去の話だ…と思っていたが、いつのまにかそんな悲惨な職場が社会のあちこちに広がってきてしまったようだ。それでも働ける層はまだいい。生活保護申請を拒否されて餓死、自殺者3万人、ホームレス数万人という現実がさらにその下にはある。冗談ではなく、日本にも本格的な左派政権が誕生する可能性はあるのではないか。犯罪者の人権大好きのうす甘サヨクではなく、困窮者の社会体制に対する不満を吸い上げ、経済の格差是正を本気で訴えていけば、必ず多くの人が支持するはずだ。※いったいたしかな野党は何をしている。党の運営をガラスばりにし、少数の人が長期にわたって代表を務めるような事態をさけ、オルグ、教宣、うたごえ、レク行事と様々な手段で党の主張を草の根に訴えるようなことをなぜしないのだろうか。そしてまた既存の社会主義国家の多くが失敗した原因を冷静に分析し、日本の現実をふまえた社会主義思想の深化、発展をなぜ目指さないのだろうか。※長野県知事選もそうであったが、選挙民がマスコミの一方的な報道におどるような時代ではない。格差こそ活力だとか、勝者を称賛しろといっても、とどまることをしらない格差拡大や生活困窮層の発生に不安を感じている人は多い。ニートやフリーターの問題にしても、現時点では多くの場合、彼らの親が問題をひきうけているかっこうになっているが、やがて親自身が高齢化してくれば、社会的に大問題になってくることは必至である。本格的な左派勢力の躍進…こんなことを期待している人は多いのではないか。※※ここでいう左派勢力とは本当の意味で声なき国民、立場の弱い国民の目線にたった勢力ということである。経済的には格差是正や労働者の権利保護を追及するが、治安については加害者よりも被害者の権利や応報感情の尊重を旨とする点でうす甘サヨクとは一線を画する立場をいう。
2006年08月07日
コメント(6)
-
長野県知事選挙結果に思う
長野県知事選にかぎらず最近では「予想外」の選挙結果がでることが多い。マスコミや政党がブームや「風」をおこそうとしても、それで人々は動かなくなってきたのだろうか。選挙といっても結局は投票所に足をはこぶのは個人個人の選挙民だ。〇〇党が推薦するからとか、△△新聞が好意的に報道しているからというのではなく、自分の判断を重視するというのであれば、民主主義の成熟をしめすよい傾向である。まあ、長野県の選挙結果をみれば、原色知事の目新しさが消えるとともにあきてきたこと、水害被害をみて「脱ダム」自体に疑問をもったことなどのいろいろな要因があるのだろうが、ことさら対立候補を推す政党がなかったことも理由なのではないか。前回の知事選ではこれみよがしに田中つぶしの対立候補をたて、それに対する選挙民の反発が現職圧勝という結果になった。今回はそれがなかったからこそ、昔ながらのタイプで人柄もまあよさそうな候補が勝った…ということではないか。こうした選挙民の姿勢の変化の背景にはネットの浸透もあるのかもしれない。誰でも考えたことを発信することができるようになったことで、マスコミ主導ではない別の世論形成のメカニズムができてきているのではないのだろうか。
2006年08月07日
コメント(0)
-
街角の空き地
去年辺りから日本の人口は減少局面に入ったという。そのせいだろうか。かっては日常的光景だった外で集団で遊ぶ子供たちの姿が消えた。公園を占拠するのはゲートボールのお年寄りかホームレスばかり。そして街を歩けば空き地がいやに目に付くようになってきた。その空き地も小規模宅地の敷地でしかないので大きな建物ができるわけでもない。かくして虫食いのように小さな駐車場ばかりが増えていく。※この空き地が目立ってきたのは少子高齢化のほかに他の理由もあるように思う。それはかってほど一戸建て住宅に住みたいと思う人がいなくなったのではないか。あの高度成長期に都会にでてきた次男坊、三男坊達は生活の基盤ができると、とにかく一戸建て住宅をほしがった。庭付き一戸建てこそは人生の成功の証であり、幸福のシンボルのようにも思われていた。どうしてあの時代、人はあれほど庭付き一戸建てにこだわったのだろうか。それはたぶん家というものを子供に継承していくもののようにとらえていたからではないか。ちょうど田舎で家を継いだ兄貴の家がそうであるように。そして自分達は老親と同居するつもりはなくても、結婚した子供夫婦や孫は自分達と同居するものと思っていたのではないか。そのためには三世代同居もできるような家を確保しておかなくてはならない。子や孫に囲まれて老後を過ごすのが幸福で、一人暮らしや施設の老人は不幸である。そんな通念もすいぶんながく支配していた。※でも今は時代は変わった。結婚した子供夫婦が親と別居するのは当然で、親の方も同居は望まない。子供と同居している老人の多くは実は子供夫婦とではなく、未婚の子供との同居だ。そんな時代なら一戸建てよりも管理も楽でいざとなればすぐに引っ越せる集合住宅の方がよいにきまっている。街の空き地は少子高齢化という以上の日本の家族構造の変化を反映しているのかもしれない。一戸建て住宅に三世代がわいわいがやがやと住んでいる家族は、すっかり少数派になってしまったように思う。
2006年08月06日
コメント(4)
-
容疑者Xの献身
窮極の愛の物語で、たぶんこんな愛は、フィクションの中にしか存在しない。主人公の心情をたどりながら、ふと「ニ都物語」を連想した。あれもまた窮極の愛の物語だから。推理小説としては、つっこみたくなるところもけっこうあるのだが、とにかく主人公のキャラとその愛の形が透明でせつなくて、おすすめの本である。ところで小説の標題になっている容疑者Xというのは何なのだろうか。主人公を意味しているとともに、Xというのは数学の世界では変数を意味する。数学者である主人公の完璧な計画が変数Xによって徐々に狂ってくる。そんな含意もあるのかもしれない。※「博士の愛した数学」もそうだけれども、小説の世界では最近数学者がはやっている。単なる「頭がいい」というのとは違って、「数学ができる」というのにはさらに別の意味があるように思う。もちろん「数学のできる」人は頭がよいのだが、いわゆる「頭がいい」人が皆数学ができるというわけではない。なんか「数学ができる」というのは凡人集団の「頭がいい」からさらに一線越えているような感じがする。それはちょうど、原始社会や古代社会で呪術師や霊的能力があるとされた人に人々が感じたであろうと同じような畏怖と尊敬の感覚が「数学者」という言葉にはこめられているのではないか。だからこそ「博士の愛した数学」や「容疑者Xの献身」の数学者が世間的にはかなり変な人であっても、十分に魅力的な人物造形になっているのではないかと思う。※※ ところでこんなサイトをみつけた。これって本物なのだろうか。http://wibo.m78.com/clip/img/127420.jpgこれ自体はどうでもよいことだと思うが、マスコミ人士が一般人をどうみているかという感覚はなんかよくわかる。
2006年08月05日
コメント(4)
-
韓流カルト「摂理」の教祖ほか
この頃よくテレビで放映される韓国カルト「摂理」の教祖って普通の人っぽくて本当に教祖なのだろうか。ふりをつけて歌っているところなんかコメディアンののりだし、水着の女性があつまった集会の様子なども宗教儀式というよりもイベントみたい…どうもよくわからん。※亀田の試合にはいろいろ意見があるようだけれど、ボクシング好きの家族によると、地元判定としてはそんなに変な判定でもないらしい。ダウン=負けというわけではないようだ。マスコミは亀田バッシングばかりやっているけど、ボクシングの判定の仕組みについて解説しているところはほとんどない。でも、素人目にはどうみても相手の選手の方が強そうだったし、ベネズエラの人達も同じ様に感じたのではないのだろうか。どっかの新聞のコラムにもあったけど、これでベネズエラの子供達が日本にどんな感情をいだくかちょっと心配。※外国人の感情といえば、映画「蒼き狼」をめぐってモンゴルで反対デモがあったらしい。当初は日本・モンゴル合作ということで、モンゴル側も全面的に協力するということだったが、いつのまにかモンゴル人が出演しない映画になっていたのが原因らしい。ジンギスカンといえばモンゴル人のアイデンティティーにもなっている民族的英雄だし、もう少し彼の国の人々にも配慮すればよいのに…と思う。いくら民間で作っている映画だといっても、なんとかならないのだろうか。モンゴルは北東アジアの国の中でも反日をいわない数少ない国ではないか。映画製作者側はこのジンギスカンの映画を世界中に配給したいと意気込んでいるらしい。でも、ジンギスカンのイメージって、国によってずいぶん違うだろうな。日本では英雄中の英雄というプラスイメージなのだけれど。
2006年08月04日
コメント(0)
-
「小さな政府」を標榜した小泉政権
すっかり過去のものとなっていた「小さな政府」論が息を拭き返し他のはいつ頃からだったろう。どうもそれはソ連邦が崩壊し、冷戦が終結したあたりからだったような気がする。社会主義体制の崩壊によって、共産主義イデオロギーが否定されるとともに、それがめざしていた平等とか連帯までも嘲笑されるようになったのではないか。そして悪平等(悪自由なんていう言葉はないのに)という新語が評論にあらわれるようになり、競争礼賛、優勝劣敗の政策が推賞されるようになった。そしてそんな政府の関与を極力ひかえ民間の自由競争を最大限に行わせるような政策が「小さな政府」なのであろう。※1917年、地上に始めての社会主義国家が出現したことで資本主義も大きく変わった。最低限の生活保障や労働条件の保証…そうしたものがあったからこそ、資本主義は勝利したのではなかったのか。社会主義の中にあった理念を資本主義もまたとりこんだのである。社会主義国家ソ連の消滅が、資本主義の再度の変質をもたらしているのだとしたら、それは歴史の逆行ではないか。※小泉総理のいう「小さな政府論」はそんなによいものなのか。そして自殺者年3万人、生活保護100万世帯、大量のワーキングプアを生み出した小泉政権ってなんだったのだろうか。
2006年08月03日
コメント(6)
-
デパ地下の試食コーナーが少なくなった?
ときどきデパ地下に行くのだが、最近めっきりみなくなったものがある。それは試食コーナー。たしか漫画「美味しんぼ」で試食で食事をすませるホームレスの話があったが、今ではそんなのまず無理だろう。試食コーナーが減ったのは、下流社会化で本当に試食で食費をうかせる人が増えたためなのか、ただのものは遠慮なく利用とばかりに試食だけして買わない客が増えたためなのか。一時代前なら、試食をしたらなんとなく買わなければ悪いと思っている人だってけっこういたのだが。※試食にかぎらないのだが、もらうものはもらう、ただのものは遠慮なく利用するという感覚の人が増えているのではないのだろうか。生活保護をはじめとする様々な扶助制度は、実際には権利のある人はもっといると思うのだが、公的福祉をうけることに抵抗があるとして申請をしない人も多い。まあ、これはプライバシーとか受給者の尊厳をふみにじるような窓口の対応にも問題があるのかもしれないが。たぶんこれからはそんな公的福祉を受けることにも抵抗のない世代がどんどんでてくる。今のフリーターとかニートとかよばれている層も今後中年になり親とも死別すればあっというまに生活が困窮するだろう。そうでなくても給料の低い不安定な仕事につきながら親と同居している若者は多い。そういう人達がどっと生活保護の窓口に殺到するような時代になったら、どうなるのだろうか。※利用できるものはなんでも利用する、でも、金でももらわないかぎり社会全体のためには舌をだすのもいやだ。こんなことでは世の中はなりたってゆかない。最近、図書館の本を平気で切り取るような人もいるというが、公的図書館だってこれでは税金がいくらあってもたりない。最近のプールの事故も公的責任(もちろんあるのだが)を問う声ばかりが聞こえてくるのだが、それ以前にあれほど大勢の人がいたのに、なぜ惨事の前に注意したりする人がいなかったのかも不思議である。
2006年08月02日
コメント(9)
-
デパ地下の試食コーナーが少なくなった?
ときどきデパ地下に行くのだが、最近めっきりみなくなったものがある。それは試食コーナー。たしか漫画「美味しんぼ」で試食で食事をすませるホームレスの話があったが、今ではそんなのまず無理だろう。試食コーナーが減ったのは、下流社会化で本当に試食で食費をうかせる人が増えたためなのか、ただのものは遠慮なく利用とばかりに試食だけして買わない客が増えたためなのか。一時代前なら、試食をしたらなんとなく買わなければ悪いと思っている人だってけっこういたのだが。※試食にかぎらないのだが、もらうものはもらう、ただのものは遠慮なく利用する…こんな感覚の人が増えてきたらどうなるのだろうか。生活保護をはじめとする様々な扶助制度は、実際には権利のある人はもっといると思うのだが、公的福祉をうけることに抵抗があるとして申請をしない人も多い。まあ、これはプライバシーとか受給者の尊厳をふみにじるような窓口の対応にも問題があるのかもしれないが。たぶんこれからはそんな公的福祉を受けることにも抵抗のない世代がどんどんでてくる。今のフリーターとかニートとかよばれている層も今後中年になり親とも死別すればあっというまに生活が困窮するだろう。そうでなくても給料の低い不安定な仕事につきながら親と同居している若者は多い。そういう人達がどっと生活保護の窓口に殺到するような時代になったら、どうなるのだろうか。※利用できるものはなんでも利用する、でも、金でももらわないかぎり社会全体のためには舌をだすのもいやだ。こんなことでは世の中はなりたってゆかない。最近、図書館の本を平気で切り取るような人もいるというが、公的図書館だってこれでは税金がいくらあってもたりない。最近のプールの事故も公的責任(もちろんあるのだが)を問う声ばかりが聞こえてくるのだが、それ以前にあれほど大勢の人がいたのに、なぜ惨事の前に注意したりする人がいなかったのかも不思議である。
2006年08月02日
コメント(0)
-
再チャレンジという言葉
再チャレンジという言葉をよく聞く。結果の平等より機会の平等。だからいったん失敗した者にも救済よりもチャレンジの機会を…ということなのだろうか。でも、本気で再チャレンジということをいうのなら、まず魁より始めてはどうなのだろうか。つまり公務員の受験資格の年齢制限と学歴制限の撤廃である。もちろん学歴制限撤廃には大卒程度の試験を高卒も受けられるというのと、逆に高卒程度の試験を大卒も受けられるというのと両方ある。フリーター枠なんていう変な議論をしなくても、30過ぎでも40過ぎでも採用試験を受けられるようにすればよい。公務員でそれをやれば、同じように新卒以外でも正規雇用をする民間企業だってもっとでてくるのではないか。※それにしても機会の平等って何なのだろうか。理屈の上では生まれた赤ちゃんはみな平等にオリンピック選手になる機会もノーベル賞学者になる機会も与えられているはずだ。でも、本当にそう思っている人はたぶんいない。人は受精の瞬間からDNAの遺伝情報が決まっており、大抵の人はいくら機会があってもオリンピック選手にもノーベル賞学者にもなれやしない。努力の価値は否定しないが、それでも人間はそれ以外のところで予め決まっている部分が多すぎる。残酷なようだが、いくら再チャレンジをいったって1度失敗した人はもう一度チャレンジしたところで同じようにうまくいかない確率が極めて高い。再チャレンジの価値は否定しないが、チャレンジしようもない弱者、このあいだ餓死した50代の身障者のような人にもぜひ目配りをしてほしい。
2006年08月01日
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-
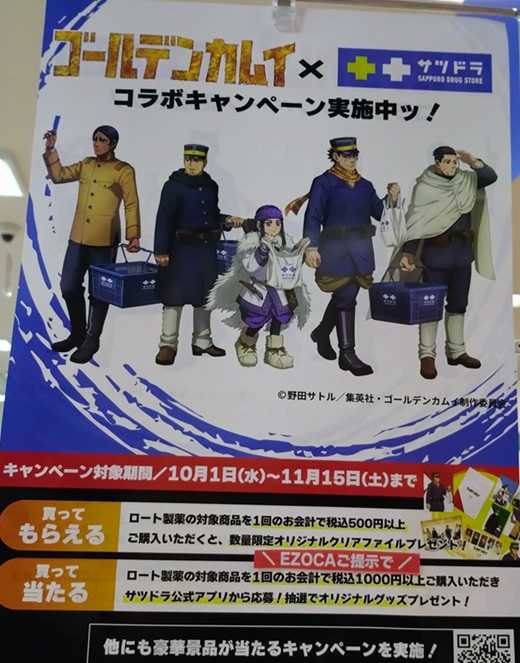
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- お買物マラソンお疲れ様でした&ゴー…
- (2025-11-15 17:02:59)
-
-
-

- ひとりごと
- 群青 谷村新司 東京都交響楽団
- (2025-11-15 00:45:46)
-
-
-

- みんなのレビュー
- 内勤です。⛅️(5度)寒い秋模様🍁
- (2025-11-15 14:51:05)
-







