2012年01月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

平目のポワレ、バルサミコ風味
平目は、卸す時に細かいうろこを庖丁ですき落とす事が多いが、市場の人が金タワシで楽々とうろこ落としをするのを見て、私も真似てみたらこれが楽!(笑)以来、ヒラメやコチやホウボウや鱈などのうろこが細かくて普通のうろこ引きの道具では落とせない魚は金タワシを使う事にしています。 前のブログで見せた平目がこんな風に魚料理になりました。ソースは1/2に煮詰めたバルサミコに軽く塩をしたものと、サルディニア島産の極上オーガニックオリーヴオイル、それにカマルグ産のフルール・ド・セルをパラリと振ってある。 魚が良いので、焼き加減も皮はカリッと身はやっと火が通ったくらいに仕上げてある。 バルサミコは高級品ほど濃度がある。というのは、アチェタイヤという熟成室が必ず屋根裏部屋にあって、夏は暑く冬は寒いというワインセラーとは真逆の環境で熟成させるんですが、大きな樽から、少しずつ小さなサイズの樽に毎年移し替えてゆく。その樽の材料の木材が何種類か決まっていて、それぞれの木材から年ごとに違った木のフレーバーを吸収しながら熟成してゆきます。 まず、トッレビアーノという白ワイン用の品種のブドウの汁を煮詰めて、モストコットという液体にします。屋根裏に運び、一番大きな仕込み用の樽(去年の液も少し入っています)に入れます。樽には半分くらいまでしか入れません。そうして、液面が空気によく触れるようにします。(これもワインと逆ですね。ワインの場合は樽をほぼ満杯にします)樽付きの酵母と酢酸菌が働いて、モストコットはアルコール発酵と酢酸発酵が同時にあるいは交互に進んで甘酸っぱい酢になっていきます。 10年物のバルサミコなら10番目の樽から出荷します。全部は抜きません。半分くらいです。そして減った分は、9年樽から補填します。9年樽には8年樽から、、、と繰り返してゆくわけです。夏はかなり気温が上がり、バルサミコは蒸発して濃くなります。この補填も、となりの一つ若い樽から行われます。その樽が、違う材質の木で作られているので色々な木の風味がつくわけ。 そういう訳で、長期熟成の高級バルサミコほど濃度があって、甘みもあるんです。そんな高級バルサミコの雰囲気を出すために普通の安いバルサミコを2倍か3倍くらいに煮詰めると熱で酸味も柔らかくなるし、甘みも増して良い感じになるんです。 私の場合は、1/2に煮詰めたバルサミコを少量常備してあります。たまにお勧めで出している、牛ヒレ肉のタリアータ。牛ヒレのステーキになりにくい細い部分を有効利用するつもりでやるのだが、人気があるので結局太くて良い部分までつかってしまう事が多いのだが、、、。タリアータはイタリア語で切るという意味ですが、肉を焼きあげて薄く切って皿に並べます。カマルグの塩、黒胡椒を挽き、ガーリック風味のオリーヴオイルとサルディニア島産の極上オーガニックオリーヴオイルをかけ、煮詰めたバルサミコを垂らし、パルミジャーノチーズをピーラーで薄く削って散らします。イタリアンのクラシックな料理ですね。普通は牛もも肉でやるんですが、ヒレならなお柔らかいという訳です。鹿肉でやっても美味そうですね。
Jan 30, 2012
-

3種肉のテリーヌと天然釣り物の平目
大きなボールに荒挽き肉を3種類。右手前が、エゾ鹿、左が富士幻豚、そしてシャラン産窒息鴨のモモ肉を各1キロずつに塩と黒胡椒とナツメグにカソナード(フランス産のブラウンシュガー) 私の場合、卵や粉などのつなぎは一切使わない、肉自体の結着力だけで固めるので、練り込むときに肉の温度が2~3℃なのが理想。これを体重をかけて手で練り込むと、冷たさで手がしびれて痛くなるほどなのだが、その温度で肉を捏ねないと滑らかにつながらないのだ。これは、ハンバーグや肉団子や餃子やシュウマイなどのを作る時も同じで、「挽肉は冷たくして練る」というのが、大事なポイント! 真ん中に少しフォアグラを入れて、テリーヌに仕立てる。程よい火の通し加減だとこのように美味しそうな赤身の色に仕上がる。火を通し過ぎると、くすんだ色になるし、食感もぼそぼそして美味しくない。何もつなぎを入れないテリーヌの火の通し加減ほど難しいものはないといってもいいくらいで、実に微妙な焼き加減なんです。 湯煎にかけてオーブンで蒸し焼きにするのだが、オーブンは160~170℃くらいの低温。さらに湯煎の温度が上がりすぎないように途中で何度か氷を入れたりするんです。冷やしてんだか焼いてんだか、、、という微妙な火の通し方なんです。 エゾ鹿、シャラン鴨、富士幻豚にフォアグラですから、このテリーヌ、美味い!!スープを作る時も、四足系と鶏系を混ぜると良い出汁が出ますが、強烈な赤身の美味さを持つ鹿、長期飼育で旨味が濃い富士幻豚、鴨の最高級品のシャランにフォアグラの風味と旨味ですからね、、、不味いわけがないですけどね、、。 本日のテリーヌで、黒板メニューにのってます。 天然の釣り物活け〆の平目。これは腹側。 背側は、黒いです。平目は、市場で陳列している時は必ず腹側の白いほうを上にして置いてあります。なぜかというと、天然の平目の腹側は必ず真っ白なんです。つまり、普段は砂に潜って、背中の保護色を利用して待ち伏せ型の狩りをする魚ですから、いつも砂に触れている腹側は陽に当たらないので、白いんですね。養殖平目は、生け簀で泳いで暮らしてますから、腹側も陽に当たるので、一部黒くなってしまいます。だから、市場では、真っ白な腹側を見せて並べて、「これは天然ものですよ」という意味を込めて置いてあるんです。これはプロの常識。 釣りあげたら、首の付け根と尾の付け根の背骨に包丁を入れて血抜きをして活け〆にします。こうすると、白身魚は身が締まって綺麗で鮮度良く肉が保てます。その活け〆にした庖丁の切れ込みを見せるためにも、腹側を見せて陳列するんですね。 釣り物の天然活け〆の平目は最高級魚のひとつです。刺身、混布〆、蒸し物、椀だね、焼き物、揚げ物(平目の天婦羅は美味いですよ!)、煮物などなんにしても美味しい魚です。 結構歩留まりの良い魚で、例えば鯛やスズキみたいな魚は、卸して正身(刺身で出せる部分)だけにすると、1キロの鯛なら300g取れればよいほうなんですが、平目1キロからは正身で500g以上取れます。だから、同じキロ単価、例えばキロ¥3000で平目と真鯛が並んでいたら、正身にすると真鯛はキロ¥9000近く、平目はキロ¥6000弱という事で、平目のほうがお得なんです。 まあ、それにしても高いのでめったに使えませんが、市場にお任せで頼んでおくと、たまに安くし出してくれることがあって、こうして使えるときもあるわけです。しかしこれを焼いて魚料理にしてしまうんですから、サンク・オ・ピエの魚料理、美味いわけですよね! あまり濃い味付けにはしたくないので、バルサミコと極上のオリーヴオイルのソースで召し上がっていただきます。今日からオンメニューですが、今日は昼夜とも予約でいっぱいです。このブログ見て、食べたい!と思った方は来週どうぞ。ここまで鮮度が良いと、上手に管理すれば、1週間は刺身で使えるくらいですからね。それに2~3日寝かせたほうが味が乗って美味しくなります。寒の平目は脂が乗っていて美味いですよ!
Jan 28, 2012
-

尾長鯛のポワレ、アンチョビとレモンのバター乳化ソース
尾長鯛は、鯛とはいっても赤ムツなどに近いフエダイ科の仲間、赤くてきれいな色のやや深海性の魚で、味は淡白ながら旨味はしっかりある白身魚。このようにポワレや塩焼き蒸しものや椀だねはもちろん、刺身でも美味しいし、混布で締めれば、さらにうまみが増して美味くなる。これが入ってくると、中落ちや尻尾のほうは、大抵私の夜のつまみになるという訳。 皮目をしっかりカリッと焼き上げ、身のほうは余熱を計算して、ギリギリやっと火が通ったくらいにしっとりと仕上げる。ソースは、アンチョビソースにレモン汁を加えて、バターで乳化させたもの。 小鍋にアンチョビソースとレモン汁とバターの冷たいキューブを入れてプラックの一番強火にかける。 あっという間にぶくぶくと沸いてきます。この沸騰する勢いが、泡立器の代わりになってソースが乳化する。 出来上がりはこんな感じ。しゃぶしゃぶ用のゴマだれに近いくらいの濃度があればうまくいったという事。 実はこのバターの乳化ソースの作り方は、とても非常識なやり方でフランス料理のソースがきちんと作れるプロの料理人に話すと、いつもびっくりされる。作り方があまりに非常識という事と、たった1人前ずつしか作らないという異常さ!しかも、作っておいた乳化ソースを温め直したり、煮詰めたりと、、、おそらくどんな料理の本にも書いてないような、目茶苦茶?なやり方だからだ。 興味のある方は、ここを見てください。代表的な乳化ソースである、ブール・ブラン(白バターソース)の非常にまっとうな作り方が書いてあります。注目していただきたいのが、絶対に沸騰させないこととか、弱火でゆっくりとか、作り置きはきかないとか、私がやっているのとは正反対のことばかり書いてあると思います。 以前、うちに研修に来たクリークの黒川シェフの目の前で作って見せたら、彼は眼が点になってました。(笑)「今何したんスか?」って言ってましたね。ソースが沸いてきたところで、軽く鍋を回すのがコツなんですが、とにかく火が強くてソースの量がせいぜい2~3人前くらいの少ない量じゃないとだめなんです。普通のやり方の真逆ですね。(笑) 話を整理しますと、普通のバターの乳化ソースは、弱火もしくは火から下ろした状態で、余熱を利用しながら、ゆっくりと注意深く泡立器を使ってバターが分離しないよう何度にも分けてバターを加えながら作る物です。沸騰は厳禁!しかもある程度の分量がないと作りにくいです。最低5人前以上、10人前くらいを作るのが一番やりやすい。出来たソースは、ぬるめの湯煎にかけて時々掻きたてながら、短時間なら置いておけるが、基本的に作り置きはできないし、冷めたものを温め直すことは、通常は出来ない。 私のやるバターの乳化ソースは、プラックど真ん中の強火でつくり、わざと沸騰させながらしかも材料は一気に全部入れてしまい、泡立器などろくに使わず、作る量は少ないほどやりやすい。3~4人前くらいが限度という、すべて正反対なわけです。しかも、温め直しはするは、作るときにガンガン煮詰めるはで、もう目茶苦茶なんですよ(大笑い) 昔テレビで見た限りでは、三国シェフはやってますね。このやり方。そのほかフランス人シェフでも結構やる人多いと思います。ただしレシピに堂々と書いてる人はいないかな?私の知る限り、、、。 で、一体どうしてこんなことができるのかというと、まずバター自体は冷たい塊の状態であれば、乳脂肪と水分と少しのたんぱく質などが乳化した状態で固まっているわけです。それをサイコロほどのキューブ状に切っておいて、激しく沸騰した水分と合わせると熱で融けるそばから、水蒸気が激しく水分とバターを撹拌してくれるのでバターが分離する間もないまま乳化が解けない状態で液化していくという訳。その時に激しく煮詰めてゆくと、どんどんソースの濃度が濃くなってゆく。もちろん煮詰めすぎれば分離しちゃいますけどね。 それで、温め直しができるわけは、手作りのマヨネーズと市販のマヨネーズの違いとでも言えましょうか、、。乳化が、しっかりできていると少々手荒に扱っても大丈夫なんです。もちろん、かなり熟練が必要ですけどね。 それで、このやり方の最大のメリットは、一人前ずつ作るので、ロスがないこと。20~30秒もあれば出来るので、盛り付け直前に仕上げられるので、熱々が出せるということか。バターは最近値上がりしているので、無駄を出さないというのはとても大切なことです。 このソースはプラックがないと厳しいですね。あと8センチとか10センチくらいの口径の小鍋が必要ですね。慣れないうちは、生クリームを少し垂らしておくとやりやすいです。これは、クラシックなブールブランの時も同じです。初心者は、はじめにバターを入れた瞬間に分離させてしまって、すべてパーにしてしまう事故をよく起こすからです。まあ、私の場合、どんなに失敗した場合でも修復可能な対処法をいくつも知っていますから、大丈夫なんですけどね。完全に分離してしまっても、元に戻せますから、、、。 フランス料理は、ソースが命なんてよく言いますけど、、、このバター乳化系のソースは一番難易度が高いんです。物理的に科学的に何が起こっているかをちゃんと把握しつつ理にかなった作業をしないとすぐに失敗します。私は日常的に長年やってますから、なんという事もないんですが、実はそう簡単にできることではないんです。(高笑)? まあ、普通は基本の乳化ソースの作り方をみっちり覚えてからの大裏必殺技ですね。良い子はマネしないでね!(爆)
Jan 27, 2012
-

Couteau クトー
銃刀法違反の押収物ではありません。(笑)私の愛用の庖丁です。この他にも10丁くらいあります。庖丁は、フランス語でクトーと言います。 上の2本は、全く同じもので一番上が新品の物。それを15年くらい使うとだいぶ細くなりますね。この2本は、スライス用ナイフで、スモークサーモンや刺身、骨付きの生ハムなどを切るのに特化したものです。かなり薄刃で、弾力があってしなります。先日弟子のブログに出ていたやつと同じです。彼のは、スペイン製ですが、これは、ドイツのゾーリンゲンのギーザーという会社のもです。フランス人も結構ドイツナイフの愛好者が多いようです。ギーザーはめったに売っていないので、ちびて使えなくなったときのために、同じものをもう一本買っておいたのでした。スライスナイフは、はじめから細身なんで、砥ぐとすぐ痩せてしまいますからね。 上から3番目は、フィレナイフとかソールナイフと言われるもので、これも薄刃でよくしなります。舌平目や平目を卸すのに適していますが、他の魚にも使えます。出刃庖丁のように一気にスパッと卸すのではなくて、骨から身をはがすような、刃の弾力を利用して、骨にそって剥がしていく感じですね。これも15年物です。 一番大きいのが、牛刀。文字通り肉切り包丁です。これは受注生産品で、特別サイズ。尺二寸ですから約40cm弱でした。もう20年以上使っているので、今は37cmくらいに減っていますが、、、カッパ橋の老舗の庖丁屋の鍔屋さんのものです。今作ってもらうと、5~6万はするようです。たしか当時は、¥45000くらいだったかと思います。鍔屋さんは、通常の業務で、庖丁が大きく刃こぼれしたり、折れた場合はいつでも新品に取り換えてくれるという、プライドが高いお店ですが、あいにく通常業務では、折れたりしません。(笑)これだけの刃渡りがあると、和牛のサーロインなど、かなり大きな肉の塊でも、すっぱり綺麗に切れて助かります。それから特大の西瓜もいくらでもかかってきなさいという感じ。スパスパ切れます。玉ねぎのみじん切りなら、1個30秒もかかりません。ただとにかくでかいですから、家庭用はもちろん、初心者にはむきませんけどね、、。 一番下のが、洋出刃です。これはほぼ魚卸し専用ですね。これも20年物です。よく砥ぐので、最初の大きさの3/4くらいになってしまいました。出刃の場合は、洋包丁でも片刃に刃付けしてあります。魚を一気にスッパリ卸すのにむいてます。 庖丁の手入れは、当然砥ぐわけですが、どうも、多くの人が砥ぎすぎるんですね。要は切れ味が復活すればいいわけですから、プロ用のきちんと刃の付いたナイフなら刃先のほんの百分の数ミリ程度砥げば、切れるようになるはずなんです。そこを通り越して、刃がまくれるほど砥いで、いったん切れなくなるほど砥ぎこんで、刃をつけ直すような砥ぎ方をする人が多いんですね。そんな砥ぎ方をしていたら、庖丁がすぐに痩せて使えなくなってしまいます。大事な道具なのにもったいないですよね。私の場合は、理にかなった砥ぎ方をしているので、20年以上も使えるんです。砥ぎすぎる人は、早いと3年くらいでダメにしちゃいます。そういう人は、休憩時間などに包丁一本を1時間くらいかけて砥ぎまくってますね。(笑)私は一番大きい牛刀でも2~3分しか砥ぎません。 料理するのにいろんなものを切りますが、庖丁の一番の強敵が実はパン、特にバゲットなんです。意外かもしれませんが、バゲットの皮のところ、クラストと言いますが、、、あれがすぐに包丁の刃をつぶしてしまいます。特に薄刃のぺティナイフなんかで、バゲットを切ってしまうと、もう完熟トマトの皮なんかとても切れません。砥ぎ直しです。だから私はパン専用に小さめの牛刀を一本あてがっていて、他のナイフでは絶対にパンを切りません。そのほうが衛生面でも安心ですからね! ちなみに刃物で物が切れるという事。実は科学的には完全に解明されていないそうです。つまり分子原子のレベルで、切るという事のメカニズムがまったく分かってないらしいのです。究明したら、ノーベル賞ものなんだそうです。不思議なもんですね、、、。
Jan 26, 2012
-

ジビエ尽くしのコース2012
ジビエ尽くしのコースが好評です。やっと画像がそろいましたので、アップします。まずは、アミューズ。 対馬のイノシシとエゾ鹿に少しシャラン産鴨も入れて、フォアグラも2割くらい、これをグレース・ド・カナール(真っ白なフランス産の鴨の脂)と少しの水分で80℃くらいを保ちながらゆっくりと煮崩してからペースト状に固めたリエット。新鮮な肉を使っているので、ジビエ独特の臭みなどは全くなく、力強い美味さがあります。 高知産の香りが良い山椒とバスク産の最高級唐辛子エスペレットを振りかけてあります。これだけでワイン1杯いけちゃう方なら、アルザスのゲヴェルツトラミネールがお勧め!山椒の香りとのマリアージュにしびれますよ。または、二人でワインを1本飲みたいという方なら、最初からこのジビエ尽くしのコースにお勧めの南仏ローヌのシラーの赤ワインでも大丈夫です。 手前が対馬産イノシシのモモ肉、奥がエゾ鹿の内もも肉で仕込んだ自家製のスモークハム。赤いんですがこれで火は通してあります。もちろん発色剤などは使わず、肉と塩のみ! 肉は、地中海のカマルグ産の塩で4~5日漬けこみ、低温長時間ローストで火を通した後一日置いて、8時間ほど冷燻にかけます。真空パックにかけて3日ほど冷蔵庫に置いて香りがなじむのを待って、-5℃の氷温庫に移してひと月ほど熟成させたものです。これは去年の暮れに仕込んでおいたもの。 鹿は、力強い赤身の美味しさ。イノシシは、赤身も美味いのですが、少しついている脂の美味さが最高です!対馬のイノシシは豊富なドングリを食べて育っていますから、イベリコ豚のベジョータのさらに上をいく感じですよ! この皿だけに合わせるなら、シェリーのマンサリーニャかもう少しコクがあるドライ・アモンチリャード、それからアルザスのゲヴェルツトラミネールも面白いでしょう。もちろん、シェフお勧めの南仏ローヌのシラーで通しても大丈夫です。 壱岐の網取りのカルガモのポワレとフォアグラのソテーにトリュフ風味のジャガイモのピュレ添え。ソースはトリュフエッセンス入りのバルサミコソースと鴨の焼き汁。 壱岐の網取り鴨は、鉄砲傷がないので肉が綺麗だし、現地で活け〆のように余分なはらわたを抜き、血抜きもしてあるので、臭みがない。塩で焼くだけで十分美味しい! フォアグラのソテーの下にはトリュフたっぷりのジャガイモのピュレ。ジャガイモとトリュフは好相性!フレンチでは定番の組み合わせです。同じ土の中の物同士なのか、びっくりするほどトリュフの香りが引き立ちます。そこにフォアグラのソテーが乗っているんですからもう最高ですね! これに合わせるワインと言うと、ものすごく贅沢を言えば熟成したシャトー・ペトリュス!下手をすれば軽く100万越え!(笑)とまではいかなくても、ボルドーの右岸系つまりメルロー主体で、まあ10年は寝かせたものが良い感じでしょうね。まあ、ここでもシェフお勧めのシラーが良い仕事してくれます。食事の初めから大きめのグラスで飲んでいれば、そろそろ開いて柔らかみも出てくる頃です。 左側がエゾ鹿の内もも肉、右の2切れが対馬のイノシシのヒレ肉。どちらも弱火でゆっくりと時間をかけてローストしてあります。 イノシシのヒレ肉はとても希少で、1頭から150~200gくらいの小さな肉が2本しかとれません。牛ヒレなら1本3キロくらいありますから、とても小さな肉なんです。だいたい二人に1本使ってしまう事になります。当然ヒレ肉ですから赤身でとても柔らかいです。 ソースは夏の間にたくさん採っておいた自家菜園のブルーベリーで作ったグランヴヌールソース。グランヴヌールというのは、「王様の狩猟頭」という意味です。木苺風味のワインヴィネガーと赤ワインに荒挽きの黒胡椒を加えて、強火で煮詰めます。ブルーベリーのコンポートと肉の出汁を加えてさらに煮詰めて、バター少しと生クリーム少しで仕上げます。 鹿やイノシシにグランヴヌールソースとくれば、答えはシラーしかない!というほど、鉄板の組み合わせです。南仏ローヌ川の上流から、コート・ロティ、エルミタージュ、シャトー・ヌフ・デュ・パープなどシラー主体のワインの出番ですね!シェフお勧めのシラーはお手頃価格の物とちょいと良いやつと、用意してありますよ! お楽しみデザートは、濃厚!カシスのソルベとフランボワーズ風味の生チョコ・パヴェ。この二つは、メインの肉料理のブルーベリーのソースとシラーのワインのベリー系果実味の余韻を楽しんでいただくための物。手前のケーキは、アーモンド粉にイタリアの栗粉を混ぜた生地にラム酒風味のレーズンとローストしたクルミを入れて焼いたもの。これは、鹿やイノシシたちが野山で木の実を食べていたことをイメージしたもの。これには、もちろん、、、 さかもとこーひージビエ尽くしのコース専用ブレンド!これがまた美味い!通常こーひーには難しいはずのカシスやフランボワーズを軽く受け止め、アーモンドと栗粉の焼き菓子をきっちりサポートしてくれます。 ジビエ尽くしのコース2012は、大好評、3月中旬くらいまで、ジビエが入荷する間はやっていきます。ご予約お待ちしております。
Jan 22, 2012
-

エスカルゴのココット焼き
エスカルゴのブルゴーニュ風です。パセリとニンニクが入ったバターソースが基本ですが、私の場合はアンチョビを入れているのが特徴です。 よくエスカルゴの殻に詰めて出してくるお店がありますが、あれだと専用のエスカルゴハサミとかエスカルゴフォークが必要になるし、食べ方を知らないととても食べにくいです。だから私の場合はもっぱらココット焼きにします。 それにエスカルゴもピンキリで、台湾やインドネシア産の海のサザエの仲間みたいなのをエスカルゴとして缶詰にしてあるのなら結構安いのがあります。フランス産の缶詰ならその倍以上の値段。一番美味しいのは、ブルゴーニュ産の冷凍品で台湾やインドネシアの3~4倍くらい。それの空輸物でチルド品がありますが、それはフォアグラより高いくらいでちょっと使えません。あと、エスカルゴの殻って意外に高いんです。台湾やインドネシア物に比べると、殻のほうが高い!(笑)極悪な店だと殻を洗って使いまわすなんて話も聞きますが、、、そんなこともあって、私はエスカルゴの殻は使いません。 エスカルゴというのは、もともとワインを作るぶどう畑の害虫で、葉っぱを食べてしまうんですね。それをワインの本場ブルゴーニュは内陸で魚介が少ないですからカタツムリを食ってみようかといことになったんでしょうね。ニンニクを利かせてやればくせも抑えられて美味しく食べられという訳です。 まあ、日本の場合は焼いて美味しい貝類がいくらでもあるので、ツブ貝やバイ貝とかサザエとかで作れば美味しいですね。 貝料理ですから、辛口の白ワインやシャンパーニュが合いますが、ニンニクが利いているので軽めの赤ワインも面白いですね。
Jan 19, 2012
-
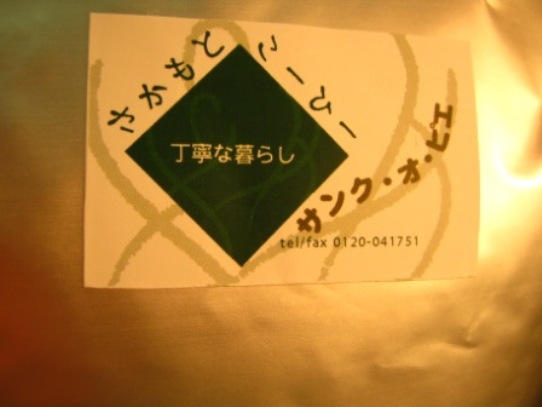
ジビエ尽くしのコース専用さかもとこーひーと鴨話のつづき
サンク・オ・ピエでは、2009年の12月からさかもとこーひーを使わせてもらっています。特に季節のコースやクリスマスディナーなど、特別メニューのときにはそのデザートに合わせた特別なブレンドを仕込んでもらっています。 レストランでさかもとこーひーのようなスペシャルティーコーヒーを使っている店はかなりの高級店でもきいたことがありません。まして、デザートとこーひーのコラボレーションなんていう事をやっているのも、おそらく世界的に見ても稀有なことだと思います。 今やっている“ジビエ尽くしのコース2012”にも、専用ブレンドがあります。そのブレンドの仕込みのプロセスが、坂本さんのブログに書いてありました。 さかもとこーひーとサンク・オ・ピエのコラボもいよいよ玄妙の域に達してきた感があります。今回のブレンドも、実にすばらしくマッチして、、、実に上品な味わいで、ワインでいえばフィネスという言葉がぴったりです。それも、デザートだけに合わせたわけではなく、食事全体の流れや、一緒に飲むワインの後味なども考慮したうえで、最後にデザートにたどり着いた時にあるべきこーひーという、実にこだわったつくりなんですね。 プロのこだわりなんていうと、素人にはわからない難しい世界?なんて思うかもしれませんが、これは坂本さんと私の間では楽しい遊びなんです。遊びというのは、真剣にやるほど楽しいわけで、、特に職人仕事は、遊び心や楽しむ姿勢がないとだめですね。 美味しいこーひーを作るこーひー屋さんはたくさんいるでしょうし、美味しい料理やスイーツを作る職人もたくさんいます。でも、自分のこーひーがどんな場面で何を食べながら飲まれるか、考えて作る人はあまりいないでしょう。料理人やパティシェも自分の料理やお菓子にどんな飲み物(こーひー紅茶やワインや酒)が合うか、考えて作っている人は少ないです。 魚だから白ワイン、肉には赤ワインなんていう、大雑把な話ではなくて、赤ワインなら、ピノなのかカベルネなのかそれともメルローとかシラーなのか?樽の香りが利いているか?いないか?熟成した古酒かフレッシュな新酒か?果実味、ミネラル感、タンニンの強さ、、、、etc あらゆる要素を考慮してワインを選びます。 坂本さんも私も長年飲み物と食べ物のペアリング(マリアージュ)を研究してきたので、今では実際に実物がなくても、頭の中で料理やコーヒーが出来てしまいます。ですから、コースに合わせたブレンドをお願いするときにも、メールで簡単に料理の説明をするだけなんです。坂本さんは私の仕事を熟知してますから、これだけで充分なんですね。ジャズミュージシャンが簡単なコード譜だけで演奏できるのと同じ感覚です。 先日のカナール・デ・マレを焼いたところ。シャラン産の鴨よりも気持ち発色が良い感じです。柔らかいし、風味も高いです。美味いですよ!
Jan 15, 2012
-

鴨話、二題
昨日あたりから寒いですね。うちの猫の日向ぼっこ。前足と尻尾で顔を隠して眩しくないように丸まってます。 これは、シャラン産窒息鴨のモモ肉のコンフィ。ソースは、イチジクのピュレ入りのバルサミコソースです。 コンフィというのは、塩漬けにした肉をラードやガチョウや鴨の脂で約80度くらいの低温で長時間煮込んだものなんです。揚げ物ではありません。脂で煮込むんですね。ちょっと日本料理にはない発想ですね。 もともとは保存食で、冷蔵庫がない時代は、しっかりと塩漬けにして、ラードで煮込んで、そのまま涼しいところで脂ごと壺などに入れて固めれば、空気から遮断されて、保存食になったわけです。缶詰やもちろん真空パックもない時代の話です。 で、今は冷蔵庫も真空パックもある時代なのになぜコンフィなんぞ作るのかと言えば、独特の魅力があるからなんですね。つまり脂で煮るので、水やワインで煮るのと違って肉の旨味が溶けださないですから、肉自体はシチューの肉のようにとろとろに柔らかいのに味が抜けてないから、美味しいわけです。さらに鴨のコンフィの場合は、仕上げに皮目をカリッと焼き上げるので、独特の香ばしさが出て、煮込み料理と焼き物の良い所取りみたいな、かなり美味しいところを持っていっている料理なんですね。 もちろん、今は保存目的ではないコンフィですから、塩漬けは薄め。食べてちょうどよい味でたくさんです。昔のコンフィなら、モモ肉一本でジャガイモ10個ぐらい食べられそうなほど塩っぱいんです。ワインもがぶがぶ飲む感じです。 鴨と相性が良いイチジクの風味の甘酸っぱいバルサミコソースが、味わいを引き立てます。今お勧めでやっていて、残りあと6人前くらいです。 これは、Filet de canard des marais au sang(フィレ・ド・カナール・デ・マレ・オ・サン)カナール・マレという、シャラン産鴨と同じヴァンデ県で作られているやはりこれも窒息鴨です。 かつて、この地域で作られていたスーラン鴨という美味しい鴨があって、それがまた繊細で世話が焼ける種類だったため廃れてしまって絶滅寸前になったそうです。そこで、近年遺伝子の研究などから、交配によりスーラン鴨に近い鴨の品種の固定に成功して“カナール・デ・マレ(沼地の鴨)という名前で少しですが出回るようになりました。 この鴨は、今パリでもっとも人気の三ツ星「ラストランス」(日本の白金の三ツ星「カンテサンス」の岸田シェフの師匠であるパスカル・バルボ氏の店)が、かなりの量を買い占めたことでも、業界でちょっと話題になりました。(まあ、普通はこんなんこと誰も知りませんが、、、笑) 実際に使ってみると、シャラン産鴨より柔らかで緻密な感じで、窒息による鉄分的旨味もしっかりあるので、実に美味しい鴨だと思いました。素材にとことんこだわることで有名なパスカル・バルボシェフが買い占めるのもうなずけます。 それで、この鴨、(やや入手困難ですが)シャラン産鴨の代わりに使う事にしました。お店のメニューには、シャラン産窒息鴨の表記のままですが、今年からカナール・デ・マレに入れ替わってます。コスト的にはシャラン産窒息鴨と同じなので値段も一緒です。しばらく使ってみて、安定的に入荷が確保できそうなら、メニューの表記も変える予定です。気になる方は、予約の時に「カナール・デ・マレある?」と確認してくださいね。 この他にもジビエ尽くしのコースの中で、壱岐の網取り鴨もつかってますので、今サンク・オ・ピエでは美味しい鴨が目白押しですね。
Jan 12, 2012
-

サンク・オ・ピエ ジビエ尽くしのコース 2012
壱岐の網取りカルガモ。 対馬のイノシシのモモ肉。 エゾ鹿の内もも肉。 アミューズ用に鹿とイノシシのリエットを作るところ。フォアグラも結構たっぷり!フランス産の鴨の脂と少しの水分で約80度を保ちながら半日ことこと煮崩れるまで煮込む。それを脂ごと、ペースト状に練り上げてかためたものがリエット。カリッと焼いたバゲットにのせてお出しします。 新年第一弾のお勧めコースは、、、サンク・オ・ピエ ジビエ尽くしのコース2012!!Cinq au pied.Menu de gibier 2012サンク・オ・ピエ ジビエ尽くしのコース¥7500 (2名様より承ります)ご予約限定です! 3月中旬ころまでの予定です(4~5日前までにご予約ください)Amuse Rillette des gibier au foie gras et au piment dit espelette et pivre du japonアミューズ、ジビエ尽くし(エゾ鹿と対馬のイノシシ)のリエット、フォアグラ風味バスク産エスペレット唐辛子と高知産山椒の香りJambon fume de Sanglier de TSUSHIMA etCuissot fume de chevreuil d'EZO avec salade 対馬産イノシシの自家製スモークハムとエゾ鹿の自家製スモークハムのサラダ添えCanard sauvage d'IKI poelee et foie gras chaudavec pommes puree truffee壱岐の網取り鴨のポワレとフォアグラのソテー、トリュフ風味のジャガイモのピュレ添えFilet de Sanglier de TSUSHIMA et Cuissot de chevreuil poeleesauce grand veneure ,myrtille de nos jardin対馬産イノシシのヒレ肉とエゾ鹿内もも肉のポワレ、自家菜園のブルーベリーのグラン・ヴヌールソースGateau aux amandes , raisin et noixPave de chocola au framboisesSorbet fort de Cassisレーズンと胡桃入りのアーモンドケーキフランボワーズ風味の生チョコ・パヴェフランス産カシスの濃厚ソルべCafe de SAKAMOTO ou the et 2painsさかもとこーひー"ジビエ尽くしのコース専用ブレンド又は紅茶、2種のパン 高級食材の国産ジビエを3種類も使った贅沢なコースです。 まずは、アミューズのリエット。鹿とイノシシのモモ肉を半々でフォアグラもたっぷり使い、フランス産の鴨の脂(グレース・ド・カナール)でゆっくり煮込んで煮崩して、練り固めた肉のペーストですね。重くて獣臭いという事になると、ちょっと引きますが、これが実に上品に仕上がりました。ワインが止まらないうまさです。カリッと焼いたバゲットのスライスにのせて、バスクの最高級唐辛子エスペレットを振りかけたものと、高知産の香りが良い山椒を振りかけたものと2枚あります。 続いて、北海道のエゾ鹿の内もも肉と対馬のイノシシのモモ肉で仕込んだ自家製スモークハムの盛り合わせに自家菜園の有機サラダ添えです。鹿もイノシシも肉を塩漬けにして、2日ほど置きシェフ得意の低温長時間ローストで火を通してから一晩置き、桜のチップで冷燻にかけてから2日ほど置き、氷温熟成させたもので、去年の暮のうちに作っておきました。味わいが練れてきた頃です。シンプルに鹿とイノシシの食べ比べが楽しめますね!美味いですよ! 3品目は、壱岐の網取りカルガモが登場!鉄砲で撃った鳥ではなく網で取っているので傷がありません。臭みの原因になる腸が抜いてあり、血抜きもしっかりしてあるので、びっくりするほどきれいな肉です。これを焼いて、フォアグラのソテーとともに、、相性の良いトリュフ風味のジャガイモのピュレ(マッシュポテト)を添えます。実に贅沢! メインは、対馬のイノシシのヒレ肉(柔らかいです)とエゾ鹿の内もも肉の盛り合わせ。肉は柔らかく焼き上げて、夏にたくさん採っておいたブルーベリーのグランヴヌールソースで召し上がっていただきます。これにはもう、ワインはシラーしかありませんね!美味しいシラー種のワインをお手頃価格とちょっと良いやつと用意してあります。 デザートは、グランヴヌールソースのベリー系の余韻を引き継ぐ形で、ピンと角が立ったパンチの利いた酸味のフランス産カシスの濃厚ソルベ(シャーベット)、フリーズドライのフランボワーズ・パウダーを混ぜ込んだ生チョコ・パヴェ、そして酸味だけではおさまらないので、ほっこりしたアーモンド生地にクルミとレーズンを入れて焼いたケーキです。これにはもちろん、さかもとこーひーのジビエ尽くしコース専用ブレンドとのコラボが最高です。 これだけの内容になると都内高級店ならきっと倍以上の価格設定になると思います。とてもお得なコースだと思います。ご予約お待ちしてます。 ご予約はホームページからどうぞ。
Jan 11, 2012
-

2012年始まりました
昨日は昼間はずっと仕込みで、ディナーだけ営業しました。正月や夏休みなど、長い休みを取ると、いったん冷蔵庫をほぼ空にしてしまうので、休み明けは仕込みが多いです。サラダの用意、スープ、付け合わせ類、テリーヌやデザートなどなど、、、まあ、新規開店というほどではないにしても、けっこう仕事量がありますね。 来週早々にもジビエ尽くしのコースを立ち上げねばならないので、これから数日は、お客様が少なくても、私は大忙しです。年末の疲れも取れて、休みにも飽きたところですから、楽しく忙しくバリバリやるのみですね!
Jan 7, 2012
-
正月休みも今日までです。
すっかり休みました。毎年正月はほんとに何もしません。まあ、毎日の夕飯くらいは作るんですけどね、、、。暮れにタラバガニを結構たくさんと、2キロちょいとのヒラメを混布〆にして(混布〆なら一週間近くもちますからね)、あとは生牡蠣30個、スモークサーモンも700グラムくらい、エゾ鹿の肉を2キロくらいと、エゾ鹿のラグーソースとイカ墨のパスタソースなんかをお店から持ってきて食べてました。イクラはまだ出番がなくて冷凍庫です。あ、あと比内鶏の肉もありましたね。シャンパーニュも安いのだけど5本くらいと日本酒と赤ワインも少し、、、。 まあ、結構贅沢な品ぞろえなんですけど、うちの場合仕入れ値だけなんで、びっくりするほど高いわけではないんです。これみんな小売値で仕入れたり、外に食べに行ったら大変ですけどね(笑)家庭でもこまめに料理作るシェフがいるとありがたいもんでしょうが、うちではすっかり普通のことなので、たいして感謝されてないかもしれません、、、。まあ、安上がりにそこそこうまいものを食いたいのは、私自身なんで良いんですけどね、、、。 2日3日は箱根駅伝見ました。ほぼ全コース。いやー、東洋大学強かったですね!圧倒的でした。今回の総合新記録と5区の“山の神”柏原の記録は当分破れないかもしれませんね。私は中学生の時にたいした選手じゃないですが、陸上競技の長距離走をやっていたし、私の同じ中学の先輩で早稲田で瀬古俊彦さんと同じチームで走った人がいたりするので、箱根駅伝は、毎年気になるんです。 12月29日が仕事納めで、30日にも少し用があって店に行って、大晦日はもう早い時間から床に入って爆睡です。元旦も二度寝して、夜は家族で新年会。で、2日3日は先ほど書いたように午後まで駅伝。ちょっと出かけて本屋など行って、小澤征爾さんと武満徹さんの対談と小澤征爾さんと広中平祐さんの対談、どちらも結構古い文庫本なんですけど、かなり面白かったですね。作曲家と指揮者というのはある程度近い世界の人ですが、近いだけに違いが大きいわけです。また、指揮者と数学者というのは全く違った世界の人ですが、勉強の仕方や美意識などで結構共通点があったりして、、、。 ちょっと読んでは、うつらうつらの読書ですから、あまり頭に入ってないですけどね、、、。 明日からちゃんと仕事しますよ!
Jan 5, 2012
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- 今日のおやつ♪
- パンナコッタ🇮🇹バター🍪➕️粒あん🫘…
- (2025-11-16 00:00:12)
-
-
-

- 変なおっちゃんの食事とその日の体調
- 良品#018
- (2023-04-20 09:54:01)
-
-
-

- バレンタインの季節♪
- 再入荷!RURU MARY’S ルルメリー「シ…
- (2025-02-21 23:46:54)
-







